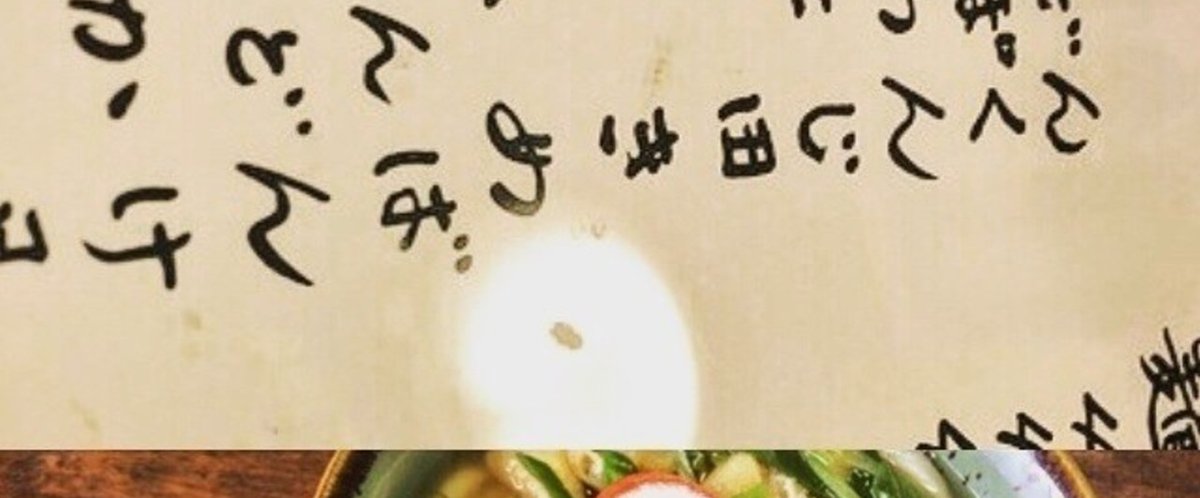
裏見葛の葉

・志乃田うどん・篠田うどん・信濃田うどん。 どれも当て字で、読みは「しのだうどん」。 名古屋以西の地域のうどん屋では、メニューに「しのだうどん」というのがあります。
たぶん、 #キャプション長え になるから、読むのはめんどいとおもうので結を先に書くと「油揚げが乗ったうどん」のこと。
うどん、饂飩。 うどんだけでも歴史や地域性のそれを書くととてつもないが、とりあえず表題の【志の田うどん】。 ボクの住む街桑名(近畿)では、この油揚げとネギが乗ったうどんのことを「しのだうどん」と呼ぶ。字は、上に揚げたように店によったりもするが、具材だけは決まっている。
関東だと「キツネうどん」になるのかな、わからないけどとにかく刻んだ油揚げが乗ったうどんのこと。
これを、なぜ関西のほうで「しのだうどん」と呼ぶか。それを書きます。
むかーしむかし、ほんとにむかし。西暦でいうと900年代とか11世紀とかのそのへんのこと。
関西の片田舎に安倍保名(あべのやすな)という、たいそう正直な若者が居て、あるとき保名が山に菜を採りにいくと、傷ついた白キツネが目の前にあらわれた。(保名は傷を手当てした:このへんは記述によってちがう)
そのすぐあと、保名のまえに、朝廷の狩人があらわれて、「このへんに傷負いのキツネが現れなかったか」と問うた。
保名は、それが先に出会った白狐だとはわかったが、「見ていませぬ」と応えた。
その夜、保名の家を訪ねる若い女が居た。
女はたいそう美しく、保名の世話をしたいと申し出て、じぶんは先に助けられた白狐(の化身)だとも明かした。
女は名を自ら「葛の葉」と云い、保名とそいとげ、子を成した。
子は男児で、優しい父と母の愛情に包まれ育った。
童が六歳に成った秋のある日、咲いた菊の花に心奪われ見入っていた葛の葉は、うっかりして子にじぶんが白狐だと見破られてしまった。
童は、その真の姿を知って驚いてしまい、それを見た葛の葉は、これ以上此処に居てはいけないと覚悟を決める。
葛の葉は、自身の「献身」と、保名に、そして子に寄り添ってきたが、どこかで破綻が来ることは解って居ながらも、いま在る幸せを解きたきなく、ずっと続くとよいと願っていた。
葛の葉は、保名の家を出るときに、子に歌を残した。
その文面は、 「恋しくば 尋ねて来てみよ 和泉なる 信太の森の うらみ葛の葉」
この歌を、"うらみ=恨み"だけでとって「人間界のなんやそれで、子から離される母の恨みの歌」とする見方もあるんやって。
なんだそれ! ゆがんでんなー!
この歌にある、「和泉なる信太の森」というのは、現在の南大阪。堺の少し南らへん。
そこに、今も信太という地区名や学校名が残る。 ...そう遠くない、いつかに別れるときが来る。そうわかっていた葛の葉は、童に獣神である自身の持てるすべてを教え伝えた。
周りに正体がばれて人間界を去らざるを得ないときに、母葛の葉は、子にだけ解るように歌を残して去った。 「恋しくば 尋ねて来てみよ@和泉なる信太の森のうらみ葛の葉」
これを読んだ、社会の者や世間様は、「子から強引に引きはがされた母の歌」と、とりなしたんだそうな。
童はちいさいから、そういう社会や世間の意見に流されそうになったが、あるとき、どうしようもなく母が恋しくなり、歌にあるように、信太の森に行き、そこに咲いていた葛の葉っぱを眺めていた。
母は居ない。
童は、葛の葉っぱを裏返して見てみた。
葛の葉っぱは、葉の裏の葉脈がつよく白く走る。それが特徴。
そして葛という植物の特性。
母者を想い、葉を裏返して見てみて、その意を知った童の視線の先に居たのは...。 ...うどんのことに戻りますね。
キツネ=油揚げ は、東西関係なく広まってますね。
んで、ネギ。
京都周辺やと、九条ネギをふんだんにあしらったりもしますが、基本青ネギ。
これが、「油揚げ-キツネ」「青ネギ-森」をあらわしてます。
うどん一杯、、、、というか、料理名ひとつに、これほどの物語を込めるのって、すっげー文化的で情緒的で、なんか、、、いいっすよねー。
あと美味しいし(๑´ڡ`๑) 。。。ちなみに、.この童が、のちの安倍晴明と成ります。
以上、うどんについてのエトセトラでした。
