
THINK TWICE 20210905-09011
9月5日(日) HONOLULU / BRASIL

その何をはばかることもない商業性にもかかわらず、ぼくはやはりワイキキが好きだ。ぼくはかつてそこに住み、そのあらゆる裏通りを知っていた。ある時期のすべての猫たち、すべての漂着した浮浪者たちを見知っていた。そこでは老残と汚辱の饐えた印象が、無機的な人工物の密林にまとわりついていた。日毎夜毎の群衆は無目的に島のこの一角のみを循回し、ありきたりな日々の祝祭を生きていた。
管啓次郎『ホノルル、ブラジル 熱帯作文集』読了。
管さんは東京大学出身の63歳。東大在学中から南米、ハワイ、アメリカ本土などに留学経験があり、現在は明治大学の教授。主に比較文化論のフィールドで研究活動をしながら、随筆家、詩人としても活躍。
この本に出会うまでお名前を認識したことはなかったのだけれど、浅田彰、伊藤俊治、四方田犬彦が責任編集していた『GS たのしい知識』(ネオ・アカデミズム時代を代表する思想誌)の「トランスアメリカ特集」や、彼が翻訳したジョアン・フォンクベルタの『秘密の動物誌』、ル・クレジオの『歌の祭り』は過去に読んだことがあったから、知らず識らず文章には触れていたことになります。
『ホノルル、ブラジル 熱帯作文集』は、1990年代後半から2000年前後に、雑誌『SWITCH』や『新潮』といった媒体に書き下ろされた文章が集められ、時系列に関係なくおおまかなテーマごとにまとめられて、ミックスCDのように流れよく並べられたエッセイ集です。特に前半のトルティーヤやタコスなど、アメリカの食に関する文章が秀逸でした。
読んでいると、早く自由に旅に出て、汗をだらだらかきながら、その土地のロコたちの〈うまい〉にチューニングされた飯を腹いっぱい食べたい───という気持ちになって仕方なかったです。
たとえばハワイにまた行けるなら、アラモアナ・センターのすぐそばの『朝日グリル』のオックス・テール・スープが飲みたい。食後は腹ごなしに少し歩いて、Hungry Ear RecordsとIdea's Music and Booksをハシゴし、中古レコードを思いっきり掘りたい。で、アラモアナ・センターまで戻り、ペーパーバックか雑誌でもBARNES & NOBLEで買って、ビール片手にアラモアナ・ビーチでジャン&ディーンを聴きながら読みたい───。
ああ、妄想しただけでも泣けてくるね。
9月6日(月) BEEF OR COW
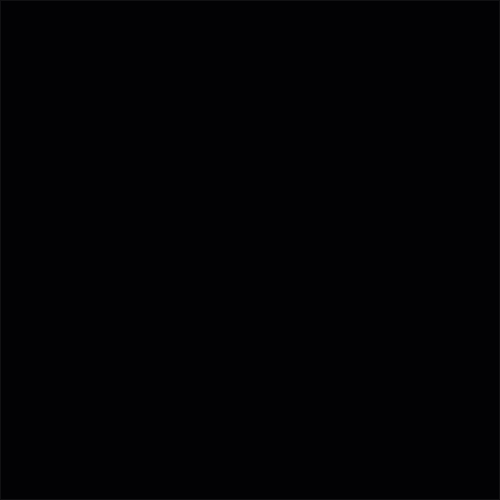
ドレイクの新作『Certified Lover Boy』と、宿敵カニエ・ウェストの新作『Donda』(真っ黒なジャケット)がほとんど同時に配信開始。さっそく聴いておりますが、英語のリスニング能力に乏しいぼくがサウンドだけで楽しむにはちょっと理解が難しい作品。要するに地味なんです。
むしろふたりのビーフ合戦のほうが派手で楽しめるんですけど、それはそれとして。カニエがリリース前後に全米各地で行なっている〈リリース・パーティ〉がめちゃくちゃイマっぽくておもしろいです。
これまで全部で3回開催されていて、第1回目は7月23日、翌日にアルバムリリースを控えた試聴会という触れ込みで、会場はアトランタのメルセデス・ベンツ・アリーナ。スタジアムいっぱいに詰めかけた大観衆に向けて、完成したばかりのアルバムを流しながら、カニエは舞台の上をウロウロしているのみだったとか。しかし、公演後に衝撃的なアナウンスをしました。
その内容とは……。
◎集まった観客から大きな刺激をもらったので、さらに良い作品にすべく、発表を2週間延期します。
◎アルバムができるまで、メルセデス・ベンツ・アリーナの中に住み込みます。
「アルバムができるまで帰れま10」、もしくは「メルセデス・ベンツ・アリーナ住みますラッパー」の誕生です。
第2回も8月5日に同会場で開催。10日間以上もスタジアムに籠もって、完成させた『Donda』を流しながら、ステージで腕立て伏せを披露。最後はアリーナ上空に宙吊りで浮かび上がって昇天。
第3回はカニエの生まれ故郷であるシカゴに場所を移し、シカゴ・ベアーズの本拠地であるソルジャー・フィールドで8月26日に開催されました。
アリーナ中央にカニエの生家をモチーフにしたという二階建てのあばら家が建てられ、その中からマリリン・マンソンやDaBaby(両者ともに差別的発言や過去のセクハラ行為などで大炎上の最中)を登場させたり、最後はカニエ自身も火だるまになるという壮大な演出が。
no one does it like kanye #DONDA pic.twitter.com/leIaTtrCkZ
— mari (@mariaveex) August 27, 2021
カニエのような世界的アーティストですら、今までのような活動がままならない状況で、こういった劇場型のイヴェントは、話題性の追求とマーチャンダイズによる経済性を両立させる試みとして、すごく面白いと思います。

かたやドレイクさんはといえば、この新作のジャケットはダミアン・ハーストが担当してるとか。iOSの絵文字をパロディにしたポップアート的な作品。

ホルマリン漬けにした乳牛(=COW)の遺骸を展示したこともある彼ですが、別の代表的シリーズ〈スポットペインティング〉を彷彿とさせますね。

Moxisylyte” (2011), one of the hundreds of spot paintings.
最近ではこういう絵に挑戦しているとか。意外だな。
ぼくがいちばん好きなドレイクさんに関するニュースはこれ。
ツッコミが秀逸すぎる(笑)。
9月7日(火) HEAVY OR LIGHT

最新のヒップホップ事情をネタにしこしこ書いていたら、某中古屋に注文していた近田春夫さんのアルバム『HEAVY』が手元に到着しました。
1986年からの約1年間、SIXTY RECORDSで近田さんが主宰していた(おそらく)日本初のヒップホップ専門レーベル「BPM」の活動を総括したコンピレーションアルバムです。
ちなみにSIXTY RECORDSは、日本コロムビアを退職した音楽ディレクターの三野明洋 *1 が設立した独立系レコード会社。近田さん以外に、越美晴、早瀬優香子、アンナ・バナナ、戸川京子、麗美、デル・ジベット───と、見る人が見れば一瞬で分かるテイストのアーティストがここからCDを出していました。80年代前半のジューシィ・フルーツやビブラトーンズなど、近田さんのニューウェーヴは主に日本コロムビアからリリースされていたので、その流れで、シックスティ傘下にBPMが設立されたのだろうと思います。
*1 三野さんはその後、JASRACが独占的に行ってきた著作権管理に風穴を開けるべく「イーライセンス(現・NexTone)」という組織を創立した。
『HEAVY』のトラックリストは以下の通り。
1 - President BPM / Nasu-Kyuri (Ultimate Go-Go Mix)
2 - President BPM / Heavy
3 - BPM Presidents Featuring Tiny Panx / Hoo! Ei! Ho!
4 - President BPM / Masscommunication Breakdown
5 - Tiny Panx / I Luv Got The Groove
6 - President BPM– Egoist
7 - F.O.E. Featuring Haruomi Hosono With President BPM And Seiko Ito / Come★Back
8 - Tiny Panx / Duvgothegroove II
9 - President BPM / Nasu-Kyuri
President BPMは近田さんのラッパーネーム、Tiny Panxはごぞんじ高木完さんと藤原ヒロシさんのユニット。F.O.E.(Friends of Earth)は細野さんが元インテリアの野中英紀らとやっていたヒップホップ/エレクトロ系のグループですが、この時期は活動休止状態。シングル『Come★Back』のリリース後、正式に解散しますが、きっかけになったのが細野さんの骨折でした。

F.O.E.の最初で最後のフル·アルバム『セックス、エナジー&スター』を作り終えたある雪の日、代官山で彼は滑って転んで、足の骨を折る。これが二度目のテクノの終わり。'86年3月のことである。足の骨を折って、テクノの終わりとはいささか滑稽な感じだが、細野晴臣は大マジメ。彼はこうした外からのきっかけを本当に待っていたのだ。というのも、YMO〜ノン・スタンダード〜F.O.E.という間、恐ろしく多忙にもかかわらず、彼は風邪一つひけなかった。彼の精神力の強さが、病気に勝ってしまったのである。その分、巨大なストレスが蓄積してゆく。
「上手なカゼのひき方」という本があるが、それによると風邪とうまく付き合えば、日頃のストレスや疲労を軽減できるとのこと。細野晴臣は、かねてから横尾忠則氏のことを「病気になる天才。実にうまいタイミングで病気になれる人」とうらやましがっていたが、遂に彼も実にうまいタイミングで足を折ったのである。足を折る前から「F.O.E.の1stラスト·アルバムのT.D.が終わったら休むぞ」と固く決意していた彼だが、足の骨を折り、「これで本当に休める、テクノも本当に終わりだ」とシミジミ実感したという。
細野晴臣『オムニサウンド』(リットーミュージック)より
この骨折のエピソードは「Come★Back」のライムに活かされたほか、テレフォンショッキング出演時 *2 にもタモさんに話していたのを今でも覚えています。
*2 1986年5月19日(月)に風吹ジュンからの紹介。細野さんは翌日のゲストとして越美晴さんにバトンを渡しました。
1979年のソロアルバム『天然の美』(キング)に、YMOがグループとして参加してるのですが、そのきっかけは1978年の秋に行われた雑誌の対談でした。ふたりは面識もなく、取材の場が初対面だったそうで、近田さんは実際の音を聴くこともなく、YMOのコンセプトを聞いただけで(YMOのファーストアルバムは発売前だった)参加を打診。細野さんもその場で快諾した───という豪快なエピソードがあります。
YMOが参加したのはM-1(作詞:楳図かずお!)、M-3、M-7、M-9(作曲:筒美京平!)の4曲のみですが、事情を知らずに音だけ聴いたら、YMOのサウンドを誰かがパロディしたように聞こえるかもしれませんね。
長くなったので、明日続きを書きます。
9月8日(水) RELAX OR TENSE

雑誌『リラックス』の2000年7月号で、ライターの堀雅人くん *1 と一緒に日本のヒップホップ特集を編集した際、近田春夫さんにインタビューする機会がありました。
*1 「ロック・ザ・ルーツ」「ミュージック・ルーツ」の構成担当で、その後、「めちゃイケ」や「BAZOOKA」といった人気番組で放送作家として活躍。もう何年も会ってないんだけど、元気かなあ。
近田さんから指定された取材場所は、西麻布交差点から外苑西通りを霞町方面に少し行ったところにあるカフェだったと記憶しています。

近田さんにご登場願ったのは「彼らはいかにしてヒップホップに出会ったのか」という見開きページ。同じテーマで中西俊夫さんと桑原茂一さんにも取材し、3人のインタビューを2ページの中に収めました。
いとうせいこうさんのアルバム『MESS/AGE』、ヤン富田さんのヒップホップ仕事、あるいはメジャー・フォース周辺に特集のフォーカスが偏ることになったのは、当時の『リラックス』の立ち位置を考えると致し方なかったとはいえ、日本のヒップホップ黎明期に近田さんが果たした役割を思えば、その扱いが小さいことは取材前から気にかかっていました。
で、これがぼくがまとめた近田さんインタビュー全文。
シュガーヒル・ギャングの『ラッパーズ・ディライト』って曲調が軽いよね。 ああいうパーティラップって文化的じゃない気もしたし、最初はラップがこれほどまでに革新的な表現だとは思わなかった。バンバータもね、あのエレクトロ的なビートに馴染めなかった。だけどライヴを見てから、印象が大きく変わったね。 これはとてつもなくヘンでスゴい音楽かもしれない、と。
あとはRUN-D.M.C.の『キング・オブ・ロック』を聴いた時に、そこまでヒップホップに対して持っていたモヤモヤがパーンと弾けたんだよ。それまではロックっていう様式が最も自由だって思ってたけど、 それ以上にヒップホップにはいろいろな可能性をぶちまけても成立する構造なんだってわかったからさ。俺は発明とか発見が昔から好きだったし。とにかくヒップホップはいろんな意味で新しかったんだよね。
あとは『クラッシュグルーヴ」 でL.L. COOL Jの動きを見た時、 早くコピーしなきゃって思ったね。 ヒップホップへの大きな感銘としてL.L. COOLJの身のこなしは重要だったから。 RUN-D.M.C.以降の音はどっかしら自分の考え方と近い部分があって、シンクロニシティみたいな感覚があったんだけど、 本気でそのままコピーしようと思ったのはL.L. COOL Jの動きだけ。 でも、 コピーして自分なりに取り入れれば笑えるんじゃないかなあっていう素直じゃない気持ちで。 まあ、 悪ふざけだよね(笑)。
あとヒップホップがある種の精神だと考えた時、自分がオリジネーターであることが一番偉いと思ったんだよね。だから大きなテイストとしてそこに入るものを次に編み出すのが一番偉いんじゃないかと。 ある刺激にインスパイアされたら、 それを自分のフィルターに一回通して、それでそれが自分にとって何なのかって考えたいんだよね。だからジャージも俺だけスソ絞ってたの。そりゃハズしますよ、 当然。
だから俺が86年に立ち上げた〈BPM〉レーベルでやりたかったことはまさに“BPM"だよね。 みんなBPMなんて言葉知らなかったと思うんだ。何がヒップホップで重要かっていったらテンポだと思ったんだよ。あのテンポが新しいんだっていうね。それを証拠として残しておくためにはBPM という名前を付けておけば良いだろうって。“プレジデントBPM” って名乗ったのもそのため。 だからBPMレーベルのジャケットにBPMのチャート表を付けたんだよ。現場でBPMを合わせるときにあのチャートがあると便利なんだ。 これはデザインじゃなくて実用なんだ。それでこのヒップホップっていう音楽の本質はなんだっていうことを俺なりに提示できたと思うし。それだけのためにやったんだよ。 証拠は残ってるでしょ? この音楽とは何なのかってことがそれでわかるじゃん? その曲のBPMにちゃんと表に丸を付けてあるしさ。いつの日かみんな気づくと思ってやっといたんだよね。 だから俺は証拠を残せたからいいの(笑)。
中西俊夫さんにはMELON時代のこと、桑原茂一さんには発禁になってしまったハードコア・ボーイズのシングル『俺ら東京さ行ぐだ』にまつわるお話を───といった具合に、他のお二方は主題が定めやすかったのに対し、近田さんはこっちがあれこれ投げかけるより前に、ヒップホップという新しいアートフォームに対して、当時の自分がどう反応し、何を考え、なぜレーベルを立ち上げるまでに至ったか───近田さんの言葉を借りれば「精神」についてのお話をしてくださったので、聞き手としてすごく興奮しながら、「せっかくこんな価値ある話をしてくださってるのに、すべては盛り込めないだろうなあ」と、がっかりしていたことを思い出します。
記事から落とした中で、いちばん印象的だったお話───もうさすがに20年以上前なので、細部に記憶違いがあるかもしれないけれど───近田さんは細野さんを例に挙げながら、彼のように良いメロディを書く、売れる曲を書けるっていうのは、神様からの贈り物みたいなもの、と仰ってました。メロディとは官能的なもの、という言葉も使っていたと思います。本人が望むと望まざるとにかかわらず、そういう才能は神様によって選ばれた人に与えられたギフトなんだ、ということです。
いっぽうヒップホップはその官能や天賦の才の束縛から解放された音楽である、というのが近田さんの見立てでした。それが記事中にある「ヒップホップとはすなわちBPM」という発言に繋がっていくんですね。
ヒップホップは、BPMでいえばだいたい75〜100BPMくらいのレンジに収まります。もちろん進化(深化)していくなかで、たくさんの変異体が産まれ、その範疇に収まらないヒップホップもあるけど、少なくとも近田さんがヒップホップを作っていた頃にはほとんど例外はありませんでした。
たまたまその号の『リラックス』は、日本のヒップホップとモスバーガーの特集だったんだけど、バンズの中に挟み込んでしまえばハンバーガーである、という考え方に似てるんじゃないかと思うんですね。つまり、一定のBPMで打ち鳴らされるビート、ブレイクビーツのなかに挟み込んでしまえば、どんな要素でもヒップホップになる、と。
MELONやメジャー・フォース周辺のアーティストは、より本格的なバンズ、本格的なパテにこだわって、本場に負けないハンバーガーを追求した。せいこうさん、ヤンさん、近田さんたちは本場の人が思いつかないような材料で、独自のハンバーガーを作ろうと試みた。
無論、どちらのアプローチが正しく、どちらが間違っているわけではなく、ただ精神や方法論の違いだけです。ただ、海外の人たちにも受け入れやすい表現だった分、メジャー・フォースのレコードは海外でも評価されるのも早かったし、モ・ワックスからコンピも出ましたが、そのうちシティポップのように、海外のDJやレコードコレクターがPresident BPMの『ナスキュウリ』や、宮崎美子の「タカラ本みりん」の7インチシングルを血眼で探す時代が来るかもしれないし、絶対にそうなると思います。
9月11日(土) THE SKY'S THE LIMIT
当時、渋谷の金王神社の近くに借りていた事務所を出て、井の頭線で帰宅しているとき、カメラマンの永田章浩さんから携帯に着信がありました。
ちょうど永田さんに撮影の仕事をお願いしていたので、きっとその件だろう、と想像しつつ、吉祥寺駅で降りて、改札と中央改札口を繋いでいる短いエスカレーターを下りながら折り返しました。しかし、電話に出た永田さんはうわずった声で「すごいことになったねぇ」と開口一番、言うのでした。
「なにがですか? 写真のことですか?」
「いや、そうじゃなくてさ───ミズもっちゃん、今どこ? 外なの?」
ぼくはちょうど電車を降りて、自宅に向かって歩いているところだ、と伝えました。
「そっか、だったらさ、早くテレビ観たほうがいいよ。ニューヨークが大変なことになってるから」
「わかりました、あと5分くらいなので、帰ったらすぐに見てみます。ところで、ぼくの写真は───」
永田さんは電話をガチャンと切り、肝心なことを聞けずじまいでした。
携帯をズボンのポケットにしまって、まわりを見回してみました。でも、世界が一変するような大事件が起きているなんて信じられないくらい、平穏な駅前の風景がそこにはありましたし、帰宅する人たちの表情もいつもと変わっている様子はなかったのです。
ほとんどの店がシャッターを下ろし、眠りにつこうとしている夜の商店街を抜けて自宅に戻ったぼくは、テレビをつけてようやくあの衝撃的な光景を目の当たりにすることになったのです。
永田さんとはすっかり縁が切れてしまい、長いあいだ会っていないですけど、毎年9月11日が来るたびにこのエピソードの登場人物として、かならず思い出します。ジョージ・W・ブッシュ、ビン・ラーディン、永田章浩───みたいな感じで。たぶん死ぬまでそれは変わらないと思います。
サポートしていただいた資金でレコードや本を無駄遣いし、執筆の糧にしております💰
