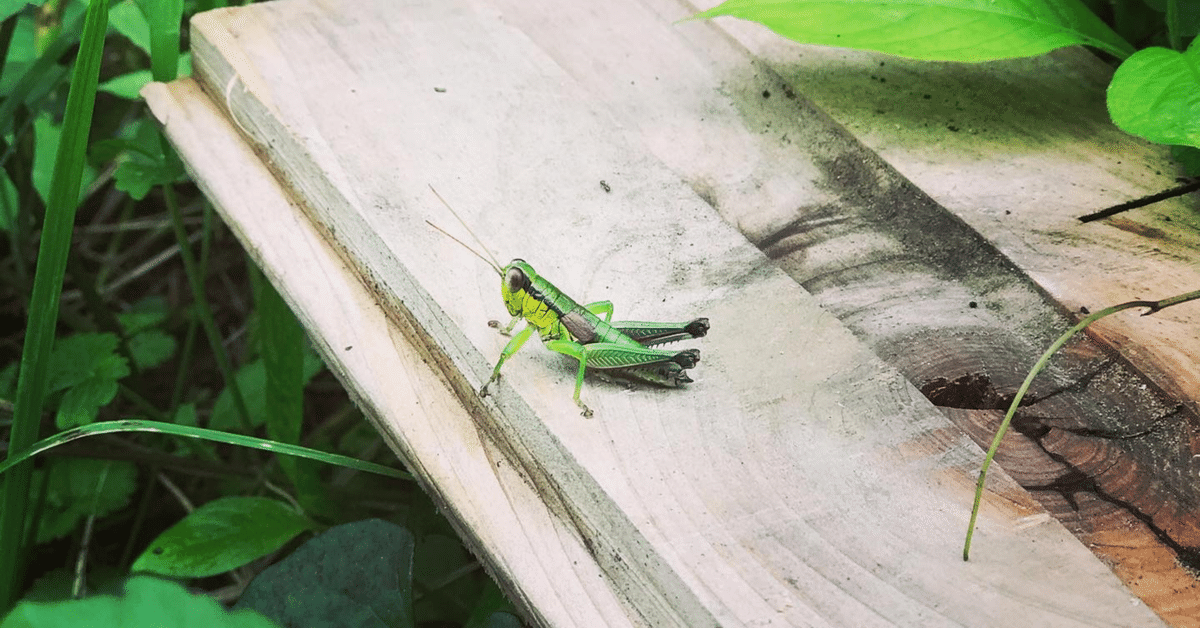
[無いものの存在]_28:ゲンシとアートを行き交う技術
非支配の対処を考える
幻肢。幻視。原子。原始。
ときの首相は原子力発電所の事故を「アンダーコントロールにある」と言っていたが、そう簡単に支配下におけるゲンシなんて無いだろうに。
一般的にネガティヴに捉えられるもの、例えば僕で言えば「身体障害」と呼ばれるようなものに対して人は極度に距離を取りたがってはいないだろうか。もちろん危険なものに対しては動物的な直感で距離を置くことがあるのはわかる。しかし、危険との付き合い方を知らずに、共生やらダイバーシティやらを語ることはあまり信頼できない。特に「コントロール」「対処」「改善」「管理」というような、対象と自分の隔たりをつくるやり方は僕の身を縮こませる。
骨肉腫で初めて入院した時に毎月決まった期間投与される化学療法、足を覆っていた無骨な装具、いつか起こるかもしれない再発への危機感、切断後に幻肢痛の痛みのレベルを聞かれて薬を処方されること。「リハビリ」という過程もそうかもしれない。これらには「困難」を絶えず「対処」し続けなくてはいけない忙しなさが漂っている。しかもこの忙しなさのほとんどは僕自身の体に向けられている。
思い返せば初めて入院した12才の時もそうだ。僕の小学校はキリスト教の学校だったので、お見舞いに来た教師が「神様が守ってくれているおかげだね」と言われ、小学生ながらムッとしたのを今でも覚えている。化学療法の副作用で髪は抜け落ち、毎晩胃液を吐いて、体重も激減しているのは紛れもない、目の前に居る12才の子供の体である。宗教自体への嫌悪感は無いが、目の前にある体を飛び越えて「神様」を語るのは、僕が受け止めている現実を「苦しいもの」と決めつけるようで、あまりにも言葉足らずに感じたのだ。病気や障害を「対処(治療)」することは誰も止めない。だからその正しさのために当事者は置いてきぼりにされてしまう。専門家や、時に家族までも、その正しさのために僕のお尻を叩くことになる。その正しさからドロップアウトする道があるのかどうかなんて迷う時間は12才の僕にはなかった。
だから僕はそうやって「対処」しなくてはいけない「対象」をつくりだしてしまう関係が今でもしっくり来ない。これは幻肢痛を当事者研究することや、義足の相棒感で実践されている。12才の僕が治療をドロップアウトする選択肢が無かったように(選択するかではなく、選択の予知があったかどうか)、幻肢にも義足にも、僕との関係について考えてもらう時間が必要なはずだ。互いに支配から逃れる関係があると思うのだ。
地続く体を構築する
非支配の関係は僕と幻肢や義足だけではない。
十代の頃からなぜか農業や園芸に興味があった。興味はあたけど実際にやることは無かったのだが、特に今年になってから農作に挑戦できる環境に暮らしているので、畑を耕し野菜を育てている。これが非支配を考えるにはとても良い環境になっているのだ。
よく芸術関連の書籍などの中でも「生態系」や「土壌」という比喩が用いられたりする。物事の因果関係が複雑に絡み合っていて、なんとなくふわふわして、豊かなイメージを彷彿とさせる言葉だ。言わんとすることはなんとなくわかるけど、実際の生態系や土壌のことなどほとんど実感が沸かなかった。
それが自分で畑を耕し、種を撒いてみると「これか!」という感じが少しずつ掴めてきたのだ。同じ種でも植える場所によって成長は著しく違う。ぐんぐん成長しても必ずしも実をつけるわけではない。可愛い虫だと思ったら害虫で葉が全て枯れ落ちる。梅雨に元気が無かったけど明けた瞬間に次々と実がなる。1日たりとも同じ景色はない。
そして周辺には蝶、クモ、バッタ、トンボ、毛虫、アリ、トカゲ、ヘビ、その他名前もわからない様々な虫が畑だけでなく家の中でも出会うのだ。自然状態では彼らは領域などなく存在している。よくよく観察し、付き合いを重ねていくと彼らの行動範囲や悪意はないことはなんとなくわかってくる。だから常にお互い様な空気がそこにはある気がする。ここに住み始めてからほぼ虫を殺さなくなった。東京の実家でクモを見たらきっとティッシュで包んで捨てていたと思うのだけど、今は家の中でクモを見ても放っておく。パーソナルスペースが小さくなったのではなく、お互いの存在が許容されているから生物の個体数が多くても居心地は良いのだ。
これは「無いものの存在」にもどこか繋がってくる。つまり、圧倒的に理解できない環境の中で、体を通じて「知らない」を許容し続ける感覚。クモやトカゲと心を通わせるわけじゃない。お互いの存在を自分の体だけで完結させず、環境と地続きに自分を存在させているようなあり方なのだ。これを書いている部屋には恐らく今もトカゲの親子が潜んでいる。その存在は突き止めて対処する必要も無く、彼らは彼らのやり方で、僕は僕のやり方でこの環境と地続きに居ればそれで良いはずなのだ。
作品が無くても存在があったはず
以前も書いたことだが「アートプロジェクトではそこに居ること」が大切になることがある。その空間に漂うリズムと自分が同期していく時間の積み重ね。ただ居ることで様々な出来事に出会う機会を生んでいくような振る舞い。
総称としてアートプロジェクトと書いたが、国内では1960年代、美術館を飛び出し屋外に作品を設置して展覧会を行っていた野外美術展が源流として位置付けられる「日本型アートプロジェクト」と呼ばれる場合もある。アートは常に記録や保管された「美術作品」の存在がある。その作品を所蔵する美術館を飛び出したアートプロジェクトでさえも、野外に設置された作品を手掛かりにされている。美術史とは作品優位に成り立つものでもある・
僕が大正時代のいくつかの出来事に興味を持っていて、その関心が「無いものの存在」に惹かれるのは、作品とは異なるアプローチの道が開かれるような気がしているからだ。
そのひとつに帝大セツルメンハウスという場所がある。関東大震災で被害を受けた東京の墨田区に建てられた広く社会福祉を行う拠点であるが、ここを設計したのは人々の生活の様子を採取する「考現学」を創設した民俗学研究者の今和次郎である。考現学とは現代アートへも脈々と影響を与えるひとつのアプローチでもある。その考現学のメンバーである新井泉男は帝大セツルメンハウスで子供達に鉛筆画を教えて展覧会を開いたという記録が残されている。今そんな話を聞けばワークショップやアートプロジェクトなんて呼ばれていたかもしれないが、作品が残っていない今となっては美術史でそれが語られることは稀である。
また、現在も世田谷区にある松沢病院で大正時代に行われていた作業療法の実践も見逃せない。患者と医者と庭師が協力して院内の敷地に小山と池をつくったり、農業、印刷業、その他ユニークなレクリエーションが行われていた。これらを決して「アート」と名付けていたわけではないようだが、そこには創造力が溢れていたのではないかと思う。
これらセツルメント、作業療法、その始まりはどちらもアーツアンドクラフツ運動が重要なきっかけになっている。現在世界的な潮流でもあるアートによる社会変革を目指すソーシャリー・エンゲイジド・アートと呼ばれるものには、このアーツアンドクラフツ運動を牽引した美術批評家のジョン・ラスキンやウィリアム・モリスの思想の影響を受けたものも見られる。
ソーシャリー・エンゲイジド・アートやアートプロジェクト、または僕が行うキュレーションという技術も「アートを社会化する方法」だとすれば、セツルメントのような社会福祉の実践、作業療法の取り組みは既にアートを社会化しているものではないだろうか。それは例えアートと名指されていなくとも、アーツアンドクラフツ運動を起点に切実な創造力を社会の中で発揮しているように思えるのだ。
現在、アートが「地域」や「福祉」という言葉と結びつく様子は、アートがアートの自律性を求めて細分化していく中で距離を置いてしまっている間に地域や福祉の中で社会化されたアートを回収しに行っているだけなのかもしれない。それらの領域が続けてきた実践の歴史には「作品」は残っていなくとも、よりよく生きることに切実な存在の数々が今もあるはずだ。現在のアートプロジェクトを美学的とは異なる価値で解釈するには、戦前の社会福祉などの分野から接続して、よりよく生きるために使うアートの姿が見えてくるのではないだろうか。
作品優位で組み立てる美術史では記録の残らないものが語られることは少なく、殊更松沢病院やセツルメンハウスに居た人々がそれによって救われたというような個別的な体験は重視されていない。しかし、僕自身が今自分の体とやりとりしている「治療」とも名付けがたい行為は、アートの創造性を社会化する実践でもあるのだ。それは極めて個別的な実践だとしても、この創造力は自分をケア(キュレーターの語源でもある)する切実な技術なのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
