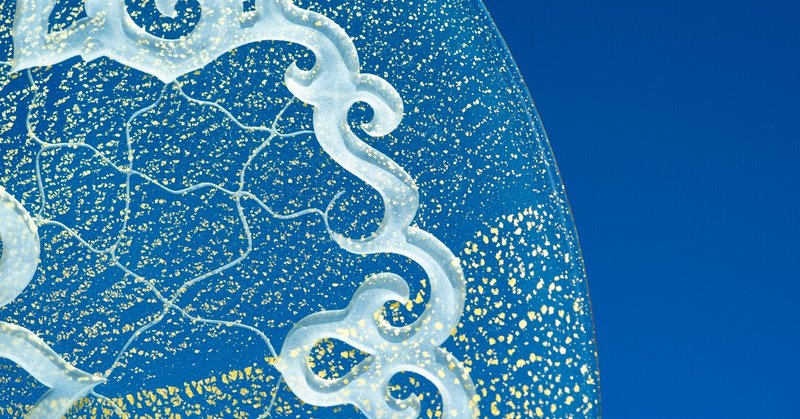
根づく・生きる・つながる:道具と伝承をめぐる対談〈下倉洋之(彫金作家)×朝倉圭一(やわい屋)〉
伝承のなかで紋様を刻む彫金と、生活のなかの道具の価値を再発見した民芸。歴史のなかで、人が培った文化を伝えるために、どのような姿勢をとりうるのか。地元の生活に根ざした作品を扱う2人の会話から、これからの継承のあり方を考える。

下倉洋之(上)|1975年生まれ。20歳より彫金を始める。アイヌの伝統衣装と出会い、その不思議な文様に衝撃を受け、アイヌを意識した装身具づくりを始め、1999年ブランド「Ague(アゲ)」を立ち上げる。2013年に阿寒湖温泉に移住、2019年アトリエ「cafe & gallery KARIP」をオープン。妻は工芸作家の下倉絵美。
朝倉圭一(下)|「やわい屋」店主。岐阜県高山市出身。県外で会社員生活を過ごし、高山に戻る。2016年「やわい屋」、2017年には2階の屋根裏部屋に古本を扱う「やわい屋書店」をオープン。2020年より書店を改装し、人文学の蔵書を公開した私設図書館にリニューアル。
——まずおふたりの自己紹介をお願いします。
下倉洋之(以下、S):阿寒湖には、東日本大震災をきっかけに移住しました。10代のころから北海道によく遊びに来ていて、いつかこんなところに住めたらいいなとは思っていたんですけど、当時は東京に仕事も仲間もいたので難しかった。ただ、2011年のタイミングで北海道に移住しちゃおうと決めました。東京にいるとなんとなく流れていってしまいそうだった、ひと踏ん張りしてやりたいことをやってみようと思ったんです。
いまは仕事場をお貸りして、そこで自分の作品作りと展示、あとは周りにいる好きな作家さんたちの作品を買い集めてきて置いたりしています。ほかにも趣味も兼ねて、自家焙煎のコーヒー屋をしています。
朝倉圭一(以下、A):ぼくはいま岐阜県の飛騨高山という観光地で、古本と民芸を扱う「やわい屋」というお店を営んでいます。20代はずっと音楽をやっていたんですが食べていけず、地元に戻って就職をして、ラーメン屋の仕事をしていました。
じつはぼくも東日本大震災の影響で、お店をつくることになりました。自分の手で何かをつくりださないといけないという思いに駆られるようになったんです。最初は農業の勉強をしたりしました。結果としては、古本や民芸の作品という人がつくったものを扱う道に進むことになったのですが、その時の経験がなければ、いまのお店はやってないなと思っています。

▲朝倉が営む「やわい屋」では、食器や照明などの生活道具と古本が扱われている。
——朝倉さんのお店は、もともと築150年の古民家を移築してつくったとお聞きしました。 歴史あるものがお好きだったんでしょうか。
A:よく誤解されるのですが、古民家が大好きなわけではないんです。地元の暮らしぶりをちゃんと理解するために、箱としての家をちゃんと土地にあったものに変えたかったという方が正確です。もちろん飛騨高山の文化はすごく大切に思っていて、勉強はしています。ただ、いわゆる「ていねいな暮らし」をしているわけではありません。コンビニには普通に行って、コーヒーを買ったりしています(笑)。
S:その感覚、わかります。ぼくはストイックに努力しているつもりがありません。ジュエリーメイキングに出会ってからというもの、やってもやってもどんどん面白くなる一方なんです。少しづつ歩を進めるたびにその先の深みが見えてくるというか。ぎゅーっと入り込むのが好きなんですね。身近な友人からは「お前は過集中ジャンキー」だといわれます。
——下倉さんは阿寒湖畔で藤戸竹喜さんの作品に触れ、衝撃を受けたそうですね。
S:熊の手のリングの原型となる作品ができたころ、それを見た友人に、クマの木彫をつくる作家の藤戸竹喜さんが運営している「熊の家」を紹介され、行ったのがきっかけですね。ギャラリーで彼の作品を見て衝撃をうけ、ずっとたたずんでしまいました。いま思い返すとはずかしいのですが、当時は藤戸さんに喧嘩を売ってしまったんです。「いつかこれよりいいモノをつくってやる」って。自分がつくっていた熊の手のリングの、はるか先にある作品を見せられたような印象をうけました。
だから当時は、地元に帰ってから、作品をゼロからつくりなおして、1年間やっては夏に阿寒湖に来てがっかりして帰るというプロセスが毎年の恒例行事みたいになってました。面白いもので、去年見えなかったことが今年見えるし、今年見えなかったこと来年見えるようになるんです。結果、彼を超えるのは並大抵のことではないとの実感もかえって膨らみました。もちろんいまでも藤戸さんの作品を超えるつもりでつくり続けていますが、未だに尻尾も掴めていないなと感じます。

▲下倉がつくる「熊のリング」。アイヌ文化との出合いのなかで、独自のかたちにアップデートされていった。
——「やわい屋」で扱われている民芸は、生活のなかにあるプロダクトを芸術として評価するムーブメントとして知られています。
A:下倉さんの姿勢には共感するところがあります。観光地なので、他県からのお客様も多いのですが、やわい屋は中心地からは離れてるし、看板も出していないので、来ようと思って来ないとたどり着けない。だから、地域に根ざして地元の人にどう買ってもらうかを考えています。民芸に思い入れ深い人だけが手に取る高級品ではなく、地元の方もお祝い品として手に取ってもらいたい。普段の生活の中に作品が入って使われることが、道具としての作品にとっては幸せなことだと思うんです。
——道具としての作品と、ただの道具はどう違うのでしょう?
A:たとえば、食器は毎日使って育てていくものだと思うんです。デニムを履いていると味が出てくる感覚に似ているいるかもしれません。たとえば、100円ショップっで売っている皿と、3〜4,000円のうちで売っている皿は、機能的には同じ。むしろ、安いものの方が割れなかったりします。ただ、使っていくなかでアンティークになっていくのが作品なんですね。大事に扱うという手をかけていただくことで、そこに愛しさが生まれることが大きいのではと思っています。

▲下倉による「吹きガラスのアイヌ文様ショウプレート」。金箔をガラスのなかに入れたもの(右上)と、完全に透明なもの(左下)の2種を制作。(写真:間部百合)
——下倉さんが今回のプロジェクトでつくられた「吹きガラスのアイヌ文様ショウプレート」についてお伺いしてもいいですか?
S:今回のガラスプレートは、上にお皿を載せるショウプレートなので実用品ではなく「見せるお皿」としてつくっています。ガラスの両面を彫った作品をつくってみたかったので、その思いを実現させました。ただテーブルの上で見せるだけではなくて、ドアの丸窓にはめても素敵だなとか、そういう用途も浮かんで、金箔入りのものと、そうでないモノの2種類をつくっています。同じ模様で同じようなものを作っても、使いたいイメージは全然違ってくるのが面白いなと思いました。
——アイヌ紋様が透明感のなかで存在感がありますよね。作品のオリジナリティを出す中で、紋様がもつ歴史性については、どれくらい意識されているのでしょう。
S:いまはそれほど意識してないですね。紋様というものは、決まったかたちがあるようでない。自由に描ているとそれがつながっていく感覚に近いです。じつは昔はいまよりマジメで、アイヌ紋様を描かなきゃという意識が強かったんです。ただ、年をとると肩の力が抜けてきて描かなければならないという意識はなくなってきました。
ただ、だからといってアイヌ紋様がただの模様だというわけでもない。呪術的な側面はあると思います。親子三世代展という企画をやったことがありました。祖父祖母世代と、その娘息子、さらにその孫世代のぼくらがつくったものを集めたんです。そこで出てくる紋様は全部違うんですよ。ただ、どこか共通する匂いみたいなものを感じました。それが伝統、いや伝承なのかなと。一族の匂いみたいなものは、違う作品をつくってても確かにあるんですよ。
A:伝統ではなく伝承というところは、ぼくも大事にしているところです。伝統を守るためには、「伝え、統べる」必要があります。つまり、歴史を伝えて、文化のかたちを統合するというものすごい強い能動性をもたなければならない。そして、外側に対する自分たちのプレゼンテーションが入っている言葉だと思います。そこには、アイデンティティを強く出すべきだという含みがある気がするんです。
一方で、伝承は「伝えて、承る」、つまり受け身なんですよ。伝わってきたものを、「承る」ことで、自分の中に入ってくるっていうようなイメージです。その肩ひじ張らない姿勢で、歴史に対して向き合っていきたい。たまたま授かったものを、できる範囲で次の世代に伝えるくらいが自分にはちょうどいい気がするんです。

▲サンドブラストによって刻まれたアイヌ紋様は、透明なガラスの上で新しい存在感を発揮していた。(写真:間部百合)
「楽しむ」という自分のスタイルに触れた下倉と、生活のなかで歴史を重ねる道具の価値を語る朝倉。生の楽しさに重きを置くふたりの言葉には、自由な魅力があふれている。2020年代という新しい時代と向き合わざるをえない我々にとって、伝承という受け身の姿勢は、より重要なものになっていくのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
