
集まり散じて|スズキという無二の親友と、このごろに続くあのころ。
今年で29歳になる。東京のとある広告会社で、「プランニング・ディレクター」という、横文字にすればそれなりに見栄えのする肩書きであるが、その実有り体に言えばただの「なんでも屋」をやっているのが、おれの現在地である。
10代の頃は、まさか自分がこのように会社に勤めているなんて想像さえできなかった。本当は英語の先生になるはずだった。当時、テレビでは林修が「明日って今さ!」とかそんな感じのことを言っているCMばかりが流れていた。東京に出て、勉強をして、地元に凱旋し、教壇に立ち10年もすればカリスマ英語教師としてCMとかに出まくっている、18歳のおれがイメージしていたのはそんな未来だった。
いま、おれは広告屋として日々面白おかしいことを考えながら、頭の中で思い描いている空想を実現させるために日々悪戦苦闘している。なかなかタフな仕事ではあるが、なんとか喰らいついて7年目になる。これから叶えたい夢や作りたいものが具体的にあるわけではないが、いまのおれを形作るものについて考えるときに、ある友人と過ごした学生時代のことが脳裏に浮かぶ。それは、当noteにもたびたび登場するスペシャルフレンド、スズキがいた大学時代の日々である。

初めて彼女と会った時のことを覚えている。2013年、おれは群馬の田舎の高校を卒業して東京の大学に入った。しかしあの頃の大学生活というのはたいへん暗いものだった。せいぜい仲が良かった同じ専攻の5人組と、あの女の子がかわいいとか話したり、自分たちのことを棚上げして、大学デビューをした垢抜けない金髪男を指さしてクソがと笑うようなものだった。友人に誘われるがまま入ったサークルに碌に顔も出さないでいた。
たしか、英文法の講義が終わった後だったと思う。いちょう並木のキャンパスで友人と話しているところに、柄物の古着のシャツに身を包み、ギターを背負った彼女がやってきた。一言、二言友人と喋ったのちに、彼女がおれに向かって言う。
「あたしさんしちゃんのこと知ってる、実はちょっと推してるんだ。いつもニコニコしてていいよね。どんな子がタイプなの?」
初対面のおれに唐突に、なんの脈絡もなくずけずけとこちらに入り好きなタイプを聞いてくる彼女に面喰らいつつも、推しだと言われて悪い気はしない。ぽつりぽつりと話すが、すぐに会話が続かなくなる。おれは人見知りだった。
それからというもの時々話すようになったのだが、スズキは東京で生まれ、東京で育ち、優秀な中高一貫の学校から大学に入ってきたという。いつもおしゃれな古着に身を包み、ギターを背負い、また一挙手一投足が明らかに垢抜けており、いかにも賢そうな喋り方をするスズキは、田舎育ちのおれにはいささか眩しく感じられ、ものすごく形式的な、表層をなでるような会話しかできなかった。

しかし、そんなスズキと明確に仲を深めるきっかけになった瞬間を覚えている。彼女は、高校時代から長く付き合っていた彼氏と別れたばかりで、「東京」と名の付く曲ばかりを集めたプレイリストを作って聴いては毎日泣いている、といつだったか話した。見るとくるり、銀杏BOYZ、YUI…いずれもおれが田舎にいたころからよく聴いていた音楽だ。音楽の趣味が合うことが分かったおれとスズキは途端に仲良くなった。それまでキャンパスで一言二言喋るだけだったおれたちは、講義をサボって釣り堀で日が暮れるまで糸を垂らしたり、夜になったら酒を飲み、朝まで歌をうたったりするようになった。

大学時代におれが摂取したカルチャーのほとんどは彼女とともにあった。スズキと一緒に新海誠や細田守の映画を観た。tofubeatsを聴いた。中南米の音楽をやるサークルに入っていたスズキからフィッシュマンズを教えてもらった。高円寺というまちを覚えた。表参道で街ゆく人を指さし文句をつけながら歩いた。深夜、新宿の雑居ビルの屋上で歌舞伎町を見下ろしながら朝が来るのを待っていた。スズキの知り合いがやっているという居酒屋に通いながら古今東西あらゆるカルチャーを摂取した。スズキと過ごす中で、おれは少しずつ「東京の人」になっていった。

都会的で文化的な一方で、「東京」というプレイリストをわざわざ作って聴いては涙を流すような、たいへんな人間くささのあるスズキのことを、一度として恋い慕ったことがないかというと嘘になる。一歩踏み込まなかったのは、なんでなんだろうな。男運のないスズキと女運のないおれとで戦友のような、兄弟のような、そんな距離感がとても心地良かったのか、男女の関係という土俵の外でただただ油断できる関係でありたかったのか、そもそもそんな度胸なんてなくてウジウジとタイミングを逸したに過ぎなかったのか?いずれにせよ、恋慕のこころはいつの間にかどこかに行ってしまった。大学でいつもスズキと一緒だったあの頃、二人は付き合っているのでは…等という噂を何度も耳にした。「男女の友情は成立するか?」という問いはしばしば疑いとともに巻き起こる。おれの答えはYESだ。しかし、そのYESには「それなりに時間がかかる、あるいは越えるべき壁がある」という但し書きが入る。

スズキとの思い出はあまりに多く、語り尽くしてもなお余りある。ここまで書き進める間に書いては切り捨てたスズキとのエピソードが山ほどある。今日書きたいと思っているのはおれが教師という仕事以外の稼業を始めるきっかけとなった話だ。その話をしよう。
大学三年生の夏、スズキはアメリカに1年程の留学に行くことになった。スズキは海外での生活が不安だと言った。スズキが日本を発つ日、なにかお守りのようなものになればと思いたって、見送りのため成田に向かう道すがら、おれはノートを一枚ちぎって手紙を書いた。なんて書いたのかは忘れた。それを別れ際に手渡して、スズキは飛び立っていった。
それから、おれはスズキが英語を一年かけて勉強するのなら、おれは日本語を勉強するぞ、と決めて表参道のコピーライターの養成講座に通い始めた。これが、今の仕事につながるきっかけといえばきっかけになるのだろう。

一ヵ月くらいたったある日、スズキから返事が届いた。寂しいけどそれなりに元気にやっているという話だ。結びには、手紙がきちんと届いたかどうか分からないから、手紙を受け取ったら返事を寄越すように、となんともスズキらしい言葉が添えられていた。おれは返事を書いて、それから月に一度くらいのペースで手紙のやりとりをするようになった。
手紙にはいろいろなことを書いた。日本の気候のこと、日本にいる大学の連中のこと、コピーライターのこと。おれは文章力が高いと過信していたが、講座にはたいへんな才能を持った人ばかりいて落ち込むなど。
スズキは、おれの書く言葉をたいへんに褒めてくれた。さんしの手紙は読んでいて楽しい、書き出しは慎重に、でもテンポよく話が進んでところどころ笑えるけど、徐々に感情的になってよくわからないワードチョイスをしながら最後はなんだかエモい気持ちになる。少なくてもわたしは何度もあなたの手紙を読んでじーんとしたので、コピーライターになるというのはすごくいいと思う、などとなんともつまらないことを書いてくれた。スズキを勇気づけるために書き始めた手紙だったが、いつしかおれ自身もスズキの手紙に救われるようになったのだった。

冬を越えて春になって、ある日CMを作る大会が開催されることを知った。徳島県の神山町というところに山籠もりをして、町おこしのPR動画を作るというテーマのものだった。グランプリを取れば、賞金とともに副賞として渋谷TSUTAYA上のでっかいビジョンで作品を流せるという。時期は、ちょうどスズキが帰国するころだった。グランプリを取って、渋谷でスズキに見せてやったら喜ぶぞ、と思ったの半分、就活のネタ半分におれはその大会に参加することにした。

ここでもまあ紆余曲折あったのだが、まんまとグランプリを取ったのが先だったか、スズキが帰国したのが先だったか、とにかくおれが当初思い描いた通りの格好になった。
渋谷のスクランブル交差点にスズキを呼び出し、無事に作品が放映されるのを一緒に見守った。永遠みたいな30秒だったが、一方でどこか冷静な自分もいた。渋谷のスクランブル交差点を歩く人々は、誰一人おれの作品を見上げようとはしなかった。そりゃそうだ。言ってしまえばたかがCMだ。よほどでなければ見たいと思わないだろう。それでも、おれが作った最高なCMなのだから、みな一様にスマホを弄る手を止め、上を見上げるはずだと心のどこかで思っていたおれは少し落ち込んだ。
落ち込んだけど、スズキが、スズキだけが、じっとTSUTAYA上のでっかいスクリーンを見上げていた。いやまあおれが無理やり誘ったんだからそりゃ見るだろって感じではあるが、少なくてもスズキには届いた。スズキは、おれを誇りに思うと言った。嬉しかった。

おれは、おれの作ったもので世界を変えられるとは思っていない。みんなそんなものに興味を示すほど暇ではないって知ってる。でも、あの日、スズキという無二の親友には届いて、手を振ってくれた。あの確かな手ごたえが、いまもこの仕事を続ける、あるいは霧の中におまんじゅうを投げ続けている理由になっているような気がする。
時には心ポッキリいくこともあるにせよ、スズキの手紙のつまらない文章をまんざらでもなく思い返しては、おれは手を動かして妄想に息吹を宿す。おれは、あの日の渋谷から帰る道の途中に今もいるのである。

そしておれは大学を卒業して、1年後にスズキもそれに続いた。学生街も様変わりし、おれとスズキがふたりいたことを知る者もやがてあの街からいなくなってしまった。一方で変わらずキャンパスで風に揺られるいちょう並木は、きっと当時のおれたちのような学生たちの悲喜交交を見守っていることだろう。
おれとスズキはそれぞれ別の職種について離れ離れになったが、半年に一回くらいか、そのくらいのペースで顔を合わせてあの頃と比べて多少なり背を伸ばした話をしたり、思い出話に花を咲かせたりしている。10代〜20代前半の、人格が形成される只中にあって、イケてなかった時代を共有してきた友人というのはかけがえのない宝物だ。手垢のついた言葉だが、ほんとうにそう思う。
スズキは最近結婚をした。少し年上だがなんとも面倒の見がいがある、兄のような弟のような人だと言う。あのころ「東京」というプレイリストを作って聴いては涙を流していると言っていたいかれたBabyことスズキの学生時代を思い返しては、おれは両手を広げて喜ぶ一方で少し寂しく思いながら、でもやっぱり祝福している。そんな感じです。
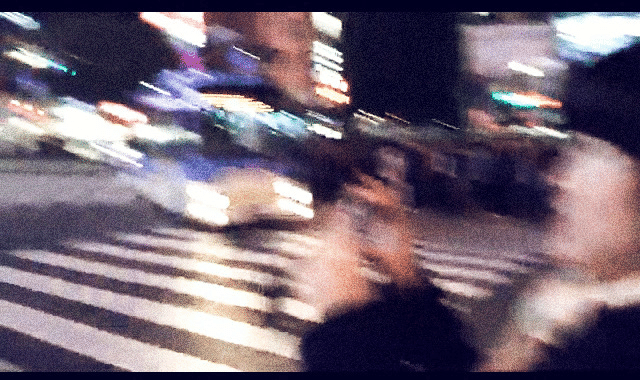
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
