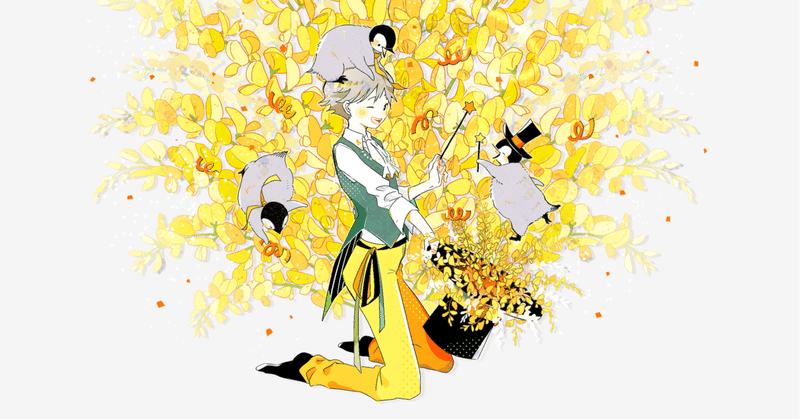
「悩みすぎ」のぼくが自分にかけた、「行動」への地道な反転魔法。
どうも、けんたです。
ちょっとわかりにくいタイトルなんですけど、今回は「悩みすぎ」で全く何も動けていなかったぼくが、「行動」しまくっているくらい動けるようになった理由をお話しできたらと思います。
書くきっかけとしては、ある方になんで悩み過ぎて全然何もできなかった状態から、ここまで活動的になれたのかが知りたい、と言われたからです。
確かに、今の自分は「活動的」という評価をもらうことはたくさんあります。まだまだ全然できてない部分も多いですが、どうして「活動的」になっていったのかについて、深掘ってみたら面白いなと思いました。
ちなみに、この前書いた話の人生の裏側的な話になっています。
どうやったら「行動」できるようになるのか
結論を言いたいところですが、実際に変化が起きたのは、さまざまな要因があると思っています。元々の能力、環境、出会った本や記事、それらの混ぜ合わせによって起きた、偶然性の高いものな気がします。
成功者の語る「成功法」みたいなものは、きっと生存者バイアスがかかっていることでしょう。
今回の記事も例に漏れず、生存者バイアスがかかったまま話していきます。
それでも何か気づきがあれば、幸いです。
脱出したいけど、何もできない、悩みがぐるぐるしているという状態の僕が、やったこととしては、「できることをしよう」でした。
「できることをしよう」は「行動」への反転魔法として、機能した例な気がします。
「できることをしよう」をキーワードとして、読み進めていただくと面白いかなと思います。
めちゃ悩むし、活動的になるなんてありえなかった。
まず、変化を話す前に、元々どんな状況だったのかをお話しできたらと思います。
すごくわかりやすい属性としては、典型的な優等生だったことです。学校の授業は寝ずにちゃんと聞くので、テストではいい点が取れますし、成績の評価も良かったです。模試よりも成績表の結果の方が良いような人でした。
しかし、イメージにもあると思いますが、典型的な優等生は、親や教師からの「これやりなさい」的な規範にとても従順なので、柔軟性がありません。僕はそのまま、それを体現していました。小中高は大体一貫して同じような感じでしたね。
学校が終わったらまっすぐ家に帰るし、友達に誘われても母親が少しでも嫌な顔をする可能性があったら、なんとなく断ってました。
学校では授業を聞いたり、言われたことに従ったりするのに疲れるので、帰ってからはぼーっとテレビを見ていました。早く寝ないと怒られそうなのと、体力が持たなくて授業で眠くなって怒られそうなのを避けたいがために、21~22時くらいに寝てました。
規範意識が強いので、なんとなく周りの人とは感覚が合いません。友達もできないですよね。
正直、テストの点や成績はいいけど、何にも嬉しさとか楽しさとかは感じてなかったですね。ただただ耐えるのが辛かった。しかも、辛いと思っているのに抜け出そうとして行動しない、できない自分自身に対して、一番怒りとか虚しさを感じていました。
当時の悩みを再現してみると、
やらなきゃ → 苦しいけどやるか → なんとかギリギリ終わった、疲れた → 疲れたから何もやる気しない → ちょっと休む → あれやらなきゃ → 苦しいけどやるか → …
この無限ループでしたね。今も完全に抜けたわけじゃないですけど、これは辛すぎます。何より突破口が見当たりません。デフレスパイラルです。
振り返ってみると、すごい動いてた
一転して、今の僕はどうなんだろうと振り返ると大きく変わってるなと思いました。
参考までに僕の今月やったことをリストにしてみます。
就活の面談・面接合わせて26回
インターンを40時間くらいした
noteを6つ書いた
情報処理学会で発表
オフ会に3回参加
日帰り旅行に行った
コンサートに行った
2泊3日のスキー合宿に行った
イベントバーのバーテンやった
自分が振り返ってみても、めちゃくちゃやってるやん!すご!って思ってます。
実際に大きなウェイトとしては、就活とインターンですね。
それに追加して、遊びもやればnote書くのもするし、初めてバーテンやったりもします。ほとんど全てのことが、誰かからやれって言われたり、やらないと怒られたりするものじゃないです。
就活とかも、絶対こんなに受ける必要もないのですが、割と楽しく面談しているところはあります。
こんな感じで、「悩み過ぎ」で動けない、規範にとらわれすぎて動けない、辛い、みたいな状態からは抜けて、面白そうなもの、やってみようかなと思うものに対して活動的になれてきているのかなと思います。
それでは、ようやく本編に行きます。どのようにして変化していったのか。できれば全ての要素を書きたかったのですが、とても難しいので、すごく厳選して選びました。お楽しみください。
大きな変化のポイント
電車と図書室。
タイトルには書いてないですが、1つ目の変化ポイントです。
僕は、実家から行くだけで、1時間くらいかかる高校に行きました。
その間の40分くらいは電車に乗っている時間だったのですが、居心地のいい場所でした。
なぜかというと、小中までは、家か学校かクラブチームの3択しか居場所がありませんでした。そのどの場所も、母親、教師、監督がいるので、規範意識からは抜けることができなかったです。やらなきゃ、みたいな意識から逃れられなくて、ずっとキツいままでした。
しかし、電車という空間においては、基本的に誰も話しかけてこないですし、干渉してきたりしないので、好きな本を読んでいても、スマホ使ってネットの記事を読んでいても怒ってきたり、何か押し付けてきたりしません。
なので、電車の中では、僕がある程度自由でいられる空間で、オアシスのようなものでした。
こうなることは、高校に入る前は全く予期していなかったので、自分の感覚的には偶然でしたね。
もう一つの居場所としては、図書室がありました。
これも電車と同じような理由で、規範的なものを押し付けられることのない、居心地の良い空間でした。
進学校ということもあって、テーブルには仕切りがあって、それぞれが集中して勉強しやすいような環境になってました。
僕はそこで本を読んだり、こっそり携帯でネットの記事を見たりしていました。
本やネット記事のいいところは、相手が干渉してこないことです。自分が好きなときにやめていいし、気になるところはたった1文について何時間かけても何も言われることはありません。好きなだけ無視してもいいし、好きなだけ気にかけてもいい。そんな関係が良かったです。
夜と霧。
タイトルには書いてないですが、2つ目の変化ポイントです。
自分に大きな変化が起きた本として、あえて挙げるとしたら「夜と霧」になります。
この本は、アウシュヴィッツ収容所に閉じ込められたユダヤ人の精神科医、ヴィクトール・E・フランクルが、
生き抜いて、運よく解放されるまでの、実話です。
アウシュヴィッツ収容所での、もはや生活と言っていいのかわからないほどの生活はすごく悲惨なものでした。
与えられる食べ物は少なければ、寝床の環境も悪い。昼間にやらされる労働もとても過酷。さらにはいつ殺されるのかわからないという不安もある。
そんな状況下で、フランクルが希望を持ちながら生き続ける様子を見ることができました。フランクルの言葉で印象的だったのは、この言葉です。
私たちが人生に意味を問うのではなく、人生が私たちに意味を問いかけているのだ。
なんかこじつけのような気もするのですが、辛い状況下でこれを思っていたことを考えると、人間の体に効くいい言葉なのかなとも思います。
この本を読んで、ここまで辛い状況でも人間は生きられるんだと思いました。
自分の今の状況はとても辛いし、動かし難い事実であるんだけど、流石にこの状況よりは絶対マシだと思いました。
そこから、僕はどんなに絶望的な状態でも、もっと絶望的な状態があることを知っているということで、少し前向きになれた気がします。
「夜と霧」を読めば、おそらく自分は前を向けるだろうという感覚があったので、行動へ目が向くための動かない指針として、心の中にあり続けています。
16歳、リスタート。
何かできごとがあったわけじゃないですけど、日記にそのときの気持ちと、どんなことをやっていきたいかが書いてあったので、のぞいてみましょう。
全く編集せずに載せてます。句読点の位置も。誤字も。意味わからない展開も。
16歳、リスタート。
これからは、自分の選んだ道を進もう。
もちろん、全部が全部という訳にはいかない。
それでもなんとか割合を増やしていこう。
自分というのは正確にはわからないけど、なんとなくならある。
そのなんとなくを深り下げよう。
ゆっくりでいい。少しずつでいい。
できる範囲でいい。もちろん無理するときだってあってもいいんじゃない。
少数派。だからって別に偉いわけじゃない。
言葉遣いを丁寧にしよう。
もちろん できることをこつこつと。
この日記を書いていたときは、辛い状況だったことは覚えています。それでも前を向きたいと思って、背伸びしつつも、それでも自分の感覚に合った言葉で前を向けないか考えていましたね。
「深り下げよう」は絶対「掘り下げよう」だし。「言葉遣いを丁寧にしよう」とか文脈を無視して意味わかんないけど、なんかすごく自分の思考回路っぽいなって感じます。
ほぼ日刊イトイ新聞。
3つ目の変化ポイントです。
大きな影響を受けたwebサイトとして挙げたいのが、
「ほぼ日刊イトイ新聞」というwebサイトです。
糸井重里さんを主体として、ほぼ日という会社が運営しているものです。
いいところを挙げるときりがないですが、あえて挙げるとすれば、webサイト全体から温かみをすごく感じるところですかね。
webサイトの色味や配置もそうですし、今日のダーリンの内容も、他の記事のタイトルや内容も、節々から温かみを感じます。
僕は特に、対談記事やインタビューの記事をよく読んでいました。色々な世界について知ることができましたし、学びが多かったです。
ほぼ日の目玉商品として、ほぼ日手帳というものがあります。それを高校1年生のときの夏から、大学に入るまで使っていました。
ちょくちょく出てくる日記の話は、全てほぼ日手帳に書いてあるものです。
いいところとしては、毎日のページの下に、誰かの言葉が書いてあることです。
「ほぼ日刊イトイ新聞」の記事の抜粋なのですが、気づきがあります。
これをきっかけにweb記事に戻って、読むのが面白いので、おすすめです。

ここで、1つ紹介したい文章があります。高校1年の2月の初めのページに書いたときから、今もずっと影響を受け続けている言葉です。
「できることをしよう」というのは、
いつごろからか、ぼく自身を励ますことばになった。
「できること」を、よく探して、
「できること」を、よくよく見つめて、
おそるおそるでいいから、やること。
「するべきこと」や「できないこと」を数えていたら、
どうしたって、悲観的にもなるし、
なにかをすることが虚しくなるだろう。
「できることをしよう」というのは、
愚かに思われるくらいちっぽけな者の結論かもしれない。
それで、いいじゃないか、と思えたのは、
たった数年前のことだった。
「できることをしよう」が、
ちいさいままで終わるとはかぎらない。
ちいさいはじまりが「できること」だったら、
当然、ちいさいことしかできないけれど、
それは、足し算されたりかけ算されたりして、
大きく育ってしまうことだってある。
ちいさくあることは目的でもないので、
「できることをしよう」は、
大きく育つことを禁じたりはしない。
「できることをしよう」が指針となったきっかけはここです。日記に書いてあったのもこの文章を読んでから考えたことだったと思います。
少しずつできることをするということにはすごく効力がある気がするし、辛い自分でも余裕が見えた一瞬の隙に、できることを少しずつやっていけばいいんだと思えました。
「思えば、孤独は美しい。」という本はこんな感じで色々発見のある言葉が書いてあるので、気になった方はぜひ読んでみてください。
僕は、ほぼ日を通して、感情を学んだ気がします。
どんな感覚でいれば心地良くなって、いい感じに生きられるのか。言語化は難しいですけど、文章の言葉の選び方や文体、句読点の使い方や、間の取り方。タイトルに「。」をつけるこだわり。そういったものから、感情の育み方を深く体験しました。
僕の文章へのこだわりや熱量はここから来てるのかもしれません。
メンタリストDaigoさん。
4つ目の変化ポイントです。
高校時代や自分の人生を語る上で、メンタリストDaigoさんの存在は欠かせません。
おそらく、人生が変わった理由の7割くらいはDaigoさんのおかげと言ってギリ過言くらいです。
Daigoさんからは、合理的に考えて、いろんな研究を参照して、どのように人生を生きたら良さそうなのかを学びました。Daigoさんが自分をメンタリズムできてないとか、なんか変じゃね?っていう批判とか見方があるのもわかりますし、自分でもちょっと思う部分もありますが、学んだことは多かったです。
高校2年生のときくらいから、ニコニコでDaigoさんのチャンネルの有料会員になって動画を見続けていました。
おそらく、1週間で20時間くらい見るのを何ヶ月も続けていたと思います。頭の中で仮想のDaigoさんが喋ってくるくらいには見てました。ほとんど洗脳みたいなもんですね。
家族からは、変な宗教にハマっているみたいと言われて毛嫌いされていました。その節は否めませんね。
正直、いい動画はたくさんあるのですが、これはめちゃくちゃ転機だったなと思う動画をいくつか紹介します。有料会員じゃないと見れないのもありますが、ご了承ください。
1つ目:無料:完璧主義と自己批判が先送りの原因! 自分を許して即やる人になれるセルフコンパッションの鍛え方
完璧主義と自己批判があるから、先延ばししちゃうよ、セルフコンパッションが大事だよっていう動画です。
セルフコンパッションに関する考え方は、今でもずっと心に残っています。自分を許すことで、できることは多いです。行動するとかのためには、すごくよく効いたと思います。
2つ目:努力がクセになる性格に変わる「成長マインドセット」入門
この動画はまじで、超いい動画です。「成長」とか「行動」とかに興味がある人限定ですが笑。見るだけで、脳に変化が起こるくらいスゲーです。何回も見返しました。有料ですが、これはぜひ見てほしいですね。
3つ目:フツーの才能で成功するための【幸運のつかみ方】〜成功に必要な7つの力
この動画は僕の人生を一番変えた動画かもしれません。
自分が、大学時代に色々な人と会って、いろんな体験をしてみようと動くきっかけになった動画ですし、今もなお大きな指針としてあります。
就活でも、ここに出てくる話をよくしています。
運をよくするにはどうするのか、運とはなんなのかをあくまで合理的に、説明された動画です。
内容については深く触れて良いのか迷うので、ぼかしておこうかなと思います。あえていうなら、「試行回数を上げよう」ってことです。その効果は色々あるけど、すごいよねって話です。
動画は有料ですが、この動画の説明欄にある本を読むだけでもめちゃくちゃ勉強になると思います。
オススメ本のリストにはこれが載ってました。
▶︎オススメ本
運は操れる を Amazon でチェック! https://amzn.to/37xmNuA
リチャード・ワイズマン博士 の 運のいい人の法則 を Amazon でチェック! https://amzn.to/36AfMbg
ロバート・H・フランク の 成功する人は偶然を味方にする 運と成功の経済学 を Amazon でチェック! https://amzn.to/2O6HQMW
ロバート・H・フランク の 幸せとお金の経済学 を Amazon でチェック! https://amzn.to/2Gxys0A
ダンカン ワッツ の 偶然の科学 Amazon でチェック! https://amzn.to/3aPzPWr
これだけじゃ本当に語り切れないほどですが、少しでも伝われば幸いです。
悩みに悩んでても、現実は1ミリも変わらなかった。
小、中学生のときから、なんかキツイなって思いはずっとあって、なんとなくずっと悩んでました。偉人の本を読んで、やる気は出てくるんですけど、結局辛い状況は変わらなかったです。
高校生のときも、電車での自由な時間を過ごしたり、図書室で本を読んで、いろんな人の考えを知ったりしても、やる気は出てきて無敵な感じはしてくるのですが、現実はすぐには変わりませんでした。
疲れて、やらなきゃって思いで苦しみながらやって、疲れて、また苦しみながらやる。ときたまふと時間ができて、俺って何やってんだろうって悩む。考えに考えて、本読んで、webの記事読んで、ほぼ日に感化されて、Daigoさんの動画を浴びて、なんでもできるような気がして。そんなことを繰り返しててもほとんどの状況は変わりません。
この経験を散々ループしていったからこそ、何か動かないと現実って変わらないんだなってことをありありと体感することができました。
そんな変わらない辛さの中でも、少しずつ自分の肌に合う考えを見つけていこうとか、睡眠時間を一定にしようとか、日記書こうとか、瞑想やろうとか、ほんのちょっとずつやっていったことが、今の大きな変化に繋がっているなって思います。
TwitterとZOOM。
5つ目の変化ポイントです。
行動面における一番の変化だったのはおそらく、大学に入った当初でしょう。
コロナウイルスが流行して、始業が4月から5月になってしまうほど混乱していた時期です。僕は知り合いの全くいない大学に入ることが決定していて、ただでさえ友達がいないのに、知り合いすらいない状況に追い込まれそうでした。
危機感があったのと、運を良くするためには試行回数を増やす、つまり行動を増やしたり人にあう量を増やすことがいいことはある程度わかっていたので、なんとかして人との繋がりを作ろうとしました。
まず、やったことのないTwitterのアカウントを作り、同じ大学の同じ学部の人と繋がれないかを考えました。
「#春から〇〇大学」みたいに検索して、同じ学部と思われる人には片っ端からDM送ったり、リプを送ったりしていました。このときの学生は、つながる方法がTwitterかInstagramくらいしかなかったと思うので、今思うと正解の行動をしてたんだなって思います。
DMでやりとりしたり、リプを送ったりしていると、ZOOMに誘われるようになります。そこで、よりたくさんの人と知り合っていきました。また、夜遅くまでZOOMをして関係を深めていきました。
このとき母親とか父親に、夜遅くまで話していてうるさいと怒られたのですが、そんなの関係ないくらい楽しくて、初めての経験でした。
後から気づいたのですが、僕は対面で会うときに、どこ見たらいいのかわからなくなることや、声が小さくて相手に内容が伝わらないことが多いことに気づきました。なので、そもそもオフラインがとても苦手で、ハンデがありました。しかし、オンラインだと、見るのは画面だけでいいし、無理して目を合わせなくていいし、マイクに近付いていれば声の音量は気にしなくても機械がやってくれます。
時代とタイミングが完璧に噛み合ったおかげでここまで来たんだなというのを感じます。
おそらくこのような偶然がなければ、僕は今もなおずっと悩んだまま、どうやって行動したらいいかわからないで、辛いだけの人だったかもしれません。
改めて、自分は運がいいなって思います。
一人暮らし。
最後に、6つ目の変化ポイントです。
僕は、すぐにでも実家から飛び出したくて機会を伺ってました。
実際にもう6月の頭には引っ越してきました。
そこからはもう生活が一変しましたね。まず、親がいない。物理的にすぐ来れるわけじゃない。これがとても大きかったです。
電車と図書室の話がありましたが、それが24時間に変わるわけです。信じられないくらい心が開放的になったのと、行動力が何倍にも膨れ上がりました。
元々小さい村に住んでいたということもあって、近くにコンビニやスーパー、駅があるのも新鮮で、自転車ですぐ行ける距離に友達の家がたくさんあるのもよかったです。
今までオンラインで話していたのが、リアルになるので、経験できる量が段違いになってきました。しかし、リアルは苦手だということがちょっとずつわかってきたので、居心地のいい場所を見つけるのには苦労しましたけど、高校の時と比べたら信じられないくらい充実していましたね。
引っ越してきてからは、本当に絶え間なく動き続けていたように感じます。楽しくて居心地がいい場所なので、実家には全然帰りたくなくなるくらいです。
僕にとって、両親からの影響がどれだけ大きかったかがわかりました。正直ここまで楽しいとは思ってもみなかったので、実家から出てみたいと思っている方の参考になれば嬉しいです。
実は大事な基礎能力。
もうすぐ締めに入ろうと思いますが、その前に1つ伝えておきたいことがあります。
それは、なんだかんだ言って基礎能力は大事だよねって話です。
僕の場合は運が良くて変化が起こったと思ってますし、波に乗れればどんどん変化していくとは思っています。しかし、基礎能力がないとチャンスに恵まれたときに、波に乗り切れないだろうなとも思います。
振り返ってみて、自分の場合はこれが大事だったなという基礎能力は2つほどあります。
1つ目は、体力です。色々と動くようになってから、忙しなくいろんなことに手をつけていました。ZOOMに出たり、友達の家に行ったり、学校でバイトしたり、ご飯食べに行ったり、たくさんのことを並行してやっていました。改めて考えると、体力がついてないとできないことだったなと思います。
小学校4年生のときからバスケのクラブチームに入ってバスケをしていました。高校3年生まで続けているので、体力はかなりついたと思います。体力をつけるというしばきを経験したおかげで、今の活力があるのかもしれないと思っています。もしかしたら、バスケに耐えるだけの体力がもともとあっただけなのかもしれませんが。
2つ目は、ある程度の器用さです。器用さがあったおかげで、人となんとなく合わない、ということ以外のことはなんとなくやればできました。なので、動き始めたときに割と上手くいきやすかったのかなと思います。もし、不器用さが大きかったら、もっといろんな壁にぶつかって苦労していただろうなと思います。
もちろん、器用であることは、あながちいろいろできてしまうがために、親や教師の期待になまじ応えられてしまって苦しむ原因でもあったなとは思います。
以上の2つの能力が備わっていたからこそ、できたことが多いです。
それぞれ、環境や持ってる能力は違うと思うので、自分の能力に合わせた戦略を持ってやることが大事なんだろうなと思います。
反転魔法の正体。
ここまでの長い文章にお付き合いいただきありがとうございます。
改めてタイトル回収をしようかなと思います。
そもそも、「反転」の意味としてはひっくり返すという意味があります。「悩みすぎ」て動けない、ということや、やらなきゃといったある種の「呪い」があって全然動けない、という状態から、活動的になるくらい動きまくっている、という状態にひっくり返ったという意味で使っています。
また、「悩みすぎ」ている状態というのはエネルギーがずっと内向きになっている状態です。なので、「活動的」な状態になることでエネルギーが外向きになっているという意味でも「反転」が起きていると考えています。
「魔法」としているのは、当時の辛かった自分から考えたら想像もできないほどの変化が起きたということから、今までやってきたことを総合すると、魔法のような効果を持つものだったと思ったからです。
つまり、『「悩みすぎ」のぼくが自分にかけた、「行動」への地道な反転魔法。』というのは、
『動けない状態から動ける状態にする、もしくは内向きのエネルギーを外向きのエネルギーにするための、魔法のような考え方や、知識や、ちょっとした行動』
のことを言っています。
最後に、「反転魔法」についてマクロ的な視点でみてみましょうか。
これまで書いてきたのは、あくまで「悩みすぎ」のぼくの視点で書くようにしてました。ミクロの視点ですね。
それではマクロな視点でみていきます。
今回の話を一言でまとめると、「エネルギーの流れる方向を変えた」という話です。
ここでいう「エネルギー 」とは、自分が持っている能力とか、あなたなら自然にできることを指します。阿吽さんを知っている方なら、「真」というとわかりやすいですかね。
「エネルギー」はおそらく水のようなもので、ある程度の方向性が決まっていないと、流れすら起きずに散らばってしまうもののような気がします。
「悩みすぎ」だった僕は、両親や学校などからの規範である、これをやらなきゃいけないとか、これをやるべきだという考えが、壁や衝立てのようなものとなって、内向きだったり、規則や意向を遵守したりすることにエネルギーが流れていました。
そういった一種の呪いのようなものを取り除きつつ、また新しい考えや呪い、壁のようなものを使って、エネルギーが流れる方向を変えて行きました。
新しい考えや呪い、壁のようなものが、ほぼ日刊イトイ新聞やメンタリストDaigoさんの動画でもあります。
ときにはエネルギーの性質を知ることも大事でしょう。自分の能力や当たり前にできることを見つめて、どういうところなら強みとなるのか、もしくは弱みとなるのかがわかるので、エネルギーの流し方や方向づけの仕方が上手くなってくると思います。
どういう方向にすればいいのかを選んだり、決めたりするのに悩むかもしれません。僕もどこにエネルギーを向けたらいいのかわからなくて、とても悩んでいました。
これはあくまで僕の場合ですが、自分の感覚がよりどころでした。阿吽さんを知っている方なら、「美」というとわかりやすいですかね。辛いと思うことや心地いいと思う感覚を1つ1つ照合していって、心地いいと思う方に行けるようにやってきました。
これがいいという考えは、その人が考えた、その人が見た世界、経験したものの中の最適解にすぎないと思っているので、僕の場合は自分の感覚を一番信じたということです。
この辺の話は一種の宗教的な話で、何を信じるのかという話なので、また別の記事にできればと思います。
総じて言えることとしては、自分がいいと思う行動するためには、
いろいろな人のこれをやらなきゃとか、これをしないとダメだとかいう規範、呪いのようなものを取り払いつつ、新たな居心地の良い規範や呪いを自分の感覚をベースにして選ぶことで、自分が当たり前にできることや得意なこと、ついついやってしまうことを方向づけて行動していけばいいんじゃないか
ということです。
阿吽さんの言葉を借りて言うと、
「善」を解除しながら、「美」を評価基準として新たな心地いい「善」を定めた上で方向を決めて、「真」を流し込んで大きくしていくのがいいのではないか
ということです。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。
以上で、『「悩みすぎ」のぼくが自分にかけた、「行動」への地道な反転魔法。』についてのお話は終わりです。
今回もかなり長文でしたが、最後までお付き合いいただきありがとうございます。
もしよければ、スキやコメントいただけると嬉しいです!
ここの部分の話を詳しく聞きたいなどあれば、ぜひお話ししましょう!
コメントなどでいただけたら、今後の記事として書くかもしれません。
それではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
