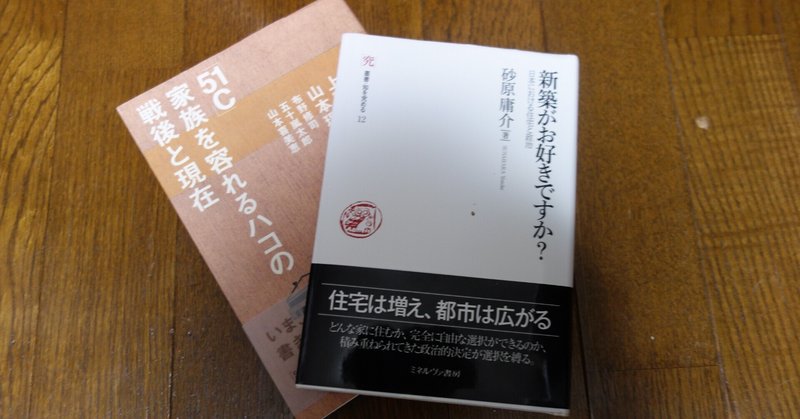
理想のキッチン探し㉘歴史編・住宅の戦後史
キッチン、キッチンと言い続けていますが、キッチンは単独で存在するのではなく、住宅の中にあります。当たり前ですが。キッチンを成立させる住宅がどういう歩みをたどってきたのか、戦後史を調べてみました。
『新築がお好きですか?』は、日本の住宅市場がいかに非効率で、個人負担が大きい方向に進んできたのかを明らかにする本です。サブタイトルに「日本における住宅と政治」とありますが、まさにその通りで、家族が暮らせるそこそこのサイズの首都圏の賃貸物件には、なかなかまともなキッチンが設置されていることが少ない。その理由が、この本を読むとわかりました。
これまでも建築家や建築史家が書いた本を読む機会はあったのですが、その中で気になっていた主張が、「日本は良質な賃貸住宅の市場を作ってこなかった」というもの。持ち家政策を推し進めたために、賃貸住宅が貧しいものになってしまった、といった内容だったと思います。確かにそうです。私たちはいつも予算が少なく、お値打ち物件ばかり探してきたためか、変な間取りや、使いにくいキッチンにぶつかることが多かった。
大阪で私が一人暮らしした部屋も、コンロ置台をちょうど実家を修繕していた大工さんが作ってくれなかったら、調理台かコンロ置台がない極小キッチンでした。東京で夫と最初に住んだ部屋は、一応はコンロが内蔵された「システムキッチン」だったものの、ミニチェストなどを置いたら冷蔵庫置き場がなくてダイニングの入り口あたりに置くしかなかった。次に住んだ部屋はやたらと低い位置にある換気扇の1列型セットキッチンでした。今回は調理台の後ろに棚を置いたら二人で作業できない狭さ。
結局、日本の政府はほかの政策でも見られるように、基本的に自活せいよ、という方針で、住宅への補助もあまり行わない。そのうえ、戦時中に居住権を非常に強化してしまったために、家賃のとりっぱぐれなどのリスクを恐れる貸主が賃貸住宅にあまり投資をしないようになったといった内容が紹介されていました。
また、持ち家は生涯住む前提になっているのも不自然だと指摘します。子供が独立した後、大きすぎる住まいを持て余す高齢者は多い。それから、私が今回物件探しをしていて感じたのは、住み手がカスタマイズしすぎた部屋は他の人が使いにくいこと。キッチンが充実していた部屋はたいていカスタマイズしすぎていて、私は使いにくいと感じて契約に踏み切れませんでした。
人はずっと同じ価値観、ずっと同じライフスタイルを生涯持ち続けることはありません。結婚や出産、育児、介護などが入ってきたりなくなったりすることは多い。働き方だって、転職や失業などで変わります。定年まで会社員、と思っていた人だって、コロナ禍でリモートワークになったりしています。2010年代後半のリノベの流行に、和室などをつぶし部屋数を減らしてキッチンとリビングを巨大化した例が多かったのですが、そうした広いLDKで暮らしていた人たちは、その後夫婦でリモートワークになったりしたらどうしたのでしょうか。あるいは、小さいお子さんがいるのに合わせて、寝室をひとまとめにした事例の人たち。お子さんは大きくなったら個室が欲しいと思うのではないでしょうか。子供の数も増えるかもしれません。
部屋の数、部屋の面積だけを考えても、ライフスタイルが変われば必要なものが変わります。高齢になって、掃除がめんどくさくなったときに、一人で4部屋もあるような住まいはめんどくさいでしょう。冷暖房も行き届きません。私みたいに、どんどん資料が増える文筆・研究系の仕事も、いくら面積を増やしても追いつかない、という問題を抱えています。
リノベ事例のある程度パターン化された雑誌の記事でも、それなりに多彩なニーズを満たすための間取りの改変が行われています。みんな同じを前提にしたマンションや建売住宅はたくさんありますが、それが本当に必要なのでしょうか。
そういう問題を考えたのが、『51C 家族を容れるハコの戦後と現在』。もともと上野千鶴子さんと山本理顕さんが対談した『家族を容れるハコ 家族を超えるハコ』がもとになって、2004年に発売された本です。nLDKというフォーマットに日本の住宅は縛られすぎではないか、と上野さんは、新聞などが「標準家族」と呼び、社会学用語で「近代家族」という、両親と子供の核家族への批判を込めて論じます。一方、51C という2DKを作った鈴木成文さんは、その後のnLDKは、食寝分離などを極小の当時の公共住宅で実現するために工夫したものに、単に部屋数を増やしてつけただけだ、と言い、上野さんの批判を不快に思っているようです。喧々諤々の議論が面白い。
nLDKの呪縛は確かにありますが、だったらどういう間取りがあり得るのか、人はどういう間取りを求めているのか、その多彩な事例をもう少し具体的に知りたい、と私は思います。発想が貧困なのか、結局今回も個性的な間取りも見つつ、家具や収納をあまり買い足さなくて済み、ニュートラルに使える、と一般的な3LDKの新しい部屋へ移ろうとしている私です。標準家族でもなく、勤め人でもなく、いわば個性的なライフスタイルを送っているにもかかわらず。
ただ、今回ほかの条件が満たさず選ばなかったのですが、「いいな」と思った間取りの部屋は、廊下は玄関横に少しだけで、あとの部屋はLDKを囲むレイアウトになっているものでした。よくあるマンションの暗い中廊下は、近代に掃除が大変な縁側をなくしたときに作られたものなんですよね。廊下があるおかげで使えない面積が増えるし、育ち盛りの子供がいるわけでもないので、部屋のプライバシーはそれほど必要ない私は、廊下は玄関周辺のみの部屋がいいなと思いました。廊下が最小限欲しいのは、仕事柄、宅配分などの人がよく来るので、部屋の中が玄関から見えないほうがいいと思うからです。
キッチンは、できればその短い廊下の先、最初にある部屋であってほしい。買い物した食材などを置けるからです。そして、できれば流しの前に窓が欲しい。今回はないけれど。お客さんはたまに来てもらうけれどめったにないので、独立型がいいかな。隣にパントリーが欲しい。仕事部屋は玄関に近いほうに、寝室は奥のほうに。こう考えると、廊下不要以外はだいたい標準間取りで満足、という感じになります。そういう部屋でしか暮らしてこなかったからかもしれません。長年の経験とは異なる新しい発想を持つには、もしかすると異なる間取りを経験する必要があるのかもしれません。お金も時間も限られる中、どこまで発想の幅が広がるでしょうか。
いずれにせよ、貧弱な住宅政策と、効率的な商品開発を行ってきた関連業界、という視点はどこまで有効なのか、これからも新しい部屋で考えながら暮らし、検証していきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
