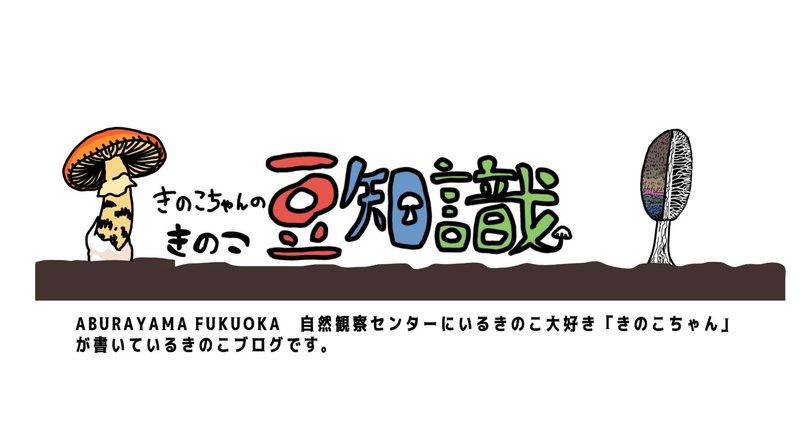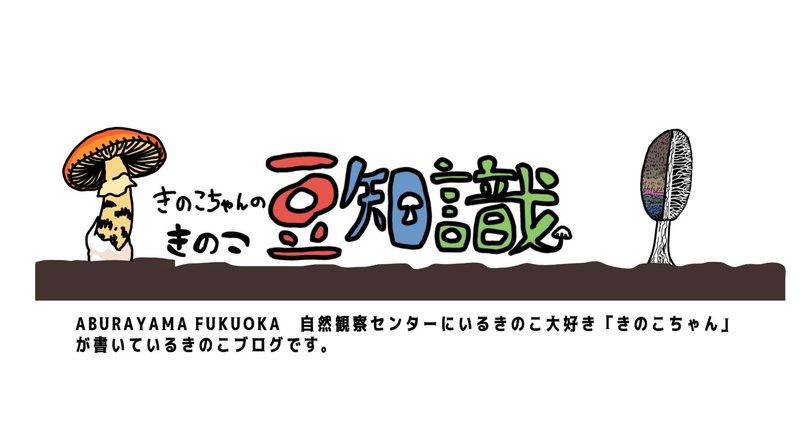きのこ豆知識 きのこの役割
自然界での役割きのこを含む菌類には、さまざまな生活型が知られています。
動植物の死がいを食べて育つ腐生菌のグループは「分解者(お掃除屋さん)」として知られています。また、生きた植物と「共生関係」にある菌類もいますし、生きた動植物から一方的に栄養を奪って生きている「寄生菌」と呼ばれる菌類もいます。
もし「分解者」である菌類がこの世界にいなかったら、本来土にかえるはずだった動植物の遺体は形を残しそのまま森の中に置き去りにされ、悪臭を放ちながらどんどん増えていたのかもしれません。