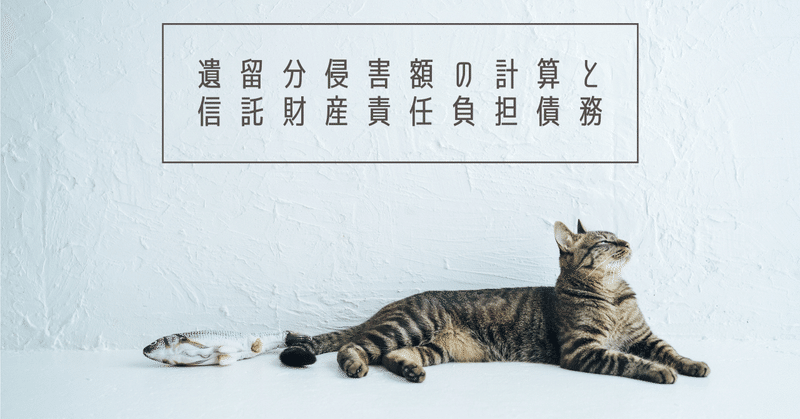
遺留分侵害額の計算と信託財産責任負担債務
1 はじめに
信託をよく取り扱う司法書士の先生からご質問があり、議論していたことなのですが、せっかくですので、noteにまとめておきたいと思います。
本記事は、信託を取り扱う士業向けです。
ある信託が遺留分を侵害する場合において、信託財産責任負担債務が存在するとき、遺留分侵害額を計算する上で、その信託財産責任負担債務は控除できるのか、という話をしていました。
例えば、Aを委託者兼受益者、Aの推定相続人の一人であるBを受託者(A死亡後は第二順位受益者)、Aが所有していたアパートP(土地と建物)を信託財産とするAB間の信託契約が締結され、Bが、信託事務の範囲においてPの修繕のために金融機関からそのPを担保に資金を借り入れたが、まだ返済が残っている中で、Aが死亡したところ、他のAの相続人CがBに対し、遺留分侵害額請求をしたような事例が考えられます。
2 遺留分侵害額の計算
遺留分侵害額は、次の計算式で求められます。
①遺留分算定の基礎となる財産額 ー ②遺留分権利者が相続で得た財産 + ③遺留分権利者が負担すべき相続債務
そして、①遺留分算定の基礎となる財産額は、次の計算式で求められます。
㋐相続開始時の財産価額 + ㋑贈与した財産価額 ー ㋒債務の全額
これは、最判平成8年11月26日民集50巻10号2747頁で明らかにされた考え方であり、先般の相続法改正により、改正後民法1043条1項、1046条2項1〜3号に規定されています。
3 信託財産責任負担債務とは
信託財産責任負担債務とは、受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務をいいます(信託法2条9項)。
信託財産責任負担債務は、信託法21条1項1〜9号に列挙されています。
例えば受益債権に係る債務(1号)、信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属するものにる債務(5号)、信託事務処理について生じた権利に係る債務(9号)などがあります。
冒頭の事例において、Bが、信託事務の範囲においてPの修繕のために金融機関からそのPを担保に資金を借り入れたことによる借入債務は、5号か9号により信託財産責任負担債務に該当すると考えられます。
4 遺留分侵害額の計算で信託財産責任負担債務は控除できるのか
(1) 通常の遺言の場合との比較
例えば、冒頭の事例において、ABが信託契約を締結しておらず、Aが引き続きPを所有している中で、自己名義でPに担保設定して金融機関から借り入れ、Bに全財産を相続させる遺言を作っていた場合です。
BがCから遺留分侵害額請求を受けたとしても、金融機関からの借入残高は相続債務として、遺留分侵害額を計算する中で当然に考慮されるでしょう。
ところが、冒頭の事例の場合、上記事例と同様のことをしているものの、信託財産責任負担債務を負っているのは、名義上はAではなくBです。
そのため、㋒「債務」(民法1043条1項)には該当せず、金融機関からの借入残高は相続債務は、遺留分侵害額を計算する中で考慮できないこととなるのが条文上の処理結果となります。
(2) 何が問題か
実質的な効果が同様であるにもかかわらず、形式上信託のスキームを組んでいるか否かによって、一方は遺留分侵害額の計算上借入債務を考慮でき、他方が考慮できないのは、とても均衡を欠く結果であるように思われます。
そもそも、受益者連続型信託は、「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する」とされ(信託法91条)、相続による承継を前提とした条文の書きぶりになっていないにもかかわらず、立法者の見解もあって、相続を前提とする遺留分の対象となるのが実務の趨勢です。
その是非はさておくとして、実質を見て信託も遺留分の対象とするならば、債務の面でも単なる形式にとどまらずに実質を考慮して、結果の均衡を欠かないように解釈する必要があるように思われます。
そうしないと、冒頭の事例のような場合に、Cが不当に有利になり、Bが不当に不利になる結果を招来してしまいます。
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には、特段の事情のない限り、相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解されるとするのが判例の考え方です(最判平成21年3月24日民集63巻3号427頁)。
なぜ判例がそう考えるのか明示的な理由の記載はありません。
もっとも、包括遺贈や相続分指定の包括性に着目し、より多くを得た者により多くの負担を課すとの認識を基本としているのであって、それは通常、被相続人の意思に沿うものと考えられると指摘する論文もあります(久貴忠彦編著「遺言と遺留分 第2巻 遺留分〔第2版〕」64頁)。
要するに、相続人間の公平が根底にあるのだと思います。
(3) どうしたものか
とはいえ、信託財産責任負担債務は、信託法21条1項1〜9号に掲げられるとおり、その発生原因には様々なものがあり、一律に遺留分侵害額の計算上考慮できる or できないと決め付けることはできないと思われます。
結局のところ、信託スキームではない通常の相続の事例との均衡を考慮して、その類似点や相違点を双方の立場から主張立証していきながら、個別具体的に決まっていくほかないのかなというのが、今日時点での考えです。
なお、冒頭の事例でいう借入債務は、(ⅰ)遺留分侵害額の計算の中での「㋒債務の全額」として考慮するのか、(ⅱ)「㋐相続開始時の財産」である受益権の評価として考慮するのか(負担が内在する権利)、いずれの判断枠組みを設定するかには検討の余地がありそうです。
とある民事裁判官、公証人出身の弁護士の先生と議論していてそのような指摘をされ、なるほどなと思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
