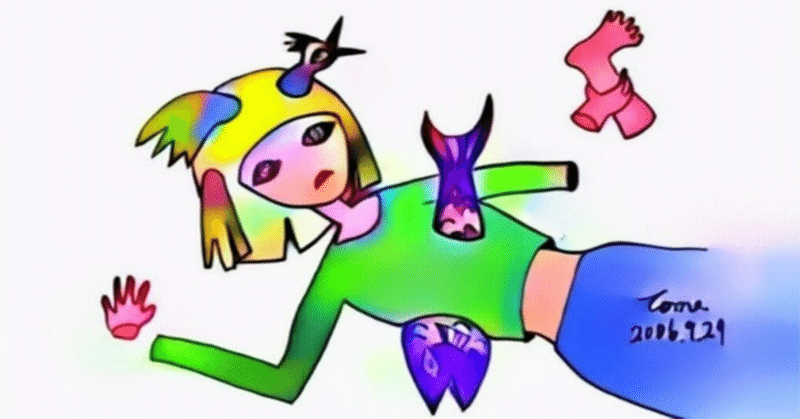
The Act of Killingと心の仮面
初めに
この映画は一言で言うと、認知行動療法ドキュメンタリーだ。
表現としてはこれまでにない、非常に新しい挑戦的な取り組みになっていると思う。
しかし、「映画」と言っていいのか正直なところよくわからない。
この映画はどんな映画なのか?
それは他にこの映画を鑑賞している☟の方たちが、色々な説明をしてくれているから、本noteでは背景情報の説明を省こうと思う。
※本noteはネタバレを含みますが、おそらくあなたはもうすでにこの映画を観ているだろうし、まだ観ていないのであれば今すぐに観てきてください。その気がないならおそらく一生観ないと思うので、このままnoteを読み進めてもらって大丈夫です。
他の方の鑑賞note
印象的なシーン
2つくらいあって、1つは放火と大虐殺を撮影するシーン。
具体的な名前とかは忘れたが、「共産主義者を皆殺しにしろ」という合図の下に、放火・殺人が行われるシーンがある。血がドバドバ流れるようなシーンは映ってないのだが、このシーンの撮影にパンチャシラ青年団に所属する(?)副大統領が立ち会っていることが異様だ。
主人公であるアンワル・コンゴ はおそらく、文字通り「虐殺」のシーンを生々しく「記録」=撮影したかったのだと思うが、副大統領はこれを「酷い撮影であり、本来の組織はこんなに血を好むようなものではない」みたいなことを言っている。
9月30日事件を彷彿とさせるようなイメージを放映するのは憚られるとの理由でこういう発言をしているのだと思う。まあ、立場的にもそうやって言うほかにないだろう。
他にも、虐殺部隊の主要メンバーアディ・ズルカドリらが9月30日事件の犠牲者の息子を、尋問シーンの被尋問役に選んだ時も印象的だった。このシーンやそれに続く車内での監督との対話シーンでは「すべてを真実として明らかにする必要はない」と述べており、アンワルとの見解の相違が垣間見える印象的な場面だ。
これは「歴史は勝者のためのものか?」という一般命題に還元される。
虐殺部隊はいわば「歴史の勝者」であり、今を生きる生存者である。
そんな彼らがあえて自分たちが不利になるような歴史を明るみに出す必要性は全くない。
しかしながら、当時虐殺された人々やその遺族は9月30日事件がアンタッチャブルなものとなっていることに対して、心の中では強い憤りや無力感を抱えていることには間違いない。
実際に前述の犠牲者の息子はリアルに涙を流しながら撮影を続けていた。
この映画を作成・公表することの意義、みたいなものは「歴史はだれのためのものか」という命題に関する話になるので、脇に置いておこう。
あなたは、どの立場に立つのだろうか。
ここで最初の言葉に戻る。
この映画は一言で言うと、認知行動療法ドキュメンタリーだ。
主人公のアンワル・コンゴは映画の冒頭では笑顔で拷問・殺害の記憶を語っていたが、最後には同じ場所で自らの行いの「サド」を自覚して嘔吐する。
アンワルは、「お前は精神病なんだ。俺ですら精神科に通ったんだ。お前も行くべきだ。」とアディに言われるほど長年悪夢に悩まされている。
監督のジョシュアさんがどのような意図でこの映画(?)を撮影したのかはわからないが、もしも虐殺部隊の彼ら―特に悪夢に悩まされるアンワル・コンゴ―を”治療”するような意図があったとしたら、それこそある意味で「サド」な表現手法だと思う。
この映画は、今では「普通の人」として暮らすかつての虐殺部隊の人々が「当時を演じる」ことで、記憶と歴史を相対化しつつ、自分のものとして消化して「しまう」一方で、その過去と向き合うことをやめる、もしくは自己の正当化を一層強める映画だ。
(まあ、カツアゲで青年団の集会を成立させている人間を「普通の人」と呼ぶのは大きな語弊があるだろう。)
現代を生きる私たちにもたくさんの「役割」があり、それは「心の仮面」として当然のものと受け入れられている。
そしてその「役割」を相対化して向き合うためには、一度私たちは舞台から降りて過去の自分が演じていたものが何だったのかを再び見返す必要がある。それは決して、舞台の上に立つ「演者」たちにはわからないし、さらに言えば「わかってはいけない」のだ。
わかってしまえばその瞬間に、あなたはたちまちに、その役割を遂行する「演者」としてはもう生きていけないだろう。
アンワルはそんな自分のことを
「こうしてout of lowの世界でしか生きていけない外れ者だ。そしてそんな人間は世界のどこにでもいる。」
と話していた。
彼らの行為を法的に・倫理的に肯定する気は全くないが、当時の彼らにとって「虐殺部隊」という演者になることは、「労働者」としての仮面をかぶって働くことと何一つ変わらないことだったのだろう。
今の彼らには数多くの家族がいて、楽しそうに暮らしている。
とすると、彼らにとって「虐殺部隊」としての仮面はあくまでも生活の一部でしかなかったのだろう。
私は個人的に、「仮面としての自分」を意識しすぎる癖がある。
これは演者にとっては最悪だ。
演者である自分でいる間は、それ以外のことは考えてはいけない。
脚本家として、自分の人生を彩る「私」という演者をどのように采配するか、そう考える時間はたまにもあっていいかもしれない。
しかしその時に、あなたは「演者」としての自分を過去とともに振り返ることになり、それは時に痛みを伴う。
何もアンワルだけが嘔吐するのではないのだ。
幼少期のトラウマに蓋をして、見ないようにすることもそれはアディ的な対処として一つの道である。
ここで善悪を論じるつもりはないし、そんなこと言いたくない。
面倒くさいし。
ここから先は
サポートはお魚ソーセージになります
