
『Angell Doll』まえがき──「それ、持って行ってみなよ」
こんばんは、蜂八憲です!`( ´8`)´
ではでは、改めまして。
10/11(土)からnoteで長編小説『Angel Doll』の連載を始めます。
どうぞ宜しくお願い致します!ヽ(=´▽`=)ノ
さてさて、前回の記事では
note連載の概要についてお話ししましたが、
本日は作品のちょっとしたエピソードについて。
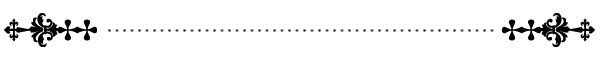
Angel Doll ──Story──
「エンジェルドール」と呼ばれるヒューマノイドが市販されている現代日本。
主人公・哲のもとに、ある日、
行方不明になっていた恋人そっくりの「エンジェルドール」が現れた。
「お願い──1週間だけ、ここに居させてほしいの」
そう懇願する人形を、彼は「人間」として扱い、匿うことにしたのだが──
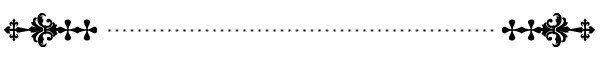
はい、ロボットものです。SFちっくです。この『Angel Doll』ですが、超水道最新作『ghostpia』とは対極に位置する作品です。
作風もそうですが、作品自体の立ち位置としても。
『Angel Doll』は蜂八の超水道以前の処女作であり、同時に、超水道と関わるきっかけになった作品でもあるのです。

制作秘話という名の昔話
今回連載する「Angel Doll」なのですが、もともとは、大学時代に同期の友人と「サウンドノベルを作ろう」ということで制作したシナリオでした。
「もう一度、物語を書き始めよう」と決めた頃のこと、そして「どんなものを書こうか」と考えあぐねていた時のこと。そんな折に、友人が話を持ちかけてくれたのでした。
「サウンドノベル作ろうぜ。おまえがシナリオ書いて、俺がプログラムを組むんだ!」
大学3年生の初夏のことだったと記憶しています。
在学中にリリースしよう、ということで始まった制作でしたが──
結果から先に言うと、そのサウンドノベルは完成しませんでした。
メンバー集め、技術的な制約、そして時間の縛り。
なかでも最大の問題は、僕自身がシナリオ制作に苦戦したことでした。
高校以来とんと離れていた「物語を書く」という行為に頭と腕は悲鳴をあげるばかりで、なかなか前進することができなかったのです。
「1ヶ月でシナリオを完成させてうんぬん」などという青写真はとうに吹き飛び、テキスト量は加速度的に増える反面、ストーリーを進めている実感には乏しく……
「在学中にはサウンドノベルとして完成しない」
気づけば、そう見切りをつけざるを得ない状況になっていました。
自分の至らなさに涙しつつ、メンバー共有の連絡網に「ごめんなさい」と中止の旨を伝えるメッセージを書き込んだことを、今でもふっと思い出したりします。
そんな経緯があって、サウンドノベル制作計画は頓挫しました。
ただ、そのシナリオの執筆だけはどうしてもやめる気になれませんでした。
──この物語は、きっともう誰にも振り向かれることはない。
そんなふうに頭の隅で理解しつつも、それでも書き続けていたのは、ひとえに自分自身のためであり、また意地でもあったのだと思います。
終わらせなければ次には進めない、という確信と、ここで放り投げればまた同じことを繰り返すだろうという恐怖。
「こんなに書けなかったのか……」という失望のなか、「こんなに書けるんだ!」という実感を頼りに、がむしゃらに書いた日々でした。
そうして、シナリオが完成したのは、およそ半年後──
秋の終わり頃になってからのことでした。
結果として、手元には「完成品」のシナリオだけが残ったのです。
一応のところ「どうにか完成しました」とメンバーに伝え、
自分のなかではすべてが終わった心持ちでした。
それから一週間もした頃でしょうか。
サウンドノベル制作の話を持ちかけてくれた彼と、久々に会ったのは。

「俺さ、蜂八の書くものはイカしてると思うのよ」
「おお、ありがと。すごく嬉しいよ、ホント」
「ところでさ、『超水道』って制作チームがあるじゃんか」
「ああ、このまえ薦めてくれたノベルアプリね。あれ面白かったよ」
「うんうん。でな、その超水道が今、ライターを募集しててな」
「……応募してみろ、ってこと?」
「いや、もうお前のこと応募しといた。他薦ってことで」
「へー。
……はっ?
……ファッ!?」
混乱している僕をよそに、彼は涼しい顔でこう続けたのでした。
「『Angel Doll』、持って行ってみなよ」
その一言がきっかけで、僕は超水道にポートフォリオとして
『Angel Doll』を含む作品群を提出し、今ここに至ります。
蜂八憲に関して、超水道作品を読んでくださっている方々の記憶に新しいのはやはり『佐倉ユウナの上京』なのかなと思います。

チームメンバーと打ち合わせを重ねに重ね、2013年から2014年まで丸一年にわたって展開した『上京』。
シナリオの執筆自体も、期間としてはおよそ半年間ほどでした。
制作にあたって、プロットを立てた段階ですでに「これは長くなりそうだな」という予感はあったのですが、それでも不思議と不安を覚えなかったのは、『Angel Doll』で曲がりなりにも15万字ほどのストーリーを書ききったという自信と実感があったからなのだと思います。
最終的に『上京』の分量はおよそ40万字、リリースに際しては季刊の展開となりました。
作品を読んでくださった方々に対する感謝はもちろんのこと、『Angel Doll』を執筆した当時の自分に対しても「よく頑張ったな」という感慨がありました。
『佐倉ユウナの上京』を書き終えることができたこと。
超水道のメンバーと創作ができていること。
読者の方々から温かいお言葉を頂けていること。
今の自分があるのは、ひとえに『Angel Doll』のおかげと言っても過言ではありません。
そういう意味でも、ひとつ思い出深い作品でもあるのです。

逆に言えば、それだけの思い入れの深さゆえに、当初は表に出そうとあまり考えていなかったのも事実です。
なにせ随分と前の作品ですし、今の自分からすれば色々な意味で「ああ若い! 若いよ自分!!」と、もだもだしてしまう所もあったりして。
しかしながら同時に、素直に「面白いじゃん」とも思うのです。
これは紛れもなく、当時の全力投球だった。
時間を置いて読み返してみると、ことさらにそう実感します。

つらつらと書き連ねてはきましたが──
結局のところ、物語は人に読まれてナンボだと思うのです。
まだ見ぬ誰かに読んでもらいたい。
そう思って書いていたものであれば、なおのこと。
「もう日の目を見ることはない」
そんなふうに一度は諦めかけた作品ですが、こうしてまた、違った形で表に出すことができて嬉しいのです。
『佐倉ユウナの上京』とはまた違った趣のシナリオですが、「へえ……こんなのも書いてたんだね……///」と生温かい目で眺めつつ、にやにや楽しんで頂ければ、書いた身としては嬉しい限りです。
ここまでお読み下さり、ありがとうございました。
`( ´8`)´<頂いたサポートはラムネ菓子となり僕の脳に100%還元されます。なお、押してくださった♡はモチベとなり僕の心に1000%濃縮還元されます。
