
カーボンナノチューブのテスラフォレシス
Lindsey R. Bornhoeft†⊥ Aida C. Castillo‡ Preston R. Smalley# Carter Kittrell†§ Dustin K. James† Bruce E. Brinson† Thomas R. Rybolt∥ Bruce R. Johnson†§ Tonya K. Cherukuri† † Paul Cherukuri*†§∥ † † † †London†† † † †London†† † †London†† † †London†† †London†† †London†† † †London
ACSナノ2016, 10, 4, 4873-4881
掲載日:2016年4月13日
https://doi.org/10.1021/acsnano.6b02313
著作権 © 2016 アメリカ化学会
元記事はこちら。
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.6b02313#
テーマ:電場,アンテナ,電線,
概要
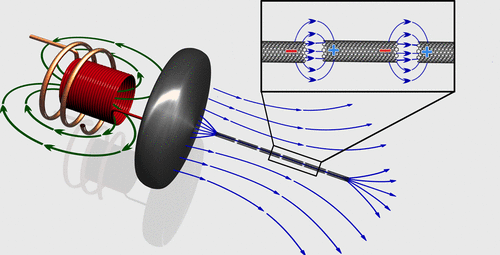
本論文では、テスラコイルによる物質の有向運動と自己組織化であるテスラフォレシスについて紹介し、単層カーボンナノチューブ(CNT)を用いてこの動電学の現象を研究している。従来の電界を用いた物質の自己組織化は小規模なものに限られていましたが、テスラフォレシスでは、テスラコイルのアンテナを用いて、自由空間に投影する勾配のある高電圧力場を作り出すことにより、この制限を超えることができます。テスラフォレシス(TEP)場内に置かれたCNTは分極し、自己組織化してナノスケールからマクロスケールまでのワイヤーを形成します。TEP場は、ナノチューブ・ワイヤーを遠隔地(30cm以上)で自己形成させるだけでなく、ナノチューブ・ベースのLED回路にワイヤレスで電力を供給できることも示している。さらに、個々のCNTは自己組織化し、TEP場に忠実な長い平行アレイを形成する。このように、テスラフォレシスはボトムアップからマクロスケールまでの指向性自己組織化に有効である。
不均一な電気力場は、さまざまなナノスケール材料(カーボンナノチューブ、グラフェン、半導体量子ドットなど)の配向、位置、集合を制御し、そのユニークな特性を電子デバイスに統合するために使用される。(1-10) 勾配電場内で粒子状物質に発生する力は、誘電泳動として知られるポンデリング現象であり、中性粒子は分極して電場密度の高い領域に向かって移動したり、電場密度から遠ざかったりする。(11-13) 従来、空間的に変化する電気力場は、適切な形状の2つの電極(μm-mm間隔)を作ることによって作られ、局所的に高い誘電泳動(DEP)力が発生するようになっています。(14-16) これらのシステムで発生するDEP力の大きさは、電場の2乗の勾配に比例し(FDEP ∝∇E2) 、ブラウン運動に打ち勝つのに十分な強さが必要です。これらの明確に定義されたリソグラフィーで作製されたコンデンサー様システム内でナノスケールの物質を操作するために、数多くのDEPシステムが開発されてきましたが、これらのデバイスは、2つの電極によって課せられる物理的制約のために、本質的に小さなスケールの体積(μL-ml)および表面積(μm2-cm2)の組み立てに制限されており、材料およびデバイスのスケーラブルなナノ製造への使用を阻害しています。(17, 18)
私たちは、テスラコイルが発信する近接場(≪ λ )高周波(RF)エネルギーを利用することで、従来の誘電泳動の物理的制約を克服できることを発見しました。ニコラ・テスラは当初、自身の名前を冠した装置を世界中に無線で電気エネルギーを供給することを目的としていたが(19)、テスラコイルは遠距離場(≫λ)における放射電力伝送には実用的でないことが判明し、今日では科学博物館で人工雷を作り出すためだけに使われる19世紀末の遺物に追いやられている。(20)しかしながら、テスラコイルの送信機の非放射性近接場領域には高強度のRFエネルギーが含まれており、テスラコイルのアンテナから自由空間に広がるこの強い傾斜電界を利用して、ナノスケールおよびマクロスケールの粒子の自己集合を長距離に渡って誘導することが可能である。テスラコイルの近接場領域は送信機から数十メートル離れているため、テスラコイルはナノスケールおよびマクロスケールの粒子状物質の移動、方向づけ、集合をスケーラブルに行うことができることを発見した。
テスラコイルの近接場エネルギーを用いて遠方にある物質を動かし、自己組織化する現象は、テスラフォレシス(Teslaphoresis)と呼ばれています。単層カーボンナノチューブは、分極率、異方性が高く、バルク粉末と懸濁液中の個々のナノチューブの動電挙動を比較的容易に研究できるため、この最初の研究に使用することにした。(21-23) 小さな塊のCNT粉末をテスラコイルの近接場内に置くと、数秒以内に爆発的な自己組織化と個々のCNTワイヤの成長が起こる。その代わりに、CNTを溶液中に分散させると、多数のナノチューブワイヤーが数秒で形成される。
一方、CNTを溶液中に分散させると、多数のナノチューブワイヤーが急速に自己集合し、1つまたは複数の大きな並列アレイに結合し始める。さらに、テスラ泳動は無制限の指向性自己組織化という明確な利点があるが、テスラコイルの近接場エネルギーが無線でナノチューブ回路を駆動し自己組織化し、ボトムアップで個々のナノチューブの平行アレイを遠隔から自己組織化することも見出した。
研究成果および考察
図1aは、ナノチューブの集合体を表面のワイヤに誘導するために、水平に配置された当社のテスラフォレティック(TEP)システムを示しています。従来のテスラコイルは、高電圧コンデンサとスパークギャップを用いて広帯域のRFエネルギーを伝送していましたが、私たちのテスラコイルは、プラズマ発生器により共振周波数2MHzで連続駆動する狭帯域の振幅変調RF送信器として設計されました。誘導結合された一次コイルと二次コイルは、発電機からのRF信号を増幅する役割を果たし、その結果得られるコイルからの高電圧出力は、中空円盤型アンテナに直接供給されます。(24)テスラコイルのアンテナを囲む近接場領域は、本質的に勾配のある準静的な電気力場であり、プラズマ発生装置からの出力(送信電力5Wで最小アンテナ電位10kV)を調節することで精密に調整することができる。図1bはアンテナの準静電ポテンシャル(E)と電界線の境界要素法(BEM)による計算結果、図1cはそれに対応する関数E2とその勾配力場線です。図1bの電位線は、各ステップでアンテナ電圧の10%ずつ低下し、送信素子の曲面限界付近で最も間隔が狭くなり、表面電荷密度の局在化が進んでいることに対応しています。アンテナ前面の平らな面に近いところでは、ポテンシャルの等高線は平行に近く、さらに離れると、アンテナの細部が全電荷に比べて重要でなくなるため、球状に広がります。図1cは、2板式キャパシタDEPシステムと同様に、時間平均したTEP力が∇E2に比例していることを示しています。しかし、我々のTEPシステムでは、TEP力を発生させる勾配電場は、システムの対称軸に平行な領域が支配的であり、すべての実験が行われた領域である。
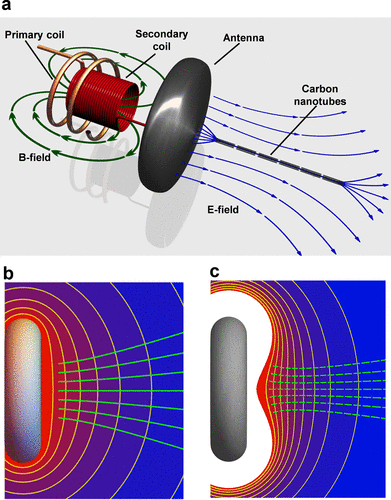
図1. テスラフォレティック(TEP)システム。(a) RFプラズマ発生器(図示せず)により通電された一次コイルからなるTEPシステムの概略図。磁場(Bフィールド)が二次コイルに誘導結合し、高電圧RF信号が中空円盤型アンテナに終端される。アンテナから自由空間に投影される傾斜電場(E場)がTEP力を生み出し、カーボンナノチューブを分極して長いワイヤーに自己組織化させる。(b) BEM計算によるアンテナ周囲の準静電ポテンシャル。黄色の線は等電位線、赤から青のグラデーションは電位の高い領域から低い領域をそれぞれ表しています。緑色の線はアンテナからの電気力を表し、それに沿って電界の大きさが減衰していく。(c) アンテナからのTEP力場∇E2のBEM計算(緑色の破線)。アンテナに近い高E2領域は、分かりやすくするために切り取ってあります(白い部分)。黄色の等電位線は、切り取られていない最も高い輪郭レベルからE2が10%低下していることを表しています(色のグラデーションは赤から青)。
図2aの拡大領域は、粉末状CNT(約1mg)が30WのTEP場下で<5秒間に細長いワイヤに自己集合する様子を時間経過とともに示したものである(動画S1)。粉末ナノチューブ粒子は、テフロン製の皿に入れた1%プルロニック水20mLに浸し、アンテナ表面から8cm離れた位置に配置した。TEPシステムを起動すると、各粒子は素早く回転し、その最長軸を電界の方向と平行に揃えた。ワイヤーは、CNT粉末の中心点の反対側にナノチューブフィブリルが芽生え、2cm/sという非常に速い速度で自己組織化し、すべての粒子が消費されて10cmのワイヤーになるまで、アンテナに向かっても離れても継続的に成長した。成長しきったワイヤーは、0.5cm/sの速度でアンテナに向かって移動し、ディッシュの端に到達しました。このテスラフォレートを用いて成長させたCNTワイヤーは、これまでに作られた自己組織化構造の中で最長であり、TEP力場の非拘束性によって実現された。(25, 26)
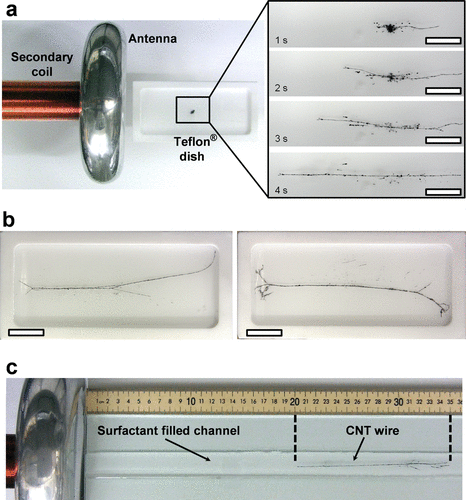
図2. TEPによるバルクCNTの長いマクロスケールワイヤーへの自己組織化。(a) 1%プルロニック水プール中に約1mgのCNT粉末を入れたテフロン製ディッシュを用いたTEPシステム。拡大した領域は、ナノチューブ粉末が自己集合し、30WのTEP磁場下で10cm長のワイヤーに双方向に急速に成長する(5秒未満)様子を時間経過画像で示したものである。スケールバー=2 cm。(b) テフロン皿の右上コーナー(左画像)および右下コーナー(右画像)から10 cm離れたところにある電気的に接地した金属板(図示せず)を使用して、ナノチューブ・ワイヤーの成長を方向制御している様子。スケールバー = 3 cm。(c)アンテナから30cm離れた場所で40秒以内に自己形成されたナノチューブ線。スケールバー=メートル棒。
動画S1では、最終的に組み立てられた構造体の形成中と形成後の両方で、ナノチューブワイヤー内に多数の火花が発生していることが示されている。これらの明るい白色の火花は、カーボンアーク灯で観察されるものと類似しており、したがって、これらの領域から発生する熱は同等であろうと予測される。しかし、放出された熱は水性環境内で速やかに放散されるであろう。また、火花の発生に伴い、電線に沿った箇所から暗黒のプルームが放出されることがある。排出された物質の光学吸収スペクトルは特徴がなく、バルクCNT粉末に含まれる炭素質物質(自動排出が望ましい)である可能性が高いことが示された。ワイヤー内のスパークは、ナノチューブマクロ粒子内の高分極金属CNTに由来すると考えられる電荷移動による絶縁破壊を示す。成長機構を考える上では、粒子内の電荷分離だけでなく、粒子間の電荷移動も含める必要がある。興味深いことに、導電性球体を用いた初期の研究において、粒子連鎖時の絶縁破壊が報告されているが(27, 28)、このように放電を直接観察することは、これまでこれほど大規模に観察されたことはない。
TEPシステムは、基本的に2枚のプレートを持つRFコンデンサであり、2枚目のプレートは仮想接地面である。(29)仮想接地面を物理的な接地面に置き換えることで、ナノチューブワイヤの成長の方向性を制御することに成功した。図 2b は、電気的に接地した金属板をテフロン皿に近づけると、ナノチューブ・ワイヤーの遠位端の成長方向が、アンテナから 30cm 離れた接地板に向かってカーブしていることを示している。アンテナから50cm以上離すまで、遠位端は常に接地板に向かって伸びていた。図2bのパネルでワイヤが皿の反対側に曲がっていることからわかるように、成長方向は常に電界線に沿って接地された金属板の位置まで伸びていた。このように、ワイヤの成長が最も近い接地面に向かって忠実に配向することは、エレクトロスパンファイバーと同様の物理現象であり、最小送信電力であっても発生する。(30) したがって、接地面の位置はTEPの組み立てプロセスにおいて重要な要素である。さらに、ナノチューブワイヤーの全長は、利用可能なナノチューブの質量に直線的に比例することがわかった。
TEP力場の理論的範囲は、アンテナからの近接場領域全体であり、私たちのシステムの場合は20 m以上離れています。図2cに示すように、送信電力を上げるだけで、離れた距離でもはるかに長いワイヤーを成長させることができる(動画S2)。長さ15cmのナノチューブワイヤは、100WのTEP電界のもと、アンテナから30cm離れた場所で急速に自己組織化した(約40秒)。円盤状アンテナの中心軸に平行な幅3cmのガラスチャネル(1%プルロニック水を含む)内に5mgの粉末状CNTスポットを堆積させた。完全に形成されると、ワイヤー全体がアンテナに向かって初期速度1cm/sで急速に加速されました。ワイヤの速度は、送信機の出力を、ワイヤがアンテナの前で静止して張った状態を保てるレベルまで下げることで制御することができる。TEPフィールドを停止すると、ワイヤは集合したままであるが、溶液中で弛緩した。動画S3は、ピンセットでワイヤーをバラバラにしたところ、送信機を低電力(5W)で再起動すると、断片が電界の方向と平行に素早く並び、自己組織化して壊れたワイヤーを治している。
図3は、TEPで組み立てたナノチューブワイヤの電気的、構造的、および形態的特性を示している。図3aのI-V曲線から、私たちのナノチューブワイヤは0.2Ω-mの抵抗率で、驚くほど一貫したオーミック挙動を示していることがわかります。図3bは、ワイヤの代表的なラマンスペクトルです。鋭いGピークや本質的に存在しないDピークなど、単層カーボンナノチューブに特徴的なスペクトルを示し、当社のTEPフィールドがナノチューブの電子構造に悪影響を与えていないことが分かります。走査型電子顕微鏡(SEM)では、ナノチューブをPMMA/ODCB(ポリメタクリル酸メチル)/o-ジクロロエチルケトン溶液中でTEPアセンブルした。走査型電子顕微鏡(SEM)では、導電性基板に転写するために、ナノチューブをPMMA/ODCB(ポリメタクリル酸メチル)/o-ジクロロベンゼンの溶液中でTEP集合させ、ワイヤを保存した。図3cは、直径150μmのPMMAコーティングされたTEP集合ナノチューブワイヤのSEM画像である。ポリマーによってワイヤーの下部構造の大部分が見えなくなっているが、PMMAの斜めの亀裂によって、高倍率撮影用の非コーティング領域が提供されている。図 3d は、割れたポリマー内の領域の SEM で、亀裂をまたいで隙間を囲むように、ランダムに配向した束状のナノチューブを発見した。
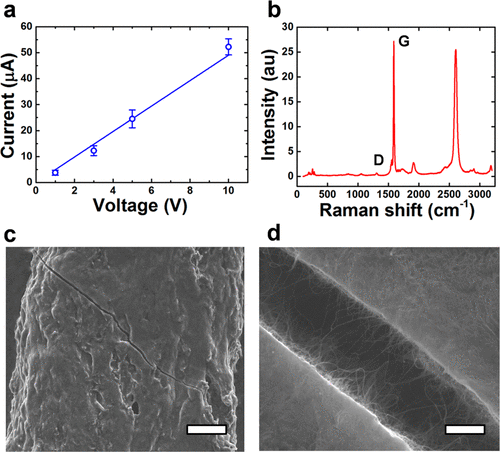
図3. TEPで組み立てたナノチューブワイヤの特性評価。(a) TEP集合ナノチューブワイヤー(n=4)のI-Vカーブ。(b) 低欠陥ナノチューブの特徴を示すTEP集合ナノチューブワイヤのラマンスペクトル(λex = 633 nm)。(c) ポリマーに斜めの亀裂が入ったナノチューブワイヤーの低倍率SEM画像。スケールバー=25μm。(d) (c)の亀裂の高倍率SEM画像。スケールバー = 1 μm。
CNTワイヤーの双方向成長を支配する複雑な力は、主に個々のCNT粒子上の電界誘起双極子と、ナノチューブが鎖を形成するにつれて強くなるこれらの双極子によるものである。私たちの観察に基づくと、初期の急速な成長の支配的な駆動力は、長い導電路に沿って大きな電荷分離が発生し、大きな誘導双極子モーメントと強く相互作用する局所場が形成されることであると考えられる。このメカニズムについてさらに詳しく説明する研究が進められているが、中央の粒子源からのTEP集合は、電界誘起電気運動が支配的で電界線に沿って純増する力の相互作用によるものであることは明白である。(31) CNT 粉末を一箇所に集中させるのではなく、溶液全体に分散させると、TEP 磁場によってナノチューブ がテフロン皿全体にわたって溶液中の多数の平行線に急速に誘導された(動画 S4)。これらのマクロスケールの配列は、多数のナノチューブが端から端まで平行に並んでおり、集合的に入射磁場の位相に追従する誘導双極子が確立している。その結果、1本のCNTワイヤーの先端が、近くにある反対側に帯電したワイヤーの先端と接近し、先端と先端が接触すると、溶液中でさらに大きなワイヤーに組み立てられることが頻繁に起こる。
テスラコイルの近接場RFエネルギーは、長いナノチューブワイヤーの自己組織化を指示するだけでなく、ナノチューブベースの湿式回路にワイヤレスで電力を供給して自己組織化することも可能である。図4は、1%プルロニック水20mLを満たしたテフロン皿に、4ピンの緑色発光ダイオード(LED)のペアを立てて、動画S5からキャプチャしたフレームを示したものである。LED 1のアノードとカソード、LED 2のカソードに粉末状のCNT(約1 mg)を付着させた。30 WのTEP電界に曝露して0.3秒以内に、LED 1は最も近いカソードとアノードに成長した自己組織化ナノチューブワイヤーによって活性化された。LED 1のカソードに隣接するCNT粉末は、アンテナ側とカソード側の両方に同時に成長した。LED 1のアノード付近のCNTスポットは自己組織化し、両方のLEDの間にCNT相互接続を形成し、LED 2を活性化させた。CNTワイヤがそれぞれのLEDのカソードに向かって伸びたり離れたりするにつれて、より多くの近接場エネルギーがナノチューブワイヤによって採取され、回路内の各LEDの発光がますます明るくなる。1つのLEDからの発光強度を既知の電流にマッピングしたところ(図S1)、低い送信電力(5W)で1μAがこの配線に発生したと推定された。このように、湿式回路の組み立てと同時に遠隔操作で電力を供給できることは、従来のDEP装置では実現できなかったTEP法独自の機能である。
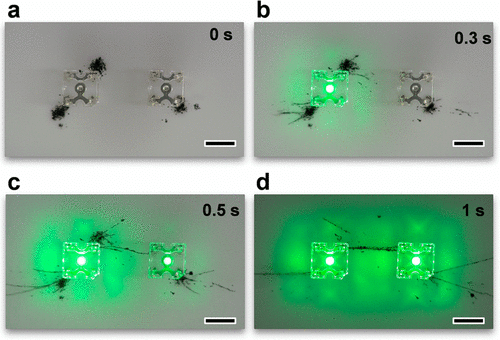
図4. TEPフィールドによって自己組織化され、ワイヤレスで給電されるナノチューブLED回路。(a) プルロニック溶液中の2つの緑色LED。LED 1の両電極(左)とLED 2の遠方電極(右)の隣にナノチューブが付着している。(b)30WのTEP電界の下で、ナノチューブが自己集合して電界からRFエネルギーを採取し、それによってLED 1を点灯させる。(c) 0.5秒後、TEP磁場がLED 1とLED 2の間にナノチューブの相互接続を形成している。(d)1秒後、ワイヤは完全に伸び、近接場からより多くの電気エネルギーが採取され、より明るいLEDが得られる。すべてのスケールバー=1 cm。
最後に、ナノチューブ粉末を1%プルロニック水で超音波処理した後、超遠心分離して大部分の束を除去して調製した個別化ナノチューブの集合を指示するTEPシステムの能力を調査した。(32) 個々のナノチューブ(図 S2 に示す近赤外発光によって証明される)に富む懸濁液の 10 mg/L 滴(50 μL)を、アンテナから 3 cm 離れたガラス製顕微鏡スライドに付着させた。50 W の TEP 電界に 20 分間さらされた後、非常に微細な平行 CNT ワイヤーがドロップの直径を横切って密に配列された(図 5a, 動画 S6)。この液滴は、顕微鏡分析用にガラス表面に組織化されたアレイを保持するため、TEP電界をかけたまま周囲条件下で乾燥させました。図5bは、乾燥した液滴の中央領域で撮影した40倍の可視顕微鏡画像であり、アレイ内の複数の平行ナノチューブ・ワイヤー(直径=25μm、間隔=60μm)を示している。ナノチューブ・ワイヤーの直径とアレイの間隔の変動は、乾燥効果と成長中のナノチューブの合体によるものである。図5cは、ナノチューブアレイのすべてのワイヤーがフォークで終端していることを観察した、液滴の端からの20倍光学顕微鏡画像である。このフォーク状のパターンは、稲妻、プラズマ球、リヒテンベルグ図形などの放電現象で観察されるものと類似している。(33)
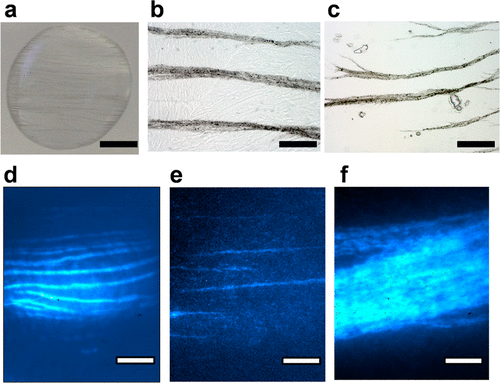
図5. TEPによる個別化CNTのマクロスケールアレイへの自己組織化。(a) 個々のプルロニック包埋CNTは、50WのTEP場(アレイに平行に向けられた)において20分後にガラス顕微鏡スライド上で自己集合し、目に見えるナノチューブ・ワイヤーのアレイに組織化された。スケールバー = 0.5 cm (b) 乾燥した液滴の中央で撮影したCNTワイヤの配列の可視顕微鏡画像(40×)。スケールバー=60μm。(c)乾燥した液滴の端にあるフォークを持つアレイの可視顕微鏡像(20×)。スケールバー=110μm。(d)厚さ10μm、配列間隔約30μmのCNTワイヤの近赤外線フォトルミネッセンス顕微鏡像(20×)。スケールバー=90μm。(e)直径1μmのCNTワイヤーを示す近赤外線フォトルミネッセンス顕微鏡像(60×)。スケールバー=30μm。(f) 大径線(約85μm)の近赤外光顕微鏡像(60×)。複数の小径線が合体して大きな集合体を形成したため、線の長さに沿って筋が観察される。スケールバー=30μm。
もう一つの重要な発見は、これらの個々のCNTが連鎖してマクロスケールのナノチューブワイヤーに合体したにもかかわらず、持続的なNIR発光から明らかなように、各ナノチューブを囲むプルロニックコーティングによってワイヤー内で脱バンドルしたままであることであった。図5dは、図5bのワイヤよりも直径が小さく(約10μm)、間隔が狭い(約30μm)ナノチューブワイヤを含む液滴の中心内の領域のNIRフォトルミネッセンス顕微鏡画像を示している。ワイヤの直径と間隔の相関は、ワイヤが太くなるにつれて、ワイヤの平行双極子からの静電反発が強くなり、双極子がさらに強くなって間隔が遠くなることに起因している。(34)また、電界に沿った細径のナノチューブワイヤー(直径約1μm)が数本観察された(図5e)。これは、フォトルミネッセンスによってより容易に観察でき、太径のワイヤーの間に位置していた。このような高アスペクト比のワイヤーは、電荷分離を最大化する手段として、個々のナノチューブが端から端まで自己集合して形成されているとしか考えられなかった。このことは、偏光した励起光がワイヤの長軸に対して垂直である場合、全体の発光が減少するという事実からも裏付けられている。このような超高アスペクト比ワイヤーの制御成長は、印加するTEP場の時間、周波数、強度を精密に制御することで最適化することが可能である。可視および近赤外顕微鏡の画像では、ワイヤーの長さに沿って筋が見えますが、これは大きな構造内で隣接するナノチューブ鎖が強く整列していることを示しています。これは、直径85μmのワイヤの60倍率のNIR画像でも非常に明白である(図5f)。SEM分析(図S3)も、TEP組み立てられたワイヤー内のナノチューブの配向を研究するために、アレイに対して実施された。しかし、ナノチューブのプルロニックコーティングは、組み立てられたワイヤーの微細構造の詳細を見えなくしてしまった。
さらに、乾燥時間を短縮するために薄膜ナノチューブ懸濁液を作製したところ、個々のナノチューブが整列し、成長するナノチューブワイヤの先端に向かって引き寄せられる様子が観察された(図S4)。これは、磁場中の鉄粉や電場中の油の中の草の種を連想させ、個々のナノチューブとこれらの大きな構造物の間に強い局所的な場があることを示す証拠である。この混合物では、金属ナノチューブが電界の影響を受けやすいが、個々の半導体ナノチューブが電界に沿っ て整列する様子も観察されている(35)。動画 S7 は、顕微鏡ステージを移動させながら、ナノチューブ・ワイヤー・アレイを NIR 顕微鏡で走査し、ワイヤーの長さの一部を追ったものである。
図6a-dは、TEP磁場下での個々のナノチューブからCNTアレイの形成のメカニズムを示している。TEP場の活性化前、ナノチューブは個々に懸濁しており、溶液中でランダムに配向している。TEP電界をかけると、個々のCNT粒子は分極され、長軸が電界の方向と平行に配向する。相反する双極子を持つCNTの隣り合う端はコロンビック引力を受け、端から端まで連鎖し、長いワイヤーを作り、電荷の分離を増加させる。隣接する鎖は、CNT鎖の末端の分極電荷による静電反発によって一定の間隔に保持され、懸濁液中の個々のCNTからナノチューブワイヤーが均一に平行に配列される。これらのステップは、先に述べたマクロスケールのCNT粒子から直接観察されたステップを反映しています。図5fに見られるように、隣接する鎖が合体してより太いワイヤーを形成すると、ワイヤーの間をつなぐ電荷反発の力が克服されるのは興味深いことである。この場合、ワイヤに切れ目があると、隣り合う鎖が結合することが観察されている。近くのCNT鎖の端は、破断したワイヤ内の強い勾配電界に引き寄せられ、それを治癒し、鎖の残りの長さを隣接するワイヤの表面まで掃き寄せます。鎖は結合し、累積電荷は新しい大きな鎖(ワイヤー)の長さに沿って分散される。このメカニズムのさらなる証拠は、溶液の急速な蒸発によってこの整列プロセスが維持された薄膜のNIR発光画像に見られ、図S4について述べたように、CNTがより大きな直径のワイヤの端に引き寄せられていることが確認されました。
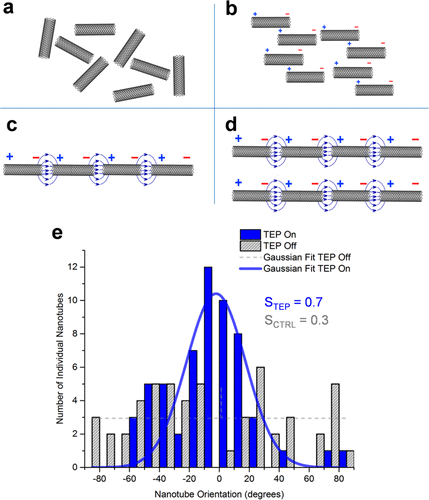
図6. TEPによるCNTアレイ形成のメカニズムと、TEP場の方向に対する個々のCNTのアライメント解析。(a) TEP力場がない懸濁液中でランダムに配向した個々のCNT。(b) 各CNTはTEP電界によって分極され、電界の方向と一致するように回転する。(c)個々のCNTの先端間の双極子引力は、個々のCNTの高アスペクト比の鎖を形成する。(d) 隣接する鎖の双極子-双極子反発により、均一な間隔を持つ自己組織化ナノチューブワイヤの平行配列が形成される。(e)ヒストグラムは、個々のナノチューブの大部分がTEP磁場の±20°以内に整列していることを示している。青色 = ガウシアンフィットのTEP磁場オン。グレー = ガウシアンフィットを用いたTEPフィールドオフ。対照試料(CTRL)のランダムな分布のため、フィットは定数に縮退していることに注意。S = 各サンプルについて計算されたオーダーパラメーター。
個々のナノチューブの配列の程度は、個々のナノチューブからの偏光NIR発光を利用することによって定量化された。個々のCNTは非常にアスペクト比の高いナノ粒子(約1 nm×500 nm)であるため、励起レーザーの偏光特性を利用して、TEP磁場の方向に対するナノチューブの配列の度合いを測定することができる。(36)ナノチューブの長軸に平行な偏光では発光強度が最大となり、垂直な偏光では発光強度が最小となった。直交する2つの偏光下でのTEP高配向ナノチューブのNIR画像は、図S5に示すように、この最大と最小の強度の効果を示している。図6eのヒストグラムは、レーザー偏光角の範囲にわたって個々のナノチューブ(アレイ内の大径ナノチューブワイヤーの間隔に位置する)の強度を測定し、強度を正弦波的にフィットさせてTEP場の方向に対する各ナノチューブの相対配向を計算することによりプロットされたものである。これらの値は、TEPシステムをオフにした状態でシステムの前に置かれた対照試料と比較された。図6eのヒストグラムは、「TEPフィールドオン」のナノチューブの64%がTEPフィールドの方向の±20°以内に整列していたのに対し、対照試料は同じ範囲に17%しか整列しておらず、ランダムに分布した試料と一致する値であることを示している。TEP曝露ナノチューブと対照ナノチューブの配向秩序パラメータ(31)を比較すると、前者は秩序パラメータが0.7で強い配向を示すが、後者は再び秩序パラメータが0.3でランダムな分布を示すことが明らかになった。
結論
TEP集合の研究はカーボンナノチューブのみに焦点を当てたものであるが、他のいくつかの材料で探索的な実験を行い、その指向性、拡張性のある集合を観察してきた。(37) また、ナノチューブやそのアレイは、この周波数帯の変化に比較的敏感でないため、伝送周波数 2MHz を選択したが、将来的には、TEP の指向性集合体の周波数依存性を探る予定である。(38-40) 化学テンプレートやリソグラフィーを用いずに、個々の半導体を表面上に一括して集積・並列化するTEP力の興味 深い能力は、コンピュータプロセッサにおける高密度並列ナノチューブのスケーラブルな作製への応用や、導電性ナノチューブ・ファイバーのボトムアップによるシステムの近視野(数十メートル)までの集積につながる可能性がある。(41-45) さらに、この単一アンテナ TEP システムは、より複雑な場と構造を作り出す手段として、複数のテスラコ イルに容易に一般化でき、それによって所望の構造物に対するより細かい方向制御が可能になる。したがって、TEP システムとその手法は、スケーラブルなナノ製造における重要なツールとなり、テスラコイルからの近接場エネルギーだけを使用して回路要素を相互接続、修復、および電力供給する能力は、従来の誘電泳動法を超える TEP アセンブラの使用についてさらに大きな見通しを提供します。
方法
TEPシステム
図S6に2MHzのTEPシステムの回路図を示す。テスラコイルの一次側は、5ターン螺旋コイル(直径5インチ、高さ5インチ、ピッチ0.25インチ)を形成して作製した中空銅管(外径0.25インチ)で構成されました。一次側を2MHzプラズマ発生装置(MKS Nova-25A, 2.5 kW RF Plasma Generator)の出力に導電結合し、コイルの残りの端は電気的に接地した。2 次コイルは,18 AWG の磁石線を中空のポリカーボネート製シリンダー(外径 2 インチ)にきつく巻いて作製した.二次コイルの一端は直径8インチのアルミニウム製トロイダル(Amazing 1, LLC)に導電結合され、残りの一端は電気的に接地された。トロイドは直径7.5インチのアルミニウムディスクでキャップされ、2MHzテスラコイルのアンテナを作製した。テスラコイルは電気的に絶縁された支柱の上に水平に配置され、すべての試料は非伝導RF透明プラットフォーム上のアンテナの前に直接置かれた。TEPシステムからの送信は、起動したテスラコイルのパワーに合わせることで最大化されました。
TEPによるCNTの組み立てとワイヤレスパワードナノチューブベースの回路
本研究で使用したCNTは、粉末状に精製されたHiPcoナノチューブ(ライス大学、HPR162.8)である。CNT 粉末(1 mg または 5 mg)をテフロン皿(6 × 15 cm2)の中央部またはガラス板(0.1 × 1 m2)の表面に配置した。テフロンディッシュ上のTEP指示組立は1%プルロニック水20 mLを含み、ガラスプレート上のTEP組立は1%プルロニック水50 mLを含む長いチャネル(3 cm × 1 m)内で実施した。すべてのナノチューブは、組み立てられたCNTワイヤーの形成が完了するまでTEP場に曝された。方向性のある成長制御は、接地した金属円盤(直径6インチ)を送信アンテナから30cm離れたテフロン皿の左側または右側に45°の角度で置くことで達成された。4ピンの緑色LEDは定格20mA、4ピンの赤色LEDは定格70mAであった。赤色LEDの電流値は、調整可能なDC電源と電圧計を使用して強度に対応させた。すべての可視動画と画像は、Canon HD ビデオ MF500 カメラを使用して 30 フレーム/秒で撮影された。
TEPによる個々のCNTの自己組織化
10 mg の CNT を 100 mL の 1% (w/v) Pluronic F108 に入れ、70 W で 2 分間超音波処理を行い、分散型ナノチューブ懸濁液を調製した(Misonex Sonicator 3000)。この懸濁液を使用前に100 000gで4時間遠心分離し、上清の50μLをピペットでガラス製顕微鏡スライドに移した。液滴はアンテナ前面から3cmの位置に置き、TEP装置を50Wまで作動させ、液滴が蒸発するまでTEPフィールドを作動させたまま室温で乾燥させた。スライドにガラスカバースリップを装着し、倒立顕微鏡(Nikon TE-2000U Eclipse)に、可視画像用Nikon DS-Fi1カメラまたは近赤外線画像用Roper Scientific OMA-V:2D 液体窒素冷却InGaAsカメラを接続して画像処理した。さらに、対照試料として、同じナノチューブ懸濁液の 50 μL ドロップを、TEP 磁場を印加しない状態で顕微鏡スライド上で風乾させた。すべての NIR 画像は、蛍光発光の鮮明度を高めるために ImageJ のホットシアン LUT を使用してフォルスカラー化し、840 nm レーザー励起下で 200 ms の蓄積で取得した。TEPフィールドによる個々のCNTのアライメントの程度を定量化するために、個々のナノチューブからの発光強度を、レーザー偏光角度の範囲(8°ステップで合計240°をカバー)で収集し、サインカーブにフィットさせて角度を算出した。(20) この計算は、TEP 整列滴中の 58 本のナノチューブと、同じ CNT 懸濁液サンプルの空気乾燥滴からの 53 本のナノチューブに対して行われた。ヒストグラムをプロットし、Originのガウス関数にフィットさせました。
特性評価
近赤外発光スペクトルは、モデルNS1 NanoSpectralyzer(Applied NanoFluorescence, LLC)を用いて660 nmの励起光で得られたものです。バルク電気抵抗測定は、1%プルロニック水中で自己組織化した約2mgのCNTを5WのTEP電界下で行った。ナノチューブは、2 cm 離れた 2 本の銅線に接触するまで自己組織化した。ナノチューブワイヤーに直流電源から定電圧(1-10 V)を印加し、ナノチューブワイヤーに流れる電流を測定した。ナノチューブワイヤーのラマンスペクトルは、レニショーのラマン顕微鏡を使用して、633 nmの励起光で取得された。マクロスケールワイヤの SEM イメージングのために、PMMA/ODCB ナノチューブのポリマー溶液の混合物上で、50 W TEP 磁場下で指向性自己集合を実施した。ピンセットを用いてポリマーからワイヤーを取り出し、導電性基板上に直接置いた。SEM 画像は、FEI Quanta 400 ESEM を使用して、10 kV で 3 Torr の水蒸気による湿式モードで取得しました。プルロニックコートされたナノチューブアレイは、Denton Desk V Sputter System を使用して、SEM イメージングの前に 5 nm の金層でスパッタコーティングされた。
参考情報
Supporting Informationは、ACS Publicationsのウェブサイト(DOI: 10.1021/acsnano.6b02313)で無料で公開されています。
追加実験データ (PDF)
動画S1(MPG)
動画S2(MPG)
動画S3 (MPG)
動画S4 (MPG)
動画S5(MPG)
動画S6 (MPG)
動画S7 (MPG)
参考動画
テスラフォレシス、電磁波により自己組織化する酸化グラフェンの性質を利用して、ネットワークを作りエネルギーを伝達する技術はどんどん進んでいます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
