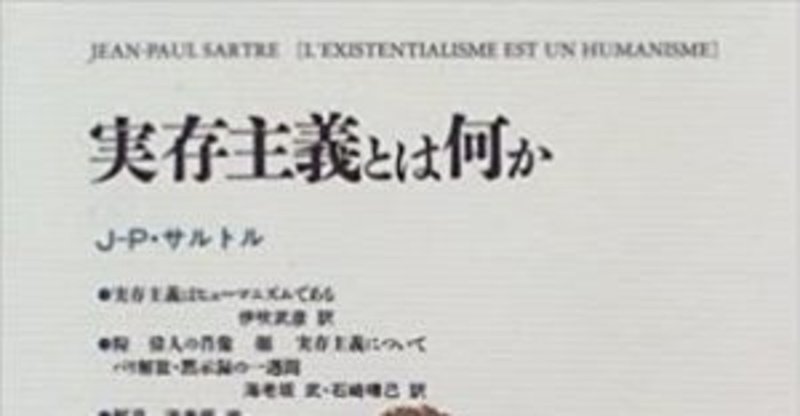
サルトル(1)「実存は本質に先立つ」
ジャン・ポール・サルトル(1905〜1980)はフランスの哲学者、文学者で、生きることの不安と不条理、そして自由を論じた。第二次世界大戦後、価値観が大きく揺らぐ時代において、人はどのように生きるべきかが問われた。サルトルが掲げた実存主義はフランスを中心に世界を席巻した。日本でもサルトル全集が300万部を超える大ベストセラーとなった。
1944年のパリ解放後のフランスでは、自由と解放感とともに失業や食料不足による不安が蔓延していた。また、ユダヤ人虐殺の悲惨が徐々に明らかになるにつれて、人々の前に人間の残酷性が否応にも突きつけられた。若者たちは時代の虚無感や未来への不安を感じていた。
そんななか、1945年のパリのとあるクラブで「実存主義とはヒューマニズムか」と題されたサルトルの講演が行われた。そこでサルトルは、基本テーゼとなる「実存は本質に先立つ」を打ち出した。
「実存は本質に先立つ」とはいかなることか。サルトルはペーパーナイフを例に挙げる。ペーパーナイフを作る場合は「紙を切るもの」という目的、つまり本質が先にあって作ることになる。しかし、人間の場合、あらかじめ人間の本質が決まっているわけではなく、本質を自らが選び取る存在となる。実存、つまり「ここにある存在」が本質より先行しているわけだ。
『実存が本質に先立つとは、何を意味するのだろうか。それは、人間はまず先に実存し、世界内で出会われ、世界内に不意に姿をあらわし、そのあとで定義されるものだということを意味するのである。人間はあとになってはじめて人間になるのであり、人間は自ら作ったところのものになるのである。このように、人間の本性は存在しない。その本性を考える神が存在しないからである』
すなわち、人間は自らの本質を選び取ったうえで、未来を作り上げなければならないというのが、サルトルの人間観なのである。
クラブでの講演は新聞で大々的に報道され、サルトルは一夜にして時代の寵児となった。
サルトル自身は、最初は「自分の哲学は実存の哲学である」として「自分は実存主義者ではない」と言っていたが、ある時期から「実存主義者」であることを受け入れた。その時期はクラブでの講演よりも前である。
「実存」とは「いまここにある」ということ、「本質」とは「なにかである」ということ。
そもそもキリスト教は「人間の本質」を定義していたが、これに対してサルトルは「もし神がいなかったなら、本質は決定していない」とした。
若者たちは第二次世界大戦を経て大人たちへの不信を募らせていた。大人たちは「戦争を始め、占領され、アウシュビッツを作った」と。この不条理について、サルトルは「人間は主体性を持って自分の価値を選び取っていくのだ」と応答した。
第二次世界大戦前夜の1938年にサルトルは「嘔吐」を発表した。この小説はサルトル自身が投影された主人公アントワーヌ・ロカンタンの日記という形式で書かれ、ロカンタンの「実存の発見」が描かれている。
ちなみに、「嘔吐」ははじめ「偶然性に関する弁駁書」と題された、偶然性についての哲学論文だったが、サスペンス仕立ての小説にするよう進言され、そのような形式となった。
ロカンタンは30歳にして働かず、なるべく人と関わらないようにして、親の遺産で暮らしている。ロルボン公爵という人物の伝記を書くことを日課とし、その生活は図書館とカフェと自宅を往復するだけの、「自由」だが、「孤独」で「単調」な毎日だった。
そんななか、ロカンタンは時々不思議な感覚に捉われるようになる。海岸で拾った小石やカフェの店員のサスペンダーに、時には自分自身の手のひらにさえ、それを感じた。彼はその感覚を「吐き気」と名付けた。
やがてロカンタンは、街を歩いていても物そのものの存在に襲われるような、恐怖に晒されるようになる。そしてついにある日、彼はマロニエの根っこを見て強烈な「吐き気」に襲われ、同時にある啓示を得る。それは物の実存、むき出しの存在に対する「吐き気」だった。つまりロカンタンは、実存の不安に襲われたのだった。それ以降、ロカンタンはロルボン公爵の研究も手につかず、生きることの不安に苛まれるようになる。
『物の多様性、物の個別性といったものは、単なる見かけ、うわべのニスに過ぎなかった』
あらゆる物は偶然性の産物で、不条理で意味がないという啓示が「吐き気」であり、ありのままの存在を前にしたときの意識の反応が「吐き気」という比喩を用いて表現されている。「世界は必然的なものとしてあるわけでは決してない」ということを発見する物語が「嘔吐」なのである。
人生はただの偶然で、なんの意味もないと気づいたロカンタンは、生きることへの不安に直面するあまり、数少ない話し相手である独学者に自らの発見を伝える。独学者は「世界にはひとつの目的があり、それは人間がいることだ」という安っぽいヒューマニズムを説くが、ロカンタンは彼に大きな違和感を覚える。ロカンタンは、独学者が実存の偶然性を自覚せずに、自己欺瞞に陥っており、不安を隠していると見たのだ。
独学者とは、いつも図書館にいて、アルファベット順に本を借りて読んでいる者だった。
人間はみんな「自分は何者かである」と思い込んでいるのだが、ほんとうは「自分は何者でもない」のであって、ゆえに価値を決定するのは自分ひとりなのだという出発点にロカンタンは立ったのである。何者でもない「生」を生きていかなければならないのだ。
たとえば、「人間は働かなければならない」という考えは、「人間は働くものである」とその本質を規定してしまっている。「人間は〇〇である」という考えを疑うのが実存主義であり、ギリシャ哲学以来、「人間とはなんだ」ということを述べてきたのだが、サルトルはそこから離れたのである。
ヴォルテールは「人間とは幸福になる存在だ」と定義したし、ソクラテスは「人間とは自己を追求する存在だ」と言い、カントは「人間とは共同体のなかで善を追求する存在だ」としたが、サルトルは「人間は自らの決断によって人生を作り上げていかなくてはならない」と発想を一大転換したのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
