
1-2 百パーセントのアメリカ製名探偵Ⅰ S・S・ヴァン・ダイン『ベンスン殺人事件』

S・S・ヴァン・ダイン『ベンスン殺人事件』1926
The Benson Murder Case
S・S・ヴァン・ダイン S. S. Van Dine(1888-1934)
ようやく二十年代を迎えて、アメリカという一国に特殊な状況をふまえた、アメリカにしか生まれない人間タイプがミステリの主人公に選ばれる条件が熟した。ヴァン・ダインのファイロ・ヴァンスとダシール・ハメットのコンティネンタル・オプ。彼らは、ポーの探偵風に自分の国のことを恥じ、蔑んでいるが、そこに居住せざるをえない人物だ。
二人の作家は、作品世界も主張も気質もすべて異なるが、共通するところは一点、第一次世界大戦の影だ。ヴァン・ダインにとって、大戦はアメリカがイギリスの文化的植民地から脱するための好機でありながら、戦時体制による抑圧は悪夢にも似たものだった。もう少し年少のハメットは従軍世代に属していた。
《アメリカの百万長者の死体が発見されたという書き出しで始まる探偵小説は、寒心に耐えぬことであるが、すでに百をくだらない》というのは、チェスタトンのブラウン神父シリーズの一作の書き出しだ。この一編を含む第三短編集『ブラウン神父の不信』26
(福田恒存、中村保男訳 S)は、ヴァン・ダインのデビュー作と同じ年に刊行された。いかにも底意地の悪い皮肉だ。これを枕に作者は、三人のアメリカ人の大富豪が殺される話を始めるのだから。
おそらくこうしたイギリス人の身勝手なユーモア(要するに、帝国主義者特有の優越意識)を前にすると、ヴアン・ダインは身震いするくらいに怒りをおぼえるタイプの人物だったのだろう。『ベンスン殺人事件』もまた、殺された百万長者によつて幕開けする物語だ。金ピカ時代のアメリカ資本主義の勇猛さは、一部の読み物に「百をくだらない」パターンを生み出していたらしい。ミステリのなかで殺されるのが通例の人間類型とは、現実世界では「殺しても死なない」タフな存在だったのだと思える。十九世紀のアメリカ労働運動史を少し調べれば、この種の資本家紳士録にも詳しくなる。ついでにいえば、『恐怖の谷』が描いた「未開の地」の冒険ロマンのでたらめさも見えてくるだろう。
ヴァン・ダインには、美術評論家・雑誌編集者としてのキャリアがすでにある。二十代なかばで「スマート・セット」誌の編集長になったことが、彼の早めの一頂点だった。ペンネームにつけたS・Sは雑誌名からとった。彼はあれこれと気の多い人物で、第一次大戦前の文学的革新思想の洗礼を受けていた。モダニズム思想には何でも影響されるという後進国知識人の典型で、イギリス嫌いのドイツ贔屓だ。大戦下の抑圧・弾圧を受けて精神的災害をこうむった。ニーチェかぶれの半端なインテリにはずいぶんと生き難かったのだろう。
彼が高名になってから記した自伝はわりと面白い読み物だ。大戦期の後、心労によって神経を病んで病床についていたと書いてある。知的刺激のある読書を禁じられたので、代用にミステリを読み始めた。すっかり病みつきになり、二千冊を読破した。この形式に実作をもって奉仕したいと思った、と。魅せられた魂の記録を綴る文体はなかなか感涙ものだった。
死後半世紀して出た待望の伝記『エイリアス・S・S・ヴァン・ダイン』(未訳)は、このあたりの件が大嘘だったと暴いている。友人のあいだでは、ホラ吹きで通っていたらしい。二千冊読破、というのがご愛敬だ。病床にあったのは事実でも、病名は阿片中毒だ。ユーモアのかけらもない作風や「探偵小説二十のルール」から推して、自伝の自己申告を疑ってかかる理由はなかった。
ヴァン・ダインはミステリの近代的確立をめざした。厳格なルール設定によって無駄なものを排する。ミステリはフェアプレイによって闘われる頭脳ゲームだ。作者は、手がかりをすべてさしだし、推理の過程も見せねばならない。探偵の下僕である警察は組織的かつ科学的捜査によって奉仕する。捜査チームの活動を重視したのも彼に始まる。一方、犯罪は芸術であるから、その解読・推理は選ばれた者たる探偵のみに可能な崇高な作業となる。小説はロマンではなく、推理ゲームの素材だという信念から、各章の頭に、日時、時間、場所を明記した。近代化確立こそ(彼の欲求にしたがえば)、後進国文化からの脱却の正道なのだった。
もう一つ彼が定理とした要素は、ヒーローとしての探偵という観念だ。この点では、作者はニーチェ主義に忠誠を捧げた。探偵は超人である。「神は死んだ」のだからミステリ世界にあっても、神はいない。いるのは超人だ。このような極端な主張は、ヴァン・ダイン以前にはだれも公にしていない。探偵は、限定された作品世界にあって、オールマイティなのだ。ヒーローと作者は幸福な一致をみている。
また、探偵の装飾物として度外れたペダンティズムも導入した。知識は力なりだった。超人探偵とペダンティズム。二つながらに、彼の理想としたミステリ近代化路線を大幅にはみ出す要素だった。

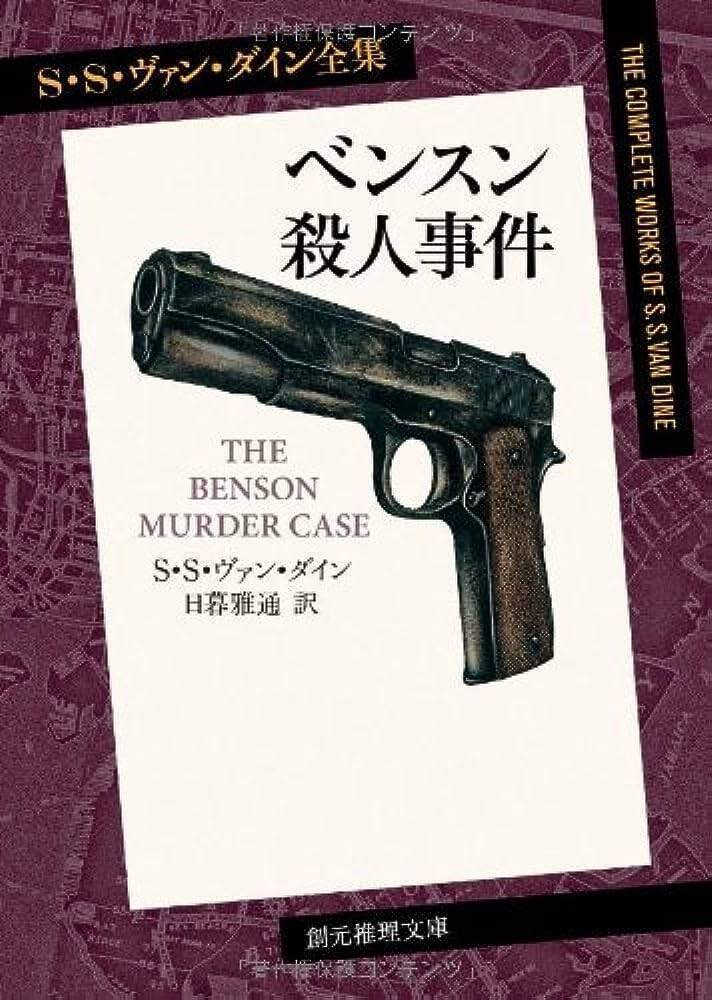
他の翻訳にーー
松本正雄訳 世界探偵小説全集 第20巻 平凡社 1930
延原謙訳 新樹社 1950
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
