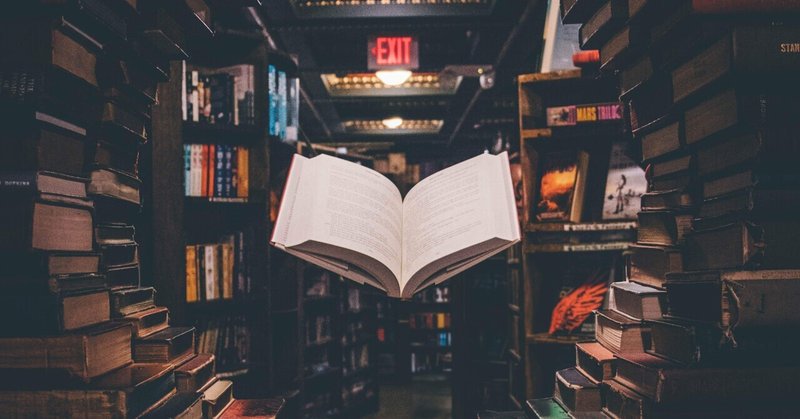
白紙の文学書の構造について。自律型の小説世界という可能性。
※この記事は文豪ストレイドッグスの考察です。
本とは一体全体なんなのか。
本が作られた意図、本を作った人物、本による洗脳を破ることができる理由、物語的整合性という制約、この辺りを検討することが本の実体を知る鍵になりそうだなと思いつつも、まだまだ情報が少ないので全然わからない…
ということで、俯瞰して見てみたら何か気づきが得られるかもと思い、引きで見た図を作って、文スト世界の構造そのものについて考えてみました。
■文スト世界は「自律型の小説」であるという可能性
文スト世界の構造を考える前に、まず一般的に物語がどう生まれるのかを図に表してみました。

書き手(著者)は物語の外にいて、いわば創造主として君臨していると思います。書き手の脳内に広がる想像性の海から着想を得て、それを原稿(白紙の本)に書き出すことで物語が誕生し、小説になると思います。この時、物語の内容を入れ替えたい場合は、別の想像から再び物語を組み上げ、書き手が原稿の内容を書き換えることで、物語の入れ替えが完了します。
…敢えて説明するほどのことでもないですね。
文スト世界にある白紙の本も、この「原稿」と機能は同じだと思います。しかしそれが物語の外ではなく、物語の中に内在しているという点で極めて異端です。書き手は物語の外ではなく、物語の中にいることになります。

書き手という創造主が物語の外にいない以上、想像力の源泉となるべきものも存在しないので、その分、白紙の本の中に組み込まれた「可能世界」という名の想像性の海から物語が誕生することになっています。
原稿である白紙の本に書き込んで世界を入れ替えることは、すなわち一般の小説で書き手が物語を書き換えるのと同じ行為にあたると考えられます。
だからこそ、白紙の本に何かを書くという行為は、物語の外にいる書き手の役割を担うことになり、いわば「世界の創造主」もしくは「神」になることと同じと言っていいのかもしれません。
物語の中にいる人物が自分たちの手で「文スト世界」という物語を創造し、演じ、書き換える。物語の中にいる人物だけで小説の構造が完結している「自律型の小説」という見方ができます。
■文スト世界を創ったのは誰か
では、なぜ文スト世界では、本来外にあるはずの「原稿」が物語の中に存在しているのか。この世界の構造を創ったのはそもそも誰で、何の目的があったのか。仕掛け人は、物語の中の人か、それとも物語の外の人か。
このあたりが気になります。
まだまだ情報が明かされていないので、ここからは妄想を働かせていくつか適当な仮説を考えてみたいと思います。
仮説①仕掛け人は物語の外の人
白紙の本が文スト世界の構造そのものに最初から組み込まれていた。どこかの誰かが意図的に自律型の小説世界を組み上げたという仮説です。
自律型の小説世界は、初期設定さえあればあとは勝手に登場人物たちが白紙の本に書き込んで続きを作ってくれるので、なんとも楽ちんな創作活動ですね…。創造主ではなく、登場人物たちが話を作っていく、新しい時代の本とも言えます。
さらに言えば、この初期の立ち上げは人の手でなくてもできてしまう。
例えば、自律型小説というコンピュータプログラムだってあり得るはずです。初期データをランダムに投入して生まれる仮想世界。あるいは適切なキャラクター像や設定をビッグデータから算出して初期値にする。その後は、登場人物が持つ自発性に任せれば、自動的に物語が生成されていく。
たった2383行あれば、一人の人間の人格はできあがるわけですから。
だとしたら白紙の本とはもはや機構みたいなものなのかもしれません。
書き手や作り手がいない、自発的に架空世界が生まれる「物語発生機構」です。
この仮説を前提にすると、白紙の本を封印しているということは世界の持つ本来の意図を妨害していることになるので、封印している人たちは権力を奪い去った悪い奴ら、ということになります。神を封じ込めているという言い方もできます。
②仕掛け人は物語の中の人。
白紙の本が本物の世界にスクリーンをかけている(洗脳している)という可能性です。もともと存在していた何の変哲もない文スト世界を、物語の中の誰かが自律型小説の仕様に変えた。文スト世界の中にそういう技術を持った人がいたことになります。
目的は世界を都合よく改変して支配できるようにするため、何かの実験のため、などが思い浮かびます。そうなると本を封印して守っている人たちは、悪を阻止しようとする正義の側の人、ということになります。
■本による洗脳を解く、頁が破れることの意味
上で書いた可能性のどちらにせよ、登場人物が見る世界は文字によって成り立っていると考えられます。
だとすると、文字が持つ「強度」とは?
そもそも人間にとって文字とは後天的に習得した技術に過ぎません。
文字は確かに文明を発展させたし、文字を使うからこそ私たちは人間なわけだけれども、人間にはもっと本質的に備わっているものがあるのでは?
文字が誕生する前から人間に備わっていたもの。
あるいは文明が崩壊し記憶を失っても、それでもなお残るもの。
それこそが魂であり心なのかもしれないなと思います。
だから魂は文字よりも強い、それ故に文字で生み出された制約を打破する力がある、ということなのかもしれません。
■物語的因果整合性という制約
物語的因果整合性がないとダメということは、小説として認められるものでないと受け付けてくれない、ということでもあると思います。
白紙の本を担当している編集さんでもいるの?出版社に撥ねられるの?みたいな愚問が思い浮かんでしまうけれど、文豪にとって小説の完成度というのは確かに死活問題なわけで。
世界自体が文字で構築された小説だからこそ、改変を読み込ませるには同じような小説の形になっていないといけないというのはなんとなくイメージが湧く気もします。
小説ではなくて、プログラムに置き換えて考えてみるともう少しわかりやすいかもしれません。
小説世界がプログラミング言語で出来上がってるとしたら、何かを変えたければ、同じようにプログラミング言語で書き直すしかない。それも、ある一定の決められたルールに基づいた文字式である必要性があります。
そうでないとコンピュータは正しく認識してくれないですからね。
それと同じようなものなのかもしれないなぁとも思っています。
一個前の考察ではジョージオーウェル云々言ってたり、少し前は異能者は堕天使だとか言っていたのに、掌を返したようにプログラム説とか言いやがって何なんだお前は、と思われるかもしれませんが、所詮カフカ先生に答えを教えてもらうまでのブレスト大会に過ぎませんので、どうかご容赦くださいませ。
白紙の文学書についてはこれから色々なことが明かされていくと思いますので、折々でまた考察を書いていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
