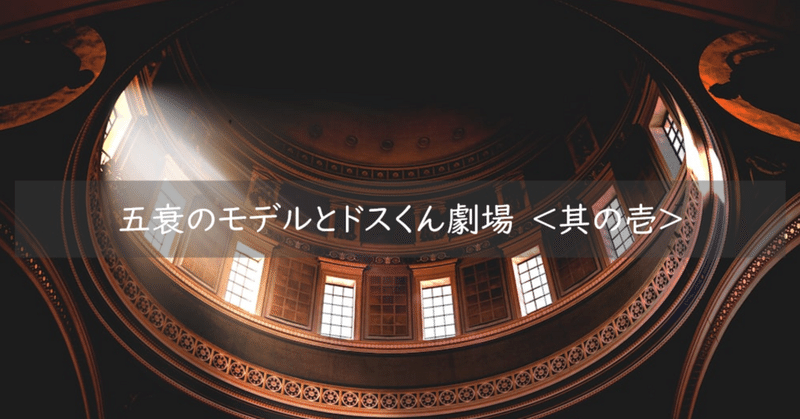
五衰のモデルとドスくん劇場<其の壱>
※この記事は文豪ストレイドッグスの考察です。
天人五衰のメンバーは、各々がドストエフスキー作品の登場人物の面影を宿しているように見えます。
福地は『罪と罰』のラスコーリニコフ、ゴーゴリは『悪霊』のキリーロフ、シグマは『賭博者』のアレクセイ、ブラムは『白痴』のロゴージン、そしてドスくんは『カラマーゾフの兄弟』の悪魔(イワン)。
五衰の作戦参謀がドスくんなだけあって、彼らの語る言葉や役柄はさながら「ドストエフスキー劇場」。
天人五衰を考察しているつもりが、気付いたら史実のドストエフスキー作品を考察させられている…?と錯覚してしまうほど。
ということで、五衰の構成員とドストエフスキー作品の登場人物の共通点について探っていきたいと思います。長くなってしまったので、記事は二回分に分けてお届けします!今回は其の壱。
■福地のモデル:『罪と罰』ラスコーリニコフ
五衰のボスとも言える福地は、世界平和の実現のために為政者を殺し、国家を消滅させることを目論見ました。
一部の人間の命を犠牲にして大多数の人間の命を救い、より良き世界を実現する。
この考え方は、正当な目的に則った殺人は正当化される、というナポレオン思想を描いた『罪と罰』のテーマと非常によく似ています。
共通点①:非凡人はより良き世界のために血を踏み越える権利がある
『罪と罰』の主人公であるラスコーリニコフは、大きく分けて二つの思想に囚われていました。
ひとつは、世の中には「凡人」と「非凡人」の二種類の人間がいるという思想。もうひとつは、「非凡人」には人類の発展のために正当な殺人を犯す権利があるという思想。
非凡人が自らの良心を乗り越えて目的を完遂した後にはたとえ人殺しでも英雄として称えられると考えていました。
歴史的にもこの思想の正しさは証明されています。秦の始皇帝であれナポレオンであれ、数々の人命の犠牲なくしては大きな変革を成し遂げることはできませんでした。
それどころか、戦争という行為そのものが、この思想の正しさの裏付けになっているとも言えます。
歴史的に、一国の権力者が戦争を遂行する場合、それによって多くの人命が奪われるという現実が存在します。しかし、戦争を成功裡に遂行した権力者=強者は、裁かれることなく生き延びることができます。生き延びることができるどころか、栄光さえも与えられる。
非凡人として世界に君臨していた福地は、世界平和の実現を自分の使命だと思ってテロを起こしたわけですが、悪びれもせずに「来年には英雄自叙伝の序文になっておるだろう」と立原に告げています。
例え為政者を皆殺しにしようとも、全ての改革が終わった後には平和の代名詞として自分には栄光が与えられるだろうというこの考えは、まるでラスコーリニコフのようだなと感じます。
共通点②:少数の犠牲が多数の人命を救う
非凡人として世界をより良いものにするためにラスコーリニコフが目を付けたのは金貸し老婆でした。
その老婆は不当に高い金利で弱者にお金を貸していて、高金利で儲けたお金で金品を蓄えていました。そしてラスコーリニコフはこう思います。
もし老婆を殺したら、老婆にこれまで搾取されていた哀れな弱者たちを負債から救うことができる。さらにこの老婆が蓄えていた金品を奪って、それを慈善事業に使って弱者に還元したらもっと多くの人が救われる、と。
そうして大義のもとに小さくテロをスタートさせたのです。
たった一つの生命のために、数千の生命が堕落と腐敗から救われるんだぜ。一つの死が百の生にかわるんだ――え、これは算術からいっても明瞭じゃないか!
500の命を犠牲にして2億の命を救うという福地の動機がアニメ61話で明かされたことから、福地も「人命の算術」をしていたことが伺えます。
余談ですが、「悪しき老婆から奪う」という点で『罪と罰』と『羅生門』は似ています。
ラスコーリニコフたる福地が、船上で芥川を勧誘したときに「君と儂は似た者同士だ」と告げていた背景には、こういう史実の繋がりもあったかもしれないなと想像しています。
共通点③:良心の呵責こそが罪に対する罰である
思想に則った殺人を遂行するにあたって、最も大きな課題となるのは、本人が持つ「良心」の問題です。
例え、世界の理が殺人を許したとしても、殺す本人がその行為による罪の意識に耐えられなくなれば、目的を完遂できず計画が頓挫してしまうこともある。その結果に残るのは、大義を失った故に無意味な犠牲となってしまった血潮の海ではないでしょうか。
良心のある人間なら、自分の過失を自覚した以上、自分で勝手に苦しむがいい。これがその男に対する罰ですよ――懲役以外のね
福地がどれほど良心に悩まされていたかは不明ですが、「まだ天は儂に使命を手放させてはくれんか」という船上での台詞から、精神的に疲れ果て死を望む福地の苦しみが垣間見えるように思います。
共通点④:望まれる「終末」
ラスコーリニコフは終末思想の持主でもあり、その点も福地さんとの共通項です。
新しいエルサレム、すなわち終末のあとに訪れる神の国が実現すれば、世界には争いのない調和がもたらされる。そのためにも世界をカオス的な状態へと導いて終末の気運を高めていくことが必要だという考えがありました。
空港の滑走路で、終末の喜劇を再現しようとしていた福地の背景にも、終末の先でこそ真の平和は実現できるというドストエフスキーの考え方が投影されていたのかもしれません。
そしてその喜劇たる終末の到来をいつも阻止してしまうのが探偵社であり、喜劇の進行を否定した結果に生じた悲劇が「黄昏のさようなら」ではなかったかなと思います。
探偵社は悲劇を受け入れながら痛みや苦しみとともに生きようとする組織だということを改めて実感させられますね。
共通点⑤:ふたつに断ち割られた男
福地とラスコーリニコフのもうひとつの共通点に、二人とも断ち割られている、という点が挙げられます。
「正義感に満ちた弱者への憐れみ」と「悪魔的な傲慢さ」のふたつを同時に持つ男。
ラスコーリニコフは無垢な人間に対しては人間的な正義感を抱いていました。それは福地も同じでしょう。罪のない子どもをこれ以上殺せないと苦しんだ福地は、無垢な人民に対しては強い良心を抱いている。
しかし、為政者を殺害しようとする傲慢さはあります。為政者の命が犠牲になるときにはそれほど心は痛まない。なぜなら彼らが戦争の元凶であり、仲間が命を落としたのも為政者の無思慮によるものだから。
戦争を無くしたいという美しい大義の裏には、為政者を諸悪の根源と捉えて一掃しようとする悪魔のように冷えた倫理観がありました。
500人の人命を直接自らの手で奪うことから来る罪悪感と、未来の2億1千万の人命を見殺しにすることから来る罪悪感は果たしてどちらが重いでしょうか。
福地の場合、為政者に対して抱く罪悪感と無垢な人民に対して抱く罪悪感はおそらく等価ではありません。
為政者の命に対して抱く罪悪感の方が圧倒的に軽い。それが福地の良心の在り方ではなかったかなと思います。
共通点⑥:自白か、それとも自殺か
『罪と罰』のラスコーリニコフは最終的に自分の大義を完遂できずに自白し、シベリア流刑になりました。
自殺か、自白か、そのどちらかしかないとラスコーリニコフは思い至ったのですが、そんな彼の末路は、自白した上でテロリストとして友に裁きを下してもらおうとした福地の最期の姿とも重なります。
共通点⑦:「英雄」を背負う
ラスコーリニコフの本名はロジオーン・ロマーノヴィチ・ラスコーリニコフ。
ロジオーンというロシア語には「英雄」という意味があるそうなので、英雄の役割を背負わされた登場人物という点でも、福地とラスコーリニコフは共通しているといえます。
さて、福地とラスコーリニコフの共通点の多さを感じ取って頂けましたでしょうか。個人的には、夢の中で福地とラスコーリニコフがごちゃまぜになってしまうほどにこの二人は似ていると感じています。
しかし、これはまだまだ序の口。他の五衰メンバーについては、次の記事でお話したいと思います。
関連記事:
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
