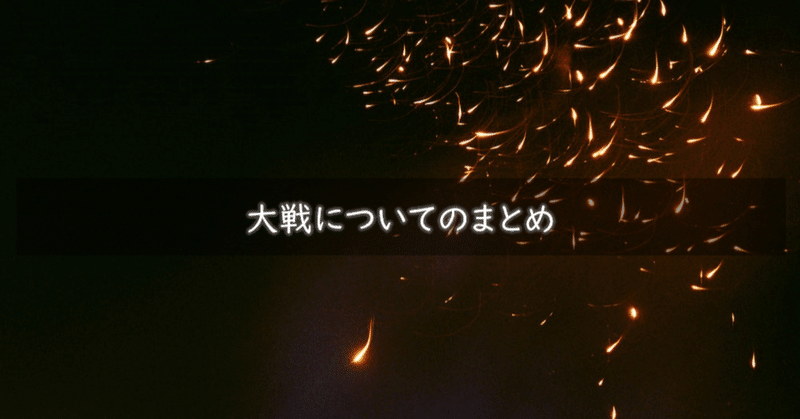
大戦についてのまとめ(お題箱から)
※この記事は文豪ストレイドッグスの考察です。
※お題箱に頂いたお題への返信です。
※大戦絡みの部分のみ、単行本と各小説のネタバレあります。
頂いたお題はこちら:
高等な考察が飛び交う中、不躾な質問失礼します。
蝶を夢むで女医先生の過去が明らかになりましたが、過去の戦争というのはどことどこが戦って、どこが勝ち、どこが負けたのでしょうか。
ぶんすとは文豪と異能力を掛け合わせた面白さ、声優や演出が好きなのですが軍や戦争の話になるとどうしても話が頭に入らなくなってしまって、、、
こんな私でも理解しやすいようにご教示いただけますと幸いです。
お題ありがとうございます!大戦のお題は初めてだったのでいい機会を頂き感謝です。
どことどこが戦って、どこが勝ち、どこが負けたのかですが…実はまだわかっていません…。それどころか、いつ始まって何年続いたのかすらもよくわからない。
かなり限られた情報しか明かされていないので、明かされている部分だけ拾って整理してみようと思います。多くは単行本、ストブリ、55minutesに書かれているものになります。
(55minにしか書かれていない重要情報って結構多いと思うのだけど、全然メディア化されないのよね…)
蝶を夢むであのような回想が出てきて、なんだか難しい…と不安になりますよね。でも大丈夫です。
そんなに複雑なことは描かれていないし、正直気にしなくてもわからなくてもさほど問題はないです。
大戦について特に理解していなくても文ストは十分楽しめると思いますのでね。気楽にいきましょう。
■大戦について最低限知っておいた方がいいこと
大戦は今のところ、終戦間際の「大戦末期」と言われる時期の出来事しか基本的には明かされていません。
大戦の基本情報としてわかっていることは、
①ドイツは日本の同盟国だった
②日本は異能を戦争に応用できなかったために敗戦した(だからこそ森さんは軍に異能の価値を訴えていた)
③異能力者が強制的に為政者に和平協定を結ばせたことで戦争が終結した
の3つくらいでしょうか。この終戦時の和平協定に日本側で絡んでいたと思われるのが探偵社設立秘話で描かれた福沢の継戦論者暗殺という過去になります。
文ストの大戦が史実の戦争をモチーフにしているかどうかわかりませんが、第二次世界大戦でも日本とドイツは同盟国であり、両国とも敗戦しています。
もし大戦が第二次世界大戦をモチーフにしているものなら、日本ドイツイタリアが負け、イギリスフランス米国ロシアが勝っていると思われますが、推測の域を出ません。
フィッツの発言からしても米国が戦勝国である可能性は高そう?(こんな野蛮な未開の国、とか言われちゃってますからね…)
最低限理解しておく必要があるのは、これくらいかなと個人的には思います。ね、大した情報量じゃないでしょう。
もう少し詳しく理解したい方のために、もう少しだけ書きますね。
■大戦末期のあらまし
大戦末期のおおまかな出来事の流れを整理してみるとこんな感じになるでしょうか。
・常闇島での大戦(大戦末期の主戦場)
森さんと与謝野さんの回想で描かれたとおり、火器も不十分な中での消耗戦が繰り広げられていた。
日本は異能者の活用や異能兵器の開発で後れを取っていた模様。だからこそ森さんは軍に異能力の価値を懸命に訴えていた。
・その頃、他国ではユゴー(仏)、ゲーテ(独)、シェイクスピア(英)などの超越者が激突し、大戦は苛烈を極めていた。ドイツ、フランス、イギリスは軍事研究でも激しく競り合っていた。
異能に適応した国々は、異能兵器の開発に成功した。英国では特異点を意図的に発生させて兵器に転用する研究も行われ、それによって殻が生まれた。
・フランスのヴェルヌが異能を使ってスタンダード島を建設。(表面上はその島を英独仏が統治)
ヴェルヌが島を建設した目的は戦争を終わらせるため。そこに各国の重要人物を集めて、脅しながら強制的に和平協定を結ばせた。
その脅迫まがいの和平協定を締結するために暗躍していたのが「七人の裏切り者」と呼ばれる超級異能力者の犯罪者たち。ヴェルヌもその一人。
・日本では福沢が政府内の継戦論者を暗殺して、戦争の終結に寄与する。福沢は「戦場にあるのは命を奪う所業だけだ」と考えていた。
・戦争終結は和平協定によってもたらされたが、その中でどのようにして日本が敗戦国にされたのかは不明。
国連の委員長曰く、「先の大戦では異能兵器という時代の流れに適応した国が勝った」ということなので、日本はその流れに適応できなかったと思われる。
他にも単行本23巻では、福沢さんが大戦中の色々な問題点などを挙げていたりしますが、難しい話が多いですし、「福沢さんの目から見た、福沢さんが考える戦争の姿」に近しいものかなと思うので、ここでは割愛します。
■文豪と戦争
ここからは文ストがなぜ戦争を取り上げているのか、という点について書いてみようと思います。
まずはこちらの表をご覧ください。(1年程前に作ってみたはいいものの、ずっと日の目を見ることがなかった可哀想な表。ようやく出番きた。見づらくてすみません。)
文豪が生きた年代と主要な戦争の時期を記しています。

この表からわかるとおり、登場人物のモデルとなっている文豪の多くは戦争が行われていた時代を生きています。
戦争との関わりとして有名なところでは、例えば森鴎外は陸軍軍医として勤務し、実際に日清戦争と日露戦争に出征しています。
他にも、太宰治は東京大空襲と甲府空襲の二度の空襲を経験していますし、坂口安吾も東京大空襲を経験し、焼野原となった東京の姿をありありと『堕落論』の中で書いていたりします。
疎開したり防空壕に逃げ込むという実際の経験が本人に与える影響は計り知れないでしょうし、身近な人を亡くすことも当然のようにあったはずです。
それだけでなく開戦の噂を聞き、終戦の放送を聞き、その折々で人々の変動をつぶさに見てきた近代の文豪は、みな戦争と隣り合わせで生きてきたとも言えるかもしれません。
その経験は文豪の人生への影響に留まらず、彼らの思想や文学への姿勢にも少なからず影響を与えてきたであろうと考えると、戦争というテーマは文豪を描く際には切っても切り離せないものなのではないでしょうか。
とはいいつつも、戦争について現代の私たちが具体的にイメージできることや共感できる部分は残念ながらほとんどなく、戦争というだけで、遠い世界のよくわからない難しい話だと感じてしまいますよね。
だからこそ、蝶を夢むを観て、森さんのSっぷりに戦慄したり、与謝野さんにもたらされた救いに涙したり、立原兄や兵士さんたちが精神的に追い詰められていく様を眺めたり、ただそうやってキャラに寄り添ってぼんやり追体験するだけで十分なんだと思います。
あまり頭で戦争のことを捉えようとせずとも、物語を楽しんで実際に自分の感情が揺れ動くという体験をすることにこそ価値があるんじゃないかなあと考えています。
貴重なお題を頂き、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
