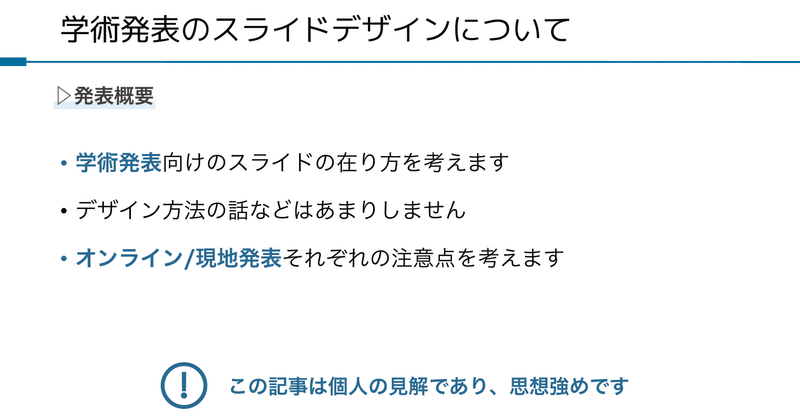
学術発表のスライドデザインについて
はじめに
こんにちは、2回目の投稿です。
私の所属する研究室ではプレゼンテーションの練習の場があり、同僚や指導教員からさまざまなフィードバックをいただけます。この記事では、私が考えていること、そしてフィードバックしてもらったことなどをまとめます。
おことわり
私はデザイナーではありませんし、学術発表の経験が豊富なわけでもありません。これは、これから書く内容の妥当性が不確かなことと、私自身の思想がこの先大きく変化しうることを意味します。一個人の現時点での思想としてご笑覧ください。
この記事では基礎的なデザイン方法については触れません。『伝わるデザイン』、『ノンデザイナーズ・デザインブック』など、数多の良記事・良書があるからです。特に『伝わるデザイン』は、学術発表をするすべての人が必読の内容だと考えています。
今回は、デザインの詳細はそれらに譲り、自分なりの考えについて多く触れられればと思います。
学術発表のスライドの特徴
私はタイトルで「学術発表の」スライドと書きました。というのも、「スライドデザイン」というだけでは千差万別だからです。スティーブ・ジョブスのプレゼンテーションと官公庁のプレゼンテーションでは、スライドの役割は全く違います。
ここで私が考える「学術発表スライド」の特徴は、
論文などを紹介する役割であることが多い:多くの場合、プレゼンテーションは論文を紹介する役割を果たします。つまり、スライドに全ての情報を詰め込む必要はなく、「細かいところは論文を読んでくれ」と逃げられます。この点で、官公庁のスライド(俗にいう「お役所スライド」)と一線を画します。
スライド自体にある程度情報が載っている方がよい:情報は喋りで全て伝え、スライドはビジュアルイメージとしてのみ使う、TEDのようなプレゼンもあります。しかし、アクセシビリティの観点からも、発表する内容の複雑さからも、スライドにも文言などでしっかり情報を載せる必要があります。
ブランディングの道具ではない:企業のプレゼンは、その企業の「顔」としての役割があります。企業のブランドイメージの観点からも、統一されたテンプレートを使うことが多いでしょう。例えばコーポレートカラーが赤の企業は、スライドも赤を多く使うのが自然です。
しかし、研究発表は基本的に、研究そのものだけを売り込むものです。従って、アクセントカラーを使うこと自体は良いものの、あまり強い印象を与えすぎないデザインにするのがよいと考えています。
などです。従って、本記事では上の内容に沿った話をしていきます。
※学術発表でも、印象を残すことが重要なプレゼン形態(ライトニングトークなど)の場合は当てはまらないことも多いと思います。この記事では、一般的な論文紹介などを主に想定しています。
根本的な思想
特に学術発表のスライドについて、「スライドの評価は減点法」と考えています。もし私がスライドを100点満点で評価するなら、どんなにおしゃれなスライドだとしても、3点くらいしか加点しません。一方で、文字が小さい、文が長すぎて読めない、レイアウトがわかりにくい、といった瑕疵があればそれぞれにつき10点くらい減点すると思います。
(企業のブランディングを兼ねたスライドなら、おしゃれさはもう少し評価されると思いますが、学術発表の場合評価の対象にならないという思想です。)
学術発表におけるスライドの役割はたった一つ。「どれだけ研究の内容や魅力を素直に、わかりやすく伝えられるか」です。その際、文字が読みにくかったりレイアウトがわかりにくければ、理解の妨げになります。ただでさえ難しい研究内容を、瑕疵のあるデザインでどうやって伝えられるというのでしょう。
私は理想のスライドを「空気のようなスライド」と呼びます。空気のような、と言うとネガティブに聞こえるかもしれません。しかしここで表現したいのは「違和感なく当たり前に受け入れられる」こと、そして、「呼吸のように自然に情報を吸収できる」ということです。視聴者が無意識に発表内容を理解し、研究内容に思索をめぐらせられる。そのようなスライドこそが良いスライドだと考えます。
この点は、英語での発表を聞くようになってから強く感じたことでもあります。日本語での発表なら、スライドが分かりにくくても話を聞けば追いつけます。しかし、国際学会等での英語発表の場合、英語が聞き取れずスライドを見ると...情報が頭に入ってこない! といったプチパニックになります。「空気のように」情報を得られることの貴重さが痛感できた瞬間です。
私が注意していること
スライドを作る上で気をつけていることを書きます。一般的なデザインの話(基本的にゴシック体を使う、など)は他の記事・書籍にゆずります。
色使い・レイアウトなど
基本的にグレースケール + 1色をアクセントで使います。グラフの塗り分けなどでその他の色を使うこともありますが、煩雑になるので最低限にとどめています。
グレースケールだけで作ったこともありますが、洗練された雰囲気になり、よかったです。
デフォルトのPowerPointのテンプレートだと、上のタイトル部の高さが高い&逆に、スライド下部は現地発表で見えにくい場合があります。そのため、スライドマスターでタイトル部を縮め、その分下部に余裕を持たせます。
レーザーポインター(やPowerPoint上の類似機能)はあまり使いません。むしろ、レーザーポインターを使わないでも視聴者がついてこれるのがあるべきデザインだと思っています。
ただし、デザインを工夫した上で、要所でレーザーポインターを使うこと自体は良いことだと考えます。
スライドの情報量
箇条書きを使いつつ、内容は多めに書きます。
スライドだけを読んでも内容が理解できる程度を目指しています。特に私自身は聞くより文字を見る方が情報が入ってきやすいので、その点でも情報量を盛り込むことは意識しています。
「良いデザインのスライド」というと、文言を絞って余白を広く取ったものが想像されるかもしれません。実際そのようなスライドはおしゃれで憧れますが、基本的には学術発表向きではないと考えています。
内容が多くなるので、太文字による強調を積極的に使います。強調の基準は「最低限その箇所を見れば内容が大体わかる」という程度を目指しています。強調が多くなりすぎると逆に目立たなくなるので、単語レベルで強調することが重要です。
こまやかな気配り
改行の位置に気を配ります。英語だと単語区切りで改行してくれますが、日本語の場合変な位置に改行がきます。PowerPoint(や他の多くの文書作成ソフト)ではShift+Enterで改行(≠改段落)ができるので、それを使います。
単語の途中で改行していると、一瞬意識が引っかかり、内容の理解を妨げます。「空気のようなスライド」という目標からすればこれは失敗となってしまいます。
当たり前ではありますが、レイアウト・スタイルに統一感を持たせます。例えば、強調は太文字なのか色付きなのか、フォントサイズは何なのか、と言った点です。
作例
以上の内容を踏まえた作例です。自分自身も良いデザインを模索中なので、意見などありましたら是非お寄せください。

オンライン発表と現地発表
近年はオンライン発表や現地発表、さらにはハイブリッドなど、さまざまな発表スタイルが存在します。
私は、オンライン発表と現地発表では、デザイン上注意すべき点が少し異なると考えています。
オンライン発表の特徴
オンライン発表では、視聴者は各自のデバイスで見ます。この際のメリット・デメリットは、
○各視聴者の手元でスライドを見られるので、多少文字が小さくても読める。
○発色が綺麗に目に入るので、コントラストの許容値が広く、細かいグラデーションなどが使いやすい。
○スライド全部が視界に入るので、制約が少ない。
×視聴者の表示環境にばらつきがある。例えばディスプレイによって発色や解像度が悪かったり、表示画面が小さかったりする。
×ネットワークが悪いと画面がスムーズに動かない。
×同じくネットワークのせいで、音声が途切れたり、最悪届かなかったりする
といったものが挙げられます。そのため、オンラインのスライドでは、
対面発表より、総じてデザインの自由度が高い。しかし、特に細いフォントを使う際に注意する必要がある
解像度が悪いディスプレイだと細い文字はうまく映らない
アニメーションは基本的に使わない
画面のラグによってうまく機能しません。
スライドに書く情報を多めにする
音声が途切れても内容を理解できるように、という理由です。対面発表より文字が小さくて良い分、情報を詰め込みやすいと思います。
と言った点が挙げられます。ネットワークの不調を想定した対応をすることが重要になると思います。
現地発表の特徴
現地発表は、会場内のスクリーンに映ったスライドを聴衆みんなが眺めるスタイルです。先ほど述べたオンライン発表と真逆のメリット・デメリットが存在するといえます。
○視聴者は基本的に同じ画面を見るので、解像度などを気にする必要はあまりない。
○(Zoomの画面投影、などの形式もありますが)HDMI接続なら、画面がカクつく心配はあまりない
○音声の不具合はない
×会場は広く、特に後ろの方に座る人には細かい文字は見えない。
×特にプロジェクタの場合、会場の明るさや投影機の性能により、細かな色使いが見えにくくなる。低コントラストの場合見えないことがある。
×前の聴衆の頭がかぶる、などの理由でスライド下部の文字が見えないことがある。
これらを踏まえて、対面発表のスライドのデザインは
動画による説明などを積極的に使える
パワポのアニメーションなどを使っても良い
ただし、アニメーションは画面を煩雑にする懸念があるので、情報を順番に出すために使う、などの用途に限定するのが良いでしょう。
見やすさにとにかく注意を払う
背景にむやみに色をつけない、薄い色を文字に使わない、文字サイズをデカくする、などです。
あまりスライド下部に情報を載せない
ページ番号や引用脚注などを下部に配置して、メインコンテンツは上寄りに配置するとよいです。特にPowerPointのデフォルトはタイトル部の高さが大きいので、縮めてしまうとコンテンツの高さが確保しやすいです。
といった点を意識すると良いでしょう。
実際には発表形態によってデザインを変えたりはせず、両者の最大公約数を攻めることが多いでしょう。特に、ハイブリッド形式では両方の形態で視聴されますので、いいとこ取りをしたデザインが求められると言えます。
おわりに
以上、学術発表スライドのデザインについて、自分の思想多めで話してきました。どんなデザインを良いと捉えるかは人によって大きく異なりますので、異論も多くあると思います。ただ、もしこの記事が、少しでも新たな視点をもたらせたら幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
