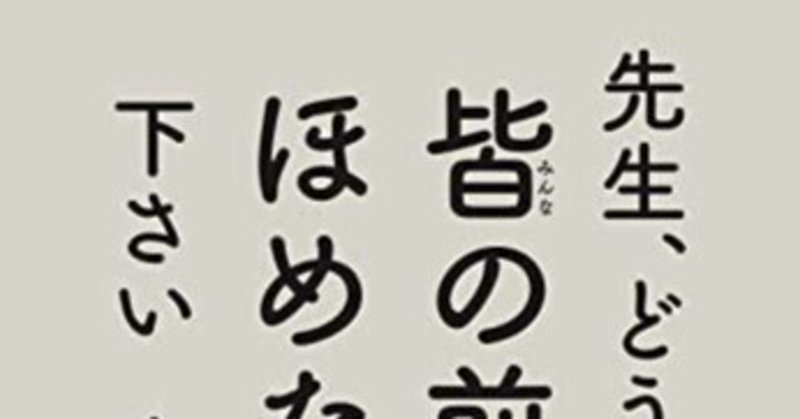
(Book)✨先生、どうかみんなの前で褒めないでください いい子症候群の若者達
自分が中学生の頃を思い出すと、かれこれ十六七年前になるのですが、それはもう苦しい世界でした。
クラスメートが裏山で決闘を始めるし、トイレで全裸になって遊んでる人達はいるし、人生の中で一番しんどかった時期だったように思います。
そんな時代から比べると、今の中高生はとってもいい子達のように思います。
そんないい子達を紐解く1冊、いい子症候群の若者たちです。
本の著者、金間先生は金沢大学融合研究融合学学系教授だそうで、エビデンスベースドで論理を展開してくれます。
よくある「個人のエピソードを世間一般論として話してきやがる」本とはきちんとテリトリーを分けていて、非常に説得力がありました。
たまに本を借りると「Twitterでバズりカウンセラーになった」みたいな著者の本があって、すごく萎えちゃうんですよね……やっぱりデータがないと信用ができないですね。
以下概要。
「いい子症候群」の若者たち
「最近の若者は…」は、いつの時代も定番フレーズ。もちろん時代とともに、少しずつ若者たちの心の中も変化しています。令和の若者に対しては、「まじめで素直」、「打たれ弱く、繊細で、何を考えているかわからない」といった声をしばしば耳にします。 本書では、「いい子症候群」というフレーズがぴったりな、今の若者たちが抱える複雑で微妙な心理や、行動原則を徹底分析します。
令和時代の若者心理、その驚くべき実像とは?
現代の若者にとっては、「目立つ」ことが最も怖いこと。「横並びでいたい」「浮くのが怖い」と思っており、この「いい子症候群」は社会人になってからも急に変わることはありません。
ーー若者からは、本当に多くのことを教わる。そして、もし変わる必要があるとしたら、それは彼らではなく大人が作った社会の方だと、強く感じさせられる。(p.10より)
学生や若手社員とのコミュニケーションの手助けとして、また、令和の若者たちが育った社会を考えるきっかけとして、複雑な若者たちの心理をのぞいてみませんか?
EqualityとEquity 公平と公正
理想の先生アンケートみたいなものが実施された際に、1番は「生徒を平等に取り扱うこと」であったことに驚いた思い出があります。
(ちなみに5位は顔がいいでした、身だしなみには気をつけます)
この本の内容も多分に漏れず、とにかく学生たちは平等が大切と感じているという調査結果でした。
例えば、りんごがここにあるとします。そして2人の学生がいたら、ひとりひとつもらう、これは公平(Equality)の発想です。
一方、片方が朝ごはんを食べていなかった場合は空腹で授業に集中できないし、もうひとりもあげるって言ってるから、その人に二個あげるというのが公正(Equity)の発想です。
調査によると、現代の学生は圧倒的に公平の価値観を大事にするそうです。
とにかく平等が大事。目立たないことが大事。集団の中の1人でいることが大事。
なんとなく自分の経験談からすると、本当にそうかなぁ?と思う疑問が拭えません。でもエビデンスには勝てませんね。
インスタライブは何のため?
人前に立つのが苦手な人間っていうのは、というか、日本人っていうのはすごくたくさんいるなっていうのは自分が中学の時から思っていました。
学級委員とか決めるのが遅くて遅くてしょうがない。誰もやらないんだったら、自分がやりますと言ったら「お前ばっかりやってもしょうがない」と担任に言われたのも覚えています。じゃあどうすんだよとも思ってました。基本的に学生の頃、教師っていう存在は嫌いだったから、この人達に教育を任せちゃいけないなって思って教育業界に馳せ参じた次第です。
でも、目立ちたいんですよね。委員長とかはやらないのに、メイクをしてきたり、眉毛を全剃りしてきたり。
目立ち方を履き違えてるのでは??と疑問に思ったりしていました。
現在でも目立ちたくない学生が多いと言いますが、インスタライブとかやってるんじゃないんですかね??それって、目立ちたいからやってるのでは……??
と非常に混乱します。目立てる場所で1歩引き、そうじゃないところで1歩前に出るっていうのが不思議だなと思います。
個性って必要?働く人とリクルートスーツ
大学3年生のときに就職活動をしていて「私服でいらしてください」って書いてあったんですね。
だからまあ、キレイめな感じの服装で行ったんですよ。そしたら周りみんなリクルートスーツで。
「え、私服で来てくださいって書いてあったじゃん?」と思ったのですが、友人にとりあえず安心安全だからみんなリクルートスーツで行くんだよと教えてもらいました。
そのとき、なんて就活って下らないんだろうって思いました。サジェスト無視して安定で行くのか、結局いかにテンプレに当てはめて、個性を消していくかが就活なのか……と感じました。
こんなに世の中ってつまらない人間で溢れてるのかって正直思いました。今思えば、バカバカしかったな。
でもあながち間違い行動ではないんですよね。若いうちって本当に出る杭は打たれるというか、ちょっとでも目立つと袋叩きにするのが日本社会の風潮だと思います。
特に新参者に対しては村意識が強い日本人はとても厳しい。自分も今の職場が四つ目ですが、今まで何度も何度も、特に初年度の時は、陰口を言われてきました。
なんで同じことをしているのにベテランの人は叩かれなくて、自分だけ叩かれるんだろうって常々思っていました。
日本社会で生きてくうちは、若い時に自分の意見を述べたりせずに、周りに合わせて既存のやり方に従属する方がメンタル的には穏やかに過ごせるんだなっていうのは嫌という程体感しました。
本当に働きづらいというか……今の職場ではその傾向が弱いので(悪口言われてるのに気づいてないだけかもしれませんが)ほんとに生きやすいです。
個性を消したい若者を裏付けるデータが理想的な会社というアンケート調査により示されていると本書で述べられている(マイナビ、2022)。
今の圧倒的人気の会社は「安定している会社」なのである。自分の個性が発揮できるより、会社自体の安定が重要なのである。
時代だなぁって思います。趣味とかが優先されるからなのかなぁ。
働くことって社会貢献だと思うんですけど、やりたいことより安定が優先されるのは心配です。働きやすさと働きがいが両立されるのかなあ
やりたいこと探しの罠〜みんながやりたいことあるわけじゃない問題〜
教育に携わっていると、将来のことについて考えなさいと言う機会が多くあります。
ただ、何の仕事をしたいかとかって全然分からないんですよね。自分も高校生の時、なりたい職業なんて思いもつかなかったし、ましてやこの仕事が立ち代り入れ替わりで消えてゆく時代に何の仕事をしたいっていうのも時代外れな気がします。
だから、どのように生きたいかっていうのの延長線上として、生きる手段としての仕事をビジョンとして考える必要があるように思います。
筆者は若者に向けて、しかも特にやりたいことがなく、悩んでいる若者へ向けて三つの問題を提起しています。
①やりたいことを世間が提示する選択肢のイメージに限定している
自分がやりたいことは公務員とか薬剤師とか、自分の知っている職業に限定する方の人達です。
自分の知っている世間一般で言われているような選択肢を並べただけなので、しっくりこず、興味がわきらないというパターン。
②「こと」に興味がない
人生の進路を決める際、考慮するのは「こと」「人」「場所」だと筆者は定義しています。
ことに興味がない人は、どういう人と働きたいかだとか、どういう場所で働きたいかとか考えている可能性があるということですね。
③本当にやりたいことがない
いい子症候群の若者は一般的な答えを自分の答えとして定義するため、やりたいことが見つかりづらいです。
この人達はとにかく言語化能力を高めることが最優先。身の回りにある物の好き嫌いをきちんと言語化することが必要です。
またやりたいことがないなら、目の前でやらなければいけないことに全力を尽くしてみると良いそうです。
こんな三パターンの呪縛に陥らないためには、以下2つを伸ばしていく必要があります。
①質問力を鍛える
人前で質問する必要はないので、疑問を持つことが大事ということです。
なぜ夕焼けは赤いのか、道路の舗装にはコンクリートが適しているのか、信号は何故赤と青なのかなどなど、帰り道でたくさん見つかるはずです。
携帯をいじっている人達って勿体ないなと思います。家でやればいいのに。外にいる時は人との交流や、身の回りにあるたくさんの人が考えて作り出した、事物に対して思いを馳せていくほうが断然頭良くなる気がします。
②メモを取ること
もちろん学校の授業でもメモを取ることは多いと思います。
先生の言ったこと、特に板書されていないことで、自分が知らないことはメモを取るべきだと思います。
加えて、自分が疑問に思ったことをメモ取ることが大事です。
そうすると自分だけのノートに仕上がります。自分が作ったものって自分好みにできているので、記憶の定着力も上がりますしね。
長くなりましたが、私が教育業界に勤めているのは1人でも多くの学生が将来幸せになってほしいからです。
そのアプローチが教育社会学であったり、社会心理学であったりと、エビデンスに基づいていることが自分の強みです。
本記事を読んでくださっている方々、どうもありがとうございます。参考になったでしょうか。
本社の著者、金間先生も書いておりましたが、これを読んで何か少し考えてくれると嬉しい、行動してくれると思っと嬉しい。その一言に尽きると思います。
非常にいい本だったので、同著者の他の本も読んでみようと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
