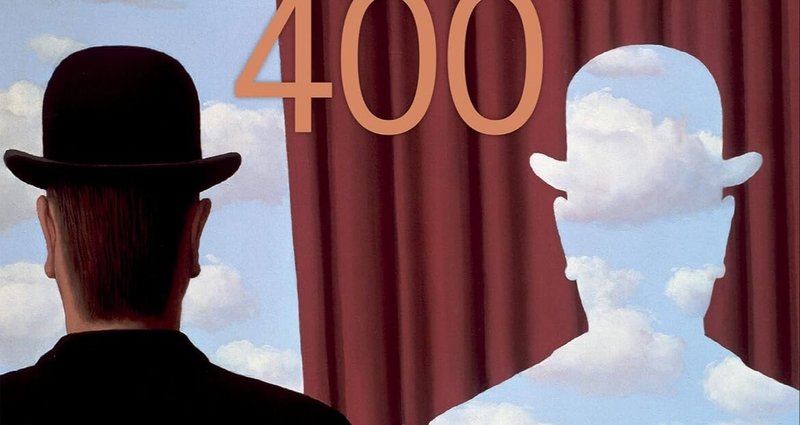#書評

【美術ブックリスト】Brainard Carey『Making it in the Art World : Strategies for Exhibitions and Funding』
訳すと『美術界で成功する : 展覧会と資金集めのための戦略』となる。 著者は奥さんとアートユニット「Praxis」を結成してコンセプチュアルアートやパフォーマンスを展開するアーティスト。無名だったにもかかわらずさまざまな「戦略」によって美術館で個展を開催するようになるまでになった。そんなアーティストとして成功するまでに実際に試した方法を次々と解説するのが本書。 例えば、これからやろうとしているプロジェクトをDVDにまとめ、すでに有名になっているアーティストたちに送って資金