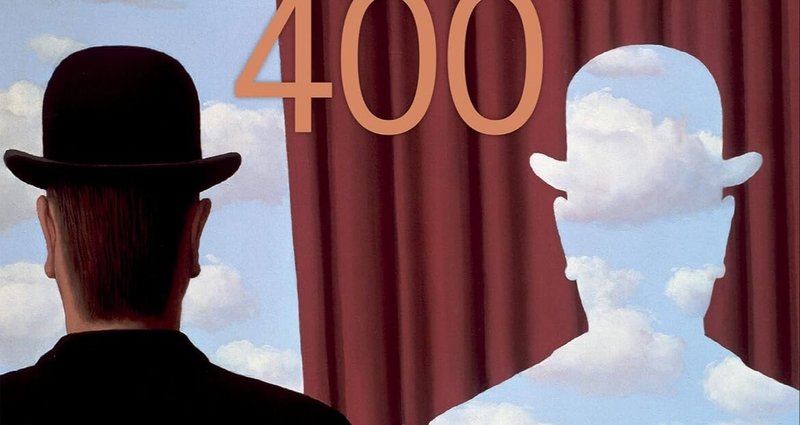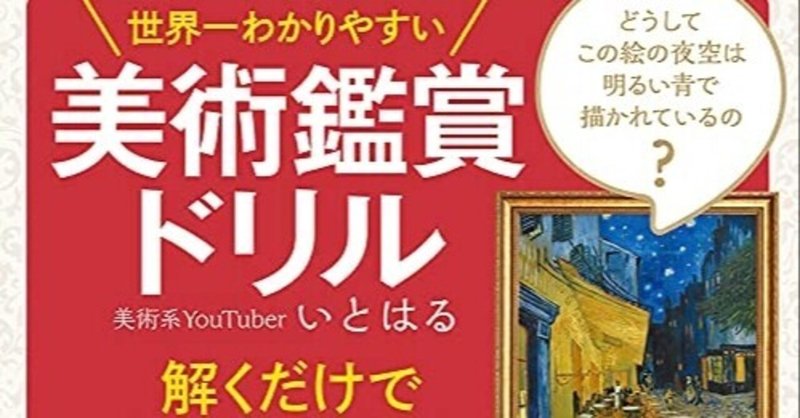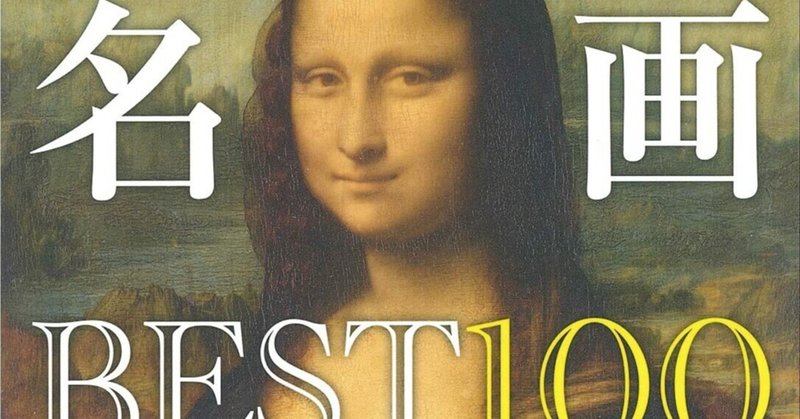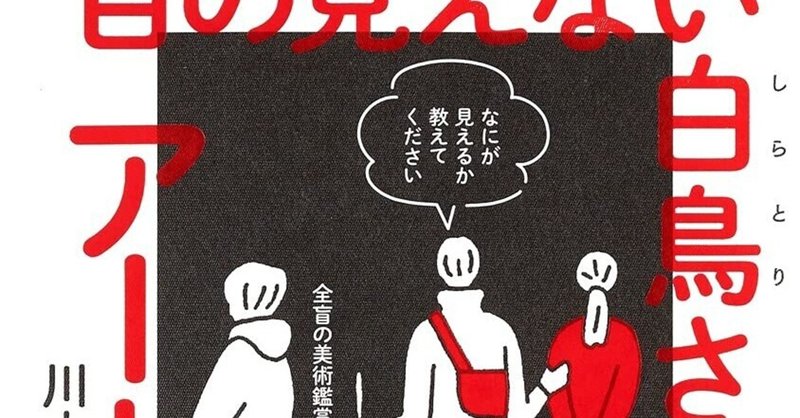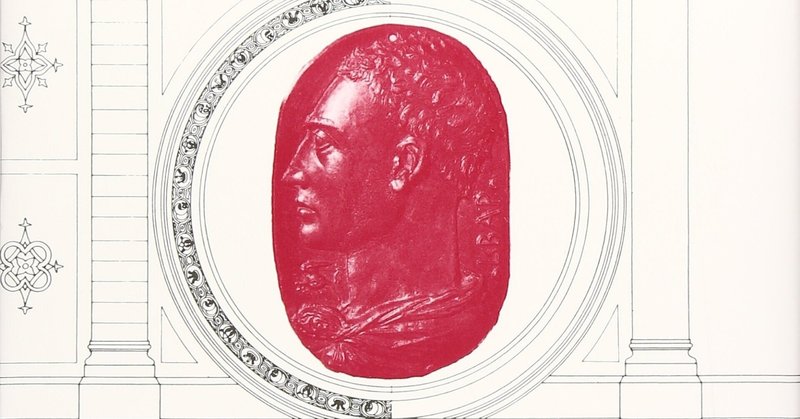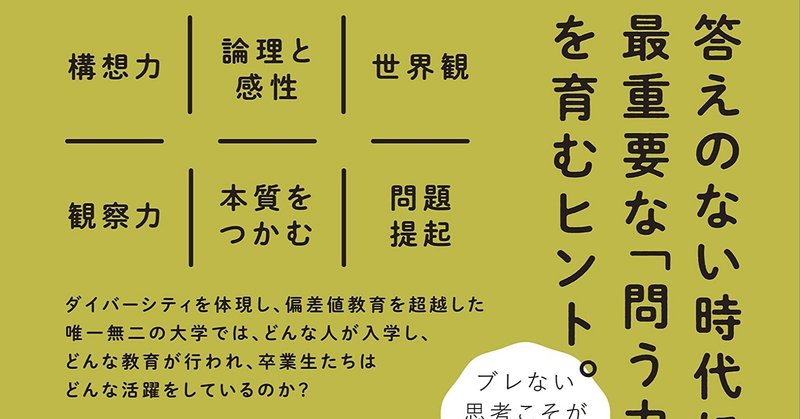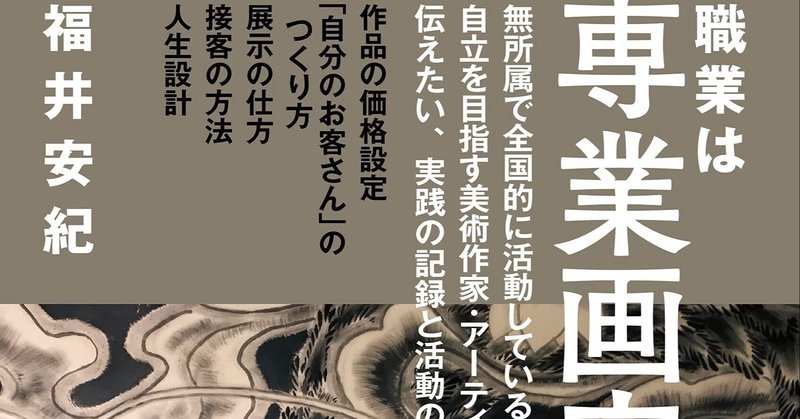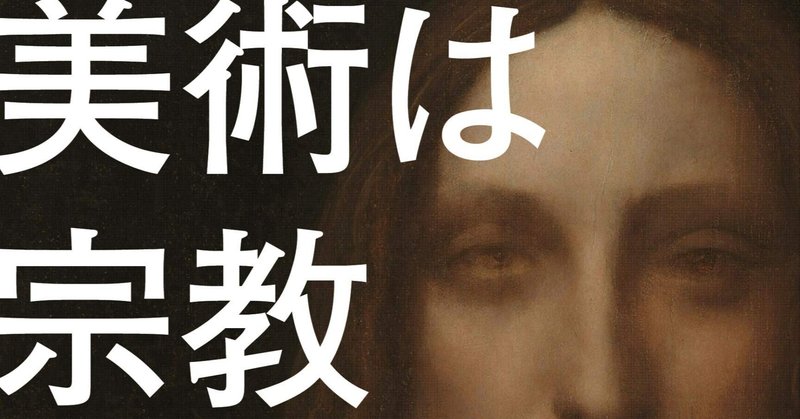#ブックカバーチャレンジ

【美術・アート系のブックリスト】 Magnus Resch著『How To Become A Successful Artist』 PHAIDON
著者はドイツ人研究者のマグナス・レッシュ。いくつかの大学でマーケティングに則ったアートマネージメントの講座をもつ一方、『Management of Art Galleries』いう、ギャラリストのための営業指南本で一躍有名なりました。Larry's Listというアートディーラー向けに大口コレクターを紹介するサイトの創立者の一人でもあります。 さてこの本は訳すと『アーティストとして成功する方法』でして、主にビジネススキルという観点から、アーティストになる方法を語っています。

【美術・アート系のブックリスト】 ジェイムズ・ホール著、高階秀爾監修『西洋美術解読事典: 絵画・彫刻における主題と象徴』河出書房新社(新装版)
1988年初版の事典の新装版。 聖書、神話、歴史的事実など、西洋の絵画と彫刻に登場する主題や象徴を調べるための事典。意味だけでなく、実際の作例の索引機能をもたせていて便利。 例えば、「指輪」の項目には、「権威の象徴」「結合の象徴」「聖職者の位」「三位一体」など作品の中でも様々な意味が列挙され、関連事項へ飛ぶように指示されます。 作品を見ながら、モチーフの一つ一つを読み解いていくこともできるし、象徴事典としてつ使うこともできます。プロメテウス、ヘラクレスなど神話の登場人物