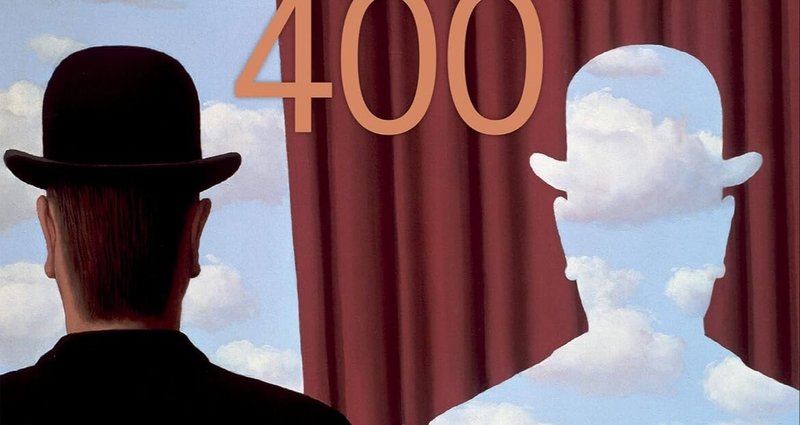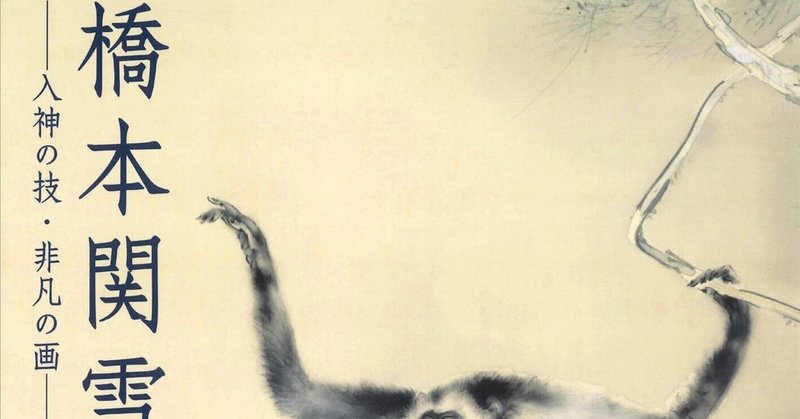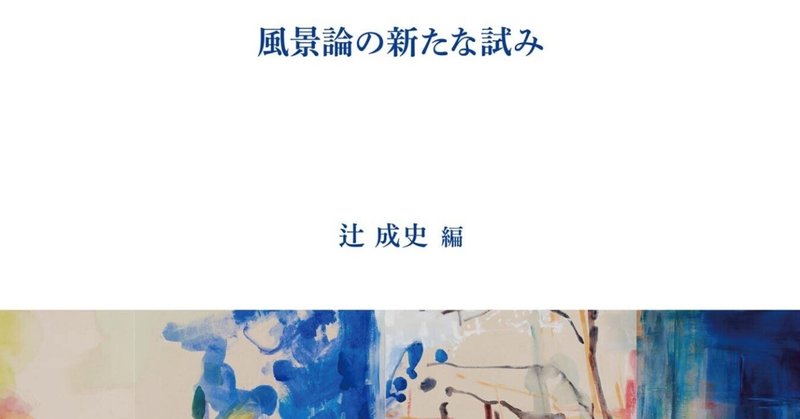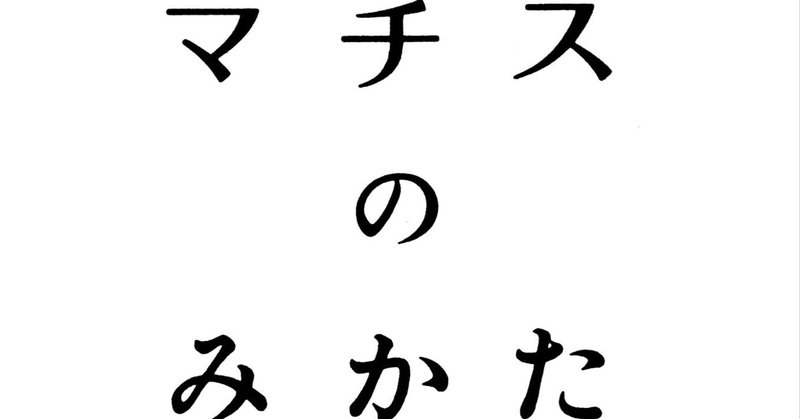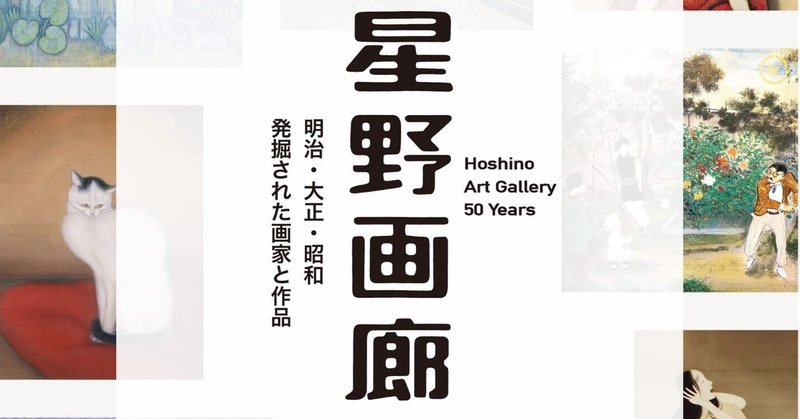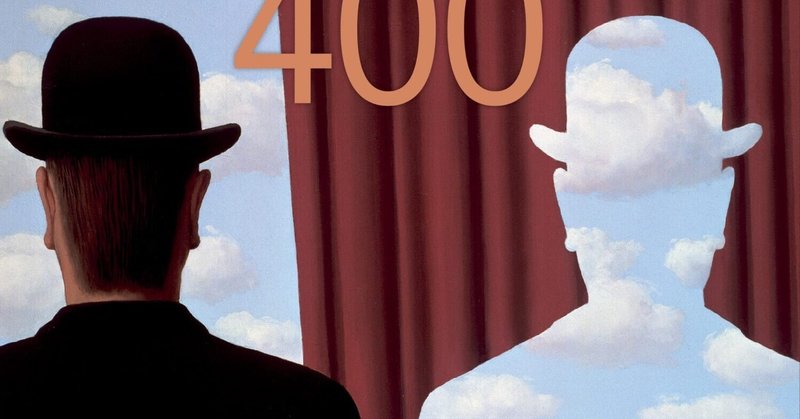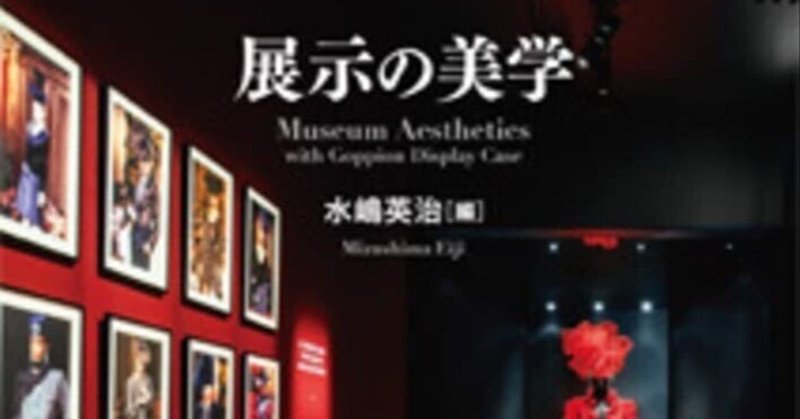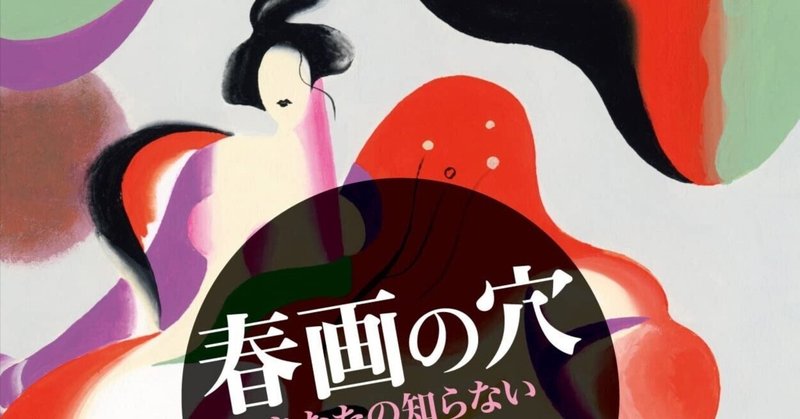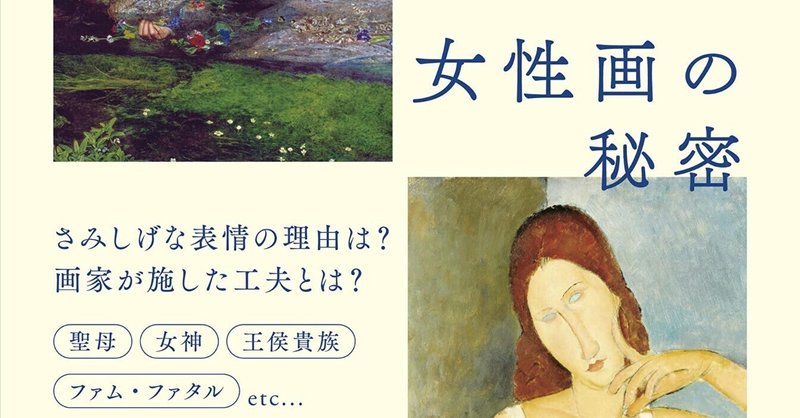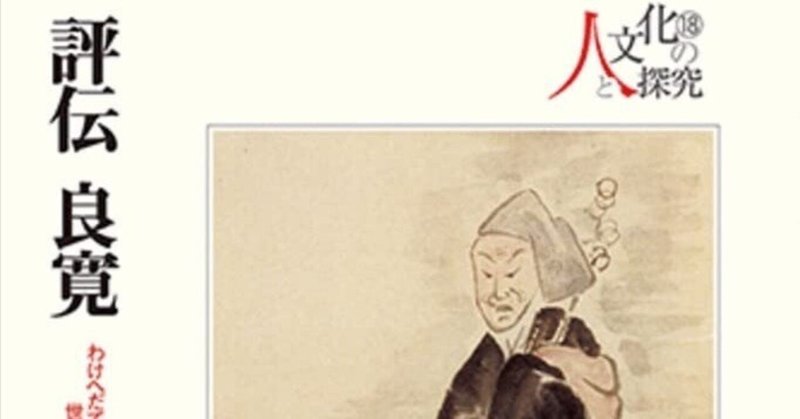2023年6月の記事一覧

【美術ブックリスト】『五角形と五芒星』Eli Maor著、Eugen Jostイラスト、宮崎興二監修・翻訳、パウロ・パトラシュク翻訳
著者は1937年生まれ、イスラエルで学びシカゴで教える数学史家。幾何学や三角法についての著作がある。 本書は五角形と五芒星について、約2500年にわたって数学、哲学、芸術、自然科学の世界で果たしてきた役割を詳細に記述する。幾何学的な性質から各分野に与えた影響を、数式とイラストで解説する。 五角形を神話的としたピタゴラス学派から、合金の5重対称性がノーベル賞受賞につながった研究、建築に見る五角形など、人類史の中での五角形を理解できる。 ここまでが概要。 ここからが感想。