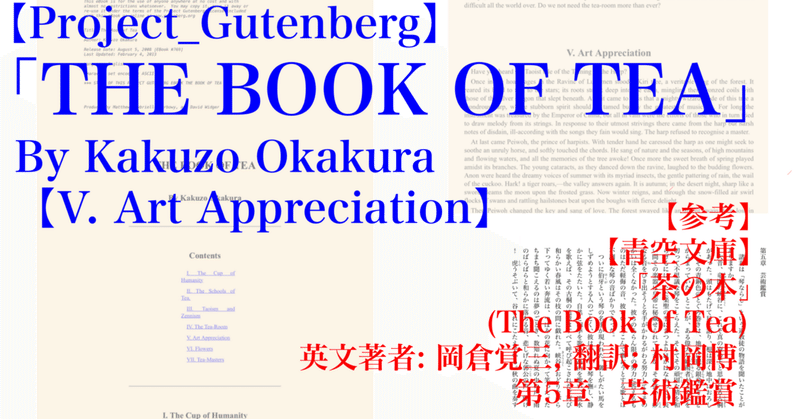
【Project_Gutenberg_200im】「THE BOOK OF TEA」その5【V. Art Appreciation】
〜〜【Project_Gutenberg】→Web翻訳版→【Project_Gutenberg_200im】
〜
THE BOOK OF TEA
By Kakuzo Okakura
〜
【Contents】
I. The Cup of Humanity
II. The Schools of Tea
III. Taoism and Zennism
IV. The Tea-Room
V. Art Appreciation ←今回の紹介
VI. Flowers
VII. Tea-Masters
〜
〜〜
〜〜[上記【Project_Gutenberg】の翻訳は以下の通り。翻訳にはアプリ「DeepL」を使用。]
〜
茶の本
岡倉覚三著
〜
内容
I.人類の杯
II.お茶の学校
III.道教と禅教
IV.茶室
V.芸術鑑賞 ←今回の紹介
VI.花
VII.茶人
〜
〜〜
【出所】URL> https://www.gutenberg.org/files/769/769-h/769-h.htm
〜〜【Project_Gutenberg】THE BOOK OF TEA
〜
V. Art Appreciation
Have you heard the Taoist tale of the Taming of the Harp?
Once in the hoary ages in the Ravine of Lungmen stood a Kiri tree, a veritable king of the forest. It reared its head to talk to the stars; its roots struck deep into the earth, mingling their bronzed coils with those of the silver dragon that slept beneath. And it came to pass that a mighty wizard made of this tree a wondrous harp, whose stubborn spirit should be tamed but by the greatest of musicians. For long the instrument was treasured by the Emperor of China, but all in vain were the efforts of those who in turn tried to draw melody from its strings. In response to their utmost strivings there came from the harp but harsh notes of disdain, ill-according with the songs they fain would sing. The harp refused to recognise a master.
At last came Peiwoh, the prince of harpists. With tender hand he caressed the harp as one might seek to soothe an unruly horse, and softly touched the chords. He sang of nature and the seasons, of high mountains and flowing waters, and all the memories of the tree awoke! Once more the sweet breath of spring played amidst its branches. The young cataracts, as they danced down the ravine, laughed to the budding flowers. Anon were heard the dreamy voices of summer with its myriad insects, the gentle pattering of rain, the wail of the cuckoo. Hark! a tiger roars,—the valley answers again. It is autumn; in the desert night, sharp like a sword gleams the moon upon the frosted grass. Now winter reigns, and through the snow-filled air swirl flocks of swans and rattling hailstones beat upon the boughs with fierce delight.
Then Peiwoh changed the key and sang of love. The forest swayed like an ardent swain deep lost in thought. On high, like a haughty maiden, swept a cloud bright and fair; but passing, trailed long shadows on the ground, black like despair. Again the mode was changed; Peiwoh sang of war, of clashing steel and trampling steeds. And in the harp arose the tempest of Lungmen, the dragon rode the lightning, the thundering avalanche crashed through the hills. In ecstasy the Celestial monarch asked Peiwoh wherein lay the secret of his victory. "Sire," he replied, "others have failed because they sang but of themselves. I left the harp to choose its theme, and knew not truly whether the harp had been Peiwoh or Peiwoh were the harp."
This story well illustrates the mystery of art appreciation. The masterpiece is a symphony played upon our finest feelings. True art is Peiwoh, and we the harp of Lungmen. At the magic touch of the beautiful the secret chords of our being are awakened, we vibrate and thrill in response to its call. Mind speaks to mind. We listen to the unspoken, we gaze upon the unseen. The master calls forth notes we know not of. Memories long forgotten all come back to us with a new significance. Hopes stifled by fear, yearnings that we dare not recognise, stand forth in new glory. Our mind is the canvas on which the artists lay their colour; their pigments are our emotions; their chiaroscuro the light of joy, the shadow of sadness. The masterpiece is of ourselves, as we are of the masterpiece.
The sympathetic communion of minds necessary for art appreciation must be based on mutual concession. The spectator must cultivate the proper attitude for receiving the message, as the artist must know how to impart it. The tea-master, Kobori-Enshiu, himself a daimyo, has left to us these memorable words: "Approach a great painting as thou wouldst approach a great prince." In order to understand a masterpiece, you must lay yourself low before it and await with bated breath its least utterance. An eminent Sung critic once made a charming confession. Said he: "In my young days I praised the master whose pictures I liked, but as my judgement matured I praised myself for liking what the masters had chosen to have me like." It is to be deplored that so few of us really take pains to study the moods of the masters. In our stubborn ignorance we refuse to render them this simple courtesy, and thus often miss the rich repast of beauty spread before our very eyes. A master has always something to offer, while we go hungry solely because of our own lack of appreciation.
To the sympathetic a masterpiece becomes a living reality towards which we feel drawn in bonds of comradeship. The masters are immortal, for their loves and fears live in us over and over again. It is rather the soul than the hand, the man than the technique, which appeals to us,—the more human the call the deeper is our response. It is because of this secret understanding between the master and ourselves that in poetry or romance we suffer and rejoice with the hero and heroine. Chikamatsu, our Japanese Shakespeare, has laid down as one of the first principles of dramatic composition the importance of taking the audience into the confidence of the author. Several of his pupils submitted plays for his approval, but only one of the pieces appealed to him. It was a play somewhat resembling the Comedy of Errors, in which twin brethren suffer through mistaken identity. "This," said Chikamatsu, "has the proper spirit of the drama, for it takes the audience into consideration. The public is permitted to know more than the actors. It knows where the mistake lies, and pities the poor figures on the board who innocently rush to their fate."
The great masters both of the East and the West never forgot the value of suggestion as a means for taking the spectator into their confidence. Who can contemplate a masterpiece without being awed by the immense vista of thought presented to our consideration? How familiar and sympathetic are they all; how cold in contrast the modern commonplaces! In the former we feel the warm outpouring of a man's heart; in the latter only a formal salute. Engrossed in his technique, the modern rarely rises above himself. Like the musicians who vainly invoked the Lungmen harp, he sings only of himself. His works may be nearer science, but are further from humanity. We have an old saying in Japan that a woman cannot love a man who is truly vain, for their is no crevice in his heart for love to enter and fill up. In art vanity is equally fatal to sympathetic feeling, whether on the part of the artist or the public.
Nothing is more hallowing than the union of kindred spirits in art. At the moment of meeting, the art lover transcends himself. At once he is and is not. He catches a glimpse of Infinity, but words cannot voice his delight, for the eye has no tongue. Freed from the fetters of matter, his spirit moves in the rhythm of things. It is thus that art becomes akin to religion and ennobles mankind. It is this which makes a masterpiece something sacred. In the old days the veneration in which the Japanese held the work of the great artist was intense. The tea-masters guarded their treasures with religious secrecy, and it was often necessary to open a whole series of boxes, one within another, before reaching the shrine itself—the silken wrapping within whose soft folds lay the holy of holies. Rarely was the object exposed to view, and then only to the initiated.
At the time when Teaism was in the ascendency the Taiko's generals would be better satisfied with the present of a rare work of art than a large grant of territory as a reward of victory. Many of our favourite dramas are based on the loss and recovery of a noted masterpiece. For instance, in one play the palace of Lord Hosokawa, in which was preserved the celebrated painting of Dharuma by Sesson, suddenly takes fire through the negligence of the samurai in charge. Resolved at all hazards to rescue the precious painting, he rushes into the burning building and seizes the kakemono, only to find all means of exit cut off by the flames. Thinking only of the picture, he slashes open his body with his sword, wraps his torn sleeve about the Sesson and plunges it into the gaping wound. The fire is at last extinguished. Among the smoking embers is found a half-consumed corpse, within which reposes the treasure uninjured by the fire. Horrible as such tales are, they illustrate the great value that we set upon a masterpiece, as well as the devotion of a trusted samurai.
We must remember, however, that art is of value only to the extent that it speaks to us. It might be a universal language if we ourselves were universal in our sympathies. Our finite nature, the power of tradition and conventionality, as well as our hereditary instincts, restrict the scope of our capacity for artistic enjoyment. Our very individuality establishes in one sense a limit to our understanding; and our aesthetic personality seeks its own affinities in the creations of the past. It is true that with cultivation our sense of art appreciation broadens, and we become able to enjoy many hitherto unrecognised expressions of beauty. But, after all, we see only our own image in the universe,—our particular idiosyncracies dictate the mode of our perceptions. The tea-masters collected only objects which fell strictly within the measure of their individual appreciation.
One is reminded in this connection of a story concerning Kobori-Enshiu. Enshiu was complimented by his disciples on the admirable taste he had displayed in the choice of his collection. Said they, "Each piece is such that no one could help admiring. It shows that you had better taste than had Rikiu, for his collection could only be appreciated by one beholder in a thousand." Sorrowfully Enshiu replied: "This only proves how commonplace I am. The great Rikiu dared to love only those objects which personally appealed to him, whereas I unconsciously cater to the taste of the majority. Verily, Rikiu was one in a thousand among tea-masters."
It is much to be regretted that so much of the apparent enthusiasm for art at the present day has no foundation in real feeling. In this democratic age of ours men clamour for what is popularly considered the best, regardless of their feelings. They want the costly, not the refined; the fashionable, not the beautiful. To the masses, contemplation of illustrated periodicals, the worthy product of their own industrialism, would give more digestible food for artistic enjoyment than the early Italians or the Ashikaga masters, whom they pretend to admire. The name of the artist is more important to them than the quality of the work. As a Chinese critic complained many centuries ago, "People criticise a picture by their ear." It is this lack of genuine appreciation that is responsible for the pseudo-classic horrors that to-day greet us wherever we turn.
Another common mistake is that of confusing art with archaeology. The veneration born of antiquity is one of the best traits in the human character, and fain would we have it cultivated to a greater extent. The old masters are rightly to be honoured for opening the path to future enlightenment. The mere fact that they have passed unscathed through centuries of criticism and come down to us still covered with glory commands our respect. But we should be foolish indeed if we valued their achievement simply on the score of age. Yet we allow our historical sympathy to override our aesthetic discrimination. We offer flowers of approbation when the artist is safely laid in his grave. The nineteenth century, pregnant with the theory of evolution, has moreover created in us the habit of losing sight of the individual in the species. A collector is anxious to acquire specimens to illustrate a period or a school, and forgets that a single masterpiece can teach us more than any number of the mediocre products of a given period or school. We classify too much and enjoy too little. The sacrifice of the aesthetic to the so-called scientific method of exhibition has been the bane of many museums.
The claims of contemporary art cannot be ignored in any vital scheme of life. The art of to-day is that which really belongs to us: it is our own reflection. In condemning it we but condemn ourselves. We say that the present age possesses no art:—who is responsible for this? It is indeed a shame that despite all our rhapsodies about the ancients we pay so little attention to our own possibilities. Struggling artists, weary souls lingering in the shadow of cold disdain! In our self-centered century, what inspiration do we offer them? The past may well look with pity at the poverty of our civilisation; the future will laugh at the barrenness of our art. We are destroying the beautiful in life. Would that some great wizard might from the stem of society shape a mighty harp whose strings would resound to the touch of genius.
〜
〜〜
〜
VI. Flowers ←次回紹介予定
〜
〜〜
〜〜【Project_Gutenberg】“THE BOOK OF TEA”「茶の本」
〜〜 翻訳はアプリ「DeepL」を使用。一部訂正「路地」→「露路」
〜
V. 芸術鑑賞
道教の「琴を飼いならす」という物語をご存知だろうか?
その昔、龍門の渓谷にキリの木が立っていた。 その根は大地に深く突き刺さり、その青銅色の巻き毛はその下に眠る銀の龍の巻き毛と混ざり合った。 その頑固な精神は、最も偉大な音楽家によってのみ手なずけられるべきものであった。 長い間、この楽器は中国の皇帝によって大切にされてきたが、その弦から旋律を引き出そうとする人々の努力はすべて無駄だった。 彼らが歌おうとする歌にはそぐわない。 ハープは主人を認めなかった。
ついにハープ奏者の王子ペイウォが現れた。 彼は、手に負えない馬をなだめようとするように、優しい手でハープを撫で、和音にそっと触れた。 彼は自然や季節、高い山々や流れる水を歌い、木のすべての記憶を呼び覚ました! 再び、春の甘い息吹が枝の間を奏でた。 若いカタラクトは渓谷を踊りながら、芽吹く花々に笑いかけた。 やがて聞こえてきたのは、夏の夢見るような声と無数の虫たち、穏やかな雨音、カッコウの鳴き声だった。 虎が吼え、谷がまた答える。 砂漠の夜、剣のように鋭い月が霜に覆われた草原を照らしている。 今は冬が支配し、雪に覆われた空気の中を白鳥の群れが渦を巻き、霰(あられ)が激しく木の枝を打ち鳴らす。
そしてペイウォはキーを変え、愛を歌った。 森は思索にふける熱烈な聖者のように揺れ動いた。 傲慢な乙女のように高く、明るく美しい雲が流れていた。しかし、通り過ぎると、絶望のように黒い長い影が地面に落ちた。 再びモードが変わり、ペイウォは戦争の歌、ぶつかり合う鋼鉄と踏み鳴らす馬の歌を歌った。 そして、ハープの中で龍門の大嵐が起こり、龍が稲妻に乗り、雷鳴を上げる雪崩が丘に崩れ落ちた。 恍惚の表情で天界の君主はペイウォに勝利の秘密はどこにあるのかと尋ねた。 「彼は答えた。「他の人たちは、自分のことだけを歌ったために失敗したのです。 私はハープにテーマを選ばせたが、ハープがペイウォだったのか、ペイウォがハープだったのか、本当のところはわからなかった」。
この物語は、芸術鑑賞の神秘をよく表している。 この傑作は、私たちの最高の感情に奏でられるシンフォニーである。 真の芸術はPeiwohであり、我々はLungmenのハープです。 美しいものに触れると、私たちの存在の秘密のコードが呼び覚まされ、その呼びかけに応えて私たちは振動し、興奮する。 心は心に語りかける。 私たちは言葉にならないものに耳を傾け、目に見えないものを見つめる。 巨匠は私たちの知らない音を呼び起こす。 長い間忘れていた記憶が、新たな意味をもって私たちに蘇る。 恐れによって押し殺されていた希望や、あえて認識しようとしなかった憧れが、新たな輝きを放って立ち現れる。 その顔料は私たちの感情であり、そのキアロスクーロは喜びの光であり、悲しみの影である。 傑作は私たち自身のものであり、私たちが傑作のものであるように。
芸術鑑賞に必要な心の交感は、相互の譲歩に基づいていなければならない。 アーティストがメッセージを伝える方法を知っていなければならないように、観客はメッセージを受け取るための適切な態度を養わなければならない。 茶人である小堀遠州は、自らも大名であったが、次のような印象的な言葉を残している: "偉大な王子に近づくように、偉大な絵画に近づきなさい"。 傑作を理解するためには、その前に身を低くし、固唾を呑んで、その作品が少しでも口にするのを待たなければならない。 ある高名な宋の批評家が、魅力的な告白をしたことがある。 彼は言った: 「若いころは、自分が気に入った絵の師匠を褒めたが、判断力が成熟するにつれて、師匠が私に気に入らせようと選んだものを気に入った自分を褒めるようになった」。 巨匠たちの雰囲気を研究することに労を惜しまない者があまりに少ないのは嘆かわしいことだ。 われわれの頑固な無知が、この単純な礼儀を拒み、目の前に広がる美の豊かな饗宴をしばしば見逃してしまうのだ。 巨匠は常に何かを提供してくれるが、私たちは自分の評価不足のためだけに飢えている。
共感する者にとって、名画は生きている現実となり、同志の絆に引き寄せられる。 巨匠たちは不滅であり、彼らの愛と恐れは何度でも私たちの中に生き続ける。 私たちに訴えかけるのは、手よりもむしろ魂であり、技術よりもむしろ人間である。 詩やロマンスにおいて、私たちが主人公やヒロインと一緒に苦しんだり喜んだりするのは、巨匠と私たち自身との間のこの秘密の理解のためなのだ。 日本のシェイクスピアである近松は、戯曲構成の最初の原則のひとつとして、観客を作者の信頼に引き込むことの重要性を説いた。 何人かの弟子たちが、彼の承諾を得るために戯曲を提出したが、その中で彼に気に入られた作品はひとつだけだった。 それは、双子の兄弟が身分違いで苦しむ『間違いの喜劇』に似た戯曲だった。 「近松は言う。「これはドラマの正しい精神であり、観客に配慮している。 観客は俳優よりも多くのことを知ることが許されている。 観客は間違いがどこにあるかを知り、無邪気に運命に突き進む哀れな人物を哀れむのである」。
洋の東西を問わず、偉大な巨匠たちは、観客を自分の信頼に引き込む手段としての暗示の価値を決して忘れなかった。 この名作を鑑賞するとき、その広大な視野に広がる思索に畏敬の念を抱かずにはいられないだろう。 近松は、「これは観客のことを考えた、ドラマにふさわしい精神だ! 前者には人の心の温かなほとばしりを感じ、後者には形式的な敬礼しかない。 自分のテクニックに没頭している現代人は、自分の上に立つことはほとんどない。 龍門の琴をむなしく呼び出した音楽家たちのように、彼は自分自身のことだけを歌う。 彼の作品は科学に近いかもしれないが、人間性からは遠い。 日本には古くから、「女は本当に虚栄心の強い男を愛することはできない。 芸術において虚栄心は、芸術家側であれ大衆側であれ、共感的感情にとって同様に致命的である。
芸術における同志の結びつきほど神聖なものはない。 出会いの瞬間、芸術愛好家は自分自身を超越する。 彼は存在すると同時に存在しない。 彼はインフィニティを垣間見るが、その喜びを言葉にすることはできない。 物質の束縛から解き放たれた彼の精神は、物事のリズムの中で動く。 こうして芸術は宗教に似たものとなり、人間を崇高にする。 これが名画を神聖なものにする。 その昔、日本人が偉大な芸術家の作品に抱く崇敬の念は強烈だった。 茶人たちはその宝物を宗教的な秘密をもって守っていた。祠にたどり着くまでには、絹の包みに包まれたその柔らかなひだの中にある聖なるものにたどり着くまでに、箱をひとつ、またひとつと開けていかなければならないことがよくあった。 対象が人目に触れることはまれで、それも入門者だけに限られていた。
茶道が台頭していた当時、太閤の将軍たちは、勝利の褒美として多額の領土を与えられるよりも、珍しい芸術作品を贈られたほうが満足したことだろう。 私たちの好きなドラマの多くは、名画の喪失と回復を題材にしている。 たとえば、ある芝居の中で、細川公方の宮殿にセッソンが描いた有名な達磨図が保存されていたが、侍の怠慢で突然火事になった。 どんな犠牲を払っても貴重な絵を救い出そうと決意した彼は、燃え盛る建物の中に駆け込み、かけらを奪い取った。 彼は絵のことだけを考え、剣で体を切り裂き、破れた袖をセッソンに巻きつけ、ぽっかりと空いた傷口に剣を突き刺した。 火はついに消えた。 燃えさかる煙の中から、半分燃えたような死体が発見され、その中には火に焼かれずに残った宝物が眠っている。 このような話は恐ろしいが、名画の価値の高さと、信頼できる侍の献身を物語っている。
しかし、芸術が価値を持つのは、それが私たちに語りかける程度までだということを忘れてはならない。 私たち自身の共感が普遍的であれば、芸術は普遍的な言語となるかもしれない。 私たちの有限な性質、伝統と慣習の力、そして遺伝的な本能が、芸術を楽しむ能力の範囲を制限している。 われわれの個性は、ある意味でわれわれの理解に限界をもたらす。 確かに、芸術を鑑賞する感覚は教養とともに広がり、これまで認識されていなかった多くの美の表現を楽しむことができるようになる。 しかし、結局のところ、私たちは宇宙の中に自分の姿しか見ていない。 茶人たちは、それぞれの鑑賞の範疇に収まるものだけを集めた。
これに関連して、小堀遠州にまつわる話を思い出す。 エンシュウは弟子たちから、コレクションを選ぶ際のセンスが見事だと褒められた。 彼らは言う、「どの作品も、誰もが賞賛せずにはいられないようなものばかりだ。 彼のコレクションは千人に一人しか鑑賞できないのだから」。 悲しそうに遠州は答えた: 「これは私がいかに凡庸な人間であるかを証明しているに過ぎない。 偉大な利久は、個人的に心を惹かれるものだけをあえて愛したが、私は無意識のうちに大多数の好みに合わせてしまう。 本当に、利久は茶人として千人に一人の存在だった」。
今日、芸術に対する見かけの熱狂の多くが、本当の感情に基づいていないことは、非常に残念なことである。 この民主主義の時代、人は自分の感情とは関係なく、世間一般で最高とされているものを求めます。 大衆が求めるのは高価なものであって洗練されたものではない。 大衆にとっては、自分たちの産業主義が生んだ立派な産物である絵入りの定期刊行物を眺める方が、彼らが賞賛するふりをする初期のイタリア人や足利の巨匠たちよりも、芸術的な楽しみを味わうための消化の良い糧となる。 彼らにとっては、作品の質よりも画家の名前の方が重要なのだ。 何世紀も前の中国の批評家が、"人は耳で絵を批評する "と苦言を呈したように。 今日、どこを向いても似非クラシックの恐怖が私たちを迎えているのは、このような純粋な鑑賞心の欠如が原因なのである。
もうひとつのよくある間違いは、芸術と考古学を混同していることだ。 古美術への畏敬の念は、人間の性格の中で最も優れた特徴のひとつである。 古い巨匠たちは、未来の悟りへの道を開いたとして、当然称えられるべき存在である。 何世紀もの批評を無傷でくぐり抜け、栄光に包まれたままわれわれの前に姿を現したという事実だけでも、われわれは尊敬の念を抱かざるを得ない。 しかし、単に年代だけでその功績を評価するならば、実に愚かなことである。 しかし私たちは、歴史的な同情が美的な識別を凌駕してしまう。 芸術家が無事に墓に眠るとき、私たちは賛辞の花を捧げる。 進化論を孕んだ19世紀はさらに、種の中の個体を見失ってしまう習慣を私たちに植え付けた。 コレクターは、ある時代や流派を説明するための標本を手に入れようと躍起になり、ひとつの傑作が、その時代や流派の凡庸な作品の数々よりも多くのことを教えてくれることを忘れてしまう。 私たちは分類しすぎ、楽しみを減らしすぎている。 いわゆる科学的な展示方法に美学を犠牲にすることは、多くの美術館の悩みの種である。
現代芸術の主張は、人生の重要な計画において無視することはできない。 今日の芸術は、本当に私たちのものであり、私たち自身の反映なのだ。 それを非難することは、私たち自身を非難することに他ならない。 現代には芸術がない。 古代人に対する狂想曲にもかかわらず、私たち自身の可能性にほとんど注意を払わないのは実に残念なことだ。 奮闘する芸術家たち、冷たい軽蔑の影にたたずむ疲れた魂たち! 私たちの自己中心的な世紀において、私たちは彼らにどのようなインスピレーションを与えることができるだろうか? 過去は我々の文明の貧しさを哀れみ、未来は我々の芸術の不毛さを笑うだろう。 私たちは人生の美しいものを破壊している。 社会の幹から、天才のタッチに弦が響くような強力なハープを形作る偉大な魔法使いが現れることを願う。
〜
〜〜
〜
VI. 花 ←次は下記〈リンク〉で紹介
〜
〜〜
【参考】
【青空文庫】「茶の本」(The Book of Tea) 英文著者: 岡倉覚三, 翻訳: 村岡博
URL> https://www.aozora.gr.jp/cards/000238/card1276.html

第五章 芸術鑑賞 先頭ページ

第五章 芸術鑑賞 最終ページ
〈リンク①〉
【Project_Gutenberg_200im】「THE BOOK OF TEA」その6【VI. Flowers】
〈リンク②〉
【Project_Gutenberg_200im】「THE BOOK OF TEA」By Kakuzo Okakura 【Contents】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
