
スーパーマンに「人権」を与えることで
シャーロック・ホームズの冒険小説にはアメリカがときどき出てきます。彼とワトソン博士が渡米して事件に挑むのではなく、イギリス国内で何か事件があって、それを捜査するうちに、犯人の犯行動機がアメリカでの悲惨なできごとに発すると判明する…そういうパターンがけっこうあるのです。
19世紀末まで、アメリカはイギリス人にとって、いやヨーロッパからは野蛮な土地と見られていたことの反映とみます。移民でどんどん人口が膨らんでいるけれど、法律がろくに回っていない無法ランドとイメージされていたのです。そういう土地で何か常識を超えたできごとがあって、それが因果因縁となって文明の王・大英帝国で凄惨な殺人事件に至り、それをシャーロックが突き止めて、ワトソン博士がことの闇の深さに震撼するわけです。

思うのですが、無限の資源、無限の土地、尽きない労働力に恵まれつつも法がフランス革命以前のままであった、19世紀から20世紀にかけてのアメリカは、そのアンバランスさゆえに、この落差を埋め合わせるものとして「コミックストリップ」そして「キャラクター」を産み落としたのではないか、と私は近年考えています。
これもまたじっくり話すと長くなるので手短に語ります。ヨーロッパで貧困や弾圧に仰ぐ貧乏人どもが、人生リライフを目指してニューヨーク港に押し寄せるわけですよ。ニューヨークで大新聞が競争を繰り広げたのも、都市人口が膨らんでいったゆえでした。英語わかんない移民一世たちをも購読者にするために、日曜版は四色カラー、ヴィジュアル重視の紙面が組まれました。カートゥーンもまた、そういう紙面の花として存在感を増していきました。

あるとき、ある人気カートゥーンの絵師さんが、ほかの新聞社にスカウトされて移籍を決意しました。今と違って新聞まんが絵師さんは社員雇用されていました。新聞記事にそえる図やイラスト描きのための絵師社員が、日曜版向けにカートゥーンも描いていたのです。そのなかでとりわけ人気の高い週刊連載カートゥーンがありました。紙面の数割ぶんを占めて掲載される、大判の一枚カートゥーンです。これに他紙が目を付けて「うちにこない?給料弾むよ。連載うちで続けてや」と絵師さんをくどいて引き抜き。彼を引き抜かれた側は、違う社員絵師さんに週刊連載を引き継がせました。
どういうことかわかりますか。日本でいえば朝日新聞日曜版と、読売新聞日曜版に、同じ主人公のカートゥーンが、違う絵師さんによって連載という事態になったのです。
この頃のアメリカの法律は、著作権法をはじめ今でいう知的財産がらみの法律はヨーロッパのものよりずっと遅れていました。そのため、こういう事態に対してどう手を打ったらいいのか、誰もわからなかった。
絵師さんは絵師さんで、自分の手の及ばないところで、自分の産み育てた人気カートゥーンが他者の手で描かれてしまうことが許せなかった。芸術家の誇りを損なう行為であると。
そこでこんなことを思いついた。このカートゥーンはもともと主人公と呼べるフィギュアがあったわけではないけれど、連載が続くにつれてファンレターが届くようになったのがいて、面白いんでそれを主人公格にしていったら連載人気がさらに高まったのでとうとう主人公に据えた。こいつに名前を付けて「特許」として申請登録したら、わし以外の誰も使ってはならぬと胸張って言えるやないか、と。

このアイディアは結局アイディア倒れに終わったのですが、目の付けどころはそんなに悪いものではありませんでした。事実その後40年ほどかけてアメリカでは、カートゥーンキャラクターを「特許」として扱う慣習が定着したのでした。
今「特許」と私は名付けましたがむろん本当は違います。違いますが実質的には特許です。スーパーマンは誰だって知っていますが生みの親が誰かなんて誰も知らないですよね。それはスーパーマンが「特許」と同じ扱いだからです。特許は売り買いできるのですよ。作者誰それは二の次です。アメリカはそういう実にプラクティカルな考え方を、40年かけて定着させたのです。
このやり方を正当化するにあたって、アメリカでは「人権」が拡大解釈されました。細部はとばして説明すると、たとえばミッキーマウスは人格を有する以上「人権」があって、もし誰かがミッキーマウスをミッキーそのひとの許諾を得ないで商品にしたり新作映画を作ったりしたら、それはミッキー君の人権侵害であるという理屈です。
「ミッキーは架空の人物やないのですか?」 そうなんですが、ミッキーマウスはウォルト・ディズニーとは一心同体であるから、もしミッキーマウスを無断で商品にしたりしたら、ウォルトおじさんの人権侵害になるからあかんよという風に理論化されたのです。

ちなみにミッキーマウスの誕生とデビューは1928年で、そのちょうど10年後にスーパーマンがデビューしています。まんが連載での登場でした。連載開始にあたって、出版社はスーパーマンまんがとその関連物についての著作権のいっさいを作者コンビより譲渡されるとする書類を、作者コンビと交わしています。つまりスーパーマンを「特許」と見なして、作者コンビより買い取ったわけです。極端にいえば、スーパーマンを無断で商品にするとスーパーマンの人権侵害になるから、そういうことするひとにはスーパーマンの所属する芸能事務所が損害賠償請求しちゃうよって論理です。
前に私はこんな話をしました。もし木村拓哉の写真集を、本人の知らないところで誰か発売したら、それはキムタクくんの人権侵害ということで、彼の所属事務所が彼に代わって発売者にお仕置きよって風にことが進むんよ、と。
キムは実在の人物ですので、彼の人権は法で認められます。しかしスーパーマンはどうでしょう?あれは完全に架空の人物です。架空なのだから人権は認められない…はずなのですがアメリカではいろいろ屁理屈をこねて、「人権」ということばは使わないでスーパーマンの人権を正当化して、最終的にはスーパーマンを「特許」化しているのです。
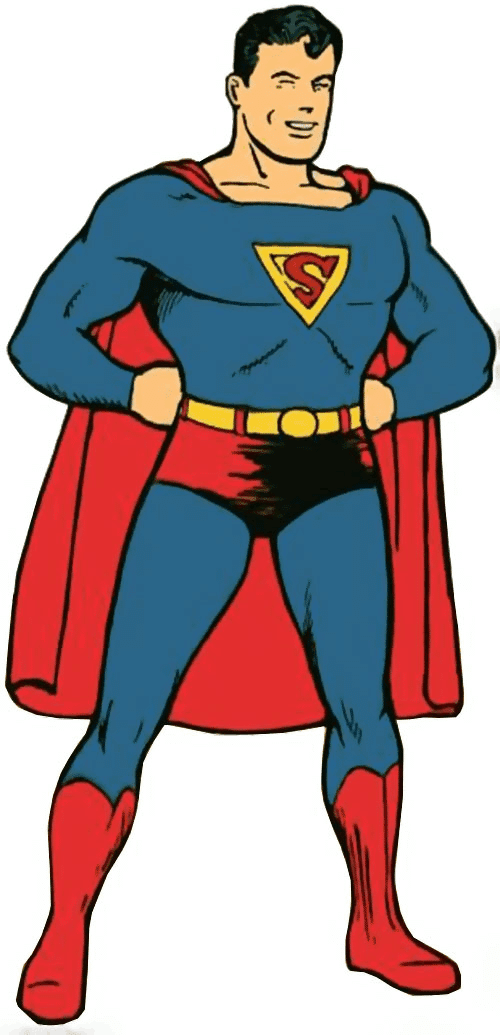
「そんな理屈あるか!」と思った方はまともなアタマの持ち主です。しかしアメリカにおける19世紀末からの、キャラクターがらみのいろいろな裁判記録を追っていくと、こういうわけのわからない論理が次第に浮かび上がってくるのです。
世界でも突出した工業先進国になっていく一方で、法制度はフランス革命以前のものだった、そういう時代のアメリカゆえに「キャラクター」は生まれ、進化したのです。

この事実は、こんな風にも解釈できます。夏目房之介先生とかは、まんがのキャラクターが落書きを脱してやがて人格を有していったのは、人間の生理や現象学的心理現象から生ずる、自然発生的なものとみなしているようですが、それは歴史的には大間違いで、架空のフィギュアを「特許」化するにあたって「人権」を足掛かりにする裏技の一環として「人格」がカートゥーンキャラクターに見出されていったとするのが正しい史観である、と。
この論は、おそらく私が世界初です。本格的に語りだすとこんな要約ではとても収まらない内容です。先行研究を探してみましたが、これといったものは今のところ見つからないでいます。理解できる方も、今のところそう多くはないと考えます。
私が抱え続ける、ことばにならないこの苛立ち、孤独感、高揚感の混交…光量子説を提唱して基地外扱いされ続けた若き日のアルベルト・アインシュタインの孤独というところでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
