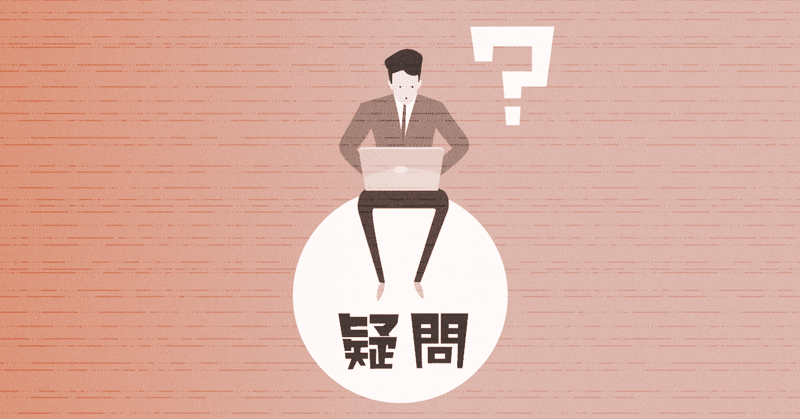
思考の変化
多くの大学がオンラインでの講義を強いられる中、法政大学でも全授業をオンラインで受講することになった。もちろん教授陣も今学期の講義方式について混乱していたと思うが、学生側は情報すら手元にないために余計に混乱していたように感じる。特に、講義内容については学生センター側の期日になっても開示しない講義も見受けられ、学生としては履修を組むことがとても難しかった。事実、講義内容を理解できないまま履修申請してしまった講義も存在した。
オンラインでの講義方式は大体3スタイルに分類される。まず、ZOOMでのリアルタイム講義方式というものがある。これは体感的に一番多くの教授が採用していた講義スタイルのように感じる。時間になればZOOMのURLが学生に届き、それをクリックすると講義に参加できるという仕組みだった。利点として、何か質問があった場合にはチャット機能を利用してすぐに質問ができたり、教授は今現在どのくらいの人数が受講しているのかが確認できたりする。双方向のリアルでの対面授業と似ているがために、違和感に残る点がある。それは、学生側の顔が映っていない場合、それは一方通行の講義になってしまうということだ。誰かとコミュニケーションを取る上で、視覚、つまりはお互いの顔が見えているかどうかという点はとても重要なポイントであり、見える・見えないによって得られる情報量は圧倒的に異なる。ZOOMでは学生側からも発言することや顔を見せることが選択できるため、学生は双方向での講義スタイルを自ら作り上げることが求められている。
次に、YouTubeや法政大学独自の授業支援システムを用いたオンデマンドスタイルがある。一般的には教授が事前に講義を録画し、それを学生が期間内にいつでも視聴できるというもの。これまでリアルタイムの講義しか受けてこなかった私にとって、学習スタイルが根本から変わった。特に朝が苦手であったため、1.2限の講義であっても自分の好きな時間に学習が可能であり、何か私用がある場合にも時間をずらしての学習が可能であった。ただ疑問点が残るとするならば、講義によって一定の期間が過ぎると視聴ができなくなることだ。そのことについて教授に何故なのかを聞くと、講義をテスト間近に一気に視聴する人がいるための対策だとの回答があった。確かにそのような学生もいるかもしれないが、テスト間近に復習することができるのは事実であるし、そもそも”いつでも、何度でも”講義を受けられることがオンデマンドの強みであるはずだ。それを避けたいのならばリアルタイムでも良いのではないかと感じてしまう。
最後に、映像は全く存在しない、紙媒体のみのスタイルの授業というものも存在した。週に一回、教授の作成したレジュメをもとに課題を取り組むというものである。これについては、正直本当に意味のない講義であったと感じる。損得の話をしようという気はないが、これなら大学に学費を払わずにオンライン上の無料学習サービスを活用したのと大差ないと思ってしまう。法政独自のオンライン掲示板というものが存在し、学生がいつでも質問できるようになっているが、全く返信がないことが多い。この授業スタイルでは限りなく一方通行のコミュニケーションになっている。
上記のように3つの講義スタイルが存在したが、普段大学で受講しているようなリアルさを求めるならば、ZOOMでのリアルタイム講義が最も双方向と感じる。もしあなたが、この社会情勢で変化が求められていると考えているのならばYouTubeや法政大学独自の授業支援システムを用いたオンデマンドスタイルが適している。紙媒体の講義スタイル以外の2方式はどちらにも良い点が存在し、デメリットも存在している。学生として、どちらが自分の学習スタイルに適しているかを判別することが重要であった。
現在私は法政大学学園祭実行委員というものに所属している。会議は基本的にZOOMで行っているが、4月に入ってから一度だけ大学で会議を行うことがあった。その際には検温はもちろんのこと、会議を行う教室は普段よりも大きな規模の教室を借り、座席も大学に指定されたように座った。いざ会議を始めた時、オンラインよりもオフラインの方が遠く感じることに気がついた。この”遠く”とはいわゆる距離感の話で、会議中のグループワークであっても基本的に前後左右1.2席は空けなくてはならず、正直とても話しにくい。他方、ZOOMではブレイクアウトルームというものがあり、これを使うことによって話したい人とだけグループを作り、メインとは異なる部屋を作ることが可能である。また、画面越しではあるものの、相手の顔が目の前に表示されるため距離が近く感じる。これが10年前であったら今よりも通信速度が遅く、距離が遠く感じたかもしれない。技術の発達はすごいもので、半年間講義を一緒に受けている人と”一度も会っていない”とは思えないほどである。後期からも基本的には対面の講義は無くすとの連絡が大学から来ているものの、1年生の語学の講義や研究、専門分野の講義等については大教室にて席の感覚を空けて実施する可能性があるとのことであった。実際、自身でどれだけ教室での講義形式が受けづらいかを体験したから言えることだが、3密対策を実施するくらいであれば確実にオンラインでの講義の方が有意義であると考える。
これを書いている今現在、私は試験期間で多くの課題に追われている。今学期はオンデマンドの授業中心で、オンラインであっても画面を映さない学生が多く、出席を取ることが難しかったために試験の評価割合がとても高い。オンライン上での試験も複数回あったのだが、サーバーがダウンすることもあり、ツイッターでは法政の授業支援システム”hoppii”が世界で8位のトレンドになってしまうこともあった。後期でもオンラインで試験を行うのであれば、是非ともこれまで以上のサーバー対策をしてほしい。講義によってはレポートを100%で評価するものも存在している。自分自身も、周りの友人も見て感じることであるが、出席点が存在したリアルでの講義よりもレポート100%である方が圧倒的に学習をしている。レポートのための、いかにも”やらされている”受け身の姿勢であるが、そこで新たな発見や、新たな興味が出る人もいるかもしれない。一見受け身の姿勢は良くないと感じるが、最初のきっかけの一つとしては一概に悪とは言えない。
前期ゼミ活動では13歳からのアート思考という本を読んだ。これまで私は、なぜ評価を受けているのかわからないアート作品というものをいくつも見てきた。しかしこの本を読んでみて、その疑問が少し解消された。それは鑑賞者自身が一定のアートの定義や答えを持っており、作品がそれを越えているかどうかということだ。自分にはこれまでアートの定義や答えを持っていなかったため、アート作品をみても”なぜ評価を受けているのか”などと思ってしまっていた。この定義や答えは世界共通のものではなく、一人一人が持っているものである。そのため、たとえルーブル美術館に展示されるような、世界中が素晴らしいと評価を受けている作品であっても、自身が定義や答えに当てはまらなければ素晴らしいと思わなくても良い。
これまで「相手に合わせるな、自分を貫け」などのような風潮の本質を理解せずに、なんとなく正しいと思っていた。しかしこのアートの本を読んだ後は、すんなりと受け止めることができた。誰しもが自分の定義や答えを持っていて、他人はそれを否定する権利はない。
例えばこの社会情勢の中、私は地元である富山への長期帰省をした。周りの反発もあったが、これから感染が加速していつ帰れるのかわからなくなる、このまま社会人になると長期帰省は難しくなる、などと考えた。当然移動は新幹線にし、感染対策を考え移動前後2週間は家に止まるということを徹底した。この選択肢を誰かに否定されたとしても、自分で見つけた答えなので否定することはないだろう。
この社会情勢の中で一貫していえることは、一人一人の意思が求められているということだと思う。緊急事態宣言であっても、強制的に自粛させられているわけではない。経済を回さなければ倒産してしまう会社も多くある。同調するのではなく、自分の判断で行動できる姿勢があるかどうかが試されている。後期はどんな基準を持って活動しようか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
