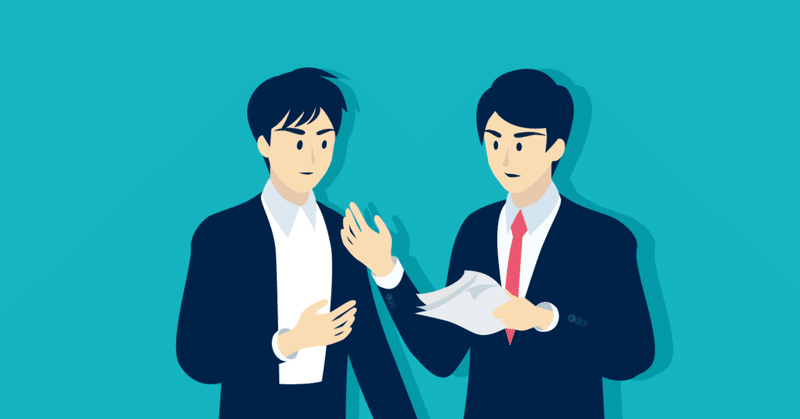
請書を発行しない場合の契約成立の有無
取引基本契約を締結していない相手方から発注書が送付されてきました。請書を発行しないまま、製品を作り、納入しましたが、契約は成立しているのでしょうか。
結論
● 口頭や電子メールなどで承諾している場合
● 製品を納入した行為が黙示の承諾と認められる場合
上記に該当する場合には、契約が成立していると考えられます。
ただし、以下の場合には発注が失効する可能性があります。
● 発注書に以下のような記載がされている場合
「一定期間内に請書の送付がない場合は、発注を取り消す」
● (特段のやり取りがないまま)発注書の受領から時間が経過した場合
解説
契約成立の一般論
契約は、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致することで成立します。
発注書が発行される取引の場合、通常は、発注書の交付は契約の申込みに該当し、これを相手方が承諾することで申込みと承諾が合致し、契約が成立します。
発注書の前に、見積書が発行されることもありますが、見積書の発行は契約の申込みの誘因であり、契約の申込みそのものではないと考えられています。
つまり、見積書に対応する発注書が発行された時点では、まだ契約は成立していないことになります。
申込みに対する承諾の方法
民法上、承諾の方法について定めがないため、書面で承諾する必要はありません。
そのため、発注内容を承諾する旨の口頭での回答も有効です。
ただし、口頭の場合、記録が残らないため、後日「言った、言わない」の争いが生じるリスクがあります。
請書を発行しないで履行した場合の取扱い
原則
承諾は、明示的に行う必要もありません。
つまり、黙示的な承諾も有効です。
例えば、買主の発注に対して、売主が製品を納入する場合
→ 納品が承諾の意思表示を兼ねた行為といえます。
例外
● 発注書に以下のような記載がされている場合
「一定期間内に請書の送付がない場合は、発注を取り消す」
この場合、期間内に請書の発行がなければ、発注書による申込みの効力が失われるため、契約は成立しないことになります(民法523条2項)。
● (特段のやり取りがないまま)発注書の受領から時間が経過した場合
期限の定めがない申込みであっても、相当の期間を経過した後は、申込者は撤回することができます(民法525条1項)。
また、商人間の契約の場合、承諾期限の定めのない申込みは、相当な期間の経過をもってとうぜんに効力を失うとされています(商法508条1項)。
そのため、「請書の発行がない」かつ「発注者は受注者が制作を開始したことを知らない」場合には、納品前に注文撤回の通知が来るリスクがあります。
ちなみに、商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申し込みを受けた場合、遅滞なく諾否の通知をしないと申込みを承諾したものとみなされます(商法509条2項)。
したがって、受注者が会社であり、当該発注者から同種製品の発注を継続的に受けていた場合には、承諾の通知をしなくても、商法509条2項により承諾したものとみなされると考えられます。
印紙上の注意点
印紙税との関係で、請負に関する発注書であって、見積書に基づく申込みであることを記載した発注書は、別に請書等を作成することが記載されていない限り、原則として契約書に該当するという通達があります(印紙税法基本通達21条2項2号)ので注意が必要です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
