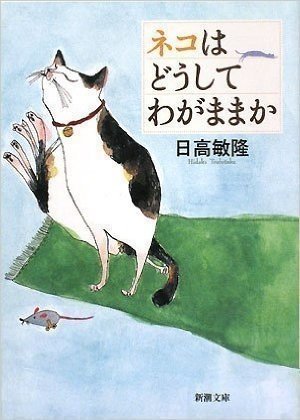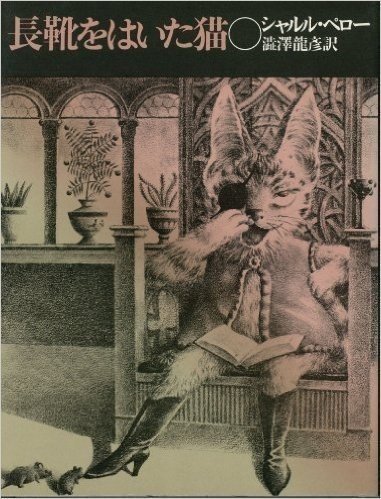猫的方法を学ぶための三冊
領域を超えた知と知をネットワークする「千夜千冊」では、一見関係のない「夜」でも、つなげてみると新しい風景が見えてきます。「千夜三冊」と題して、掘り出し物の千夜をご紹介します。
柔らかい毛並みに大きな瞳、つやつやとした桃色の肉球。甘えたかと思うと、すぐにどこかへ行ってしまう。古来猫たちは人を魅了し、慰め、癒してきました。しかし猫の魅力は可愛らしさだけではありません。
ときに生物学者を困らせ、国家の策略に加担し、人間の思考をパチンと切り替える。それは、猫たちがなんらかの「方法」を持っているからかもしれません。
千夜千冊に登場する猫たちの姿からは、「猫的方法」が浮かび上がってきます。今回は猫たちに学ぶ3つの方法をご紹介します。
◉猫的方法その1|猫のごとくはぐらかすべし
エソロジスト(動物行動学者)の日高敏隆さんは「猫的方法」を熟知していました。日高さんは日本に動物行動学を紹介した第一人者です。昆虫から爬虫類、哺乳類、人類に及ぶまで、あらゆる動物の行動を知り尽くし、「チョウはなぜ飛ぶか」といったシンプルかつ難解なことを説明できる稀有な科学者です。
しかしそんな日高さんも、猫のこととなるとちょっと様子がおかしい。
日高家には多すぎるほどの猫がいましたが、世話をするのは動物好きな日高さんかと思いきや、実際は奥さんです。奥さんはしばしば人前で、動物学者の夫がいかに猫を理解していないか、まるで「国際会議で宿敵を破るために雄弁をふるう」ごとくまくし立てました。松岡もそんな夫妻の激論の場に居合わせたことがあるそうです。
ところが日高さんはそれには全く反論しません。リチャード・ドーキンスやコンラート・ローレンツなどの数々の名著を世に送り出した日高さんが、反論の言葉を持たないはずはありません。これは、ちょっと変です。
そこで『猫はどうしてわがままか』というこの本の登場です。日高さんはついに本書で反論に挑むのでしょうか。
話は春のウグイスの縄張り争いや、ゼンマイの芽吹きや、ドジョウの生態やオタマジャクシの発する恐怖物質など、誰も知らなかった動物の秘密を暴いていきます。そしていよいよ猫の話かと読者は待ち構えます。しかし、読んでも読んでもネコが出てきません。やっと最後のほうで出てきたかと思うと、肝心の「猫はどうしてわがままか」についてはろくに議論もせず、そのまま本書を終えてしまいます。
「期待してはいけなかったのだ。先生は自分の言葉で自分に有利なことだけを話すのだ。ネコがわがままなのは先生が世話をしていないだけでなく、世話したところで自分に有利にならないことを知っていただけなのである」
このはぐらかしぶり、まるで猫のようです。日高さんは「はぐらかす」という猫的方法を本書を通して実践してしまったのです。松岡はこんな風にこの一夜を閉じています。
「やはり先生はよくよく『利己的遺伝子』ということを研究しつくしている」
◉猫的方法その2|猫のごとくしたたかであるべし
猫の物語といえば『長靴をはいた猫』を思い出す人も多いかもしれません。この物語は17世紀にシャルル・ペローによってまとめられました。
シャルル・ペローはフランスの詩人で、昔話を初めて子供向けの詩としてアレンジしました。それまで伝承の詩といえば大人向けのものでしたが、ペローによって子ども向けの新しい物語のスタイルが開拓されました。『赤ずきん』も『眠れる森の美女』もペローがまとめたものです。
そもそも“長靴”をはいた猫なんて変わっていますが、それだけではありません。貧乏な青年に仕え、この主人を突然「カラバ公爵」と呼んで敬います。
長靴猫は名うての策略家でもありました。ある日、長靴猫は森に罠を仕掛けてウサギを生け捕りにし、これをその国の王様に献上しようとします。しかも、自分で獲ったにも関わらず「カラバ侯爵からの贈物でございます」と言うのです。長靴猫はこれを繰り返し、王様は貧乏な青年にすぎないカラバ侯爵のことをすっかり気に入るようになります。そしてついには王様の娘の姫をカラバ侯爵に惚れさせるまでに至るのです。日高さんの「わがまま」な猫の姿とは一線を画します。
「長靴猫が変なのは、いろいろ自分がしでかした計画によって、主人がお姫さまと結婚できることよりも、『国が栄える』ということを知っていたことだった。どうも、長靴猫はアダム・スミスのようなのだ」
主人が出世すれば国が栄える。そのためには巧妙な演技をして人間を手なづける。つまり、長靴猫は理由もなく忠実なのではありません。したたかに策略を練るという猫的方法だったのです。千夜では長靴猫のさらなる策略に迫ります。
「おそらくは長靴猫はマルセル・モースがのちに気がついた『贈与の意味』を知っていた。おそらく長靴猫は“命と引き換えに”というほどのことをすれば何かがおこるにちがいないという『交換の意味』を知っていた」
シェアやフリーが謳われる時代だからこそ、アダム・スミスにもマルセル・モースにもなれる長靴猫の物語は読みたくなる一冊かもしれません。
◉猫的方法その3|猫のごとく回転扉をひらくべし
756夜『ゲシュタルトクライス』
ヴィクトール・フォン・ヴァイツゼッカー
かつて松岡正剛の仕事場には猫がいました。猫どころか、犬もいました。犬2匹、猫2匹が一日中、勝手気儘にうろうろしていたと言います。
今は松岡の自宅に猫が3匹います。「みーこ」「佐助」「ナカグロ」の3匹です(数年前までは「小麦」がいました)。松岡が無類の猫好きだということに加えて、一見勝手にうろうろするこれらの犬や猫たち、実は思考するうえで重要な役割をはたしていました。
「アタマの中で何か思考しようとすると、目の前で猫がうごく。すると思考しようとしているものと目の前を動いているものとの関係が互いにかみあっていく」
この「かみあいぐあい」のことをフォン・ヴァイツゼッカーは「からみあい」(Verschrankung)と呼びました。「知覚するということは運動している何かを知覚の中に現出させて、それをサッとつかむことなのである」と松岡は言い換えます。ときに猫たちが思考の中で重大な役割を演じるパラメーターになっていたのです。
たとえば、マルセル・プルーストの小説『失われた時を求めて』(935夜)では紅茶に浸したマドレーヌの香りによって、幼い頃の記憶が呼び起こされます。このように私たちの知覚と思考は常に相互に働いています。一方で、知覚を意識すると思考が止まり、思考を意識すると知覚を意識できないという矛盾が出てきます。
ヴァイツゼッカーはこれを「回転扉の原理」と呼びました。私たちの知覚と思考はまるで回転扉のように、一方を意識すると一方が遠ざかる。そこで、ウロウロする猫たちが回転扉のスイッチとなるのです。
「その後ぼくは、そこをいろいろ自分で実験的に発展させて、何かを思考しているときに別のものが目の脇を動いているときにも応用するようになった。アリストテレスを読んでいるときにナカグロが動き、ソンタグを考えているときに小麦が動く。それがいいのである」
猫は知覚と思考のあいだを自在に行き来します。私たちの視界のすみっこをチラチラと動きながら、かわいらしい前足で回転扉のスイッチをパチンとはじく。これこそが思考を加速させる猫的な方法だったのです。
猫はもふもふしているだけがとりえではありません。もっと深く、もっと面白く、世界の見方をちょっと柔らかくする方法に満ちています。きっと明日から「にゃ〜」という鳴き声が方法の言葉に聞こえるかもしれません。たまには猫を探して千夜千冊を読んでみてください。もちろん、そばに猫がいれば、ぜひご一緒に。

---
■カテゴリー:千夜三冊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?