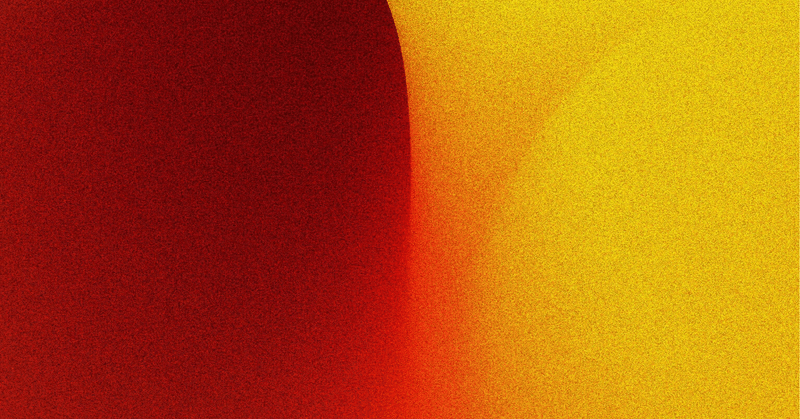
ロードショー(著:二宮 弘人)
灯りの落ちた客席の椅子から、思わず腰を浮かしそうになった。大画面に繰り広げられている仮想現実と、シートに座っている現実。あちらとこちら。私は徐々に、その境目を見失いつつあった。
肘掛けをつかんだ右手の上に、あたたかく柔らかな手がふわりと添えられた。ほっとゆるんだ次の瞬間、「突撃!」という、声にならぬ絶叫が、シアターに轟いた。銀幕に映し出される戦闘場面。息を飲む。かろうじて立つのは控えた、と言うより身じろぎもできなかった。それでいて居ても立ってもいられない。
おかしい。どうして私は、知っているのだろう。
暗がりの中、とうに車の途絶えた県道を歩いている。闇の一本道を歩きながら、私は、一ヶ月前に新宿で観たロードショーを思い出していた。
車が途絶えたというよりは…、と腕時計を見る。三時、だが、通行車両が皆無なのは時間が時間だからではない。
それにしても暗い。いつもなら遠くに認められるはずの街の灯りもない。車道の街灯も落ちており、一片の月影さえも見えない。私はおののいた。世界の終わりに、真っ暗な夜の底を、たった一人で歩いている。
先ほどから心は、行ったり来たりしている。つながらない電話とつながりすぎる映画。耳元で呼び出し音がループする失望と、バンザイ突撃の前の兵士たちの、あるいはスーサイドクリフから身を躍らす直前の女たちの、絶望。
左手には携帯を握りしめているが、バッテリーの充電量は残りわずかだ。あと一回かけたら切れてしまうに違いない。
なぜ、あの手につながらないのか。
「太平洋の奇跡」をロードショーで観た。建国記念日だった。それにしても分からない。なぜに私は「生きて虜囚の辱めを受けず」に、あれほど反応したのだろう。
つらつらと思い返してみると、子供の頃の私は、「絶望」からは遠いところにいた。とは言っても何ら特別な境遇だったわけではない。父はサラリーマン、母は専業主婦の家族という、当時の平均的な家庭で私は育った。家族仲は取り立てて悪くなかった。
私は「戦争」からも隔てられていた。終戦時、父は徴兵年齢に達していなかった。父は私に戦争のことは何も語らなかったので、少年の父が、どんな思いで戦時下を生きたか知らなかった。家族団らんの話題は、スポーツや映画やテレビやレジャー、経済、もしくは私の学校についてであり、意図的だったのだろうか、戦争の話は除かれていた。親戚に、大戦に生き残った将校はいなかったから、武士道精神の矜持に触れる機会は無かったし、洗脳され恥の意識と罪悪感で締め付けられ、恐怖でコントロールされる一兵卒の悲哀も知らなかった。
それなのになぜ?
大人になってはじめて、浮き世の辛さを知った。人生は不条理だった。なりゆきのような結婚、突然の愛児の死。
あの日私は、たまたま早く帰路に着いた。ショートケーキの箱を提げて洋菓子店から出て交差点に立つと、横断歩道の向こうで信号待ちをしている母子が見えた。妻と息子だった。息子も私を見つけた。息子は、横断歩道の信号が青に変わるや、妻の手を振り払って私に向かって走り出した。こぼれんばかりの笑みで。ちぎれんばかりに手を振りながら。
だが、次の瞬間、息子が不意に消えた。信号無視の車が小さな命を空に飛ばしたのだった。即死…。
「どうして早く帰って来たのですか」
それ以来、妻は私を責め続けた。平成の世、空から砲弾は降らなかったが、妻の言葉は私の心に着弾し、その度に破裂した。
それでもやはりおかしい。罪悪感は、息子の事故死以前に心の奥深くにあったように思う。いや、生まれる前から知っていた、そんな気がするのはなぜだろう。とにかく、「自分は罪人だ。生きているのが恥ずかしい」という意識、こいつに捕まるとおしまいだ。生への無感動、絶えざる自責の念、時折の感情の暴発…。
映画の中では、最後の突撃、玉砕決行の直前に、負傷兵達は足手まといでしかない自分を恥じ、ピストルであるいは手榴弾で次々に自決していった。
フォックスと呼ばれた男、大場大尉は真逆に生きた。彼は斎藤中将の自決と戦陣訓に背を向けた。生きるために戦い、その都度互角以上の戦いを繰り広げた。大尉を頼って、兵士と民間人が集まるや、「彼らを生かさねば」と思い、生かし、自らも生き延びた。
彼らを?その頃の私にはもはや、「彼ら」はいなかった。離婚してすぐに、妻は再婚した。私には、生きるための戦いにおける、守るべきものが一人もいなくなったのだ。孤独、そして絶望。
六年前、夜の底にうずくまる私を引っ張り上げてくれたのが、彼女だった。
「私が愛するあなたを、あなたも愛してあげて」
あの声で私は浮上できた。そう、声。人にとって声とは何なのだろう。別の人間の違う声で同じ言葉を手渡されたとしても、決して救われなかっただろう。あれから私は一歩ずつ歩み、やっとトンネルを抜けたのだ。
映画は終わった。ピカデリーから出ると、小雪が降っていた。傘はない。しばらく空を見上げた後、私たちは手をつないで、新宿の街に歩きだした。
今日はその新宿を目指していた。彼女へのプレゼントを買いに行こうと、東京駅で、発車待ちの中央線の電車に乗ってすぐだった。
突然、シートが揺れた。いや、体ごと浮いた。違う、車両ごと飛び跳ねていた。私の向かい側に立っていた二人連れがうろたえて、「降りようか」と怯えた声で言った途端、電光掲示板がホームに落ちた。世界全体がきしみ、うねり、轟いた。東日本大震災。
すぐに彼女に電話をした。しかし、つながらない。次に考えたのは会いに行くことだ。JRは運転中止だ。私は、東京駅発の高速バスを思い出した。首都高も閉鎖だろうが、運が良ければ下道を通って、彼女の街の近くまでいけるかも知れない。
バスは一本だけ出るという。四半時ほど待たされたが、バスは出た。けれども、道路は大混雑、大渋滞だった。バスの窓から見ると、歩道を歩く人の群れが、私のバスを追い越していった。
泥まみれになりながら、ぼろぼろの服でジャングルを移動する兵士と民間人の姿が目蓋によみがえる。脳内に映じられる南国の仮想現実と、バスのシートに座りながら見る被災した首都の現実。言いようのないあちらと、居ても立ってもいられないこちら。
いらいらしながら何度も電話をする。携帯は呼び出し音を空しく響かせるだけだ。彼女は無事なのだろうか。太平洋戦争の末期、兵士達の家族も、空襲の合間に南の空を見上げては、夫のあるいは息子の無事を祈ったことだろう。声が聞きたい。無事であって欲しい。
男の大声が聞こえ、私は我に返った。中年の紳士が、ワンセグ片手に、ニュースの解説を始めたのだ。我々は、彼がアナウンスする度に、地震の被害の大きさに驚かされた。
マグニチュード七・九という超巨大地震が起こったことは、すでに携帯のニュースで知っていた。十五時過ぎに三陸沿岸に津波が到来したことや、お台場の火災も。しかし、男がみんなに見せるワンセグの画面の津波の映像に、息を飲んだ。市原市の石油コンビナートで爆発が起きたことも、男のワンセグで知った。仙台空港は冠水した。
バスは相変わらず、人の歩行の速度で動いていた。電話はつながらない。辺りが暗くなった。マグニチュードは八・八に訂正された。官房長官が会見を開き、原子力緊急事態宣言を発表した。福島で何かが起きていた。
いつの間にか、車内の空気が変わっていた。ワンセグの男はバッテリー不足を理由に、ニュース実況をやめていたのだが、長時間バスに閉じ込められていて気持ちが腐ったのだろう、大声で愚痴をこぼし始めたのだ。「バスがのろい」、「まだ帰れない」、「無事に帰れるのか」等。ネガティブな空気は、瞬く間に伝染した。
突然、バスが止まった。運転手が、
「予定が変わって申し訳ありません。このバスはここが終点です。本日はご利用、ありがとうございました」と言った。新都心と呼ばれる街の駅前だった。騒然となる車内に、私はしばらく留まっていたが、やがて乗客が降り始めた。私も仕方なく降りた。すでに二時半、タクシー乗り場に行ったが、無駄足であった。星ひとつとてない夜空を見上げ、大場大尉の苦闘の道を思った。
深呼吸をして意を決し、私は彼女の家までの道のりを歩き始めたのだった。ジャングルから降伏式の会場までの道程を、大場隊四十七名は「歩兵の本領」を歌いながら堂々と行軍した。とても真似はできないが、何時間かかっても歩き通して、彼女に会うと決めた。それでも、やはり、できれば今からでも電話で無事を確認し、これから行くことを伝えなければ。
歩き出してすでに三十分が過ぎた。私は立ち止まってきつく目を閉じた。
「私は愛に生きたい。私が愛するあなたを、あなたも愛してあげて。私もわたしを愛して生きる。私にとって『わたし』とは、生あるすべてのいのちなの」
彼女の声が胸の真ん中で響いた。すべては必然。彼女は無事で、まだ眠らずに起きており、彼女は彼女らしく生きているに違いない。そう思ったら、少しだけ心が楽になった。
私は彼女の携帯に、電話をかけた。ワンコール、ツーコール、呼び出し音が鳴っている。
〈了〉
二宮 弘人がおすすめ映画を紹介↓
二宮 弘人の前作「初恋」↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
