
初恋
「あたし松山に行く」
美沙子がそう宣言すると食卓が静まりかえった。
「美沙ちゃん、急にどうした?」
夫の高志がご飯茶碗を手にしたまま当惑顔で言った。
「行けばいいじゃん。たまには水入らずでのんびりして来なよ」
次女の佳音は長い腕を伸ばしてきんぴらごぼうを取ろうとしていた。韓国のテーマパークでダンサーをしていたが、祖母の葬儀に帰って来たまま戻れずにいた。今は近くのコンビニでアルバイトをしている。韓国に付き合っている相手がいるらしい。そろそろ孫の顔がと思っていたらコロナ騒ぎで時間が止まった。
「そうだよ。二人ともワクチン打ったんだから感染の心配もないんでしょ」
長女の安珠が目の前にあるきんぴらごぼうをブロックしながら言った。安珠の方は都内にある劇団の女優だった。端役だが映画にも何本か出たことがある。しかしコロナ騒ぎで全く仕事がなかった。安珠も佳音と同じダンサー志望だったのだがいつの間にか役者になっていた。こちらはまったく男の影がない。それなりの美人なのに顔つきと性格がきつくて男が寄りつかないようだ。
「あんたたちにも一緒に行ってほしいの」
美沙子が言うと、きんぴらごぼうを取り合っていた娘たちの箸が止まった。
「えーっ、松山あ。……ねえ、松山ってどこだっけ?」
「愛媛県に決まってるでしょ。そんなことも知らない人にきんぴらはあげなあい」
「あっお姉ちゃんずるい」
姉妹のきんぴらごぼうをめぐる攻防はしばらく続いた。美沙子は長い間看護師をしていたので姉妹は姑の味で育った。姑の啓子は料理が上手だった。習い覚えたのは唯一、きんぴらごぼうだけだ。もっと教えてもらっておくんでした。美沙子は隣の部屋の奥にある姑の遺影に話しかけた。啓子は三ヶ月前に入院先の病院で亡くなった。コロナではなかったが危篤になっても面会もままならなかった。一人で死なせてしまったことは深い悔いになっていた。美沙子はずっと啓子に甘えていた。それだけあなたが看護師の仕事に打ち込んでいたってことよ。啓子の慰める声が聞こえるような気がした。
「ママ聞いてる」
安珠の声が美沙子を現実に引き戻した。
「あたしはいつ仕事が舞い込むか分からないからパス」
「あたしもがバイトがあるから行けなあい」
「俺はいつでもママに付き合うよ。松山かあ。しばらく行ってないな」
高志が姑に似た優しい微笑みを浮かべて言った。夫の高志は五年前に脳溢血で倒れて左半身を思うように動かすことができなくなり、長年勤めていた旅行代理店を早期退職した。美沙子が定年退職した一年前までは不自由な身体で姑の介護をし看護師として働く美沙子を支えてくれた。高志は美沙子の一つ年上の六十二歳。ちなみに娘たちは三十四と三十三の年子だ。
「ありがとう。あなた」
「ねえパパ、松山って何があるの?」
佳音がデザートのメロンを食べながら高志に尋ねた。
「有名なのは道後温泉だな。日本で一番古い温泉だと言われている」
「そこ知ってる。坊っちゃんが入ったのよね」
安寿は冷蔵庫から缶ビールを持って来てみんなに配りながら言った。
「ああ。道後温泉本館には立派な石の浴槽がある。坊っちゃんが入ったので『坊っちゃん湯』と呼ばれている。パパも何度か入ったことがあるよ」
「誰よ、その坊っちゃんって」
「まったく何にも知らないんだから。松山と言えば夏目漱石の『坊っちゃん』の舞台でしょ」
「知ってるよ。マドンナが出てくる奴でしょ」
姉妹がマドンナの「ライク・ア・ヴァージン」を歌いながら踊り始めた。全く仲がいいのか悪いのか分からない。手足の長い佳音は伸びやかに踊った。だがスレンダーな体は色気に欠けた。安珠の方は美沙子に似て背が低い。ただ踊り出すと何となく凄みがあって注目を浴びた。二人がダンスをやっているときには姉妹の仲は最悪だった。食卓でもほとんど口を利かなかった。どんなつまらないことでも競い合った。二十代半ばに安珠が女優としての道を進みはじめてから、次第に二人でなごやかに語り合ったり笑い合ったりするのを見るようになった。
騒動が一段落すると、微笑んで見ていた高志が、
「夏目漱石は神経症に苦しんでな。転地療養もかねて松山の中学校で英語を教えていたことがあるんだ。松山は漱石の親友正岡子規の故郷で今でも俳句が盛んなんだよ」と説明した。さすがに長く添乗員をしていただけのことはある。
「日本一古い温泉ねえ……」
佳音が直前の高志の話を無視して呟いた。さすがにB型だけある。
「でもママ。なんで急に松山になんか行きたくなったの」
「それがね。SNS始めたら、たまたま中学の同級生とつながってね。それで柳君のこと聞いたら会いたくなっちゃって」
言いながら美沙子は動悸が速くなるのを感じた。
「なに小娘みたいに顔赤くしてんの。キモッ」
「こっちが恥ずかしいんだけど。誰よ、その柳って奴」
娘も三十を過ぎると母親にも容赦がない。
「呼び捨てにしないでちょうだい。ママの初恋の人なんだから」
食卓が凍り付いた。
中学三年の秋。
合唱部は文化祭で『ロミオとジュリエット』をミュージカルとして上演した。美沙子はジュリエットを演じた。美沙子の夢は歌劇団に入ることだった。そのために幼い頃からバレエも習っていた。ただ残念ながら背がなかなか伸びなかった。本当はロミオを演じたかった美沙子にとってジュリエット役は不満だった。ところが皮肉なことに美沙子のジュリエットは観客から大絶賛を受けた。文化祭が終わったあとも校門でサインをほしいと他校の生徒が待ち伏せをしていたほどだ。
柳駿介は全国大会でも活躍した野球部のエースだった。県下の複数の強豪校から声が掛かっているという噂だった。精悍な顔立ちをしているので女子にも人気があった。一度も同じクラスになったことはないが美沙子も密かに駿介に淡い思いを抱いていた。
ある日、美沙子は同じクラスの野球部員から「柳が屋上で待っている」と告げられた。
美沙子が屋上に行くと、柳は野球部のスターとも思えぬ素朴さで訥々と交際を願う言葉を語った。美沙子にもその言葉は胸に響いた。だが美沙子の答えはノーだった。柳は青ざめて屋上を走り去った。
美沙子が柳を振ったという噂はたちまち広がって学校中が大騒ぎになった。そして美沙子は男子にも女子にも非難され、しばらくは針の筵だった。
「なんで、なんでよ。その柳君って野球部のエースなんでしょ。格好よかったんでしょ。なんで断ったりしたのよ。バッカじゃない」
佳音が二本目のビールを開けながら言った。
あれから四十六年。娘にまで責められる因果に美沙子はうんざりした。
美沙子の脳裏に背の高い一人の少女の姿が浮かんだ。その子は美沙子とロミオ役を競った後輩だった。美沙子と同じように子供の頃からバレエを習っていて、将来は歌劇団に入りたいという夢も同じだった。部内で行われたオーディションで美沙子は彼女に負けた。それなのに上演後に注目されたのは美沙子の方だった。彼女は自信と輝きを失い部活も休みがちになった。美沙子のせいでないことは分かっている。しかし、美沙子は責任を感じずにいられなかった。そしてその後輩がずっと前から柳に憧れているのを美沙子は知っていた。それが理由なのかは自分でもはっきりはわからない。だがもしも柳の思いを受け入れたら彼女はさらに傷つくだろう。美沙子はその責任から逃げたのだと思う。
ただ家族にはもう一つ理由の方を告げた。
「仕方ないでしょ。柳君は背がそれほど高くなかったんだから。あんたたちは絶対歌劇団の男役にしたかったから、背の高い男の人と結婚したかったのよ」
美沙子は自分と同じ目線で語る柳を見ているうちに、柳がそれほど背が高くないことに気付いてしまった。一度気付くとそれは歌劇団の男役を目指す自分にとってあってはならないことだと思い込んでしまったのだ。
「それって初恋の相手なんでしょう? 結婚のことなんてまだ早くない?……ねえ」
佳音が安珠につないだ。
「あるよね。ママにはそういう重たいとこ」
安珠がため息混じりにそう言った。美沙子ははっとした。もしかするとこの子たちにも歌劇団の男役という重い夢を押し付けていたのかもしれない。そして、どちらかというと美沙子に性格の似ている安珠は自分自身のそういう性格をもてあましているのだろうか。
美沙子は安珠の女性としてはきつすぎる横顔を見つめた。
「あのさ。誰でもその時はこれが初恋だなんて思わないもんだよ。純粋だからこそずっと先のことまで気になってしまうんじゃないかな」
高志が静かに言った。
「パパ、可哀想……」
佳音がぽつりと言った。その言葉は美沙子の胸に刺さった。今更初恋の男に会いに行きたいなんて高志を傷つけたに違いない。そのことには気づいていながら無視していた。姑の啓子にだけでなく美沙子は高志にも甘えていた。
「あたしもおかしいと思う。今更初恋の人に会ってどうすんのよ。お互いに幻滅するだけじゃないかな」
美沙子もそれは考えた。美沙子は結局歌劇団には合格できなかった。ちなみにロミオ役の後輩は数年後に歌劇団に合格しデビューしたが大きな役はもらえないまま退団していた。一方の柳も甲子園常連校に入学したものの、甲子園大会に出場することはできなかった。今さらそんな夢破れた者同士が会うことに意味があるのだろうか。
「危なかったなあ。もしその柳君の背が高かったらママは彼と結婚してたかもな。俺はかまわないよ。ママの初恋の人に会ってみたい」
高志の寛大な助け船に美沙子は泣きそうになった。おそらく高志だけは美沙子の気持ちに気付いていた。コロナ禍によって医療現場は深刻な人手不足に陥っていた。当然、美沙子にも復帰してくれないかと声がかかっていた。現場に戻れば感染の危険は覚悟しなければならない。どんなに奇妙に思われても会いたい人には会っておきたかった。
「パパもずいぶん物好きね」
「まあな」
高志は動く右手で頭を掻いて笑った。
「ごめんね。あたし歌劇団目指さなくて」
佳音がしんみりと言うと、
「あんたは受けても受からなかったから同じ」
と安珠がからかった。
「お姉ちゃんこそチビだからぜったい無理」
「なんだと」
二人がじゃれ合うのを高志は微笑んで見ていた。美沙子はあらためて高志と結婚してよかったと思った。歌劇団の男役にはならなかったけど二人ともいい娘だ。
「結局ママが歌劇団に合格することはなかったし、あんたたちも歌劇団を目指すことはなかった。人生は思い通りには行かないものね」
美沙子が言うと娘たちが黙った。人生は思い通りには行かない。その言葉がそれぞれの心に様々な思いを呼び起こしたようだ。
「なあ、みんなで松山行こうぜ」
高志が娘たちに言った。
「そうだね。温泉にも入れるし」
「ママの初恋の人にもちょっと興味ある」
「それで柳君は今何をしてるんだい」
「今は道後温泉の旅館で板前をしてる」
「旅館の板さん! だったら美味しい料理にもありつける。ヤッター」
安珠と佳音がハイタッチをして盛り上がった。
「みんなありがとう」
涙で湿った感謝の言葉は娘たちの騒ぎにかき消された。
一週間後、美沙子たち家族は道後温泉の旅館にいた。初恋の相手の柳君も家族を歓迎して楽しい時間を過ごすことが出来た。
初恋を追って松山糸とんぼ 美沙子
美沙子は帰り支度のためにロッカールームにいた。病院に復帰してから一週間が経った。スマホを手にとるとまずSNSのアプリを開いた。最近、SNSの俳句の会に入ったのだ。昨夜も夜勤の休み時間に下手な句と写真をアップしていた。写真には美沙子と娘二人が浴衣姿で踊り、それを当惑顔で見ながら杯を交わす二人の男の姿が映っていた。もちろん顔にはぼかしを入れてある。案の定「初恋の人に会うなんて信じられない。夢は夢のままがいい」というコメントがいくつか送られて来ていた。なかなか私の気持ちは分かってもらえないだろうなと美沙子は思った。
松山の柳からメールが送られてきていることに気付いた。そうだ。少なくとも柳君だけは私の気持ちを分かってくれている。そう思って柳のメールを開いた。
「先日はありがとうございました。美沙子さんのご家族に会えてとても嬉しかったです。私にとってもあなたは初恋の人でした。
でも、ごめんなさい。実は私は柳駿介ではありません。駿介の弟の謙介です。私と駿介は双子の兄弟なんです。美沙子さんが勘違いなさっているのは最初から分かっていましたが、なかなか言えずに結局騙すようなことになって申し訳ありません。私も兄も幼い頃から野球をやっていました。ずっと競い合ってきました。リトルリーグでは駿介の方が注目されていたので一緒の中学に行くのが嫌で両親に頼んで私立中学に進みました。駿介も私も学校ではあまり双子の兄弟の話はしませんでした。だから美沙子さんが駿介に双子の弟がいたことをご存知ないのも無理はありません。
双子同士はとにかく競争心が強いのです。しかし結局は二人とも甲子園には行けませんでした。駿介は大学卒業後も実業団で野球を続けていましたが、プロ野球選手になる夢は叶わず、代わりにプロ野球球団のスカウトの仕事をしていました。私は高校で出て調理の専門学校に進学しました。別々の道を進むようになってはじめて仲良く付き合うことができるようになりました。
駿介は二ヶ月前に病気で亡くなりました。緊急事態宣言の最中でしたので遺骨になった状態で実家に戻って来ました。葬儀も親族だけで行いました。誰も駿介の死を知らなかったので、今回のような間違いが起こってしまいました。たいへん申し訳ありませんでした。美沙子さんは私にとって憧れの女性でした。文化祭でジュリエットを演じた美沙子さんを見てから忘れられない人になりました。私の恋心を知った友人が校門前で待ち伏せして美沙子さんのサインをもらって来てくれました。そのサインは今でも大事に持っています。駿介も私が美沙子さんに恋い焦がれていることに気付いていたと思います。双子ですから黙っていても分かってしまうのです。私が美沙子さんと会ったことを知って駿介は草葉の陰でさぞ悔しがっていることでしょう。いい気味です。
看護師のお仕事。くれぐれも気を付けてください。そしてまたご家族で松山にいらしてください。その日を楽しみにしております。謙介」 了
著・高平九
こちらの作品は、「山田組文芸誌vol.6」に収録されているものです。
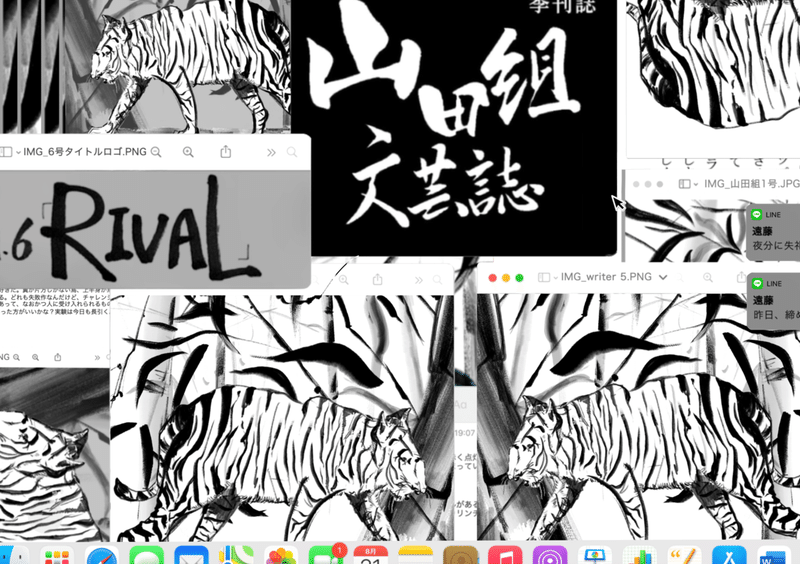
「山田組」とは、2019年に発足された文芸部です。現在は会員4人、準会員1人で活動しています。指定されたテーマに沿って小説を書き、季節ごとに文芸誌を発刊します。
最新号『山田組文芸誌vol.6「ライバル」』はこちらから無料ダウンロードできます。お読みいただく際には、PDFリーダーの使用を推奨しております。↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
