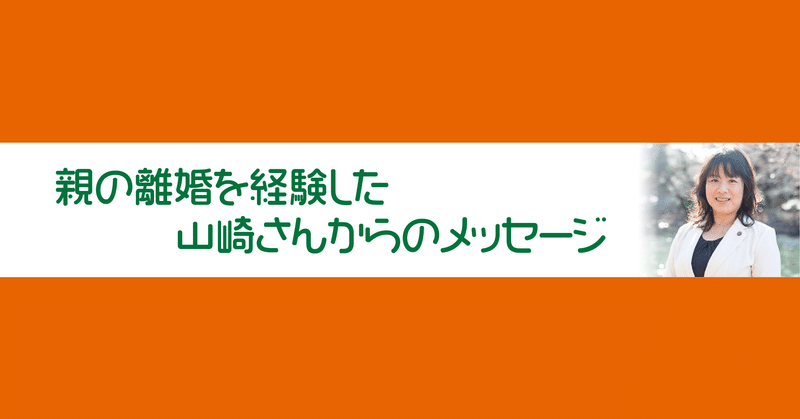
「親が離婚したから天命と言える仕事に出逢えた」親の離婚を経験した山崎さんからのメッセージ
親の離婚を経験して大人になった人たちからの、子どもたちへのメッセージ。 第3回目の今日は、弁護士として活躍されている山崎新さんにインタビューしました。
山崎先生は、お仕事をされてから『離婚家庭に育ったこと』を話すことがなかったそうですが、今回振り返って『良い機会になった』とおっしゃってくださいました。

ウィーズ(以下、ウ):まずは、ご両親が離婚されたときの状況を教えていただけますか?
山崎さん(以下、山崎):はい。私が10歳、妹が4歳の時に母親が家を出ていきました。そこから父と私たちの3人で暮らしていたのですが、1~2年後に赤ちゃんを連れて母が帰ってきたんです。別の男性の子どもだったみたいですが、おそらく両親間で話をして、赤ちゃんと共にまた一緒に暮らすということになったのだと思います。
でも、1か月後には、母はその赤ちゃんを連れてまた家を出ました。後から聞いた話によると、その赤ちゃんの父親である男性が「戻ってこないなら死ぬ」と連絡をしてきたようで、母も迷った末に家を再度出て行ったみたいです。その後私や妹には何も知らされず数年たち、私が中3の時にようやく「離婚が成立した」と父に聞かされました。
ウ:突然お母さんが出ていかれて、帰ってきたと思ったら赤ちゃんを連れている……。壮絶ですね。
山崎:うちの場合は、とにかく何も教えてもらえなかったんですよね。子どもである私たちの目からは、母親がある日何も言わずに帰ってこなくなったという感じだったんです。「お母さんいつ帰ってくるんだろうね」と話していたら、次の日も帰ってこない、その次の日も。だんだんと、「もう帰ってこないのかな」とは思っていたけれど、父には理由を聞いてはいけないと思っていました。もちろん父母間では話をしていたんだとは思いますけれどね……。
というのも、母が赤ちゃんを連れて一度帰ってきたとき、父はその事実を承知していた表情だったんです。だからきっと、赤ちゃん含めて受け入れるから戻って来いと母を説得したんだと思います。妹はまだ小さかったので、母親に抱き着いてとても嬉しそうにしていましたが、私は「は?」という感じ。「第一、あなたは今までなぜいなかったの?」「その子は誰の子?」という思いだったし、「もう行かないよね?」と何度も母に聞きました。
だから、また出て行ったときは裏切られた気持ちでしたね。中学生になるころには「もう離婚だろうな」と薄々思っていましたが、父から離婚の話を聞いて「やっぱりそうだったのか」と確定的に状況を理解しました。
ウ:それでも、「なぜ?」という思いは残りますよね。
山崎:そうなんですよ。親の離婚を経験した子どもの立場の人はみなさんよくおっしゃいますが、なんで母が出ていかないといけなかったのか、この家がなんでこうなったのか、事実を知りたいですよね。先がどうなるかわからないし聞けないのは本当にしんどかったです。母がもう帰ってこないなら、そう言ってほしかったですし、自分であきらめをつけなければならないのは辛かったです。
ウ:ご両親の別居の前は、どんな思いを抱えていらっしゃいましたか?
山崎:とにかく喧嘩ばっかりだったんですよね。母親が家に帰るのが遅くなることが多くなってきて、それも、時に夜中になるんですよ。そうすると、父が怒って喧嘩になる。当時の父のやり方も今となっては良くないなと思うのですが、玄関にチェーンを掛けて、母が入れないようにもしていたんです。母も母で、ベランダをよじ登って2階に来て、家族全員で寝ていた部屋の窓をたたいて『あらた!入れて!!』と起こされたりね。
両親が1階で喧嘩している声が2階まで聞こえることもありました。そういう声を聞くと嫌な気持ちになったし、最初の頃は仲直りしてほしいと切に願っていたのを覚えています。
ウ:親の争いに触れることは子どもにとって本当に辛いことですよね。父子家庭となったあとにはどんなしんどさがありましたか?
山崎:母の姉が近くに住んでいたのですが、母が子どもたちを置いて出て行ったことを申し訳なく思ってか、父子家庭である、うちのサポートをしてくれていたんです。父は教員だったので、毎週水曜日が職員会議だったんですよね。水曜日は学校帰りにおばちゃんの家に行って晩ごはんを食べて、夜に父が迎えに来るというのをしばらくやっていました。
中学生になる頃から、母が不在であること、長女であることから自動的に「母代わり」を自分がやらなければと思っていました。料理なんかもやっていましたが、父に「やれ」と言われたわけではありません。「やらなきゃ」となぜか思っていたんですよね。父からの暗黙の期待は絶対あったし、それに応えなければという思いを持っていたと思います。
あと、母が家にいないことが私の中でどんどん当たり前になってきていたのですが「お母さん、出て行っちゃって、いないんだ」と誰かに言うと「それはかわいそうに」「ごめんね」と言われるのが本当に嫌でしたね。自分の傷つきを否定したい気持ちもあるし、父も楽しい家にしようと頑張っていたと思うので、不幸だというレッテルを人に貼られるのがしんどかったです。そう言われると、母がいないことが自分の汚点のように思ってしまいますよね。
ウ:離婚前から、家の中でも、対外的にもいろいろなしんどさがあったと思うのですが、それを乗り越えるきっかけになったものはありますか?
山崎:高校1年生の時に、母から十数枚ある分厚い手紙が届いたんです。そこには、こういう理由で家を出たという経緯が書かれていました。父との関係でどんなことを思って、別の男性と出会って、どうして出て行ったか、出て行ったあとどうしていたか等々。そういったことを含めた謝罪の手紙でした。
それを受け取ったときは、ショックではありましたが、嬉しかったですね。それまでは母がいないことが当たり前になっていたので、母に会いたいという気持ちもわいてこなかったんです。誰かこの状況を説明してくれとは思っていましたけど、母が悪いということは理解していましたし、私が母と会うことを父が望んでいないだろうと思っていましたから。
それに、父は母のことを恨んでいて、母が私たちを捨てて出て行ったんだということを聞かされ続けていましたが、この手紙で母の視点での話も聞いて、両親が離婚をしたのはしかたがなかったと腑に落ちました。母が私たちを捨てたと思っていましたが、父との関係がうまくいかなかったことが原因で、本当は私たちと離れたくなかったんだと思えたことも良かったなと思います。
ウ:家族の関係性が客観的に見えてくると、少し楽になれますよね。
山崎:そうですね。あと、この手紙が届いた頃は、私も反抗期で父との関係が悪化していました。毎日ともに暮らす唯一の親である父との関係が悪いことは、母が出て行ったことよりしんどいことだったかもしれません。「嫌なら出ていけ!」と言われたこともあります。だから「ああいう人を配偶者にして持つと大変だよね」と、母を理解できる部分もあったんですよね(笑)
20代になって、1人暮らしをすると、父との関係も良くなりました。離れて暮らしていた方が良くなる関係というのはあるのだなと思いました。
でも、「もう一人の大人として母がいればよかったのに」「いてくれたら、家族の関係性が変わったかもしれないのに」と思ったことはありますね。
ウ:逆に、今振り返って、両親の離婚を経験してよかったと思うことはありますか?
山崎:自分のライフワークを見つけたことですね。今の弁護士という仕事は天命だと思っています。親の離婚を経験しなければわからなかったことがたくさんありますから。
母の別居もそうですが、親族の話を聞いていると、母方には離婚経験者が多いんですよ。その話をはじめて聞いたとき、私自身も彼氏との関係に悩んでいたので「私も将来そうなるかも」と思ったんですね。それが理由で大学は心理学科に進学しました。DVや虐待をはじめとする家族関係の病理が『世代間伝達』する仕組みを知りたいと思いました。ジェンダーのこともこのとき学びました。特にこのときは『アダルトチルドレン』という言葉がよく出ていて、これについて読んだときは手が震えましたね。「私に当てはまる」と思いました。当事者の集まりにも参加しました。それらがすべて今の仕事に繋がっています。
ウ:今、親たちへ伝えたいことはありますか?
山崎:もっと状況を説明してほしかったし、それぞれの想いも話してほしかったなと思います。高校生の時に母から手紙をもらってはじめて両親の関係を客観視することができましたが、それが小学生だからできないということはありません。親がタブーを作ったり、カッコつけたりすることなく、そのときわかる言葉で伝えてくれたらよかったなぁと思います。子どもだから言わないようにしようとすると、子どもは余計に混乱します。何もわからないから気を使って、子どもが背負うべきでない重荷まで背負ってしまっていたように感じます。でも、本来子どもがそうあるべきではないですよね。
それに、自分たちの恨みと、「子どもにとってどうか」というのは別に考えてほしかったと思っています。父は母のことを恨んでいましたが、だからといって私たちに「お前たちは捨てられたんだ」と言うのは違うと思うんです。子どもが捨てられたのではなく、夫婦の関係がうまくいかなかっただけですから。
ウ:本当にそう思います。最後に、今、親の離婚を経験し悩む子どもたちにメッセージをお願いいたします!
山崎:親の離婚が自分のせいだと思う必要は決してありません。それに、子どもが年齢以上に大人になる必要はないので、周りの大人に頼ったり、甘えたりしてほしいと思います。それは子どもの権利として守られるものです。
私は今、弁護士として中学校や高校に行って出張授業をすることがありますが、日本は「人権教育」が遅れていると思います。つまり「あなたは生まれた時から素晴らしい」「あなたには価値がある」ということを教えてもらえる場がないのです。「素直なのが良い子」という日本の文化が原因であるようにも感じますが、子どもも個人として尊重されるべきです。
ただ「これからうちの家族どうなるの?」なんて、親以外に誰に聞いたらいいかわからないですよね。本当はそういう窓口や仕組みを作らなければならないと思うのですが、まずは私自身が、そういうことを聞いてあげられる大人になりたいと思います。
■山崎 新 さん
・アイリス法律事務所 弁護士
・アイリス法律事務所HP:https://iris-lo.com/
このnoteが何かの参考になれば、とても嬉しいです。 こんなことを聞いてみたい……といった、ご質問もどしどしお寄せくださいね★ 記事をシェアいただいたり、サポートをいただけますと、より励みになります(^^) 今後ともよろしくお願いいたします<m(__)m>
