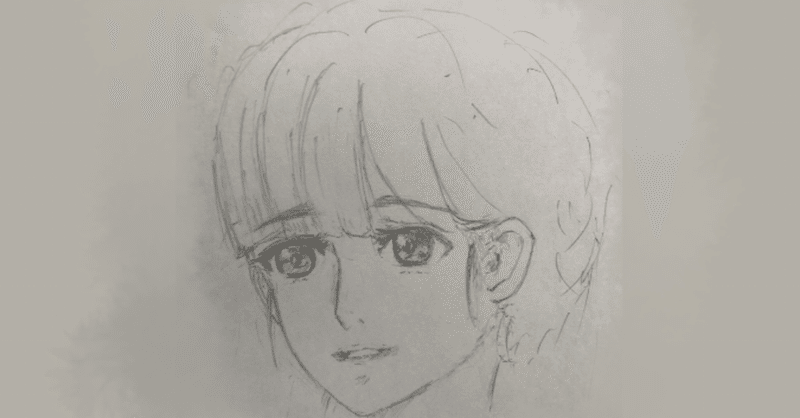
小説「美しきこの世界」 四
クイナの町の朝の気温は日に日に上がってゆきました。それと同時に町や自然から聴こえてくる音も様様増えてゆきました。
「良かった、あったわ」
台所の吊り戸棚を開いた夢はそう言うと、中から瓶を一つ取り出し、そっと戸棚の戸を閉めました。夢が手に取った未開封の瓶には茶色の粉が入っていて、開封するとコーヒーの甘苦い香りが広がりました。コーヒーの粉の香りはこの最初の瞬間が最高です。
「うん」
おばあさんと夢はコーヒーが大好きです。今日はいつものお菓子とこのコーヒーをミロクおばあさんに出す事にしました。夢はおばあさんの喜んだ顔を想像し、「絶対大丈夫」と心に声を掛けました。
お菓子とコーヒーの用意を終えた夢は台所を後にすると、別の作業を始めました。以前約束した食事会が数日後にあるので、その話も出来たら良いなと思い用意していた新聞の切抜きと印刷した店のホームページのメニューをテーブルの上に並べました。
そうしておばあさんを迎える準備を終え、窓の外を眺めていた夢はふと壁の時計に目をやりました。朝早くに起きたせいか時計の針はそれほど進んでいませんでした。少し考えた夢は食器棚からノートを取り出すと、ページを適応にめくって読み返し始めました。最近のもの、書き始めた頃のとても古いもの、それは夢の胸を熱くするものばかりでした。
「入るよ」
突然聞こえたミロクおばあさんの声に夢は驚いてしまいました。鐘の音に気付かないほど夢はノートに夢中になっていたのです。おばあさんは羽織っていた深い紺色の上着を玄関のポールハンガーに掛けると、いつもの椅子に腰を下ろしました。
「今日は遅いんだね。今見てるのかい?」
夢はノートを食器棚にしまい、小走りにおばあさんの所へ向かいました。
「ううん、昔のなの。ちょっと思い出したくなっちゃって」
夢はそう言いながら椅子に座ろうとしたのですが、紙を広げただけのテーブルに気付き、慌てて台所へ駆け込むと二人分のコーヒーを用意し始めました。
「今日はすまないねぇ」
「構わないわ! 私が行きたいだけなの。心配しないで、大丈夫よ」
そして最後に夢は、「絶対大丈夫」と微かな声を零しました。その言葉は他の誰でもない、自分自身に掛けた言葉でした。
小さく深呼吸をし、再びコーヒーの用意を始めた夢がふと手元に視線を移すと、手に持っているスプーンは空になっていました。思わず声を上げてしまった夢はスプーンを傾けてしまったようです。唇を強く閉じた夢は瓶を手に取ると、もう一度コーヒーの粉をすくい取りました。
「ンフフ。あんたはやっぱり変な子だねぇ」
優しく笑うミゲロおばあさん。しかし夢は、おばあさんの声に微かに滲んだ不安に気付き、胸の奥でズキッとした痛みを感じました。次第にその痛みは黒い血が広がるようにジワッと熱くなり、焦る夢を更に不安にさせました。
ズザリ。夢は靴で踏んだ粉に気付かないまま、カップに湯を注ぎ、おばあさんの所へ足早に戻りました。
「きっとすぐに終わるから、見てお店のメニュー! 私はこれが美味しいと思うの」
夢は持ってきたコーヒーをテーブルの端に置くと、メニューの写真や店の内装の写真が載った紙を広げました。
「あら、美味しそうだねぇ。これはどうやって食べるんだい?」
夢はおばあさんが指差した写真に目をやりました。
「これはおば様が持ってきて下さった記事のメニューだわ! 魚介類が沢山入っていて一つ一つ殻を剥きながら食べるの」
そして二人は沢山の料理の話をしました。どの料理も色彩豊かで美味しそうで、色んな種類の穀物と油、野菜に魚介類、香りが広がる沢山のスパイス、そして立ち上る水蒸気、メニューを眺めながら会話しているだけで舌下がそわそわとしてきました。
そうして今日一番の笑顔になったおばあさん。でも、おばあさんは最初から分かっています。夢が用意した少し先の明るい予定、それは夢の思いやりなんだと。だからこそおばあさんは心からの笑顔になれました。
それから少しして会話が落ち着くと、おばあさんは壁の時計に目をやりました。夢もおばあさんの視線を追って時間を確認すると、「まだ少し時間があるから飲みましょ!」と声を掛け、持ってきたコーヒーとお菓子をおばあさんの方に寄せました。これはいつもの光景なのですが、二人共それほど食欲はなく、その後もコーヒーとお菓子にはほとんど手を付けませんでした。
「楽しみの続きは帰ってからにしましょう」
夢が明るく提案すると、「そうだね、後に取っとこうかね」とおばあさんは笑顔で応えました。そして夢はテーブルをそのままにし、二人は出かける用意を始めました。
「素敵な色ね」
夢がポールハンガーからおばあさんの上着を手に取りそう言うと、二人はそこから少しだけファッションの話に花を咲かせました。
「そろそろ時間だね」
おばあさんは夢にそう声を掛けると、玄関の扉を開きました。その瞬間、季節を感じる空気が波のように流れ込み、光が二人を照らしました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
