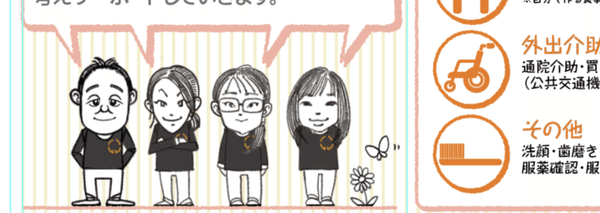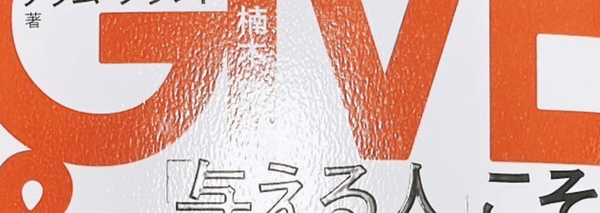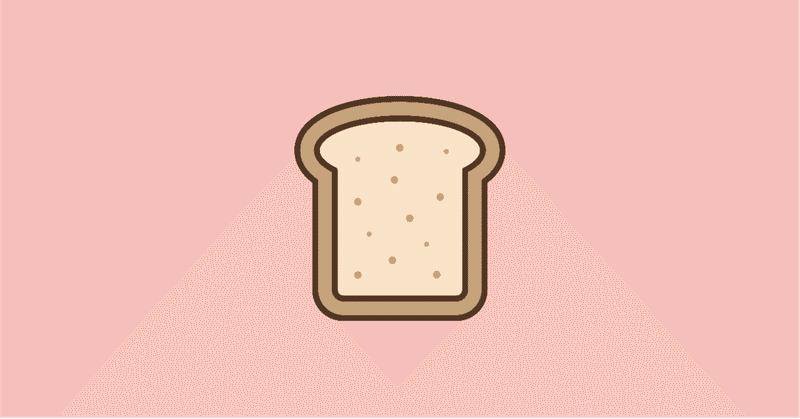最近の記事
- 固定された記事
- 固定された記事
マガジン
記事
-
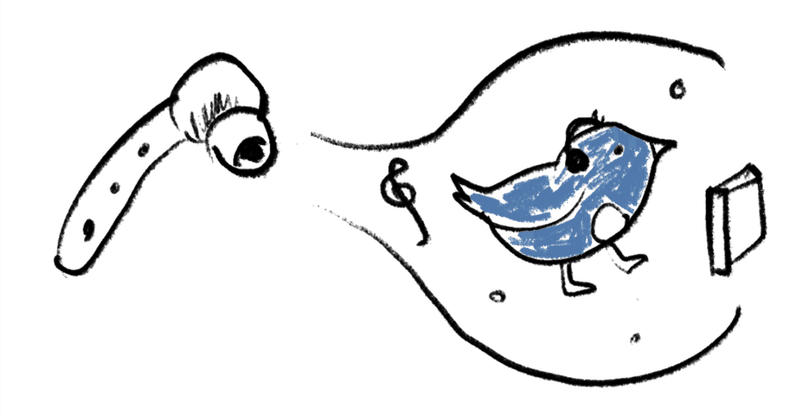
【調査レポート】COTEN RADIOリスナーのメイン層は30~40代ビジネスパーソン!通勤時間や家事中に「ながら聞き」で楽しめる歴史キュレーション番組・・・という記事の紹介です。
今日は、毎週楽しみに聴いているコテンラジオの視聴者アンケートの報告をピックアップしようと思います。 ▼ コテンラジオ公式ホームページはこちら ↓ ▼ コテンラジオ公式のnoteはこちら ↓ ▼ そして、本日の内容のポッドキャストによる特別編はこちら ↓ リスナーアンケートは、今回で2回目ですね。 1回目の時は、まだ僕はリアルタイムで視聴していなかったのでアンケート協力できませんでしたが、今回はアンケートに協力できました。 今日の本題のプレスリリースの記事はこちらにな