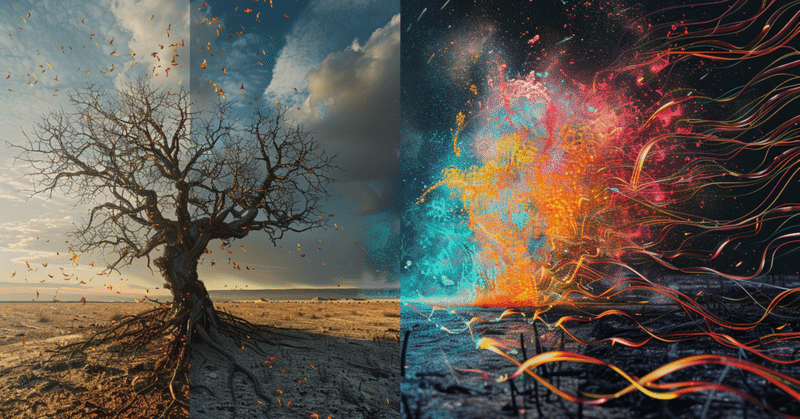
【米国株】決算を前に - エヌビディア投資において、景気動向は気にするべき?
5月22日に予定されているエヌビディア(NVDA)の四半期決算が大きな注目を集めています。足元の米国経済に関しては、雇用や消費の弱さを示すデータが散見されます。このような環境下で、エヌビディア株式への投資判断において、景気動向はどのような意味を持つのでしょうか。この点について、考えを整理してみたいと思います。
結論から言えば、AI実需の拡大という大きなトレンドを考えれば、仮に景気後退が起きても、それがエヌビディアの業績に与える影響は限定的である可能性が高いと考えます。
雇用や消費などのマクロ経済動向がエヌビディアの業績にどのような影響を与えうるのか、その道筋を思考実験的に考えました。
まず、エヌビディアの売上にとって最も重要なのは、クラウドサービス需要に支えられた大手テクノロジー企業の設備投資です。現在、クラウドサービス需要は加速しており、大手クラウド事業者は設備投資を拡大しています。したがって、少なくとも次の決算では、エヌビディアの実績や業績予想に懸念材料はないと考えられます。
さらに、クラウドサービス需要の多くは企業のAI投資ですが、不況時においても、消費減少や企業の売上減少と、企業のAI投資の間には一種の「壁」が存在すると見ています。コスト削減と効率化を目的としたAI投資は、景気後退期にも継続される可能性が高いと考えます。
実際、過去の景気後退期を振り返ってみると、業務効率化や競争力強化に直結するIT投資は、コスト削減を目的とした支出として優先的に実施される傾向がありました。
つまり、細かい短期の景気動向は、エヌビディア投資にとっては問題とならない可能性が高いと言えます。
ただし、エヌビディアのGPUが「資本財」であることには留意が必要です。クラウド大手は、拡大するAI処理実需への対応のための設備投資としてGPUを購入しています。
「原材料」と違い、資本財は、実需の拡大が止まれば、既にある設備で対応可能なため、新規の購入が不要になります。つまり、AI実需の拡大ペースが大きく鈍化すれば、クラウドサービス企業のGPU投資は大きく縮小する可能性があります。ただし現時点では、AI処理実需は明確な拡大傾向、縮小を引き起こすような深刻な景気後退も見えていません。
したがって、エヌビディア株式への投資判断においては、短期的な景気動向よりも、中長期的なAI実需の成長持続性を見極めることが極めて重要だと考えます。

景気動向がエヌビディア売上に影響する経路を考える
雇用や消費などのマクロ経済動向がエヌビディアの業績にどのような影響を与えうるのか、その道筋を思考実験的に考えてみましょう。

まず、雇用が増加すると、消費者の購買力が高まります。これにより消費が拡大し、消費者向け企業(B2C)の売上が伸びると予想されます。B2C企業は、消費者を直接の顧客とする企業で、消費拡大の恩恵を直接受けるからです。
次に、B2C企業の業績が向上すると、企業間取引を中心とする企業(B2B)の売上も増加すると考えられます。B2B企業は、他の企業を主な顧客とする企業で、取引先の業績向上により間接的に消費拡大の恩恵を受けます。
業績が好調な企業は、業務の自動化や生産性向上のため、多くのAI導入プロジェクトを開始するでしょう。企業のAIへの投資が増えれば、AI処理をサービスとして提供するクラウドサービス企業の売上が伸びます。
AI関連の需要増加に対応するため、クラウドサービス企業は設備投資を行い、AI処理に不可欠なGPUを購入します。エヌビディアのデータセンター売上の50%程度がクラウドサービス企業とメタ向けとされているため、これがエヌビディア社の売上拡大につながると予想されます。
図の矢印の関係が有効だとすると、現在は、堅調な雇用・消費に支えられ、全体の好循環が起きている状況です。
クラウドサービス需要は加速。大手は設備投資を拡大
まず、エヌビディアの業績を見通す上では、上の図で直前にいる、クラウドサービス需要の動向が最重要になります。
現在、AI関連のクラウドサービス需要は急拡大しており、クラウドサービス大手はそれに対応するために、データセンターへの設備投資を積極的に行っています。これエヌビディアの売上拡大を力強く支えている状況です。


クラウドサービス企業の設備投資は増加傾向にあり、その大きな部分がAI関連、つまり、引き続きエヌビディアのGPUに向かいます。
各社決算でのコメント:
マイクロソフト:AI/クラウドへの投資を拡大。2025年度の設備投資も2024年度を上回る見込み
アマゾン:2024年は設備投資が大幅に増加する見通し。主にAWSインフラと生成AIへの投資
グーグル:2024年の設備投資は高水準の今四半期以上が継続
メタ(フェイスブック):長期AIロードマップを見据え、今後数年間もAI投資を大幅に増やす方針。2024年設備投資見通しを$30-37Bn ⇒ $35-40Bnに上方修正
以上の動向から、少なくとも次の決算では、エヌビディアの実績や業績予想に懸念材料はないと考えられます。クラウドサービス企業の旺盛な設備投資が、同社のGPU需要を力強く支えると期待できます。株価の反応は分かりませんが、少なくとも大きなネガティブサプライズを懸念すべき材料は見られません。
次に、景気後退は、エヌビディア投資において本当に重要な要素なのでしょうか。つまり、この図で示した、クラウドサービス以前の矢印の関係は有効なのでしょうか。
景気後退期に何が起きるのか?
上で示した好循環の流れの中で、出発点となる雇用と消費に関して、その堅調さを懸念するデータが散見されます。例えば直近でも、
雇用:5月4日時点の米国の新規失業保険申請件数が、前週比2.2万件増の23.1万件となり、昨年8月以来の高水準に達した。
消費:米ミシガン大学が5月10日に発表した5月の消費者信頼感指数(速報値)が、67.4と6カ月ぶりの低水準に落ち込み。4月は77.2で、市場予想は76.0。
雇用と消費への懸念が顕在化すれば、消費者向け企業(B2C)や企業間取引中心の企業(B2B)の業績は悪化する可能性があります。
しかし、それが直ちに企業のAI投資の減少につながるとは限りません。この図で言うと、消費減少、企業の売上減少と企業のAI投資の間には一種の「壁」が存在すると見ています。

その理由は、企業のAI投資が主に業務効率化とコスト削減を目的としているからです。企業は厳しい経済環境下にあるからこそ、コスト削減に注力する可能性があります。AIへの投資は、まさにこのコスト削減を主目的としたものなのです。
大手企業によるAIを使ったコスト削減の成功事例が報告されています。
プロクター・アンド・ギャンブル:製造工程にAIを導入し、生産効率を高めて製造コストを削減。
シェル:AIを活用して油田開発を最適化し、資源採掘の効率化と環境負荷の低減を実現。
大手資産運用会社:AIを活用した仮想アシスタントを導入し、コンタクトセンターの運営コストを大幅に削減。
アメリカン・エキスプレス:AIを用いて不正取引を検知し、関連する損失を数百万ドル削減。
ネットフリックス:AIで視聴パターンを分析し、ユーザーの好みに合わせたコンテンツをレコメンドすることで、顧客満足度を高めつつコンテンツ制作コストを最適化。
過去の景気後退期では、長期的な「コスト削減」を実現する支出は維持された
過去の景気期においては、全体のIT投資は全体としては減少したものの、長期的なコスト削減を目的とした支出は継続さる傾向があったようです。(下記AI調べ。)
リーマンショック(2008年)前後
世界的な金融危機の影響で、多くの企業がIT支出を抑制
コスト削減を目的とした支出が優先され、新規投資やアップグレードは延期される傾向
ただし、業務効率化や競争力維持に直結するIT投資は継続される傾向
ドットコムバブル崩壊(2000年)前後
IT関連企業の経営破綻や株価下落を受け、IT投資に対する慎重姿勢が広がる
投資対効果の見極めが重視され、費用対効果の高い案件に絞り込む動き
一部の企業では、IT投資を戦略的に継続し、競争優位性を確保する動きも
欧州債務危機(2010年)前後
ギリシャ、スペインなどの債務問題を受け、欧州企業を中心にIT支出が抑制される
クラウドサービスの利用拡大など、柔軟でコスト効率の高いIT投資が選好される傾向
一部の企業では、不況下でもIT投資を維持・拡大し、業務効率化を推進
つまり、多少の景気後退が起きたとしても、それが直接的にAI投資の減少につながるとは限らないと考えられます。むしろ、不況下でこそ、企業はAIを活用したコスト削減と効率化を推進する可能性さえあるのです。
ただし、長期の深刻な景気低迷下では、AI投資も徐々に減少せざるを得なくなるでしょう。また、AIによる業務効率化の結果として、必要な人員数が減少し、失業が増加するリスクも懸念されます。
GitHubコパイロットなどのAIコーディング支援ツールがエンジニアの生産性を大きく向上させていることが報告されていますが、米国テック業界で相次ぐ解雇は、これと無縁ではないと見ることもできます。AIの導入により、同じ仕事量をより少ない人数で処理できるようになった結果、余剰人員の削減、つまり「AI失業」が進んでいる可能性があります。そして、広い業界でAIを用いた生産性向上が進むと、「AI失業」が拡大する可能性があります。
仮に景気後退が長期化する環境下で、「AI失業」の流れによって雇用が更に悪化すると、より深刻な景気後退に陥る可能性があります。そのような状況では、エヌビディアの業績も無傷ではいられないでしょう。今は遠い懸念ではあります。
改めて、GPUは「資本財」であることには留意
エヌビディアのGPUは、クラウドサービス企業にとって「資本財」の一部です。資本財への投資は、将来の実需の成長を前提に行われます。つまり、AI実需の成長が止まれば、資本財であるGPUの購入は不要になるのです。
資本財と原材料には大きな違いがあります。
原材料は、現在の生産水準を維持するために常に一定量が必要です。たとえ成長がなくても、前年並みの購入は続きます。
一方、資本財である設備・機械への投資は、将来の成長が見込まれる場合にのみ行われます。成長が見込めない場合、新規投資は不要になります。すでにある既存の設備で生産は維持できるからです。

決算説明会コメント、23/9期 3%、23/12期6%、24/3期7%がAI需要による伸び、から算出。
エヌビディアのGPUも例外ではありません。何らかの理由で、企業によるクラウドサービスのAI関連需要の伸びが止まれば、クラウドサービス企業は設備投資を大幅に減少させるでしょう。その際には、エヌビディアのGPU売上は急減することになります。
したがって、エヌビディア株式への投資判断においては、短期的な景気動向を追うよりも、中長期的なAI実需の成長持続性を見極めることが極めて重要になります。
また、GPUの性能向上や電力効率の改善などの技術進展は、買い替え需要を喚起するため注目すべき点です。しかし、実際の需要の成長がない場合、こうした技術進歩は市場全体の停滞を打開する決定打にはならないでしょう。
まとめ
長期的な成長トレンドに支えられたハイグロース企業への投資において、短期的なマクロ経済動向はあまり重視する必要がない、というのは教科書的な結論かもしれません。しかし、AIブームという大きな潮流と、その中心に位置するエヌビディアの存在は、それ自体がマクロ的な事象とも捉えられます。
このAIブームというマクロトレンドと、足元の米国経済の先行き不透明感という別のマクロ事象が、エヌビディア株式投資にどのように絡んでくるのか。この2つの関係性について、混乱を感じている投資家も少なくないと思います。
本記事では、景気動向がエヌビディアの業績に与える影響は限定的である可能性が高いと論じました。その理由は、AIの実需拡大という大きなトレンドが、景気後退局面でも継続すると考えられるからです。
ただし、エヌビディアのGPUが「資本財」である点には注意が必要です。AI実需の拡大ペースが大きく鈍化すれば、クラウドサービス企業のGPU投資も縮小する可能性があります。
したがって、エヌビディア株式投資では、景気動向よりも、AI実需の成長持続性を見極めることが重要だと言えます。
本記事が、AIブームと景気動向という2つのマクロ事象の関係性について、投資家の皆様の頭の整理に役立てば幸いです。
米国株インサイト
2024に始動。米国株に特化した【無料note】で、独自視点の投資判断の材料を、図表を多用し簡潔かつ深度を持ってご提供します。note🗒️更新はXでも共有いたします。Xかnoteでフォローお願いいたします🙏
Note: https://note.com/tender_deer595
X: https://twitter.com/invest_us_jp
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
