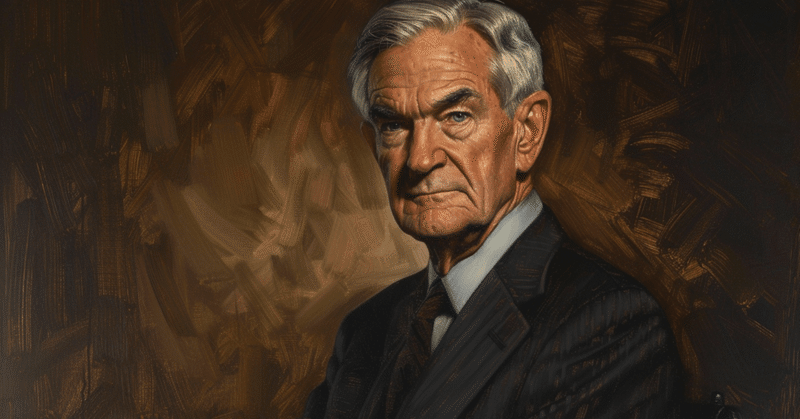
【米国株】5/1 FOMCのポイントを議長発言とデータから考察
5月1日に開催された米連邦公開市場委員会(FOMC)からの示唆を、パウエルFRB議長発言とデータから考察します。
ポイントは下記と考えます。
FOMCのアクション検討フレームワークが整理して示された
現状認識①:今のFF金利は制限的、インフレは低下に向かう
現状認識➁:しかし、インフレ低下には予想より時間を要し、利下げは遠のいた
予想よりも大きいQT(バランスシート縮小)減速
「」内は記者会見でのパウエル議長の発言内容です。
FOMCのアクション検討フレームワーク
パウエル議長は、次のアクションについて、このように整理しました。
「利上げの可能性は低い。」
金利を維持するシナリオ
「労働市場の強さが継続し、インフレ率が予想以上に粘り強く推移し、2%への低下に対する自信が失われた場合。」
金利を引き下げる2つのシナリオ
「インフレ率が 2% に低下すると確信が持てるようになった場合。」
「労働市場に予期せぬ弱さが見られた場合。」
FOMCの現状の認識①:FF金利は制限的、インフレは低下に向かう
「現在の FF 金利は、インフレ率を 2% に戻すのに十分に制限的。」
「今年中にインフレ率が再び低下していくと予想している。」
複数の理由が示されています。
理由①:昨年、強い経済とインフレ低下が共存した
「昨年観察されたのは、非常に強い労働市場と、かなり速いペースでのインフレ率の低下。」
「背景には二つの力があると考える。①コロナによって混乱したサプライチェーンの正常化、➁金融引き締め政策の効果」

理由➁:サプライチェーンの正常化継続の期待
「高いインフレを抑制するためには、ある程度の痛み(失業率の上昇など)を伴うと考えていたが、これまで、その痛みなしにインフレを抑制できていることは素晴らしいこと。」
「その理由は、インフレの主な要因がサプライチェーンの問題に関連していたからだと考える。」
「サプライチェーン問題が完全に解消したとは考えておらず、正常化による恩恵はさらに継続する可能性がある。」
「企業はまだ供給サイドの問題を指摘。」
「たとえ供給サイドの問題が解消されたとしても、それがすぐにインフレ指標に反映されるわけではない。」

理由③:経済成長は加速しているわけではない
「経済成長は、今年の第1四半期は概ね2023年を通した水準と同程度であり、成長が加速しているわけではない。」
「したがって、昨年からの金融環境の緩和が経済活動の上昇をもたらし、それがインフレの再加速を引き起こしたとは言えない。」
「現在のインフレ再加速の原因は、金融環境の緩和に支えられた経済の加速が原因ではない。」

理由④:正常化に向かう労働市場
「労働市場の求人がまだコロナ前より強いものの、落ち着きを見せ始めている。」

「自主的な離職率と雇用も同様に正常化しつつある。」

「賃金上昇率はコロナ前と比較すると依然として約1%高いが、低下してきている。」

「移民の増加と労働参加率の上昇により、労働力が増加。」

「強い労働市場がインフレに直接結びつくとは考えていない。」
理由⑤:家賃の下落が今後インフレ低下に貢献する
「市場の賃貸料の動向を考慮すると、住宅関連サービスのインフレ率 は時間をかけて測定されたインフレ指標に反映されていく。」
「予想よりも、インフレ指標への反映にはラグがあるようだが。市場の家賃が低ければインフレ指標上も低下する確信を持っている」

理由⑥:金利の影響が大きい住宅・投資需要の減速
「住宅投資や設備投資にも、現在の金利水準が重石となっている。」
FOMCの現状認識➁:利下げは遠のいた
しかし、インフレ低下には予想より時間を要し、利下げは遠のいた、という認識を示しました。
「我々は、1-2ヶ月のノイズに惑わさぬため、第1四半期の3ヶ月間のデータを精査するまで、何らかのシグナルを読み取ることを控えていた。」
「第1四半期のデータを得た今こそ、シグナルを読み取るべき時。」
「そのシグナルとは、インフレ率を持続的に2%に収束させる軌道に乗ったと確信を持つまでには、より長い時間がかかるだろうということ。」
「今年中にインフレ率が再び低下していくと予想しているものの、その確信度は以前よりも低くなった。」

「予想以上に高い財のインフレ率と、住宅関連を除くサービスのインフレ率の上昇が見られた。」
時間軸は後ろ倒しされたものの、現状認識①、で上げた理由から、インフレは2%以下への低下に向かう、という想定は変わっていないことを示しています。
注視すべき、インフレ、失業率水準
インフレは、3%以上が重要な水準
「これまでは、インフレ率が非常に高かったため、物価の安定に完全に焦点を当てていた。しかし現在、インフレ率(前年同月比)が3%を下回るまで低下したことを受けて、最大雇用も考慮に入れたバランスの取れた政策を実施できる状況になった。」
つまり、インフレが3%を上回ると、再びインフレ完全フォーカスの政策に戻ると示しています。その場合は、予期せぬ失業率上昇が起きたとしても、対応余力は限定的になると考えられます。
現在、PCEインフレは2.7%、コアPCEインフレは2.8%(前年比)でバッファーは大きいわけではありません。

失業率は4.1%以上が重要な水準
記者の質問:仮にインフレ率が現在の水準で推移し、失業率が4%まで上昇した場合は対応するか?
「対応を検討するためには、失業率が予期せぬ意味のある水準まで上昇する必要があります。」
FOMCは前回会合時に公表した経済プロジェクションで、委員の平均として、失業率が4.1%まで上昇するという予想を示しました。つまり、この水準までは想定内、これを上回ると、インフレが大きく上昇していない状況においては、利下げによる対応の実施が検討されると考えることができます。

QT(バランスシート縮小)減速の意味
保有する米国債の縮小ペースを月600億ドルから250億ドルに減速する方針が示されました。市場は半分の300億ドルへの減速を予想していたため、市場予想を上回る減額となります。
これは金融緩和を意図したものではなく、むしろ資産規模の縮小をスムーズに行うための処置、とします。
「QTの減速は長い間議論されてきた事項であり、金融緩和を目的としたものではない。」
「その目的はむしろ、目標とする水準まで資産規模を縮小する過程で、マネーマーケットを混乱させることなく、スムーズに行うためのものです。」
しかし、近年、米政府による新規国債発行は財政赤字拡大を背景に拡大しており、FRBが国債保有を減らす中、買い手が求められている状況にあります。中・長期金利の上昇はこの需給悪化による要因もあると考えます。

買い手として大きいのが、MMFです。MMFは短期資金を運用するファンドで、個人や企業の一時的な資金の置き場として非常に大きな資金を運用しています。MMF資金の大きな部分がFRBの提供する「リバースレポ」という運用手段に置いてありましたが、国債の利回り上昇により、国債の買い手になっています。

「リバースレポ」にあるMMF資金が減少傾向で、枯渇した際の国債需要の減少が懸念されていましたが、まだ枯渇していないため、今回のFRBもQT減速は、国債の需給改善要因になると考えます。実質的に緩和方向の作用があるり、需給を改善させるため、金利にじわじわと効いてくると考えます。
まとめ
FOMCは、現在のフェデラルファンド金利が制限的な水準にあり、インフレ率が目標の2%に向けて低下していくと予想していますが、利下げの可能性は当面低いとの認識を示しました。また、予想よりも大きなペースでのバランスシート縮小の減速が示唆されました。今後のFOMCの政策決定は、インフレ率と労働市場の状況を注視しつつ、慎重に行われるでしょう。金融政策が経済に与える影響を見極めながら、経済データとFOMCの動向を注視します。
米国株インサイト
2024に始動。米国株に特化した【無料note】で、独自視点の投資判断の材料を、図表を多用し簡潔かつ深度を持ってご提供します。note🗒️更新はXでも共有いたします。Xかnoteでフォローお願いいたします🙏
Note: https://note.com/tender_deer595
X: https://twitter.com/invest_us_jp
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
