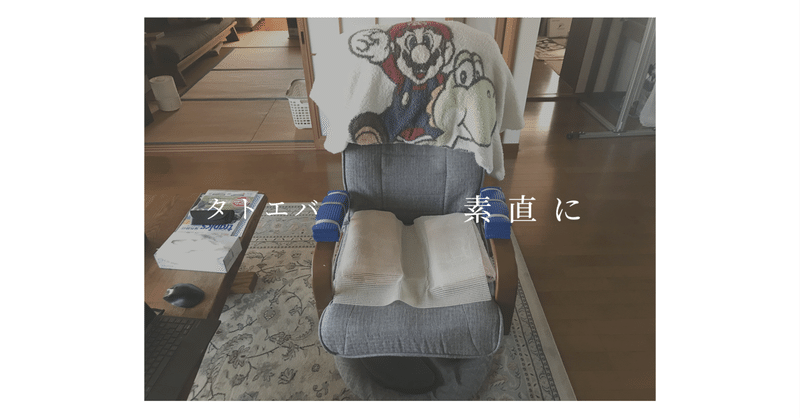
タトエバ10 素直に -ALSだった母と暮らして-
素直に 24年1月16日
手放していく。自分が、という理由を持ち出して、大抵は手放していく。
母と暮らす。手にするのに理由はなかった。それはただ素直に自分はどうするかを手にしただけ。母の病気を知らされ、東京で生きることはもう終わらせるとすぐに思った。そう決める前からすでに、設計事務所で働くことは終わらせようとしていた。福島に戻ろうとしていた。社会が可笑しくなり始めてたときに、都合良く事務所の所長から辞めてくれないかと持ち掛けられた。様々な理由が重なり合って、決断をさせたようだけれど、自分がもっとも素直に手にしたのは母と暮らすということだった。考えるよりも先に自分がどうするかはもう自分のものだった。
母がこの家で死ぬところまでともに暮らした。母のために、母の代わりになって、母を支える、という言葉は、いつの間にやらどこかで付け足されたものにすぎない。僕たちはただともに暮らした。生活は母がこの家で繰り広げてきたものを同じようになぞるものだった。母が繋いできたものを変わらず繋ぎ留めていくものだった。母が手に入れていく、病気があることで表れてくることになった新しい世界に、母らしい繫がりを同じように紡いでいくものだった。朝起きて、トイレに行く。3食ご飯を食べる。昼寝をする。ラジオを聞く。相撲を見る。言葉を交わす。だれかへのお裾分けを目論む。頂きものへのお返しをあれこれと計画する。孫を喜ばせる算段をする。次のイベントを計画する。娘に色々と注文する。父の駄目なところを指導する。看護士へのお土産を見繕う。楽しいことがあり、うれしいことがあり、悲しいことがあり、苦しいことがあり、辛いことがありながら、過ぎていく。ぼくは母のためにいろんなことをしながら、母はぼくのためにいろんなことを気遣った。母を喜ばせるために、母を居心地良くするために、母が穏やかに過ごせるようにしたかった。言われたことをちゃんとやらず、言ったことを忘れ、同じ失敗を何度も繰り返し、母を苦しませた。自分の仕出かしたことを棚に上げて怒り、それを母にぶつけ悲しませた。母の苦しみにきちんと向き合ってあげることをせずに、自分のイライラに呑まれてそれを母に表してしまうことがたくさんあった。良いことも悪いことも、どちらもがたくさんあった。それはふつうの親子の暮らしがあったということ。
でも、その当たり前の暮らしをすることで手に入れたんだと思う。だからこそ、手に入れたものがある。
みんな、どこかで何かを諦めている。自分が立っているところから見えるものに意味を付け足して、考えて、理由を見つけて、それにそぐわないものは手放すことにしていく。手放したことに自分だけの理由を当て嵌め、その前にあったはずの可能性には蓋をして、そこにはもう戻らないようにして前に進んでいく。はじめに、自分に向けて、一番大きな理由を仕立てて飲み込んでしまうからこそ、それ以上のものは自分の前にもう二度と表れなくなる。理由は次々に理由を作り出していく。諦めるのを当たり前にしていく。受け入れることを自分の正解にしていく。それは自分が素直になることを遠ざけていく。
例えば、大切な人が病気になって入院する。もちろんそれしか選択肢はないのだとしても、自分が抱えることができる責任や可能性は、自分ではないところへ離れていってしまう。多くのことが自分にはできなくなる。手放した先で起こることに傍観者でいることしかできなくなる。起こることのほとんどに、ただ結果を受け止めることでしか自分は存在できなくなっている。はじめに諦めがある。そしてそれ以上の諦めは手に入ることはない。
諦めるとか諦めないとか、そんなことより先にただできることをするだけだった。母とともに生きられるのならばそれが僕にとって手に取るものだった。母は機械的な方法に頼って生きることを選ばなかった。僕らにとってそれは母の生き方のそのままに思えたからただ受け留めた。可能性を無造作に手放したわけではない。母も僕も考えることを決して止めなかった。いま自分に見えている可能性に自分が囲われることがないように、やってくるその都度に変わっていくだろう世界をきちんと見極めて考え続けようとしていた。母は折りに触れ施設に入りたいと言った。それはきっと僕たちのために出た言葉だ。僕たちのことを何よりも大事に思う母が言うことだった。僕は、じゃあその選択肢を考えてみようと言った。調べ検討して、可能性のひとつとして持ち続けようと言った。そしてその後に、でもあなたは最後までこの家で暮らすし、僕が最後までそばにいてあなたを支えるんだからね、と確認するように話した。母はうれしいような悲しいような顔をいつもしていた。いろいろな福祉サービスを受けたり、施設を利用してみたりすることで分かったことは、サービスという仕事にはできることとできないことがあるということ。専門的なサポートは受けられるとしても全体のなかのひとつとして自分に向けられるサービスは限られるということ。結局は医療や介護だって人が行っていることで、人によってできるできないが表れてくるということ。この家で暮らすようにはまるでいかないということ。母と僕が生きるようには生きられないということを僕は思っていたし、母も同じように分かっていたはずだ。
ぼくはこの暮らしを手放したいと思ったことはなかった。苛々が募り、時折母にまで辛く当たってしまう自分に陥るくらい、心がバランスをなくし、行き詰まるような気持ちに苛まれていても、それは母とはまるで関係のないことだった。ほとんどは、こちらが見ようとしているものを、母のために手に取ろうとしているものを、同じように分かち合えない父の振る舞いのせいだと理由は分かっていた。もう考えることができなくなっている父に対して、先がなくなってしまうような諦めを覚えていただけのことだった。そんな僕はどうにもならないものに追い込まれていたけれど、母のために暮らすいまを、行けるのならばどこまでも続けていきたいと、できることがあるならば何でもすると、ただそのことだけが僕の目の前には表れていた。
ただ素直にしただけ。ただそうしようという自分があっただけ。
それでも、いま僕が思っていることは、だれにも手に入らないもの。だれかと分かち合えるものではない。手放さないということによって、手に入れたものがあるとわかった。これは母が最後にぼくに与えていったもので、母は母らしく手に入れていったものだと、そう思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
