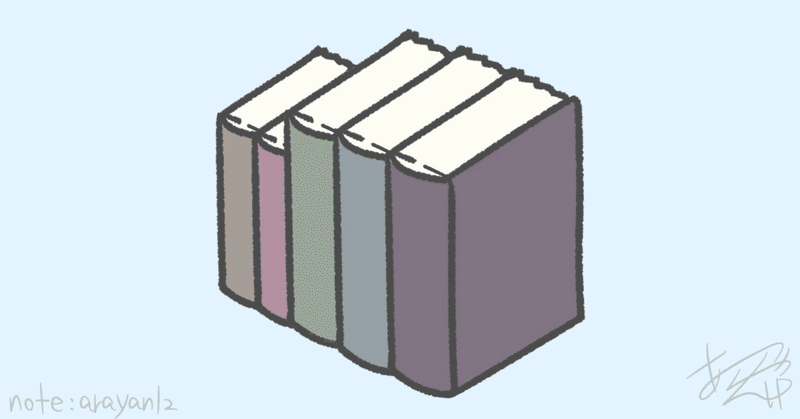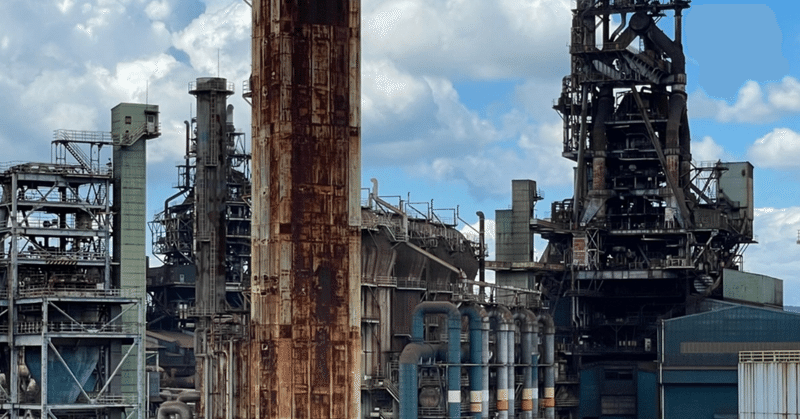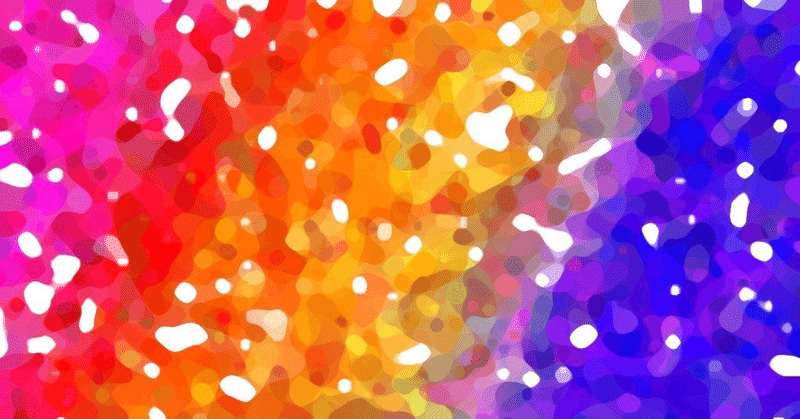最近の記事

社内の勉強会(学びフェス)で「RSGT2024 証券取引所のサービスをアジャイルに開発し続ける上での学びと取り組み」を視聴しました
6月は会社で毎日、勉強会のイベントをやっていますが、RSGTの常田さんの講演を皆で見ました。 出てきた意見 ・富士通で1デベロッパーから「登壇したい」という想いでお客様とも内部とも調整して案件を報告している事がスゴイ! ⇒「お客様の案件だし、発表出来ない」という時代は古いと感じていて、お客様への価値貢献のためにもお客様も巻き込んで発表していく事が大事 ・金融系でのリーンスタートアップアジャイルができているというのはすごいですね。適切な要件がわからないとはいえ、決まり事な
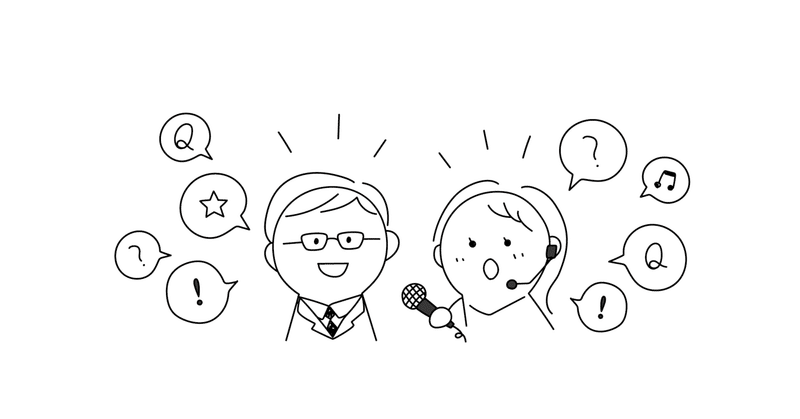
社内の「プロダクト勉強会」で“UXデザイン”のキモ『ユーザーインタビュー』の具体的テクニックを詳解!| UXデザイン基礎セミナー 第2回のスライドを見ました
表記スライドをメンバーで読み合わせる勉強会を行いました。 ちなみに前回の勉強会はコチラです。 感想・意見 ・最初のラポールが重要 ・自分の主観を入れずに、相手の話をありのままに受け止める ・ユーザーに興味を持って心の中でなぜ?をくりかえす ・指示語を使われたときは、自分の言葉で穴埋めせず確認する! ・一般論ではなく、インタビュイーの主観を引き出す ・具体的な情報が出たら、背景情報も引き出す ・何と比べていたのか?どんなことを期待していたのか?といった比較感を確認する(比
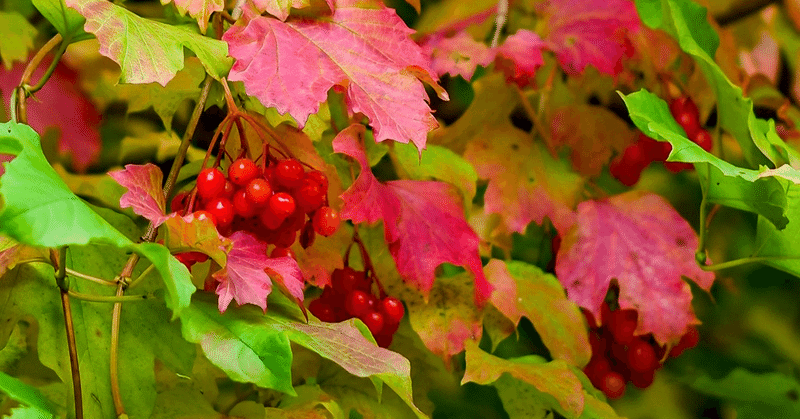
社内のプロダクト勉強会で「DevOpsTokyo2024_境界を越えたアジャイル:他社間で構成されたスクラムチームで私たちが試行錯誤していること」を視聴しました
社内の勉強会に参加して下記動画を見ました。 ちなみに前回の記事はコチラです。 見て話した内容 ・もうすぐスクラム2年ということで、ほぼ自分達と同じくらいだったので気になる ・お客様との共同出資会社という事で体制が気になった。ビジネスパートナーだけでなくお客様側ともどのように関係性を気付いていったのか? ・DEV内で主体的に改善活動を進めていけるようになった。(これまでは指示されるものだった)という事は良くわかる ・会社を超えた話でしたが、ビジネスパートナー側の実際の意見