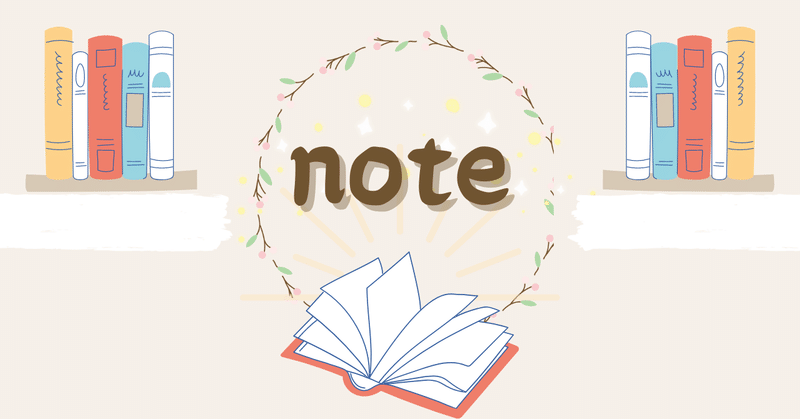
言葉に寄り添う。自分を育てる旅に出る。【とある日の読書記録】
こんにちは。RaMです。
数あるnote記事の中から、
こちらの記事を目に留めてご覧くださり、
本当にありがとうございます😊
こちらのnoteアカウントでは、
自分のことを大切にしながら暮らす中で、
感じたことや学んだこと、
日常に活かせるポイントなどを
わたし自身の言葉で紡いでいます。
どうぞ、気を楽にして、
ゆっくりしていってくださいね♪
◎
はじめに
今回の記事では、
わたしにしては珍しく
読んだ本のご紹介をしてみようと思います。
と、宣言しておいて、本のレビューなんてしたことは、ありません。
しかも、読むのに長けているこのnoteという場で、みなさんに見せる文章など書けそうにないです。
そうであったとしても、どうしても、形として残したくなりました。
どんな形だったら、わたしに書けるかなあ?と悩んだ結果、今回は、この本を読んだわたしが得たものについて、お伝えしてみます。
あなたは、読んだ本から、
どのようなことを得ますか?
得たいですか?
それでは、本編へどうぞ。
◎
わたしが、今回読んだ本は、こちらです。
言葉の舟 心に響く140字小説の作り方

本屋さんに入ってすぐ、目に飛び込んできました。
いわゆるジャケ買いとか、パケ買いの部類になります。表紙の色味が完全に好みでした。
次にタイトルを見て、一旦この本のことを検索しました。
集英社さんで発行されていて、2024年4月26日に発行されたとのこと。まだ出て間もないのですね✨
そして、わたしが検索してたどり着いたサイトに書かれていたひとこと。
自分の言葉で物語を紡いでみたいと考えているすべての人へ。
魅力的なショートストーリーの書き方入門書!
この声かけで、直感的に決めました。
本の帯や宣伝に、いとも簡単につかまっています。
そんなわたしは、いいお客さんかもしれません。
このタイトルと内容に、飛びついたということは、わたしの脳内が完全にnoteで占拠されているということです。笑
そして、本を手に取る前に、いろいろ情報を漁っていたら、こちらの本の刊行記念として、企画が行われていることを知りました。
わあ…。興味は、とってもあります。
でも、みなさんそれこそ場慣れしていらっしゃる方々ばかりだろうし…と、半ば後退りしています。
読まないことには、始まらない。
気を取り直して、本を手に取り、早速、コーヒー片手に読み始めました。
このあたりで、ちょっとだけ、こちらの本の概要に触れておきます。
わたしが検索した時に見た、集英社さんのページの内容を抜粋いたします。
詳しくは、リンクからご覧くださいませ。
【内容紹介】
活版印刷や和紙、金継ぎ、和菓子などの伝統文化を題材としたおはなしを執筆する一方で、自身の活動としてX(旧Twitter)で140字の短いおはなしを10年以上発表してきたほしおさん。
本書は、そんなほしおさんがこれまで講座等で教えてきた140字小説の構成の組み立て方や書き方のポイントに加え、ほしおさん自身の作品がどのように生まれたか、コンテスト入賞者の方の作品がどのように優れているのかなどの解説も盛り込んでいます。
どのようにすればより魅力的なおはなしが書けるようになるのか。たくさんのおはなしを紡ぎ、そしてその書き方を教えてきたほしおさんだからこそ伝えられる創作のヒントがたくさん。
【著者】
ほしおさなえ
作家。1964年東京都生まれ。1995年「影をめくるとき」が群像新人文学賞小説部門優秀作に。おもな著作に「活版印刷三日月堂」「菓子屋横丁月光荘」「紙屋ふじさき記念館」「言葉の園のお菓子番」などの文庫シリーズ、『金継ぎの家』『東京のぼる坂くだる坂』『まぼろしを織る』、児童書『お父さんのバイオリン』、「ものだま探偵団」シリーズなど。
恥ずかしながら、ほしおさんのことも、140字小説のことも存じ上げておらずでした。
今回本屋さんで出逢って、初めて知りました。
140字という短く、以前のTwitter仕様でちょうどよかった字数なのですよね。
字数制限がありながらも、世界観や風景、思い(想い)がしっかりと伝わり、心に響いてくる作品が多くて、大変魅力を感じました。
言葉の舟というタイトルについて、思うこと
奇遇にも、先日このような記事を投稿しました。
わたしにとっての、言葉、文章とは?という、書く部のお題をいただいての投稿したものです。
実を言うと、この本を読み始める、まさに直前に書き終えた記事でした。
記事内でも触れておりましたが、投稿時点で、満足がいっていなかったもの。
なぜ、満足いかなかったのか?
投稿前に読み直したとき、表現に深みが足りないように感じたからです。
今思うと、タイトルも問題では?と感じていたりするのですが、その時はお手上げになり、投稿したのでした。
だからといってはなんですが、そういうこともあって、よりこの本へ引き寄せられたのかもしれませんね。
乗り物とか、発着場とか、ちょっとこの本と重なる単語があったりして、カンニングを疑われかねないですけれども、その判断はみなさんにお任せするとしまして。
この本のタイトルになっている、『言葉の舟』という表現は、純粋に惹かれました。
この本に関する作品も読ませていただく中で、
いかに、
・物語に魅力を感じてもらうか。
・情景を思い浮かべるような言葉選びをするか。
ということが大切なポイントであるように感じました。
『言葉の舟』と聞くと、
ポツポツと生まれた言葉が、それぞれの形の船に乗った状態で、広い海原に放たれて、旅をしているのかな。
ステキな世界を旅して、戻ってきて、新しい世界観をみせてくれるのかな。
なんて、タイトルだけでも、想像して、楽しませていただいたのでした。
『書く』ことに対する意識の変化
先に投稿した記事のように、わたしは、言葉を大切にしたいと思っている人です。
もちろん、そんなことは、noteの街にいらっしゃるみなさんは、もう当たり前のように思われていることと思うのですが、最近のわたしは、そのことをより強く感じています。
時に、『書く』ことに対して、怖くなることもありますが、それでも書き続けることができるのは、noteだからです。
【おはなしのなかなら好きなことができます。自由に楽しんで大丈夫。】
という、ほしおさんのお言葉を見て、
恐れすぎずに、自分の世界を見てみたい。
そのように思いました。
自分の世界観を見るために、わたしが選ぶ場所が、このnoteであって、『書く』ということにつながっていたことを自覚しました。
書き手であり続けるために大切なポイント3選
ここからは、わたし独自の視点で、この本から感じたこと・得たものとして、書き手であるために大切だと思うポイントを3点お伝えします。
①ありきたりな日常こそ、大切に。
本の中に、書いてみよう(基礎編・実践編)という章があり、実際に140字小説を推敲していく流れや、これまでに受賞経験のある作家さんとの対談を読ませていただけたのですが、
日常こそ、ネタの宝庫なんだな〜、と思いました。
普段何気なくスルーしてることも多いと思うので、宝探し感覚。
けど、これこそいろいろな視点を持っていないと、気付けないことがたくさんありそうです。
②不要なものは削って、的確な表現を探し続ける。
早速出ました、わたしの苦手分野です。
140字でも、工夫次第でこんなに伝わるものなのかと知ってから、わたしは書きすぎである現実を再度つきつけられました。笑
何でもかんでも説明入れればいいものではないということは、わかっているつもりなのですが、どうしても書いてしまうクセをなんとかしたいものです。
本を読ませていただいて、推敲作業を丁寧に行うことに大切さを知りました。
毎日note投稿して、そんな時間は取れなさそうですが、せめて、たま〜に書く短編小説だけでも、丁寧に添削したいです。
③続けることで、目を養う。
すぐに書けるようにはならないのて、結局は、継続していくことが、成長のコツなのかな、と思うのです。
書くだけではなくて、読むも含めて、言葉や文章、物語に触れ続けること。
どんな想いで書いて、どういうことを伝えたいのかを想像しながら、読んでいくと、より楽しめそうじゃないですか?
言葉に寄り添って行くと、
なんだか旅に出られるような。
自分だけでは知り得なかったところへ
連れて行ってもらえる感じがします。
いつの間にか、
こんなことにも気づくようになった!
って、思えるようになりたい。
ただの願望になってしまいました。
おわりに
久しぶりに、本屋さんにゆっくり立ち寄ったら、ステキな出逢いをしました。
ここまで書いて、気づきました。
わたしは、書くこと・読むことを通して、言葉に寄り添って、伴走して、自分を育てる旅に出ているんだ。
旅から帰ってきて、日常に戻った時に、自分が少しでも成長していたら、なおうれしい。
未来の自分に、期待を持ちたいと思っていることに。
20字小説は、言葉遊び感覚で投稿したことはあったのですが、140字はまだないので、いつか挑戦してみたいなぁ。
140字にしたからといって、Xに投稿することはないですが。
(今となっては、Twitterではなく、Xになり、長い文章でも投稿することができるようになっていますね。)
短くても、伝えたいことが伝えられるような物語を書こうと意識するだけでも、物事を端的に伝えられるようになる練習ができるのではないか、と期待したいです。
短く…って言って、いつもよりもだいぶボリュームある記事になってしまいましたね。
ここまでついてきてくださった方、
貴重なお時間をたくさん頂戴しました。
心から感謝いたします。
◎
最後までお読みいただき、
ありがとうございました!
スキ・コメント・フォローなどいただけると、
大変励みになります。
ここまでお読みいただいたあなたに、
幸せが訪れますように🍀
また次の投稿で、お会いいたしましょう。
*--*--*--*--*--*--*--*--*
これまでの記事は、
すべてマガジンにまとめています!
他の記事も気になる・・・
という方がいらっしゃいましたら、
サイトマップから、お好きなマガジンへ
どうぞお越しくださいませ☆
▼サイトマップは、こちらから▼
▼本日の記事が入っているマガジンは、こちら▼
▼有料マガジン、はじめました▼
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます(^^)!もしよろしければ、サポートいただけると大変嬉しいです✨いただいたサポートは、今後のnote活動をもって、還元していくことができるように使わせていただきます。
