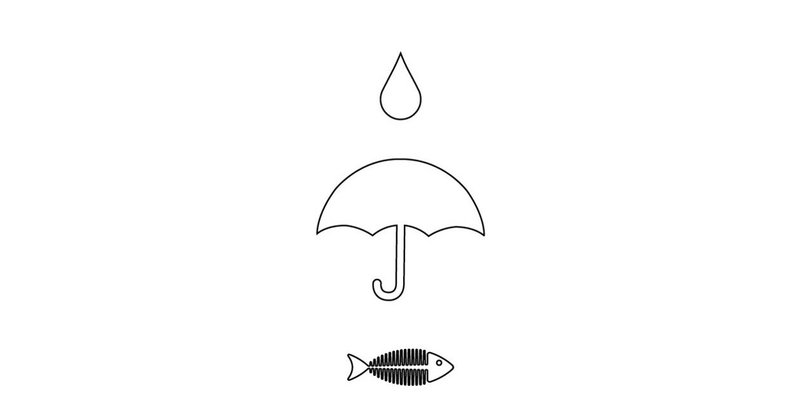
詩集『最後の数滴』
傘の外で
三日かけて書いた手紙は橋の上から川に放り投げられました。頬を伝うことなく涙が直接水溜まりに落ちました。毒薬を垂らされたオアシスに二羽の白鳥がやってきて、片方の体内にわたしの言葉が収められています。
挨拶も断りの言葉もなく自転車が去っていく音だけが頭に残っています。今日は土曜で学校は休みで雨が降っていて土の香りが久々に部屋の窓を開けた瞬間を思い出させて。雫の冷たさがいつも眠っているような感覚だった十四歳を抜け出した瞬間を思い出させて。
現在の自分が遠くなったり近くなったりしながら時間をかけて形成されてきた思想の周りを浮遊しています。傘をささない手に誰か、わずかでも優しい言葉を。
交差
祖母の部屋を訪ねると洗濯ものが揺れている。それは売れ残った饅頭によって補われる暮らしのうちのひと場面。手を振ると笑顔が返り、とても軽い糸によってわたしたちは繋がる。
わたしの部屋はアパートの細胞内に埋め込まれた四角。生活の中央に寝転ぶ出不精な大学生を跨いで麦茶の氷が音を鳴らす。指を下ろすと反応があり、とても速い回路によってわたしたちは繋がる。
猫の神様
ここにいれば何者にも襲われない。我々は波から島を守り、島民の安全を確保する。ここにいれば自由に創作活動ができる。利益も、意味も、視線も倫理も気にせずなんでも作ることができる。これらはすべて、人間が想像力によって作り出した本質的ではないもので、我々には通用しない。我々が必要とするのは我々に対する献身的な気配りだけ。なんでも作ったらいい、木製の巨大なスプーンでも、毒キノコの傘でも、ふたりが混ざり合う砂の城でも、誰も咎めることはない。宇宙はここから始まり、ここに終わる。夜空に小天体が光り、我々の姿が環境から明瞭に浮き出てくる頃、自分のために泣く子らの涙を堰き止め、我々が飲み干す。涙はガラスとなり人々の食器として毎日使われているが、それをみな知らない。島民が知らないことが多ければ多いほど我々の力は強くなり、彼らの気配りもまた手厚くなる。恐怖でも畏怖でも観測できるのは行動のみ。どれほど黒い腹心を持っていようが、ここに住んでいる以上その黒は表に出てこない。一方、我々はここでしか通用しない。我々はこの島およびその周囲の海を統べているが、その他は知らない。みなこの事実を知らないが、知らないからこそ、我々は存在できるのだ。
カイソウ
現象のように生きたいわたし、カメラにおさめた背景の光、海藻のようにくねる髪は、プールの波と同化する。モザイク模様の雲の間に、あいた孔から線が伸び、水面に雨が降り注ぐ。雨粒の衝撃に耐える虫、回想に浸るその眼瞼に、空から光が零れ落ちる。
毎日眺めていた、通学路のラジオ局は改装された、ぼろぼろだが個性的な建物から、どこにでもありそうなオフィスビルへ。ガラス窓を透過して、将来が想像できなくなった苦しみにより、屋上から予定調和が飛び降りる。わたしは一定の速度で歩き続け、その表情は怒っているとよく言われるが、本当は悲しんでいて、変わってしまった道筋を雲の中に探していた。
無人駅
無人駅に吹く風が特別なのは、誰の溜息も運んでいないからだ。この場所で聞こえるのは波の音と鳥の鳴き声くらい。雨の日はざくざくした背景が加わる。ときどき汽車が通っていく。ここに何時間もいればすべてを許せるようになるかもしれないから、いつも数十分で立ち去ることにしている。世界をすべて許してしまったら、思考する時間はもういらないと神様に言っているみたいだから。置いてけぼりにされたジュースや傘、誰かが恋する相手に宛てたラブレター(今回はケンくん宛だった)は、駅員さんか地域の人か、本人ではない誰かが処理してしまった。誰もいない場所で考えるのが誰かのことだなんて不思議だ。誰かと一緒にいるときには、無人駅へ心が飛んでいるというのに。気持ちを遠くへやるのが癖になっている、夏の夕日へ向かう道中、目の前の電柱にぶつかっても誰のせいにもできない、想像するだけで自分が嫌になる。ぼくの溜息で無人の清潔さを打ち消すわけにはいかないので、代わりに、なんとなく頭に思い浮かんだメロディを口ずさんだ。
悪夢
風船が降ってきて爆発した、みんな慌てている、炎に包まれている、友達を助けようとしたら、知らない人に抱き締められたので、引っ越しを決意した。
*
場所は河川敷へ移り、動画撮影をしているみんなを橋から見下ろしている、南の方から炎が迫り、水面は膝まで上がってきているのに、みんな撮影を続けている。
*
家に帰った、余り物のチョコレートの香りで鼻づまりが抜け、眠りにつき、目が覚めてから無駄にトイレの電気を確認している、怖い、誰かいる、一人で暮らしているのに、鏡に映る顔は自分のものではなくて、ここで初めて、横で眠る人の夢を見ているのだと知る
*
無呼吸を気にしながら、まだ夢を見ている、普段はネックレスをしないのに、今日だけはしていて、体温と同じくらいに温まっている、鎖が重くのしかかり、人に会いたくなった、つまりわたしのことだった、ぼんやり見える、写真が何枚も排水として流れ、まだ夢を見ている
リンク
雨の日と煙草の相性はいい、入れ込みすぎた小説の冒頭部分、探偵が優雅に煙草を吸う姿に魅せられて、自分も始めたこの公園。小雨に降られ、東屋に逃げ込んだ、東屋に住んでいるという噂の少女は、傘を閉じては広げ、広げては閉じ、を反復して時間を過ごしている、何かを待っているようにも見えた。
東屋は少女に譲り、小雨の中を移動して、公園の隅に居住する心許ない木の陰で煙草に火をつけた。昨日見たドラマの俳優が吸っていた銘柄と同じだ。特有の甘味と苦味と湿気が混ざって、少年の頃の梅雨の日、友達と一緒に雨の中、畦道を走って帰ったことを思い出した、その子の父がヘビィスモーカーで、服から煙草の香りがしていたから。
一秒一秒が過去とリンクしている、二十四歳、何をするにも昔のことを思い出してしまう病気にかかっている、傘で遊んでいる少女を見たときも同様に。
東屋の少女が傘をテーブルの上に置き、道路にいる猫を見つめているとき、ほとんど減っていない煙草の火を雨で消し、次の十秒間で、道路へ飛び出そうとする少女を、少年の頃の友達を、とても長い時間を経て、間接的に守った。
救われた少女と救われなかった友達が重なり、あの日のぼくも動き出した、その途端、十二年の月日が一瞬で流れ、いま、傘と煙草の吸い殻と土の香りと共に立ち尽くしている。
長靴アパート
『長靴と生きていた猫』
片方の赤い長靴を拠り所に生きていた子猫がいました。子猫は決して長靴から離れようとしなかったので、長靴は子猫の世話をしました。ある日、子猫は急激な腹痛に襲われて死にました。信じていた長靴は、危険な細菌やウイルスの巣窟でした。長靴は死んだ子猫を雨から守り続けましたが、やがて子猫ごと焼却され、街の人々の記憶から消滅しました。
海に落ちたとき、海底に置いてきた長靴が生き物の住処になった。海の淵で聞き続けた波の音はもう聞こえないほど遠くにいる。一人で生きていたあの島に、沢山の文字を残した。例えば詩。
『無人島で』
言葉でできた無人島にひとり住んでいる、海の中にあるものを知らない、船を待つ、正確には船を漕ぐ人との遭遇を待つ、海について詳しく教えてほしいから
数日間、粗大ごみの筏に乗っていよう、誰かが文字を見て助けてくれるかもしれない、あるいは物語に読みふけり、メッセージに気付いた頃にはぼくはもう死んでいるかもしれない。それでもいい、思い残すことがないような毎日を送っていたから。
(罪と海の話)
木彫りのスプーンでいろんなものを掬ったし、陸に打ち上げられたウミガメの口の中につかえていた網の塊を取り出して彼の命を救った。いろんなものを助けたスプーンはひとりで海を渡り、アジアの島の砂丘の淵にたどり着いた。スプーンを拾ったのは小説家を夢見る地元の大学生で、彼女はスプーンを題材に小説を書いた、それは彼女自身や読者をすくった。ぼくは生きてただ死ぬだけでなく、他者の命にもポジティブに関与したので、罪悪感を抱かなくてもいいはず、それなのに、救えば救うほど深まっていくこの孤独と言えそうな罪悪感、暗い海底のような、じめりとした気持ちはなんなのか。
週末アーティスト
切り取られた青葉を拾い集め、大事にノートに書き記し、最後の一枚だけ大勢に受け入れられたが、残りはどこへ埋めようか。生み出してしまったものをどう殺そうか。
最後まできちんと面倒を見ましょう。
ポスターの子犬は片目を閉じ、イルミネイションで点滅する。鍵盤の数だけ指をかき集め、ひとつだけ選び取られたが、残りはどこへ埋めようか。集めてしまったものをどう殺そうか。
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
