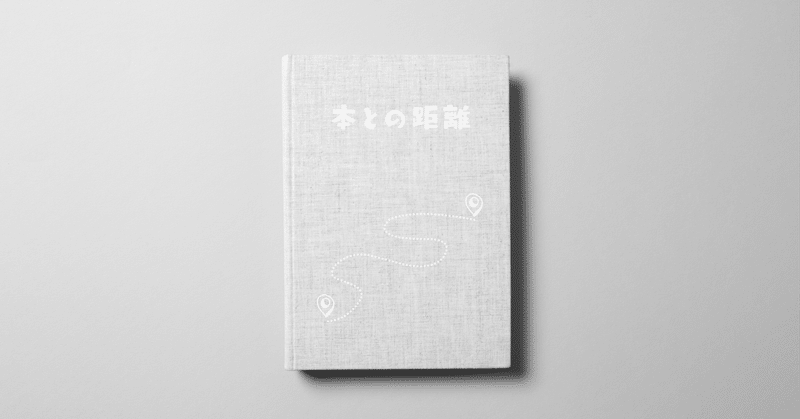
本との距離⑦(1226字)
「給食早食いできるとすごい!」みたいな、低学年特有のなんでも競争としてはしゃいでしまう性質のせいで、小学校の図書室でちょっとしたバトルが勃発していた。
貸出カードをめぐる争いだ。
図書室の本の最後のページには、必ず小さな封筒が付いてて、カードが挟み込まれている。そこに過去に借りた人の名前がずらりと記されていた。知ってる名前もあれば、全く知らない名前もあったが、今思い出すと、facebookのように校内の人の情報をかじる媒体としてカードは存在していたんだなあ。
まずは、本についているカードに鉛筆で学年と組と名前を書く。その次に、図書室の入り口あたりにクラスごとに保管されてた、もう一枚の貸出カードにも記録をつける。このカードは自分のものなので、どんな本を、どれだけ読んでいたか、が一目瞭然となっている。
(ちなみに、今の学校では、この貸出カードはどうなっているのだろうか。「貸出日」「返却日」そして「書籍名」を書くだけの、ごくごくシンプルなデザイン。クリーム色のちょっと厚手の紙が、茶色の線で区切られている。
学生になって、初めてコンビニバイトをしたときに、タイムカードを見て、なんか似てるなぁと思って、記憶の底から引き摺り出せたのが図書室の貸出カードであった。ついでに、「バーコードを読み込む」という所作も図書室が最初だったんじゃないか)。
そう、この個人の貸出カードに記された本の数が争いの種火だったのだ。(たしか)学期ごとに借りた本の数が多かった人に図書カードが贈呈されるようなシステムがあった。
が、単純にクラスメイトの「あいつには負けたくない!」の一心から、足繁く図書室に通っていた。公文のおかげもあってか、テストでは負けてないのに、読書においては敵わない子があまりにも多かった。過度の負けず嫌いだったぼくは、そこに熱を注いでしまった。
シリーズものが読みやすく、数も稼ぎやすく、そして借りやすいことに気づいたので、王道の『かいけつゾロリ』を始め、『めいたんていカメラちゃん』シリーズに手を出した。謎を解く「推理もの」との出会いはここだった。
カメラちゃんシリーズについては『あやしいUFOのなぞ』を借りた記憶は強く、水木しげるが扱う「怪しいもの」に近しいものを感じてたんだろうし、たしかちょうどその頃、世の中的にもUFOブームでもあったんじゃないだろうか。テレビで宇宙人を解剖する映像が流れていて、衝撃を受けたのもよく覚えている。
ゾロリからカメラちゃんへ、少しずつ、文章比率が多くなり、文字ばかりの本への耐性がついてきたのもこの頃(2年生)だったっけな。
そんなこんなで読書数を伸ばし、どうにかクラスの上位争いに食い込もうとしていた時期だった(記憶があやふやだが、1位にはなれずとも入賞はしていたんじゃなかっただろうか)。少なくとも月に10~20冊は読めていた頃だ。
そこから、転校を経て、本を読まなくなる(本を読んだ記憶のない)暗黒時代が2年ほど続く。
もしも投げ銭もらったら、もっとnoteをつくったり、他の人のnoteを購入するために使わせてもらいます。
