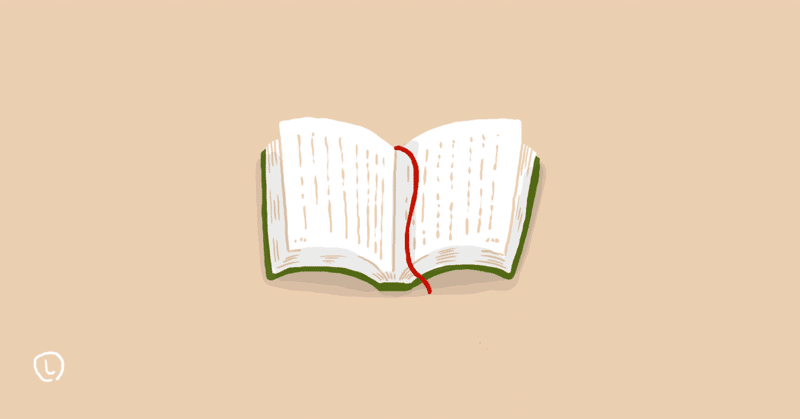
【NOVEL】復体 第9話(最終話)
「そういえば、おばぁちゃん」
「ん」
「私、今日、お邪魔すると言いましたっけ」
祖母は皮を剥きながら答えます。
「言ったよ」
「…四時に来ると」
「んだよ」
「…」
剥いたみかんの白い筋を取りながら、祖母は言った。祖母は眼鏡を掛けていますが、難しい顔をしています。目の調節が出来ていないようでした。私は深刻なトーンで話すことは避けることにして、自分のみかんに向かって続けて尋ねました。
「すみません、私、自分で約束しておきながら忘れてしまったようで…いつ、おばぁちゃんに電話しましたっけ」
私は頭をかきながら、間抜けなふりをしてみせました。
「電話でねくて葉書よ」
「葉書ですか」
「んだぁ」
「私がですか」
「んだっちゃ」
「…」
祖母は口をもぐもぐさせながら徐に膝立ちになると、茶棚の引き出しに手を伸ばしました。何やら、がさごそと探しています。
祖母が、見せる誠実さというのは、と言うより、孫に見せる外形的な善さは、孫である私が成熟していないと理解出来ません。そりゃ学生の時分であれば、晩飯が終われば祖母に背を向け、頬杖をついてテレビを眺めることになるでしょう。私は首を伸ばして、引き出しの中身を覗いて見るのですが、光熱費の伝票や古い型の電池など一体何の用途で取っておくのか不明なものばかりでした。
その中から、たくさんの葉書を取り出すのです。それを卓の上に広げて私に見せるのです。計二十二枚あります。いずれも官製葉書でした。差出人は私であり、私の住所が記載されています。一瞬、弟のいたずらと思いましたが、だとしたらあまりにも悪趣味ですし、そもそも彼が祖母にいたずらするのも合点が行きません。
先の会話を振り返っても、祖母は私を憲二郎だと勘違いしていませんし、現況からすれば、むしろ私自身の記銘能力に疑念が生じてきます。
私は背筋が寒くなってきました。隙間風でしょうか、天井から伸びる円錐形の蛍光灯が僅かに揺れています。
筆跡が非常に良く似ており、というか、もはや私の字です。歳に割に枯れた字を書くので、周囲に驚かれることがありますが、母からは、自流にしか基づいていない自分勝手な字と酷評でした。私の字は、当時の感情に左右され易く、心持、乱雑な気がします。文面には気負った節は無く、頭語と結語がありますが、改まった様子ではありません。祖母への安否の気遣いと、自身の近況報告、訪問する日時など、いずれも簡潔に判読出来るように書いています。葉書を郵送した覚えはありませんが、もし、祖母に何か書くのであれば、同じような形式を取るに違いありません。くだくだしくない、要領を得た文章が好きなので、これらを読んで、納得せずにはいられませんでした。
私は、指で無精髭をざらざらさせ、あれこれ推量していると、祖母は一枚一枚を振り返り「あんがとうねぇ…」と呟きました。
「これを送っているのは私ではありません!」と言えればどんなに楽だろうと思ったのですが、過去に私らしき差出人(?)が来ている様なので、事実を否定することになってしまいます。
「憲二郎は最近来ていませんよね」私は祖母の顔を見て訊ねた。
「葬式以来、見でねぇな」と祖母。
「…以前、私、何泊しましたっけ」
「一週間ぐらい、いだんでねがったが」
「一週間ですか」私は驚いた。
「もっどいだがもな。あんだ覚えでねぇの」
「…」
私は、はいともいいえとも答えることが出来ませんでした。この家に一週間も滞在しているのであれば、覚えていないで済む話ではありません。
閉口する私を見て、不思議がる祖母でしたが、すぐににんまりとするのです。
どうして戸に南京錠があったのか、漸く納得しました。私が、訪ねる予定だった時間に、祖母は留守になるので、あえて戸にぶら下げていたのでしょう。
葉書で記された日時に、たまたま私が訪問しているとなると、丁度良い偶然だったかもしれません。何せ、祖母は不思議がることなく私と接してくれるのですから。しかし、その時宜がずれていないことが、真実を明かす鍵となっていることに漸く気付いてしまうのです。
つまり、この家のどこかに、私と祖母以外の誰かがいるとなれば、一応辻褄が合います。
しばらくして、私はこう言った。
「いやぁ、そんなはずはないと思います。何せ、私、お母さんの葬式以来会っていないはずですよ、おばぁちゃん。それにこの葉書だって見覚えありませんし…おばぁちゃん、何か勘違いしていませんか」
祖母は「まぁ、不思議なごともあるもんだねぇ」と言い、困惑しているようにも見えますが、やはりどこかとぼけている様にも見えて、まるで分らなくなった。ただ、祖母の発した言葉は本意ではない気がするのです。
「おばぁちゃん、その時私とどんな話しましたか」
「覚えてねぇな」
「何にもですか」
「んだ」
「…」
祖母はミカンの皮をくず籠へ捨てると、テレビを見てこう言った。
「今年も終わるねぇ…」
年末恒例の歌謡特集には、母が幼い頃に流行ったアイドルであろうか、スタジオで大いに張り切っている。
「早いねぇ…」
祖母の口角は上がっているが、哀しい眼をしていた。私は「そうですね」とも言わず、テレビを見ている祖母の横顔をじっと見ていた。そうしている中に私は、祖母の気持ちを汲むことにしたのです。
この手記の内容と表題を合わせると、私が恰も情熱を失い、分別を振り回していただけの人間に思えるかもしれません。しかしこれは、真理を追究せず、物事の勝敗や結果に拘泥しない私の性格上、差出人の正体が何となく分かった今、これ以上詮索するのは野暮な気がしてくるのです。もしこれが、絶妙な均衡で保っていたとすれば、私が介入することにより、つり合いが破れてしまう心配がありました。祖母だって望んでいませんでしょうし、いくら本当の孫であっても、さんざ顔を出していなかった私に、その権限は無いはずです。度々やって来ては、祖母の身の回りの手伝いをやっていたことで、祖母を孤独にさせないパートナーだったことに違いはありません。
もしかすると、祖母は、葉書の差出人が、私では無いことに気付いているのかもしれません。生活にもとい、何事にも動じない心境に至る彼女は、出入りする人間が孫であろうが、孫に似た人間であろうが、正直どうでも良かったのでしょう。
ただ、体験したことに基づいて書き綴ってみたところ、私は自分の反省に欺かれていた気になって来るのです。この好い加減な結末が、人に知れることは決してないけれども、今現在、胸中穏やかで無い私に対しても、祖母はむにゃむにゃし出すので、ここで私があわあわとなっても、祖母を困らせてしまうだけなのでしょう。
心霊ですか。怪奇ですか。いずれにしても、共存出来そうです。私は、膝に手を付いて、すっと立ち上がると祖母を見下ろしてこう言った。
「おばぁちゃん、そろそろ眠いでしょう。私、お風呂沸かしてきます」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

