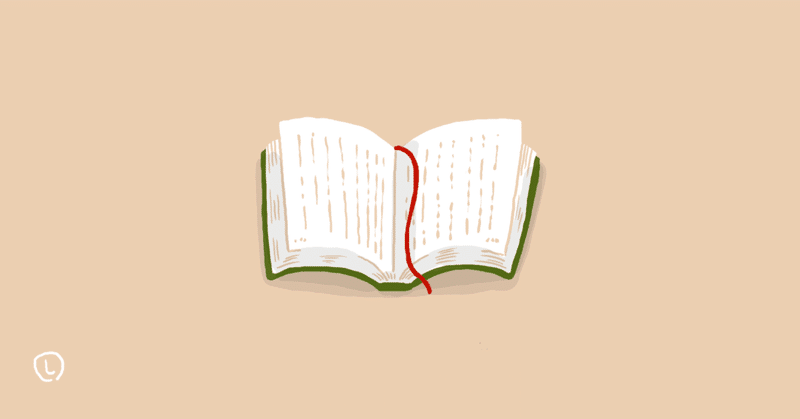
【NOVEL】復体 第6話
祖母が帰って来たのは、五時を回っていました。雪国の寒空は、陽が出ることなく薄暗くなっていくので、余計に日が短く感じます。家の前の砂利を踏む音が聞こえたので、私はすぐ気付きました。ハザードランプの橙色が、カーテンの隙間から漏れてきます。
私は、踵が足りないサンダルを履き、玄関を開けてみると、外は大きな雪片が降っていました。車の後部座席から、のそのそと出ようとしている祖母。その横で運転手が手を差し伸べています。私は「あ、どうもすみません」と言うと、運転手の男は、くるりとこっちを振り返り「これはこれは」と会釈してくれました。「トランクの奴、出しでけね」と運転手の男が言ったので、私は急いで半開きになっているトランクから買い物袋二つと米袋を玄関脇に置きました。
祖母の腰は、矩尺でも入っているかのように曲がっていました。左足が言う事を聞かないのか、跛を引いています。私は、祖母の手を取って、玄関まで先導すると、再び表へ出て、庇の下で一服していた運転手に向かってお辞儀をしました。「お孫さん」と運転手に聞かれたので、私は「そうです」と答えると、彼はちょいちょいと手招きをしました。私は頭の上に疑問符を立てて、彼の元へ向かうのです。
「知子さんて、何歳なんの」
「もう九十になりますが…」
祖母の年齢を聞かれて、何時だったか、私は祖母の米寿を祝ったことを思い出しました。
「身寄りねぇの」
「まぁ…え、どうしてですか」
胡麻塩頭のその男は、煙草をふうと吹かして一息入れたかと思うと、先程より少し低い声で話し出すのです。
「今日戻っで来る時、駐車場で迷子になっでね」
「え…」
「まぁ要するに、おらいのタクシーが分がんなぐなってしまっだのよ」
「…」
私は薄々心配していたのですが、このことを他人に指摘されたのは初めてでした。祖母の意識ははっきりしているし、生前の母も祖母の物忘れは年相応だと言っていたからです。
「それも一回や二回でねぇよ」
男は祖母の身の上を案じたようでしたが、それは私にとって耳が痛いものでした。私は思わず「すみません」と謝ってしまいましたが、彼は首を振って、咄嗟に言いました。
「いやいや、別に謝っでくれとは言っでねぇけんともさ、やっぱ心配だね」
「…」
私はすみませんと再び言ってしまいそうでした。3を描く煙草の煙は、白い背景と同化していくのです。
「今晩、話してみます」と私が答えると、男は苦り切った表情を少し緩ませて「…の方が良いがもね」と言ってくれたのです。すると、思い出したかのように男は続けました。
「ほいでも、あんだ偉いよね」と言って、煙草の先端を私に向けてみせるのです。
「まぁ、たまには顔出さないと」
「いやいや、よぐ来てんでねぇの。知子さん言っでだよ、自慢の孫だって」
「祖母が」
「うん、あんだ来年がら学校の先生になんだべ」
「まぁ…」
祖母が、私のことを話題に出していたので驚きましたが、その一方で、この男は、何を持って私が祖母の家をよく訪ねていると言ったのかが、不思議でなりません。しかし、詳しく聞いてみると、どうやら祖母は、この運転手に、根も葉もない私の孝行振りを自慢げに話している様だったのです。先日、河川敷を一緒に散歩したり、時折、電話を掛けてきては話し相手になったりと、もっともらしい孝行息子でした。
私は、背筋が寒くなるのを感じ、くしゃみをする。男は幾分、巻紙を残して、吸殻を携帯灰皿に詰め「ほいでな」と言って、車に乗り込もうとする。私は「ありがとうございました」と発したのですが、ドアを閉める音にかき消されてしまいました。
思えば、余計なこと聞いてしまったのかもしれません。主観的な要素に、私は振り回されてばかりですし、あの男だって正しい情報をくれたとは限りません。彼らだって仕事柄、交際範囲は広いわけですから、勘違いってこともあり得る。田舎の対人関係がいくら密接し易いとはいえ、それが錯綜しない根拠にはなりませんし、人伝の噂話の方が、却ってひどい方向に向かうこともあるでしょう。ですが、分析癖は良くありません。
薄く積もり出した雪道をタイヤチェーンは蹴り出す。離れていないが、それでも遠くで聞こえるようで、先程まで会話をしていたのも拘わらず、雪国の特殊な沈黙が、まるで耳の役割を忘れさせている気にもなった。
【NOVEL】復体 第7話|Naohiko (note.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

