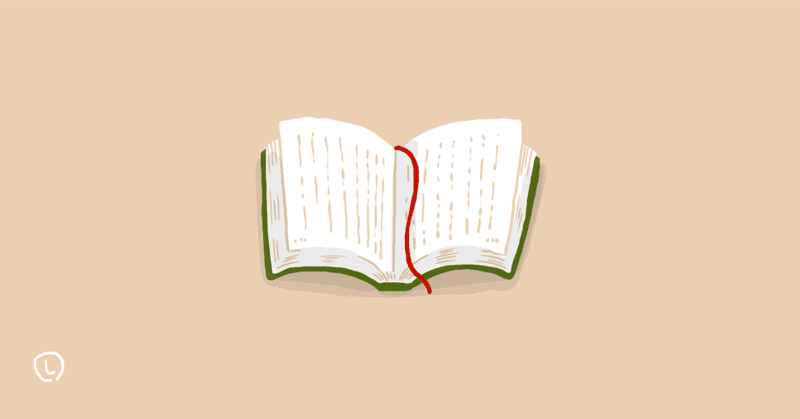
【NOVEL】復体 第7話
私は家の中に戻ると、すぐさま台所へ向かいました。硝子戸を開けると、祖母は既に夕飯の支度をしており、米を研ぎながら「テレビでも見でらい」と言ってくれました。私は、そうはいきませんと、口の開いた米袋を持ち上げ米櫃の中でひっくり返してやるのです。私は、何を作るのかと尋ねると、祖母はカレーと答えましたので、俎板担当の祖母と、火元担当の私で上手い具合に分業することにしました。
出窓の結露がひどいです。曇り硝子の先で、勢いが増す降雪の陰影を見て、私は言いました。
「おばぁちゃん」
「なんだい」
「今日、泊まっても良いですか」
祖母は、にこにこして良いよと言ってくれました。元々そのつもりだったようですし、不思議と楽しそうです。
料理をしている間、祖母と私は大した話をしませんでした。近頃の天候だったり、ここへ来る際、道は混んでいなかったかとか、自炊はしているのかなどと聞いてくれるのでしたが、私が二言三言で返します。
「近頃、家で何作ってんだい」と祖母。
「まぁカレーであれば…」と私。
「んだが、なら安心したよ」
「…」
私は、祖母に聞きたいことがありますが、その核心が思いもよらぬ方向ですと、台所の雰囲気が悪くなりそうだったので止めておきました。勿論、その気遣いは無用です。ただ、この後、居間で談話する時間があるとなれば、腰を据えて話した方が良い話題は、そっちに取っておくべきと思ったからです。
祖母は俎板を洗い始めました。たわしで擦る祖母の手筋は、日頃庭で土いじりをしているからか、皺が寄っており、女とは思えぬほどごついです。まるで草食動物の足のようで、何だか年季が入っています。鷲鼻で色白、顔も体も卵型という東北地方には特に多い体格です。
田舎臭くて、不格好な容姿だと思っていた時期もありましたが、一社会人となった今、熟練した風体に憧れるときがあります。
そう言えば、私が同窓会へ行ったときのことです。友人は皆、各々の定職へ就いていました。逞しくなった者もいれば、職場での苦労がにじみ出ている者もいましたが、集えば当時の口調に戻ります。そんな彼らが、髪の色を変えたいとか、新しい服が欲しいとか言っていると、私は「そんなこと、未だに気にしているのか」と、ついつい返してしまいます。対して、横に座っていた友人は「そりゃそうさ、アラサーとか何とか言われたって、俺たちはまだまだ元気あふれる年頃だ」と言ってきました。私の場合、気持ちと身体の年齢に齟齬が生じてきているので、そしてこの間隙が開いていく一方なので、それならば、いっそのこと落ち着いた印象が欲しいのです。同時に、もう少し男性的でありたいと思っているのかもしれません。青年期を経て、本当の意味で成人として扱われるためには、染髪などの同一性の混乱を捨てきらないと、世間から受け入れてもらえないのではないか……容姿と人格が、一貫する日を漸く迎えたのだ。そう考えていると、取り繕うことが馬鹿馬鹿しく思えてくるのです。
私は、フライパンで具材を炒めていると、菜箸で野菜を転がす自分の手を見てがっかりしました。若々しく、ひょろひょろとして傷跡一つ無い、肩から伸びでた肢を見ていると、もっと頑張らなくてはと思ってしまうのです。
思えば、祖母と料理をしたことは一度もありません。学生だった時分、実家では自室にこもり、食卓に飯が並ぶのを待っているだけの人間でした。両親とは特に会話もせず、唯々飯を食っていました。食べ終わると、自分の食器だけ台所へ持って行き、再び自室に戻るという、今思えば息子でも何でも無い、行儀の良い家畜のような人間でした。
人間というのは、どうしてこうも長きにわたって、家族と身を寄せ合うのか疑問でした。所詮、若気でしたし、月並みですが、大切なものは失ってから気付くとは、まさにこのことです。大人になってからの孤独が、いかに辛く、寂しいものなのかやがて知ることになる。生活にめりはり出たのは、ある種改心をしたのです。ここ最近ですよ。今現在、肥えた私を飼育してくれた彼らは、もういません。
思うに、この国の一般家庭で育つ学生は、本当に得手勝手な生き物です。やがては成熟していかなくてはいけません。おそらく、血のつながりを大切にすれば、こうした沈黙にも違和感無く、祖母の隣で料理が出来るのでしょう。
底の厚い鍋の中で、沸騰する音が聞こえて来ます。私は、炒めた具材を中に入れ、鍋蓋をすると、先程起こった疑問を少しずつ話題に出してみることにしたのです。
「そう言えば、おばぁちゃん、携帯電話買ったんですか」
「いんや、どうしてだい」
「どうやってタクシーから電話を掛けたんですか」
「あぁ、丸山さんの借りたのよ」
「あの運転手さんの」
「んだんだ」
「…」
私は心の中で「なぁんだ」と言ってしまいました。正直、そんな手軽な方法があったとは思い付きませんでした。「あ、段ボールにあったみかん、勝手に食べましたよ」と、私は思い出したかのように言うと、祖母は「あぁ良いの良いの、良がった良がった、見つけでくれで」と喜んでくれました。祖母は、買って来た福神漬けをタッパーに開けたり、サラダを小皿に盛りつけたりと、手を動かしながら続けて私に言いました。
「底にあった奴、腐ってなかったべが」
沸騰する水面から、灰汁が出るのを待っている私はすぐに「いいえ」と答えましたが、続けてこうも言いました。
「でも、かなり、しわしわな奴もありましたよ」
祖母は、あらやっぱりと、にこにこしていました。「ごめんね、食べたりしなかった」と、言ってくれます。受け答えを察するに、祖母は身の回りのことをきちんと分かっていますし、感知している。手先だって良く利きますし、小皿に盛り付けられた野菜の配色も均一で鮮やかです。台所にいる分には、何も不審な点はありませんでした。むしろ、孫である私を思いやって気を付けている風でしたから、それには感心しました。
それならば、私は幾分、遠回しに他の事も聞いてみることにしたのです。
「おばぁちゃん、最近どこか旅行にでも行きましたか」
「いんや、どうしてだい」
「…いえ、何となく、家が片付いているなぁって…」お玉で灰汁を掬い上げると、私は強火にしていた火力を抑えました。
「んだいが、いづも通りだっけよ」
「…」
いつも通りと言ったので、これにも安心しました。定年まで仕事と家事労働を両立させていた祖母からしてみれば、日常生活で起こる雑事は大したものではありませんでしょうが、世の中には、それすら面倒がる高齢者だっていますから。丸山という運転手の杞憂に終わるのかもしれません。
それとも、私もあの男も、祖母を想う根本が間違っていたのかもしれない。痴呆の進行により、介護が必要となる人生を迎えたとき、人は、自身が介護されている心境を、まざまざと受け入れているのでしょうか。痴呆が進んだ患者の意識や意志は、従来の自己と呼べるのかが甚だ疑問だと言っているのです。そういった人間は、もはや我々とは異なる方向へ向かっている様な気がしてなりません。己を忘れても差し支えない境地、そうありたいと念じていた人もいるのではないのでしょうか。
取留めのないことを思ってしまったのには、祖母がこう続けたからです。
「それに……」
「それに、何ですか」
「あんだも、良ぐ来てくれるがらね」
「?」
「この間だって、寒いのに床拭きしてくれで助かっだわぁ」
「??」
私は、敢えて肯定も否定もしませんでした。一件、言外に意味があるように思えますが、冗談を言うようなウィットに富む会話は、お互い出来ません。祖母は、配膳台から取っ手の付いた漆器の長手盆を取り出すと、食卓に並べる器を乗せて、台所を出て行きました。
私は頬に手を当てて、難しい顔をして、煮える鍋を見つめていました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

