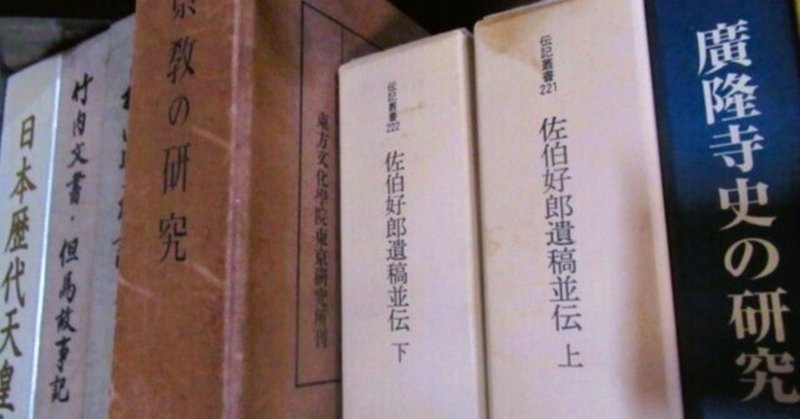
甲州ワインの謎#19/佐伯好郎の日ユ同祖論
やはりここで佐伯好郎という人の話はするしかない。
明治4年8月1日生まれの言語学者である。ゼネラリストで複数分野にまたがる西洋古典学の研究・教育で大きな業績を残してた人物だ。特にネストリウス派キリスト教の東伝史に関する研究では国際的な評価を受けており「景教博士」とも呼ばれた。しかし、日本人とユダヤ人が同祖であるとする日猶同祖論を唱えたため、学会では異端としてキワモノ扱いされたまま現在に至る。
実際に彼の著作を読んでみると、発想が突飛でポンポンと視点が飛ぶ。南方熊楠のそれと同じだ。地道に言葉を重ねていく人々は幻惑されるどころか、むしろ嫌悪感を持たれてしまうであろう論調だ。彼のような自由な視座は、その快刀乱麻ぶりに爽やかを感じる柔軟な脳の人々以外には、不快なだけだろう。
佐伯好郎の「日猶同祖」の軌跡を追うには、まず青年期に書いた「 太秦( 禹豆麻佑)を論ず」から始めるのが本寸法だと思う。明治40年に発表されたものだ。久米邦武の「聖徳太子論」が出た直後(4年後)である。
佐伯は秦氏の出自に強い関心を持った。彼はこの論文で、秦氏がはユダヤ系の渡来人だったのではないかと唱えた。彼は論拠として
①太秦広隆寺の東側に「 大酒」という名前の神社がある。秦氏が建てた神社である。呼名は「大辟」である。佐伯はこの「 大辟」が漢籍「大闢」に通じるとする。「大闢」はヘロデ王ダビデのことである。ダビデの神殿を作るのは、当然ユダヤ人という。
➁また「ダビデ」は固有名詞なだけではなく「幸せうるるもの/愛されたるもの」という意味でもあると続ける。そして「大辟」の辟は幸を意味し「 大辟は、希伯来語に於けるダビデと云ふ固有名詞の意味と付合する」と書く。
➂広隆寺西に「いさら」と呼ばれる井戸がある。「伊佐良井」と書く。佐伯は、これがイスラエルをしめしているとした。
なかなかの快刀乱麻ぶりだ。
この秦氏→ユダヤ系の理屈の延長として、佐伯は日猶同祖論を唱えるようになる。
僕は若き佐伯が久米邦武の「聖徳太子論」を手にして大いに刺激されたのではないかと思う。久米邦武の厩戸仮説は、きめわてユニークだ。彼の取った視座から聖徳太子を語ったものは古今東西全くなかった。
久米はこう書いている。
「遣唐学生学僧が羅馬の天主教を聞伝へたるといふを怪まず」
「耶蘇教の支那に伝播し、其説を太子の伝に付会しあるといふも、決して牽強の説とは聞ことながるべし」
ちなみに、聖徳太子の母の名は穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)という・・間人(はしひと)という名は、直観的に波斯人(はしひと)を連想させる。波斯はペルシャのことだ。
久米邦武は、極東日本が世界文明に吹く風の吹き溜まる所・・という印象を外遊から得ていた。おそらく、オノレの足元の古代日本の様々な風習に、ヘブライズムにあい通ずるものが無数にあることを感じ取っていたのだろう。
http://fomalhautpsa.sakura.ne.jp/Science/Other/sintou-kozoku.pdf
つまり明治に入って、碩学たちは漢学/蘭学を越えて「ユダヤ」なるものを体感した。その過程で彼らは、古代日本とユダヤ文化との間に、さまざまな類似点があることに気付き始めるのである。
佐伯好郎の「日猶同祖論」は排斥されなかった。しかし疎んじられた。彼が学者としての道より政治家としての道へ進んだのは、既存学問が持つ狭隘さ/頑迷さにヘキヘキとしたからではないか・・そんな風に考えてしまう。
無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました
