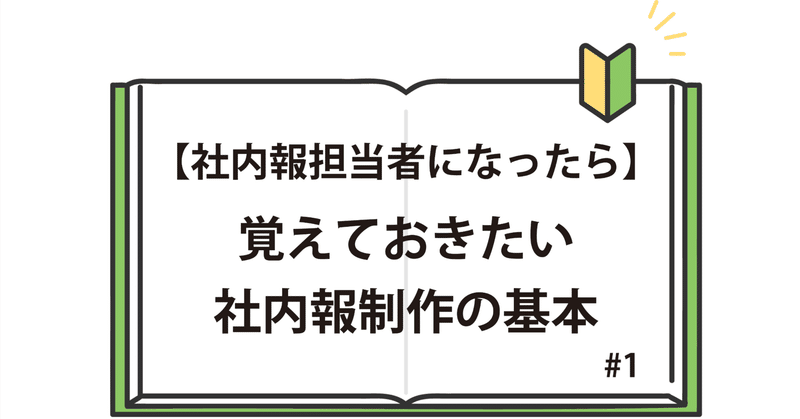
#1 【社内報の役割とは】 企業はなぜ、社内報を発行するのでしょう?
■社内報を“わざわざ”作る意義
自社内で企画から原稿作成まですべて完結させる場合も、制作会社に一部の業務をゆだねる場合も、社内報を作るには多大なコスト(お金も時間も!)がかかるものです。それでも多くの企業が社内報を発行するのは、そこに意義を見出しているからにほかなりません。
社内報の意義としてよく言われるのは、「社内コミュニケーションの促進」「社員のエンゲージメント(※)向上」といったところでしょうか。
実際、「社内報がある」環境が当たり前だと実感しにくいかもしれませんが、組織体制や就業環境によっては、数カ月に一度発行される社内報が「社内コミュニケーション」や「社員のエンゲージメント」に働きかけるほぼ唯一のチャネルになっているケースもあり得ます。
しばいぬが新卒で入った会社(社員300人強)には、社内報がありませんでした。いえ、厳密に言えば社内報らしきものはあったのですが、2色刷り4Pのうち3Pは業界の健康保険組合発信と思われる当たり障りのない記事が並び、自社固有の情報が掲載されるのは裏表紙の約1/2のスペースのみ、という代物でした。そこには、資格試験に合格した社員の名前や、慶弔出産に関連する情報が列挙されていました。文字を並べただけで、画像もなければ、目をひくデザインでもない。内容と情報量からいえば、“社内報未満”の存在です。
しかし、当時のしばいぬは、隔月で手元に届くこの4Pの印刷物を、実はかなり楽しみにしていました。はじめの3Pはほとんど読み飛ばし、裏表紙の1/2のスペースに吸い寄せられるように目を凝らしていた時の感覚は、今でもぼんやりと思い出すことができます。

背景をお話すると、しばいぬの所属会社では、社員の大多数がお客様企業に常駐して日々の業務にあたり、自社に顔を出すのは月1回程度という就業形態で成り立っていました。単身で常駐しているわけではなかったものの、お客様企業という“アウェイ”の地にあって、自社の人々の活躍や近況を知ることができる「1/2スペース」内の文字列に心を温めてもらったのは間違いありません。また、「1/2スペース」で仕入れた情報が、一緒に常駐している先輩社員との会話の糸口になったことも度々あったように思います。新入社員にとって、先輩との共通の“ネタ”探しは意外とハードルが高いものです。(その点、社内報はネタの宝庫といえます!)
つまり、“社内報未満”の作りでありながら、「社内コミュニケーションの促進」や「社員のエンゲージメント向上」という観点で、しばいぬにとっては多大な効果をもたらしていたわけです。
所属会社にしてみれば、コスト(手間はほぼかけていないが費用はかかっている)に見合うだけの発行の意義があったといえるでしょう。しばいぬの昔話は極端な例であるかもしれません。しかし、社員が組織への帰属意識を持ちにくかったり、そもそも同僚との接点が乏しい就業形態をとっている(とらざるを得ない)会社の例は、ほかにも無数にあるはずです。
会社や同僚との接点が乏しい環境の中で、仕事に取り組む社員。
そうした社員が(おそらくは本人も無自覚のうちに)抱えている欠落感を、社内報は(完全ではないにしろある程度まで)埋めることができるのです。
※社員のエンゲージメント:企業と従業員との、信頼関係や結びつきの強さを示す指標のこと。社員のエンゲージメントが高いほど、離職率が低く、業績も向上しやすいとされています。
■奮闘する社員に光を当て、活躍を広める
「社内コミュニケーションの促進」や「社員のエンゲージメント向上」という観点について、もう一つ強調しておきたいことがあります。
それは、社内報の読み手側だけでなく、記事で取り上げられる社員の側にも、その効果が及ぶということです。
これは、先述した「裏表紙の1/2スペース」にだけ自社固有の情報が掲載される社内報を愛読していたヤング時代のしばいぬには思いも寄らなかったことですが、その後何年も経ち、編集・ライターとして社内報の制作に携わるようになってから実際に見聞きし、また肌で感じてきたことです。
社内報では、「活躍中の社員にインタビューしました!」系の企画が連載されることがしばしばあります。(皆さんの会社の社内報にはあるでしょうか?)
制作の過程では当然、取り上げられる社員へのインタビューを行います。自身が、日頃何を想いながら業務にあたっているか。直近の仕事ではどのような点に苦労し、またそこから何を得たのか。そういった事柄を、多くの人の目に触れることも念頭に置きながら思い返し、言葉にする経験というのは、普段はあまりないはずです。そして自身の語った言葉がデザインされた紙面に落とし込まれ、(場合によってはプロカメラマン撮影のかっこいい写真とともに)全社に向けて発信される。発行後は、部署内の同僚はもちろん、普段はあまり言葉を交わす機会のない上司や後輩社員からも記事へのコメントが届く––––。そうした、取材から公開へ至る一連のプロセスを通して、取材対象となった社員にはスポットライトが当たるわけです。

某缶コーヒーの有名な広告コピーに「世界は誰かの仕事でできている。」というものがあります。(しばいぬも、このコピーにグッとくるクチです)
無数の「誰か」の頑張りによって、社会は成り立っています。普段は、一人ひとりの「誰か」の顔や名前がフォーカスされることはなく、ましてや、手がけた仕事の裏側にある想いが外に向けて発信されることなど皆無に等しい。(だからこそ、「世界は誰かの~」のコピーがグッとくるわけですが…)
そうしたなかで、同じ社内で今日も頑張る「誰か」に、とっておきのスポットライトを当てることができるのが社内報というツールです。(社内報制作担当者はさながら、お立ち台に立つヒーローにマイクを向けるインタビュアー!)
自身が取り上げられた紙面は、当の社員にとってはまぎれもなく、自身の仕事に対する誇りと明日への活力を授けてくれる忘れがたい記録となることでしょう。
しばいぬは、社内報の編集ライター時代には「活躍中の社員にインタビューしました!」系の企画に多く携わってきました。取材開始前は、(おそらくは照れもあって)あまり乗り気ではなさそうに見えた取材対象者の方が、自身の仕事について語る中でどんどんイキイキした表情になり、実際にできあがった紙面に感激のコメントを寄せてくださったことは一度や二度ではありません。
こうした経験を通じ、しばいぬは社内報が持つ「社内コミュニケーションの促進」や「社員のエンゲージメント向上」の効果を確信するに至りました。
また、日頃の面識の有無はさておき、誰しも仲間の仕事ぶりには多かれ少なかれ関心を抱いているものです。しかも社内報で取り上げられるのは、全社の価値基準に照らして「見どころ」のある社員(いわゆるロールモデル)であることが通例。なおさら興味を掻き立てられるはずです。
仲間が「仕事」について語った言葉の数々に触れることは、自身の仕事に対する姿勢や考え方を顧みたり、より良い変化を遂げたりするためのきっかけを得ることにもつながります。(ヤング時代のしばいぬにも、そんな記事に触れる機会があれば…!)
直接的な意味での「社内コミュニケーション」が成立するわけではありませんが、ロールモデルが備えている仕事に対するマインドセットや姿勢が、社内報を通じて社内に(そのエッセンスだけでも)伝播していくとなれば、「社内コミュニケーションの促進」という命題が目指すところは十二分にクリアしているといって良いでしょう。
■「経営戦略ツール」としての社内報
さて、社内報の発行について、「社内コミュニケーションの促進」「社員のエンゲージメント向上」などの観点に加え、また別の意義を見出している企業も数多く存在します。
具体的には、「経営戦略ツール」としての役割です。

企業の経営層は、中期計画や長期計画などの経営計画、あるいはパーパスやミッション・ビジョン・バリューなどの理念を策定し、それを自社の社員に浸透させることにより、経営目標の達成や企業としてのあるべき姿の実現を図ろうとします。
ところが、経営計画や理念の「浸透」は、そう簡単なものではありません。しつこいほどに何度も発信し、社員の目に触れさせ、しかも社員がそれを「自分ごと」として我が身に引き付けて受け止められるよう繰り返し働きかけることで、はじめて「浸透」が実現します。
余談ですが、しばいぬは若手社員時代、年に2回あった自社の経営方針説明会に何食わぬ顔で出席していましたが、経営層が語る言葉の2割も理解できていなかったと思います。(出てくる単語がなじみのないものばかりで、まったく内容が頭に入ってこず、当然「自分ごと」とは程遠い状態)
経営計画の何たるかを理解し、硬い言葉の羅列をそれなりに読み解けるようになったのは、後に務めた社史専門の編集プロダクションで、クライアント企業の社内報や経営資料に数多く触れるようになってからのことでした。
何度も繰り返し行うべき発信や、ターゲット(若手と中堅以上の社員では“読解力”に差があるものです)に応じたアプローチの切り替えが必要な発信は、社内報のように定期発行できるツールを活用するのが効果的です。
手を変え、品を変え、社員が繰り返し情報に接する機会を作り出すことで、少しずつ「浸透」が実現していくのです。
「コミュニケーションツール」と形容されることも多い社内報。
けれども、経営計画や理念などを繰り返し発信する場として、これほど適したチャネルは他になかなかありません。「経営戦略ツール」としての可能性に目を向けてみると、社内報制作という自身のミッションが持つ奥行きに気が付くはずです。
■いま、あなたの会社に必要なのはどんな社内報?
ここまで、一般論としての社内報の役割・意義について述べてきました。
肝心なことは、あなたの会社には今どのような課題があるのか、という視点で、自社が発行する社内報のねらいを見つめ直すことです。

たとえば、拠点間の没コミュニケーションや、世代間の知識継承不全といった課題が顕在化しているのであれば、
そのすき間や断絶を埋めるような発信を目指す。あるいは、経営方針や理念の浸透が課題となっているならば、それらを社員に繰り返し投げかけるような発信を目指す。
対処すべき「課題」を設定し、その課題に「社内報でいかにアプローチするか」を考えてみる。
そのプロセスを通して、自社の「社内報の役割」が明確になるはずです。課題は一つとは限りません。複数の課題を思いついた場合は、それらの課題に優先順位をつけた上で、「社内報の役割」を複数個設定するのが良いでしょう。
社内報の制作担当者に必要な準備運動前編はここまで!
社内報制作には、社内の担当者が担う領域と、プロ(制作会社)の手を借りるのが望ましい領域があります。課題設定と具体的なアプローチ(企画立案)の検討も、プロがサポートすることのできる領域に含まれます。
制作会社への依頼でお悩みの場合、まずはお気軽に弊社までお問合せください。
株式会社メッセ(東京都中央区京橋)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
