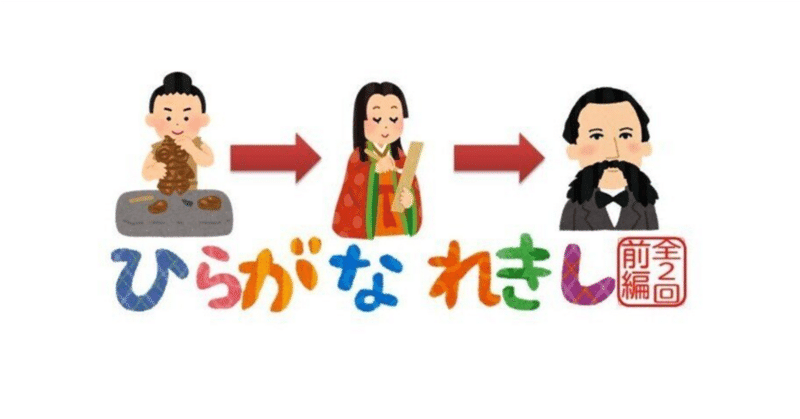
大日本帝国憲法起草者 井上毅
このノートは、『思想史講義【明治編Ⅱ】』 山口輝臣・福家崇洋編 ちくま新書 2023 の「第一講 第日本帝国憲法」の内容を要約したものです。
・「大日本帝国憲法」の一般的なイメージ
大日本帝国憲法(明治憲法)は、正統内閣制の英国モデルを排斥した明治一四年の政変後、主としてドイツに憲法調査に出かけた伊藤博文の主導の下、ドイツ憲法をモデルとして、井上毅が中心になって起草されたもので、当然にドイツの君主主義や官僚主義の影響を強く受けて、君主権力が強大で、議会権限が脆弱な、本来の立憲主義にはほど遠い憲法であった。
・「井上毅」の一般的なイメージ
明治憲法の実質的な起草者である井上毅は、強大な君主権力の確立をめざし政党内閣制を警戒して議会の権限を極力抑えた人物
・明治憲法の起草作業
伊藤博文、井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎の4人は「憲法起草者」であるが、この4人の憲法構想は必ずしも一致していたわけではなく、激しい論争を孕んだものであった。その中でも、お雇いドイツ人のロエスレルと組んだ伊東巳代治は「天皇大権や行政権の裁量を拡大しよう」としていたのに対して、井上毅は「人身の自由を含む国民の自由と権利を重視し、自由と人権を擁護する制度的保証という観点から議会の権限を尊重する」という主張をして真っ向から反対した。
・本講における試み
井上毅の思想史的背景と、従来の議論では見えにくかった明治憲法の思想史的系譜をたどろうとする試み
・岩倉使節団前の井上毅
井上が本格的に西欧の法政理論と遭遇するのは1872年(明治5年)の岩倉使節団の一員として司法省からフランスに派遣されてからであるが、井上の西欧体験はそれ以前からすでにあった。井上は儒学的教養とともに、幕末期に公刊された様々な書籍を通して関心のあり方がある程度方向づけられていた。井上は蕃書調所に集まった幕府系知識人によって著された憲法や立憲政体に関する体系的で深みのある書籍によって、よき統治とは何か、のぞましい政治制度とは何かという問いに出会い、西欧の法政思想に接近していたのである、
・津田真道と西周による『泰西国法論』(西欧国宝学)
井上の西欧体験に決定的な重要性をもつのが、津田真道と西周の2年間のオランダ留学である。ここで、津田と西はライデン大学教授のシモン・フィッセリングの国法学の講義を受けて、それを1868年(慶応4年)『泰西国宝論』として刊行する。津田と西は幕府崩壊前夜の政治的混迷のなかで、西欧の人文社会科学の一端に触れ、従来学んできた漢学とはまったく異なる「実に可驚おどろくべき公平正大之論」に驚愕し、日本の政治改革のために、西欧法政理論を修学するという使命感に駆られてオランダ留学を決意した。
・『泰西国宝論』の政治思想
津田と西が赴いた1860年代初頭のオランダ王国は、自由主義改革の直後であった。国王の専制的な統治に反発し、国王と国民との協調を旗印に、憲法改正によって責任内閣制の導入と参政権を拡大した、新たな立憲君主制が創設されたばかりの時期であった。この改革の立役者こそ、シモン・フィッセリングの指導教官であり、オランダの内務大臣を3回歴任し、教授職の前任者でもあるヨハン・ルドルフ・トルベッケであった。
トルベッケの政治的施策は、フランス革命の衝撃から始まる。自由主義的知識人であったトルベッケにとって、フランス革命は「自由と人権の確立にとって不朽の価値を持つ出来事」であったと同時に、「国家や法の人為性を過度に強調して秩序を破壊し、未曾有の参事を引き起こした政治的悲劇」でもあるような、両義性を持つものであった。フランス革命へのこうした評価をもつトルベッケは、自由主義的立場から旧来の専制君主性を批判するとともに、ルソー流の社会契約論や人民主権論を非歴史的な革命理論として排斥し、各国固有の歴史的事情に基づく穏健な立憲君主制を主唱した人物であった。
フィッセリングは以上のようなトルベッケの思想的立場に立って、津田と西に国法学を講義した。フィッセリングは、国家の起源を社会契約に求める見解を、王権神授説とともに、妄説として斥ける。そして文明社会における国家の基礎を「国民の権利の保護と義務の確定」に求め、それを「法的に規定する憲法の制定」とそれを「政治的に保証する立憲君制」を「立憲主義」の具体化として高く評価した。
こうした思想に基づいて、フィッセリングは「君主の専断」と「民衆の暴政」を防ぎ、国民の自由と権利を保護するために、国家の主権を行政・立法・司法の三権に分かち、それぞれ均衡させる政治制度を重要視した。具体的には、国民の暴走や立法権の濫用を防止するため、「議会を二院制」とすることや「国王に議会の解散権を付与」すること、逆に王権の暴政や行政権の専制の歯止めとして、「議会の自律性と十分な監督権」、あるいは「国王の不可侵性を認め」つつ「行政権を監視する大臣責任制」の導入を提案した。
つまり、井上が学んだ『泰西国法論』は、明治以降に朝野(朝廷と民間)で議論される憲法や立憲制に関する政治的モチーフのほとんどが先取りされている。ここでの「よき統治」とは「国民の自由と権利を、王と民衆という二つの専制の脅威から保護して、国民の生活に平安を与えること」であり、「のぞましい政治制度」とは「そうしたよき統治を制度的に保障するもので、具体的には、国王が保持する国家主権を三件に分かち、それぞれが権力濫用に陥らず均衡と協調とがはかれるように憲法を制定して確立すること」であった。
・権力分立論と混合政体論
権力分立論=国家権力を三権に分立することにまず意義を見いだす
混合政体論=三権分立を前提とせず、権力の一元化を否定し、多元的な主体や制度を均衡させて自由と権利の確保に繋げる
トルベッケとフィッセリングが推奨した「立憲君主制」とは、王政と貴族政と民主政とが均衡し調和する英国の混合政体をモデルとしたものであった。
西欧の自由主義者にとって政治改革は、国王によって一元的に保持された国家権力の専制に対する異議申し立てから始まったものではあるが、フランス革命によって民衆の「暴政」の惨劇を経験したことで、国民や議会による一元的な権力保持もまた同様に専制をまねく危険があることを体験し、身分によるものであれ、政治機構によるものであれ、国家権力の一元化に対する強い警戒が生まれた。
・加藤弘之の(日本風)立憲政体論
津田や西の同僚でもある加藤弘之も、フィッセリングと思想的に近い穏健な自由主義者ブルンチェリを参照しつつ立憲政体に関する三部作を著した。加藤は『泰西国法論』の学術的な文体とは異なり、平易な親しみ易い文体を使った。加藤は『立憲政体略』において、政体を4つに類型した。それは「君主専治」「君民同治」「豪族専権」「万民共治」であり、加藤はこの中でも「君民同治」を日本に適する政体として推奨した。その具体的なあり方は『泰西国法論』の統治イメージと多くの共通点を見いだせるが、加藤の議論には、「日本風に改変された混合政体論」という角度がつけられていた。
加藤も、多元的な主体や制度を通して権力を均衡させる点では同様であるが、英国風の国王、貴族、庶民の三要素ではなく、日本においては、貴族(華士族)を除いた君主と国民との二つの要素の均衡をはかる「君民共治論」を提唱した。そして、君と民との関係についても、民の専制よりも、君権の専制力の方を脅威として強調した。君権の専制を防ぐために、「一君のために億兆がある」という国学者流の家産国家論を否定し、国家は君主の私有物ではなく「天下の天下」すなわち公有物であると繰り返し主張した。日本の現時の政治情勢においては、民衆騒乱の危険よりも、幕府や明治政府による「君権の専制」こそが現実的な課題であるという実感と、「法が為政者の命令であるという日本の政治的伝統」を考慮すれば君権の専制的性格こそが取り組むべき優先的な課題だと考えられたからであろう。
また、加藤は国民の自由と権利も二つに分類した。それは「国民の私的な自由や人権」の「私権」と、「参政権」を意味する「公権」である。加藤は特に「私権」を重視した。私権の保護こそ立憲政体の要諦と力説し、それが君権によって侵された場合は、単なる不服従に止まらず、抵抗と反逆を義務づけた。これに対して「公権」の実現については、時勢と国情に鑑みて漸進的に実施されるべきものであった。
・井上毅のフランス留学
津田と西から「混合政体論」を、加藤から「君権の専制への警戒」と「私権の重視」をそれぞれ学んだ井上は西欧の法政思想の世界に接近していった。井上は留学準備のために、加藤の著書である『真政大意』を精読し、また「明治一四年六月再閲」との朱書きもあり、井上と加藤の思想的な関係の近さも示唆されている。
井上は司法官僚としてフランスへ留学し「治罪法(刑事訴訟法)」を学ぶが、それを通して井上なりの憲法構想を深掘りしていくことになる。井上は刑事訴訟法を調査する中で、拷問による自白の強要が常態化している東洋の「夷風」に対して、文明国たる欧州においては推定無罪の原則に基づいて被告人を人道的に扱うことを目撃して愕然とする。このような人権の確立の契機はフランス革命であり、「人身の自由」を始めとする各種の基本的人権を憲法の根本原則として翻訳する。さらに、井上は「人身自由」と「家宅不侵」と「民権(私権)ノ大義」として詳細に解説もしている。
井上はプロイセン憲法を翻訳して『王国建国法』を書いているが、そこでも「私権」の保護という関心は一貫している。井上がプロイセン憲法を選んだ理由は、それが人為的で数多い欠点があるにもかかわらず、国民の私権に対する保護の手厚さのゆえであった。「国民に付する所の私権に至ては、言語、著述、行動、来止(きとう?)、教授、礼拝の自由、名実完全して、民俗に浸潤すること、実に欧州の冠首たり」。興味深いのは、井上は人権宣言の翻訳において、「国家主権は国民に由来する」という第三条を注意深く除いているが、これは井上の非民主性というよりも、西欧自由主義者のフランス革命に対する両儀的な評価を共有していたがゆえであろう。
・明治十四年政変との関係
① 井上が大隈意見書に反発したのは、政党内閣制が混交政体論的発想とは真逆であった
政党内閣制は立法権と行政権を一体化し、専制の危険を孕んでいた。政権交代はこの時点では、現実味はなかった。
② 大久保暗殺、自由民権運動の隆盛によって民の「専制」という可能性の浮上
国民の私権の擁護への見直しを感じた。ドイツ学への接近。
③ それでも井上は国民の自由と権利の擁護こそが憲法の要諦であるという原則にこだわった
加藤弘之は明治一四年に自らの初期の著作を絶版としたが、井上はそうはしなかった。
