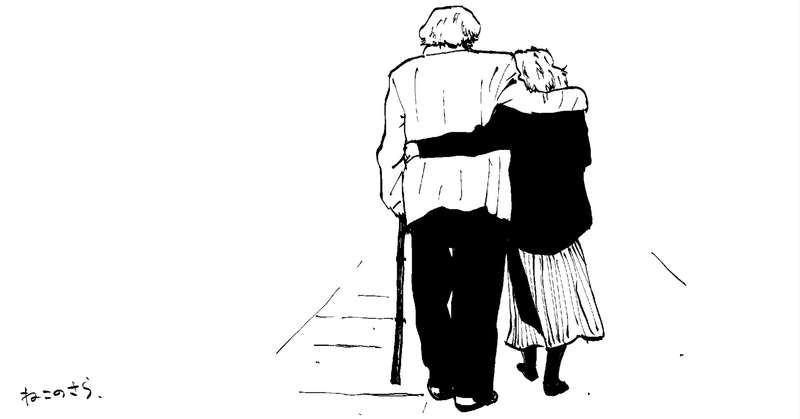
「民主主義の緩慢さ」は大切という話
「民主主義の緩慢さは大切である」という議論を見た。
今、流行りの哲学者であるマルクス・ガブリエルの著書『世界史の針が巻き戻るとき』の中に出てきたのだ。
民主主義の「遅さ」に対して、独裁国家の場合は「早い」のだ。独裁国家の場合、議論をして納得ができない場合は議論を続ける必要はない。より強い者が弱いものを「抹消」したらいい。実際、中国やロシアでは権力者に楯突いた人たちは行方不明になってしまう。
民主主義はとにかく「遅い」のである。
裁判を例に取ろう。裁判がすぐに決着することは少ない。いくつもの段階を経て、さまざまな視点から考えて、最後には決着をするが、その決着についても「不服を申し立てる」ことができる。つまり、決着が決着ではないのだ。もちろん、どこかで最終的な決着はつけるが、この例からも民主主義の基本的なスタンスが見て取れる。それは「議論の決着を遅らせる」ということである。
国会での議論は特にわかりやすい。
最終的な決着である多数決の場面になっても、昔は「牛歩戦術」というものが取られることもあった。これは「投票箱までゆっくり歩く」という子どもでも浮かぶような戦術である。狙いとしては、ゆっくり動くことで時間を稼ぎ、日付を跨いで決着を先送りにするなどがあったらしい。その効果のほどは怪しいが、決着を少しでも長引かせるという意味でのパフォーマンスは「民主主義」の本質を体現しているとも言える。
牛歩戦術は特異な例ではあるが、形式にこだわり議論が遅々として進まないというのは、国会中継を見ていても感じるであろう。
そして、それを見て不満になった国民が「わかりやす」くて「論旨が明快」な政治家に惹かれるというのは、まさに大阪で起こった「維新旋風」である。
「我々は、既得権益者を退治しに来た」という明快でわかりやすいストーリーに多くの大阪の人は共感した。
しかし、これを知識人は警戒する。
なぜなら「快刀乱麻を断つ」ごとき政治は、その決定のプロセスが軽視され(「我は民意を得たり」という振る舞い)、独裁を招くことになるからだ。
人間はそんなに賢くない。
一人が森羅万象について理解できることなど望むべくもない。特に、現代のような複雑な社会では、それはなおのこと困難である。だから、専門分化する必要があるのだ。そして、決定はなるべく多くの専門家の知見を持ち寄って、緩慢になされなければならない。独裁国家は「他国を侵略」のような単純な世界でなら通用するかもしれない。しかし、そんな単純な世界はとうに終わっているのだ。政治は複雑系なのである。
話を単純にして、わかりやすくすることの弊害は他にもある。それは「他のこと」に目が向かなくなることだ。
「公務員を減らして、財政支出を抑える」という明確な目標を掲げてしまうと、その弊害を考えることができない。そんなことを考えていては、目標の達成が進まなくなってしまう。「民主主義の緩慢さ」へのカウンターパートとして登場した政治家は、その宿命として「早さ」に価値を置かざるを得なくなってしまう。結果、取り返しの付かないことをしてしまうことがある。
ある地域のの図書館は外部委託が進んでいるらしい。
専門家である司書は一人だけで、残りはアルバイトや人材派遣会社からの派遣社員らしい。確かに、図書館は「儲からない」。だから、図書館にかける費用はすべて支出として計上される。図書館にかけたお金がどれくらい返ってくるかという費用対効果の側面のみで考えれば、図書館は「負債」なのである。
しかし、地域の図書館は「そういうもの」ではない。市民の「知的センター」として、そして「憩いの場」として立派に機能している。
蔵書の管理だって、ただ貸し出して、返ってきたものを本棚に返すというシンプルなものではない。どの本を配架するかや、その方法などはかなりの専門性が問われるであろう。そうでなければわざわざ「司書」という役割は生まれていないはずである。
新しくできた綺麗な建物の図書館に行くと「雑誌」や「新刊」だらけだったという話を聞いたことがある。確かに、それらの本には「市民のニーズ」があるのだろう。しかし「ニーズ」ばかり考えて「あまり読まれない本」を置かなくなった図書館は、「Amazon」と同じである。
配架というのは「これを読んで欲しい」という司書の「教化的なメッセージ」をも含んでいる。それは、少し大袈裟に言えば「私は市民の皆さんにこれを学んでほしい」という「司書の願い」なのである。
もちろん「アルバイト」には、そんな願いは持てない。彼女たちには、そんな願いを持つことは許されていない。そうして業務が細分化されていき、専門性は排除されていき、人気ランキングというわかりやすいアルゴリズムに則って運用される図書館は「明快でわかりやすい」かもしれないが、知的水準というモノサシで測ればどんどん劣化していく。
なぜなら、知的水準というのは「誰かが誰かを教育したいという意図」によってしか引き上がらないからである。
本棚に「願い」が籠っていない図書館は、ニーズには合っていても知的ではないのだ。
公共というのは儲からない。だから、「緩慢さを嫌う」政治家からすれば「負債」にしか映らない。
公園の話をしよう。
公園は儲からない。だから、その運営を民間委託しようという動きがある。公園内に有名珈琲店を誘致したり、大規模アスレチックを作ったり、大きなイベントを開催したりする。
そのような公園を歩くと、本当にうんざりさせられる。なぜか。それは「何をするにもお金がかかる」からだ。
子どもとその公園を歩くと「あ、あれ楽しそう」となる。それは空気で膨らませた大型遊具である。そして近づいてみると「5分500円」と書いてある。電車のような移動手段があり近づいてみると「一人300円」。歩いて疲れたがベンチが少ないので、珈琲店に入ると、1000円くらいを支払うことになる。
公園は公共施設なのに、これではディズニーランドと変わらないではないか。すべてがお金に換算されたサービスになる。小学生にも教えることであるが、「お金のないものは来るな」という場所を「公共施設」とは呼ばないのである。
だから、公園の民間委託は、「公園の脱公園化」なのである。それはいずれ「公園型テーマパーク」となり、お金のない人は入場料を払えないので入れなくなる。
私は3児の父である。
家では毎日のように喧嘩が繰り返される。先日も「これは私の!」と言って長女が怒っていた。すると、それを見た末っ子の次男が「じゃあ、これは僕の!」と言い出した。そして長男も「これは僕が誕生日で買ってもらったもの」と言う。その状況を見て、呆れながら以下のような話をした。
「確かに、それらは君たちのものだ。でも、そうやって「これ、私の」と言い合っていたら、「相手のもの」が使えなくなるよね。すると、「あなたの使えるもの」がどんどん減ってきてしまう。みんなが「自分のもの」と主張するからね。結果的に「自分のものでしか遊べない」と言うのはとても不便になると思うんだ。」
かのカール・マルクスは「資本主義はすべてのものを商品にする」と言ったが、そんな世界は「公共性」が無くなってしまう。なぜなら、「公共の価値」は市場の概念では測れないからだ。そんな事実に新自由主義者が気付けないのは、まさに当の新自由主義者たちが「市場は万能である」と信じているからである。
そして、我々もその価値観を深く内面化してしまっているのだ。そのドクサ(臆断)を振り払うことができなければ、我が家の兄弟喧嘩のように、いずれ「自分が買った商品」しか使えない狭い世界で生きることを強いられる。
ここは俺の道だから通行量を払え。
この公園の入場料は〇〇円です。
マルクスの『資本論』は置いていません。人気がないから。
私は教師である。
だから、こんなことを論じる必要はないと思われている。
教育者は教育のことだけを語ればいい、と言うことである。しかし、それは短見というものであろう。
なぜなら教育は「未来の社会の形成者」である「子どもを育てる」営みだからである。これは言い換えれば「未来を創る営み」なのである。そんな教師が無知であることを望む人はいないであろう。これを読んでいる諸氏の老後の日本を支えるのは、紛れもなく現在の「子どもたち」なのであるから。
