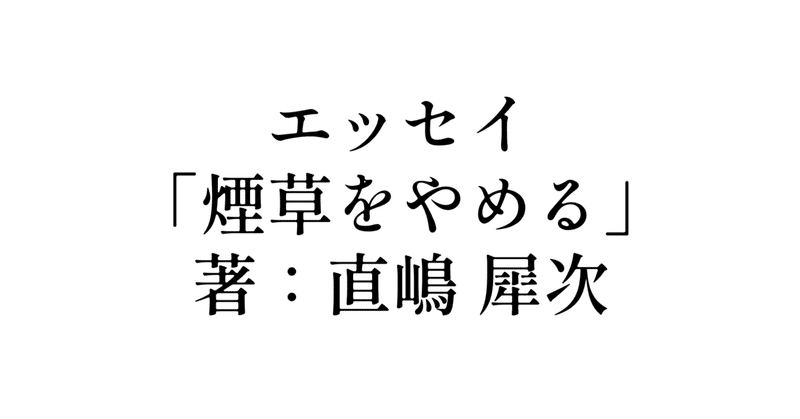
煙草をやめる 著:直嶋 犀次
煙草を、やめてみようと思う。
もう、というべきか、まだ、というべきかわからないが、今年29歳になる。さすがにそろそろやめておくか、というわけだ。30歳になっても吸っていたら、それからずっと吸ってしまうような気がするから、やめる。なんとなく、一生続ける趣味でもない気がするのだ。
しかしこれはなんだか、僕自身にとって空を掴むようなというか、どうにも、どう捉えたらいいかわからない問題なのだ。たぶん無理だと思っているところがあるし、しかし一方でどうにかなるような気もしている。今回noteに投稿するエッセイを任され、(『上陸』の作者紹介と同様に)何も思いつかなかったから、こういう極めて個人的な、自分にとっては有意義そうなテーマを選んで、以て自身の今後にとっての何かの足しになればいいなという魂胆である。
禁煙とは何か。こう書いてみて、そもそも「禁煙」という言葉が苦手なことに気づいた。煙という掴み難いものに無理やりばつ印を貼り付けようとしているようなイメージがある。通りもしないはずの筋を通そうとしている感じがして、どうにも非人間的な感覚がする。禁煙。そうはならないだろう、という感じ。だから以下では、煙草をやめる、と表現するよりない。
さて、煙草をやめるとはどういうことか。これは、煙草を吸わないでいる、ということだ。そう言われると、そんなに難しいことではない気がする。しかし、これは精確な表現ではない。ただ煙草を吸わないだけではないのだ。つまり、途方もなく長い時間の間、煙草を吸わないでいる、ということである。ここに煙草をやめることの難しさがある。
たった5分、煙草を吸わないでいることなら、できる。間違いなくできる。10分でも同様。30分だって簡単。1時間だって、大丈夫。2時間、できるだろう、よほどのことが起きない限り。3時間、たぶん、結構な確率で大丈夫。では、まる1日。まあやろうと思えばできる、というか決断すればいつだってできる。2日だって、全然、不可能ではない……。しかしこうして時間を延ばしていくと、どこかで必ず無理がやってくるのがわかる。だって、まだ何年、何十年という単位で生きるつもりなのだから。これから先、続いていくであろう自分の生の時間を思うと気が遠くなる。
おそらくこういう感覚は、非喫煙者の人たちにとって、理解はもちろん、想像することすら難しいだろう。薬物依存なのだから、そういうものに侵されていない人にはわからなくて当然な話ではある。そこで、非喫煙者の人に想像してほしいのは、何らか自分が依存しているものである。それはもちろん煙草みたいな世間的に良しとされていないものだっていいし、反対に、世間では良いとされているもの、あるいはこと、であってもいい。You Tubeでも、TikTokでも、あるいは家族、仕事、恋人、勉強、推し……とにかくなんでもいいのだが、自分の生活と切り離すのが困難、そうすることが考えづらいもの。それを、金輪際、一切触れることなく生きていく、生きていかなければならない。そう考えると、我々の困難さがわかってもらえるかもしれない。
つまり、煙草をやめるというのは、これまで連綿と続いてきた自身の生活のひとつを切り離す作業である。この「生活のひとつ」というのは、自らの在り方の一部とも言いかえられる。それがあってこそ自分の人生だ、などと胸を張るほどのことでなくてもいい。そこまでは言わないけれど、しかし生活にそれがあって、これまでやってきた。それがあってこその思い出、情緒、見方、そういうものが来し方を振り返ると確かにある。それをこれから一切、手放すということ。その時点をもって、あなたの人生は明確に以前と以後に分けられることになる。他人からすれば見分けがつかないような些細な変化だが、それ以前の人生は、それ以降のあなたにとっては、もう二度と、接続できない領域へ流れていってしまう。
ここで、ふと思い出した話をひとつ。
昔、「どうして煙草を吸うのか」という問いを投げられたことがあった。それに対して僕は、自分の一部を手放したくないからだ、と答えたわけではなかった。
ひょんなことからノルウェーに行ったときだった。オスロではない、おそらくこれを読んでくれる人は誰も聞いたことがない、ちょっとした、都市、と表現するよりも、町、と表現したほうがしっくりくるような、こじんまりとしたところだった。大聖堂と呼ばれる黒々とした教会を中心に、色とりどりの三角屋根を戴いた家々が海岸線まで続いている。
僕らは粗い石畳に覆われたゆるい坂道を、夕陽に背中を照らされながら登っていた。大聖堂のある町の中心からその日の宿まで、少し丘を登らなければならなかったのだ。季節は夏で、北極圏の手前だったから、時刻としてはもう夜だった。この太陽は真夜中になってもほとんど沈まず、ただ長い長い夕方だけが続いて、そのまま朝になる。そんなことをいまさら確認するかのように話しながらも、僕らは苛立っていた。学生の気安い思いつきでこんな遠くの国まで一緒に来てみたが、全く性格の合う二人ではなかったということだ。彼女が折に触れて僕に伝えようとしてくる日常、あるいは過去への愚痴にはすべて、僕の神経を逆撫でるようなところがあった。全く正義に適った主張じゃない、と思ったことを覚えている。恋人ですらなかったにもかかわらず、「お前みたいな人とは絶対に結婚しない」とまで僕は言った(女性にお前、なんて言葉を使うとは、今日の僕からしたらあり得ないことなのだが)。いまになって考えてみれば、たった数日間のことなのだから、いちいち気に留めたりせず、彼女の喋りたいこと、認めてもらいたいこと、みんな肯定してあげればよかったのだ。彼女だって、きっとそれ相応の理由があり、また僕という他者から肯定されれば、その分救われたに違いないのだから。しかし僕は、自分でも全く制御できない何かに支配されたかのように、どうしたら彼女の意見を誤りだと認めさせ、自分の考えが正しいとわからせられるかばかりを考えていた。
ところで、僕は必ず煙草を吸うときは何か甘い飲み物をお供にするようにしている。これは、飲み物なしで煙草吸うと喉が痛くなるために始まった習慣だったが、いつしか単純に甘いものを味わうだけの際にも、煙草が欲しくなるようになってしまった。依存と依存が、習慣の中で結びついたわけだ。そしていつしかそこにもうひとつの依存、すなわちカフェインの依存も合わさって、端的に言うとレッドブルを飲みながら吸う煙草が、僕にとって至高なのである。
坂の途中で出くわした、物置小屋みたいな風体のコンビニで、僕はそんなレッドブルを買った。日本では見ることのない、やたらと大きな缶だった。それからノルウェーでは(いま現在もそうかはわからないが)屋外でならどこでも煙草が吸えた。道行く人たちもみんな、歩きながら煙草を吸い、石畳の上に吸い殻を投げ捨てていた。それを見て、彼女は非難するようなことを言ったのだと思う。僕は何も答えずに缶を開け、一口飲んだ。渇いた舌の上に、よく冷えた、極彩色ともいうべき味わいがなだれ込んでくる。その潤いが消えないうちに、さっと煙草に火をつけ、浸された口腔全体を燻すかのようにして吸い込む煙草の煙が、なんと美味しいことか。
すかさず、どうして煙草なんか吸うの?という言葉が追ってきた。もちろんそれは喫煙の理由を問う疑問文ではなかった。だからこそ、僕は復讐の意味を込めて、あたかもそれが純粋な疑問文であるかのように何か答えてやろうという気持ちになったのだった。
しばらく無言で歩いて、ようやく丘の上に出たところで、僕は、「人は、いつだってなにかに依存してるってことを忘れないためだよ」と怒鳴るように答えた。
キザというか、どうにも格好悪い返答だが、そのくらい僕の頭は激していたのだろう。一方で、煙草というものの正体に迫る回答としては、これも悪い答えではなかっただろう。実際僕は、それからだいぶ年月が経ったいまになっても、自分という存在が否応なく何かに縛り付けられて在ることを、日々、数度ずつ、思い知らされている。
僕は一体、煙草をやめられるのだろうか。ノルウェーのことを思い出して、僕はやはり否定的な気分に飲み込まれつつある。何しろ、ここで当時の彼女の肩を持つようなことを書いておきながら、僕は、いまになってもこの女性と和解できていないどころか、謝罪一つ、できていないのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
