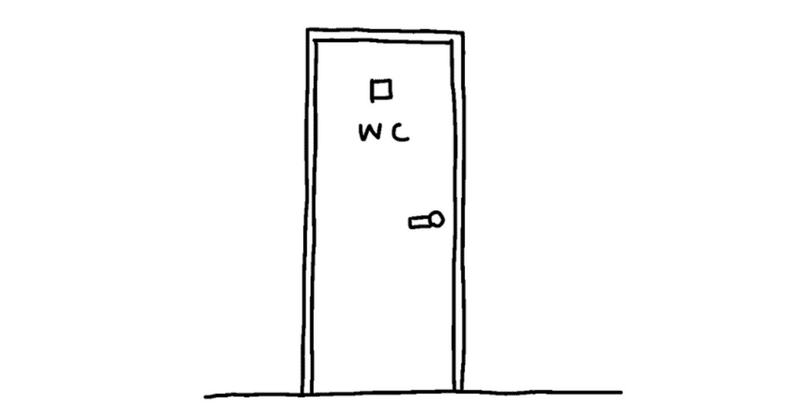
認知症との折り合い その1
「コーヒー淹れるわ」
「ありがとう。コーヒー飲むと目がさえます」
「目は”さめる”やろ。”さえる”のは頭や」
100回以上繰り返した会話です。
短期記憶がほぼゼロの母との暮らしは、こんな牧歌的な光景ばかりではありません。
日々の生活において母にやめて欲しいことが多々あります。
例えば、
トイレのドアを大きな音を立てて閉める、
歯磨き中にお湯を出しっぱなしにする、
わざわざ取り寄せた歯科専用ガムを噛ませても、味が無くなったらすぐに捨てようとする、
そのガムを捨てるための紙を目の前に用意しても、新しいティッシュを抜き取ってガムを包んで捨てようとする、
などなど、他にもたくさんあります。
これらについて、いくら言葉を尽くしてお願いしたところで、直ったことがありません。何度も繰り返します。
お願いをしても、そのことを忘れるからです。5分もすれば見事に忘れてしまいます。
お湯やガムやティッシュなどはケチな話だけど、ドアの大きな音は寝ているところを起こされるので、かなり重大な問題でした。
ケチなほうも、毎回ほんの少しだけ心が削られ、それが1日に何回も積み重なるので、やっぱりしんどいと感じてしまいます。マイクロストレスと言って、蓄積すると看過できないそうです。
必死に説明してお願いをしたその時は理解してくれます。ものすごく神妙な顔をして「わかった。もうせえへん」と言ってくれます。言葉を尽くした甲斐を感じます。
しかし5分後にはすっかり忘れているのです。
ただ記憶にまったく定着しないわけではないようです。
事実、冒頭のコーヒーの会話では「目がさえます」と言った後に、
「目は?」「目は?」「目は”さえる”のか?」と問い詰めると、
「あっ。さめますや」と思い出すので、記憶はどこかに蓄えられていて、単にそれが引き出せないようなのです。
話していて記憶に蓄えられている感触があるからこそ、ボクは何度も説明しようとしてしまうのでしょう。
あるいは何らかの悪癖を見たら反射的に「それはやめてくれ、なぜかと言うと」と説明してしまう癖がボクにあるのかもしれません。
誰でもするかな。
とにかくどんなに合理的な説明をしようと、うまい例えでスッキリさせようと、感情を込めて訴えようと、ほぼ全てが無駄なのです。徒労に終わります。
ではどうすればいいのか。
80分しか記憶できない数学者の話「博士の愛した数式」(いい小説です。泣けました)のように、そこら中に注意書きの貼り紙をするべきか。
しかしそれは効果がありませんでした。
トイレのドアに「ドアはゆっくり閉める」と張り紙をしたけど何も変わらなかった。
こんな時は問題解決のセオリー通りにすればいいのです。
真の問題はどこにあるかを深く突き詰めればいい。
トイレのドア問題は「母がドアをそっと閉めてくれないこと」を問題の本質と捉えるから、母に対して何とかしなければならないと考えてしまうのです。
それはかなり表層の問題です。
問題の本質は「ドアの音でボクが起きてしまう」ことです。
しかしこれは解決が難しかった。ドアの音で起きないようにする手段がどれも課題が多かったからです(耳栓、部屋を遠くする、部屋を遮音する等)。
それは諦めて、次に深い本質を考えます。
次の本質は「ドアの閉まる音が大きい」ことです。
これは何とかなりました。ドアの音を小さくすればいいのです。
ネットでドアダンパーなるものを入手しました。取り付けは面倒だったけど。
その他、いろいろ工夫して静音化に努めました。
以降、寝ている時に起こされることはなくなりました。
このあたりは当たり前なことですね。
問題はケチな諸案件です。
しかしケチ案件は、どれも母に染みついた習慣をボクが直接見て感じることなのでなかなか解決は困難でした。
どれも、ボクが”もったいない”と不快に思うことが問題の本質だからです。
快不快問題はボクに言わせれば、超本質です。根源的です。
では、どう折り合いをつけるか。
これは”もったいない”という不快さをなくせるかどうかです。
”もったいない”と言えば、ボクはそもそも小銭をゴミ箱へ捨てられる人間でした。
そんな記事を書きました。
ここはどれくらい”もったいない”のか、定量化するべきでしょう。
定量化して、もったいなくないと自分で理解する必要があります。
ティッシュは1回につき1円もかかっていません。お湯も1円あるかないかでしょう。
これらは年間でせいぜい数百円です。
ボクのビール代の1日分ないかもしれません。
そう考えるとお湯やティッシュの無駄遣いはバカバカしく思えてきます。
ガムは数円ありそうです。
そもそもガムは、咀嚼による脳への刺激、唾液分泌による歯周病予防や消化促進などを目的に、母に噛ませています。
まあ気休めかもしれません。ある意味ボクの自己満足のためのものと言えます。
そこへのコストと考えれば、そのコストを2倍に見積もればいい。
ガムを早々に捨ててしまったら、もう1個母にあげればいい。
そのように考えました。
他にいろいろと数万、数十万と惜しみなく使っているのだから、ガムごときに”もったいない”と言うほうがバランスが悪い話です。
そうやって心の折り合いを付けていきました。
しかしなあ。
なかなか難しいですね。
頭で理解しても、まだ不快さは残っています。
ちょうどここを書いている現在、母は風呂に入っていますが、もう10分以上お湯を出しっぱなしにしています。
やっぱり、なぜそんなに湯を使うか聞いてしまうだろうし、湯を使うなら湯船から汲めばいいと言いたくなってしまいます。
おそらく以前の施設にいる感覚なのかもしれません。
そう言えば何度も「ここの従業員さんに言われた」と言っていたし。
家やぞ。ここは。
そもそもお湯を出しっぱなしにしていることを注意して納得させても、どうせ次回もやってしまうのです。
心の折り合いって、言うは易しで実際は付けにくいよなあ。
なんだか自分に言い聞かせているだけの記事になってしまいました。
読まされたほうは、たまったものじゃないですね。
It must have been intolerable for those of you who have to read it.
うおっと。
笑いなし、オチなし、オリジナリティなし、突然無意味な英訳ありで終わりそうだ。
自分に課したハードルとの折り合いも付けにくいなあ。
「その1」として次に託そうか。
だとしたら次のハードルが高くなるなあ。それが一番折り合いが付くけど、まあいいか。それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
