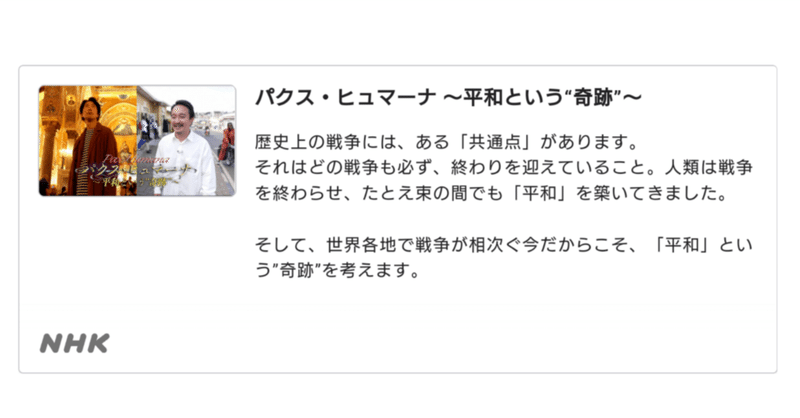
パクス・ヒュマーナ 〜平和という“奇跡”〜 その2.1 ”幼少期の教育“ 当たり前過ぎて意識しなくなっていること
NHKさんの作品を取り上げ、平和への1つの切り口、史実を元にした深堀りをするという話です。
(特に駐在したイスラエル、飽きるほどデレゲーションのアテンドで行ったエルサレムと私の人生に大きく影響を与えた稀有な経験に直結しています。ですから食い散らかした現役時代を卒業したこともあり、コンテンツとして残す事に意義ありという認識です。立ち止まって丁寧に考察して行きます。)
その1では、神聖ローマ皇帝のフリードリッヒ2世がその理性的な能力を発揮し十字軍として交戦すること無く、交渉でエルサレムの統治権を得たという史実の話でした。
今回は、その偉業を成し遂げたフリードリッヒ2世のその理性的な能力の根源という話です。
(丁寧に整理して理解して世代の平和に繋げたいという思いです。)
幼児期は教皇領にあるペルージャ
その南の小都市フォリーニョ
で過ごしています。父の信頼するスポレート公の妻に育てられています。所謂乳母(めのと)なのかなぁ。いきなり他人に育てられるという境遇からのスタートでした。
詳細は私には不明ですが、この幼児教育は大いに成功している様でした。
閑話
私も始めの子どもは横浜から1歳になると日本海側の地方都市、その後の東京に3ヶ月住み、2歳から4歳まで米国で育てるという機会に(敢えてこの表現を選びます…)恵まれました。幼児期に転居4回。これは子どもにとってはしんどいのかもしれませんが、人生を俯瞰すると貴重な経験になったと確信しています。多様な文化に触れ、多様な人間関係の中で揉まれることも、1つの有益な選択肢だったと感じています。
特に米国のプレスクール。基本は働く親を支援する仕組みなのですが、私の場合は現地教育の場として捉えて利用しました。吾妹が厳選した選択肢から選んだ学校でした。ここでの教育は吾妹の幼児教育の上に米国流を乗せる形で子どものファンダメンタルズ形成に大きく寄与しました。平日9時〜17時と最大限活用させていただきましたので、その効果はたった2年間でしたが絶大でした。英語のヒアリングや流暢な発音から始まって、合理的な考え方や創造力まで、世界標準のマナー、男女平等、自由、民主主義なんて言うキーワードガイドライン子どもの所作から滲み出ます。
その見事にダブルスタンダードが熟して今に活かせて居ると微笑ましく見守っています。
これが私にとってはフリードリッヒ2世理解のリファレンス。
閑話休題
その後父親は早逝。その父親とは人生で短時間、2回しか会っていないという人生。なので対面という意味での直接的な影響は無いかと思います。しかし、父親は子どもをドイツ王にすべく、精緻に手配を整えることで子どもの人生に大きな影響を与えるというアプローチを採ったのでした。これはこれで決定的な影響でした。
この時代なので、将来、平和という大きな課題に対してのソリューションを提示する事となる人物としては極めて有効な影響だったと理解しています。
閑話
今の時代は、情報化社会なので平和へのソリューションの提示には、何も王の様な立場にならなくてももっと多様なアプローチの手段が与えられて居ると思っています。個人の情報発信の手段は格段に多様化しその影響力も別次元。
そういう社会を創るべく、特に半導体やセキュリティといったインフラから社会貢献した自分への自画自賛かなぁ…
閑話休題
そもそも父親は敵対する家系との婚姻でドイツからシチリアまでの広大な地域への支配を確立して居ました。その父親が亡くなると世の中は乱れました。そのような状況下で子を案じた父親のドイツの家系とは敵対していたシチリアの家系からの妻(詰まり産みの母親)の元に呼び寄せられました。そして3歳でその母親の意向で強引に母方の家系が治めていたシチリアの王となります。その前後ではかなりの能力と知識を得たようです。その知識·能力獲得の経緯は、類推の域を出ないものしか残っていない様です。
しかし、その母がシチリアに居るドイツ人を排除したことから孤立して行きます。やがて極まって、当時は歴代の教皇の中では最もやり手で、学問にも長けた実力派の教皇を頼ります。母親は子どものためにと父親が用意したドイツ王、皇帝への切符を放棄してまで。しかし鴨葱(かもねぎ)状態。教皇に上手くあしらわれ政治的に利用され、体よく身ぐるみ剥がれることになります。そして心労で夫の死の1年後に他界してしまいます。
詰まり結局は何と…
(格別の知識·能力を持って)
4歳で孤児になるのでした。
このしぶとく生きることを強いられた波瀾万丈の幼児期が、後の平和へのソリューション提示の礎となっているという理解です。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

