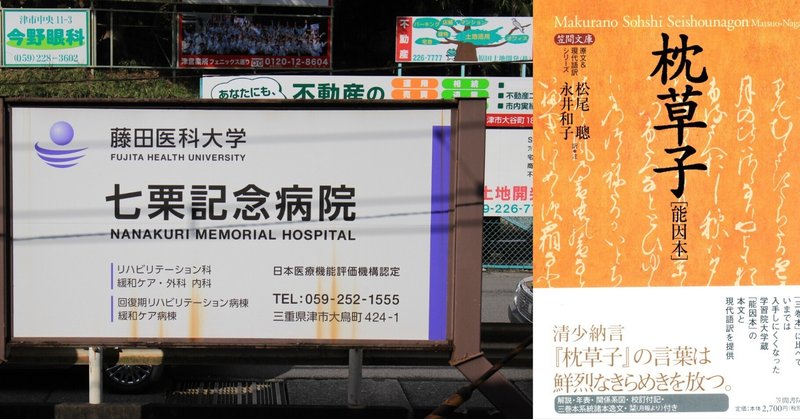
温泉とほうとう
早くも真夏日が到来している昨今、いささか季節はずれのタイトルをつけてしまったが。
『枕草子』のお話である。
『枕草子』お勧めの名湯?
『枕草子』の一部の本には、以下の記述が掲載されている。
湯は ななくりの湯。有馬の湯。玉造の湯。
現在一般の書店に流通している『枕草子』の本に、この段はない。『枕草子』には”三巻本”と”能因本”という、異なる系統の写本があるがゆえの現象である。
平安時代にはもちろん印刷やコピーの技術はない。書かれた作品は人力で筆写して広めていくより他なかった。誤写や脱落などの”うっかりミス”は当然生じる。長い時間を経て、幾度も筆写が繰り返されるうちに、原型からの乖離が大きくなったと考えるほうが自然である。昔の小学校で行われていた「伝言ゲーム」を思い起こせば理解が及ぶだろうか。さらに紙質の劣化、取扱い不備、災害や戦乱による損傷なども加わる。
現代まで伝えられている『枕草子』の写本は4系統あり、そのうち”三巻本”と”能因本”の2系統が原型に近いとされている。
能因本と三巻本
三巻本はペンネーム「耄及愚翁」さん(耄碌した愚かなジジイ?)が1228年に筆写して、丁寧な校注をつけたテキストに基づく系統の本である。耄及愚翁さんは藤原定家であろうと言われている。その時代にこれだけの仕事ができる人は、他に誰もいないからだろうか。1228年といえば承久の乱(1221年)が終わり、後鳥羽上皇たちが遠国に配流されて間もない頃。朝廷の動きを監視する役割を持つ六波羅探題が京に設置され、武家の全国支配が完成した時期にあたる。古の宮廷文化の様子を何とかして後世に伝えていかなければ!という危機感と使命感は、並々ならぬものがあったと想像がつく。
しかし定家は、”現時点において既に状態のよい写本はなくなっていて、このたびまとめた本においても不審箇所が多々ある”と奥書に記したという。「老いてなお力及ばず」という無念感が滲むペンネームである。
この時、定家がまとめた本も現存していない。後年さらに筆写が行われたはずである。現存本は室町時代末期に書かれたものが最古という。
能因本は、能因という僧侶が所有していた写本が源流と言われている。俗名は橘永愷(たちばなのながやす)、988年生まれ、1050年もしくは1058年没という。すなわち『枕草子』のほぼリアルタイム世代である。歌人としても有名で、小倉百人一首に歌が選ばれている。他に
都をば霞とともに立ちしかど
秋風ぞ吹く白河の関
が有名で、私は調べていて「あっ!」と思い出した。
この能因の姉妹が、清少納言の子・橘則長の妻になったという。その伝手で『枕草子』写本のひとつをゲットしたとされている。現存本の奥書には以下のように記されている。
枕草子は、人ごとに持たれども、まことによき本は世にありがたき物なり。これもさまではなけれど、能因が本と聞けば、むげにはあらじと思ひて、書き写してさぶらふぞ。(中略)さきの一条院の一品(いっぽん)の宮の本とて見しこそ、めでたかりしか、と本に見えたり。
<枕草子は、誰もが持っているけれども、本当によい本は世にあまりない物である。これもそれほど良くはないけれど、能因の本と聞くので、そう悪くはあるまいと思って、書き写している。(中略)先帝一条院の一品の宮の本ということで見たのこそ、すばらしかったと、(筆写に使った元の)本に記されている。>
「一品宮」とは脩子内親王(997-1049)のことで、彼女が善本を所持していたという。
脩子内親王は一条帝と中宮定子との間に生まれた、待望の第一子である。もしこの記載が事実ならば、能因本の原型となった本は清少納言が最終稿とした”決定版”である可能性も浮上してくる。脩子内親王にとって『枕草子』は、亡き母の優しく賢い姿が克明に記されている、それは大切な忘れ形見だったに違いない。清少納言も殊の外彼女を気にかけていただろうし、宮仕えを辞して摂津に向かう際、自分が書いた中で思いの丈を最もよく綴ったバージョンを託そうとしたのはごく自然な流れとなる。しかし奥書の記述はあくまで「伝聞」であり、そこが弱点となっている。そのまま読むと
(1)清少納言が脩子内親王に託した原本(一品の宮の本)
↓
(2)清少納言の親族が、内親王の許可もしくは依頼により写し、後に能因の手に渡り保管された本(筆写元の本)
↓
(3)この奥書の筆者が写した”孫コピー”本
という流れになるだろうか。(2)と(3)の間にも書写があるかもしれないから、曽孫コピー本・玄孫コピー本の可能性さえある。現存する能因本は三巻本同様、室町時代後期に書かれたものが最古というから、上記(3)のコピー本からさらに複数回の書写を経ていると考えられている。
能因本は現存本にたどり着くまでに雑なコピーがなされたと考えられていて、現存本には誤字脱字が多く、意図不明になっている箇所も少なからず見られる。現在笠間文庫で発刊されている現代語訳つき能因本(amazonなどで購入可能)でも、ざっと目を通すだけで、文意不明を示すカタカナ表記が頻出している。
対して三巻本は、藤原定家という当時の権威文学者の監修を経ているゆえか文意不明が少なく、理路整然とした構成になっている。
江戸時代に出版の技術ができると、『枕草子』はまず能因本ベースで広まった。俳人北村季吟(1624-1705)が編集した「枕草子春曙抄」が最も広く流布して、1930年代まで『枕草子』といえばこの本、が常識だったという。
しかし1928年に、国文学者の池田亀鑑(1896-1956)が『枕草子』伝本系統に関する詳細な研究成果を発表したことから三巻本の評価が上がり、戦後は「より正確な伝本」という位置づけのもと、ほとんどの『枕草子』テキスト本が三巻本ベースに変わり、それに基づいた解説書や現代翻案本、マンガなどが作られる現況に至っている。
書き加えられた?重複を解消した?
能因本には三巻本より「〇△は」で始まる”類聚段”が多いという特徴がある。幾度も写される過程で、書く人が自分のお勧めの事物をちゃっかり織り込んだ可能性もゼロとは言い切れない。著作権の概念など存在しなかった時代である。物語の写本はそう勝手にいじれないだろうが、類聚段ならばオリジナルを思いつける人は多いだろう。ゆえに「湯は」の段は後世筆写した人の付け足しとみなす考え方もある。
配列を見てみよう。
能因本117段「湯は」は、「関は」(114)「森は」(115)「卯月のつごもりに、長谷寺に」(116)と「常よりことに聞ゆるもの」(118)の間にある。
三巻本では「関は」(108)「森は」(109)の次に「原は」(110)が入っていて、「卯月のつごもり方に」(111)「常よりことに聞ゆるもの」(112)と続く。すなわち「湯は」の代わりに「原は」を入れた形になっている。一方、三巻本の「原は」は2ヶ所あり、挙げている原の名前が一部重複している。
三巻本の原型本のほうが先にできた(定子に見せた初稿をもとに清少納言が編集した)と考えられていること、および能因本は脩子内親王に託すことを前提に清少納言が再編集した本の可能性があることを勘案すれば、後世の人の付け足しとも言い切れなくなる。「原型能因本を編集する際、”原は”の重複に気づいて、”湯は”に置き換えた」とも考えられないだろうか?
伊勢 or 信濃
それでは、『枕草子』がお勧めする”日本三名泉”はどこを指しているのだろうか。「有馬の湯」は言うまでもなく、現在の神戸市北区有馬町の有馬温泉のことである。地元では豊臣秀吉がこよなく愛したとアピールしているが(キダタローさん作曲のCMで有名な旅館「兵衛」は太閤から賜った名と宣伝している)、それに遡ること1000年前から知られていたという。清少納言が生きていた時代の貴族たちも、当然よく知っていたであろう。
対して「ななくりの湯」はそう知名度が高いとはいえない。私も今回初めて知った。調べてみたら、伊勢国一志郡(現在の三重県津市)にある榊原温泉のことという。古くは七栗上村と称されていて、伊勢神宮の祭祀に使う榊が自生する地であった。1889年の市町村制度発足当時は一志郡七栗村・榊原村があったが、後に久居町に統合され、市制施行(久居市)を経て津市に合併された。七栗は京から伊勢神宮を目指すメインルート上にあり、ここで「湯ごり」をして身を清めてから参拝する習わしがあったというから、平安時代の貴族にもよく知られていたであろう。清少納言本人が行ったかどうかは不明だが、後宮女房時代の知り合いで実際に行った人がいたとしても決しておかしくはない。
地名としては伊勢神宮に納める榊のほうが有名になったようで、榊原温泉として今に至っているが、現地にはそのものスバリ「清少納言」という温泉旅館があり、今でも営業している。
近鉄津駅のホームには「七栗記念病院」の広告看板がある。旧七栗村に建つ、地元の拠点病院らしい。

「ななくりの湯」は伊勢で決まりかと思いきや、異説があるという。長野県上田市の別所温泉が該当する。現地では「七久里の湯」もしくは「七苦離の湯」の文字を当て、ヤマトタケルノミコトの東征伝説に由来すると語られている。
根拠として、平安時代の歌学書で「ななくりの湯」を信濃の歌枕とするものがいくつかある一方、伊勢の七栗の湯を詠んだ和歌はほとんどないということがあげられている。
信州別所温泉説を取るとすれば、清少納言と親しくしていた貴族たちが直接訪れていたとは考えづらくなり、他の類聚段であげられている地名と同様、発音の面白さに着目した記述ということになる。
ちなみに榊原温泉の七栗の湯も、別所温泉のななくりの湯もアルカリ性で、お肌がすべすべになる「美肌の湯」としてPRしている。清少納言自身は容姿にコンプレックスを持っていたとされているが、時代が下がると「平安の才女に着目されていた温泉」というだけで、どこかエキゾチックな印象を喚起させる効果が出てきたのだろう。さらに「ななくりの湯」を詠んだ和歌の多くは「恋の病」とセットになっているゆえ、両温泉とも「恋の病に効く温泉」としている。
「玉造の湯」は島根県八束郡玉湯町の玉造温泉で決まり!と思いきや、笠間文庫の『能因本枕草子』の注釈では「宮城県玉造郡鳴子町にある温泉」、すなわち鳴子温泉のこととされている。もし陸奥とすれば「はばかりの関」(宮城県柴田郡柴田町)などとの関連も考えられうる。
現代の「日本三名泉」は草津(群馬県)、下呂(岐阜県)、有馬とされているが、この選定は室町時代の詩人が行い、江戸時代初期に林羅山が漢詩に詠みこんで定着したという。他にも『風土記』『延喜式神名帳』などで三名泉が記されているが、有馬温泉はその全てにエントリーされている。
”ほうちはうたう”
話は飛ぶが、私の好物のひとつに「ほうとう」がある。甲斐(山梨県)の郷土料理で、太く平たい麺を根菜や豚肉などとともにゆで、味噌煮込みにする。私は山梨県に縁はないが、寒い季節になると近所のスーパーマーケットで真空パックほうとう麺が常備されるので、よく買い、おいしくいただいている。
今般『枕草子』についていろいろな情報を見ているうちに、「ほうとうは枕草子にも登場している」という話題をキャッチして、思わずのけぞった。これは詳しく調べてみたい。
「ほうとうが記されている」とする段も三巻本に基づくテキストには存在しない。能因本第319段「前の木立高う、庭ひろき家の」である。この家の主人が物の怪(病気)に苦しんでいるので僧侶を呼び、「憑坐」(よりまし)役の女の子に物の怪を移すべく祈祷を依頼して、薬湯を飲ませたところ快復したという話である。現代で言えば医師の往診のようなものだろうか。
祈祷を済ませた僧侶が「勤行の時間だから」と言って屋敷から帰る際、家の主人がお礼をふるまおうとする場面で「ほうちはうたう」が登場する。
「しばし候ふべきを。時のほどにもなりはべりぬべければ」と、まかり申しして出づるを、「しばし。ほうちはうたうまゐらせむ」などとどむるを…
<「もうしばらくお付き申し上げているはずですが、勤行の刻限にもなってしまいそうでございますので」と、退出のご挨拶をして出るのを、「もう少しお待ちを。ホウチハウタウを差しあげましょう」などと言って引きとめるのを…>
訳文は笠間文庫より引用
笠間文庫の『能因本枕草子』注釈欄には「不審。一説、『法施報当』でお布施の意。」と記されているが、山梨県内では「熟れたまくわうりとほうとう」の意と解釈されているようで、地元料理店や製麺メーカーのみならず、甲府市のホームページでもこの話が取り上げられている。ほうとうは、6世紀ごろから唐で作られていた「餺飥」(はくたく)を起源として、9世紀ごろ日本に伝えられたとする。
これを観光客向け地元伝説と無碍に退けることはできない。小麦粉に水を加えてこねて引き延ばし、細長く切って食べる「麺」の原型は平安時代に唐から伝えられたという伝説は香川県にもある。讃岐は空海の故郷であるため、空海伝説とともに語られている。空海は804年に遣唐使に参加して、西安に2年間滞在した。そこで「混沌」(こんとん)もしくは「はくたく」という、小麦粉に水を加えて練った料理に出会い、日本に持ち帰り、やがて「饂飩」(うんとん)に変わったと伝えられている。
いずれの伝説においても、当初は練った小麦粉を平たく伸ばした形状だったが、時代が下がると細長く伸ばして切って食べる形に変化した、とされている。『枕草子』で描かれている屋敷の人が、加持祈祷をしてくれた僧侶にお礼としてごちそうしようと考えた、としても不思議ではないだろう。
七栗の湯もほうとうも、『枕草子』にそれらしき物が記されていることを宣伝に使っている。それは、『枕草子』が平安時代を代表する文学作品であるという、国民の教養的共通認識を前提としている。さらに、能因本が長く読まれて親しまれてきたからこそ成立するPRでもある。伝本としてより正確と見なされるからという理由のみで、現代人が読める『枕草子』を三巻本ベースで統一させてしまってよいのだろうか。現在”最善本”とされている三巻本にも、明らかに書写者の不注意による脱落箇所が認められていることも勘案すれば、能因本の役割は決して終わっていないと思われる。
長谷寺 or 清水寺
2024年3月30日、BSで「古都の春 光る君へ千年の桜」という番組が放送され、藤原忯子役の井上咲楽さんがNHK奈良放送局のアナウンサーとともに長谷寺からのレポートに臨んでいた。寺の本堂で僧侶たちが20時の時報として法螺貝を鳴らす模様が生中継され、アナウンサーは「『枕草子』に、法螺貝の音を聞いて大変驚いたという記録が残されています。」と説明していた。
これを見て、お手元の『枕草子』を手に取り参照しようとした人は「えっ、どこに書いてあるの?」と首をひねっただろう。実は、三巻本では「清水」(清水寺)になっている。「初瀬」(長谷寺)と記されているのは能因本である。
正月寺に籠りたるは、いみじく寒く、雪がちに氷たるこそをかしけれ。(中略)初瀬などに詣でて…法師の坊に、をのこども、童べなど行きて、つれづれなるに、ただかたはらに、貝をいと高く、にはかに吹き出でたるこそおどろかるれ。
正月に寺に籠りたるは、いみじう寒く雪がちに氷たるこそをかしけれ。(中略)清水などに詣でて…師の坊に、をのこども、女、童べなどみな行きてつれづれなるも、かたはらに貝をにはかに吹き出でたるこそ、いみじうおどろかるれ。
後日NHK大津放送局で制作された、吉高さんの石山寺参拝番組ではこの段に記されている「若い男は、とかく女性がいる部屋のあたりをうろつく」くだりを「清水寺」として紹介していた。『枕草子』に対する勉強不足…というよりも、能因本の記述が今でも生きている証左のひとつだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
